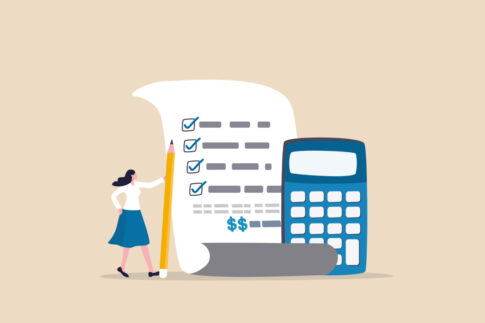発注書だけでファクタリングは可能か——結論、決算書や担保は多くの案件で不要ですが、発注書“単体”での成立可否はエビデンスの厚みに左右されます。
本稿では〈不要→必要〉の順に書類を体系化し、成立条件、提出の並べ方、手数料の見方、契約まわりのリスクまでを客観的に整理。迷いなく相見積もりへ移れる実務フローを提示します。
結論|不要書類→必要書類

多くのファクタリングでは、決算書や担保・保証人は原則不要です。判断の基礎が「申込者の財務」ではなく「売掛先からの入金(債権の確からしさ)」に置かれているためです。
一方、発注書のみでの成立は例外で、請求書・納品/検収・入金履歴など、債権の実在と連続性を証明する資料が重要になります。
実務では「一件一式」で資料を束ね、同一の取引について契約→発注→納品→請求→入金の流れを一本で追える状態を整えるのが近道です。
下表は、現場で問われやすい書類の位置づけを俯瞰したもの。表面の“不要/必要”だけでなく、「なぜ必要(不要)なのか」まで理解して準備すると、再提出が減り着金が早まります。
| 区分 | 例 | 位置づけ・理由 |
|---|---|---|
| 不要になりがち | 決算書・確定申告書/担保・保証人 | 融資ではないため必須でない場面が多い。売掛先与信と債権実在で判断。 |
| 基本的に必要 | 請求書・納品/検収・通帳(入金履歴) | 同一取引で時系列整合。実在性・継続性を示す中核資料。 |
| 状況で変動 | 基本契約書/発注書/通知・登記 | 契約条項(譲渡禁止など)や2社間/3社間の運用で要否が分かれる。 |
多くの案件で不要となる書類一覧
「決算書がないが利用できるか」という相談は珍しくありません。重視されるのは、対象売掛債権の実在と期日支払い見込みであって、過去業績や担保の有無ではありません。
このため、融資で求められがちな決算書や財務諸表、代表者の連帯保証や物的担保は、基本的に不要となる例が多いです。
加えて、2社間ファクタリングは売掛先への通知・承諾を前提としないため、売掛先の印鑑証明や実印書類が不要な運用も一般的。
さらに、債権譲渡登記は「常時必須」ではなく、通知・承諾など代替手段やリスク評価に応じて省略される場面もあります。
重要なのは「不要リスト」を暗記することではなく、「何を根拠に判断されるか」を理解し、必要な証拠を丁寧に揃える姿勢です。
- 決算書・確定申告書(主要な判断軸ではない)
- 担保・連帯保証人(融資ではないため)
- 売掛先の印鑑証明・承諾書(2社間では通常不要)
- 債権譲渡登記(通知・承諾で代替できる場合あり)
基本セット|必要書類と目的
必要書類は「請求が事実で、相手が払う」ことを示す最低限のセットです。要は、一つの請求に関する資料を時系列で突き合わせられるよう纏めること。
請求書だけでは“金額の主張”に過ぎず、発注書・納品/検収が加わって初めて“取引の流れ”が立体化。さらに通帳の入金履歴や取引明細が加われば“継続性・実績”が補強されます。
本人確認や事業実態を補足する軽い資料(登記事項証明・開業届控え・業務委託契約など)は、不正防止の観点で求められることがあります。
提出は「対象請求を1〜3件に特定→関連証憑を1セット化→金額・期日・発注番号にハイライト」が基本動線です。
【基本セットと役割】
- 請求書:金額・期日・相手先の確定(“何をいくら請求か”)
- 発注書・契約書:合意の存在(“なぜ請求可能か”)
- 納品書/検収書・完了報告:履行の確認(“約束を果たしたか”)
- 通帳(入金履歴):継続性・与信の裏づけ(“過去も払われているか”)
- 本人確認・事業実態資料:不正防止・照合(“誰の取引か”)
追加で求められる資料の範囲
追加資料は、案件リスクやスキームで変わります。2社間で通知なしなら、対抗要件の補完として債権譲渡登記を依頼される場合があります。
3社間なら、支払先切替に関する通知・承諾や、支払部門との接続手順(支払依頼書式)を求められることも。
業種によっては、出来高計算書(建設)、受入検収台帳(製造・卸)、検収メールのヘッダー(IT・SaaS)など、実在性を補強する資料が有効です。
返品・値引き・相殺が生じやすい契約なら、該当条文の抜粋や、相殺を行わない覚書の提出で事前にリスクを低減できます。要は、必要性の理由を理解し、提出負担とのバランスで最短経路を選ぶことです。
- 債権譲渡登記(2社間での対抗要件補完)
- 通知・承諾書(3社間での支払先切替)
- 出来高・検収台帳・検収メール(業種固有の実在証拠)
- 契約条文の抜粋(譲渡禁止・相殺条項の確認)
発注書のみの可否と成立条件

結論として、発注書“だけ”での成立は例外的です。ファクタリングは「既発生の売掛債権」を資金化する取引で、成立には実在性と支払見込みを示す客観資料が不可欠。
発注書は「今後の履行を依頼」する段階で、納品・検収前は請求権が確定していないため、単独では根拠が弱い位置づけです。
もっとも、定期取引で仕様・納期・検収条件が明確かつ、過去の入金が安定しているなら、発注書に加え早期に納品・検収の証跡、請求書ドラフトや進捗確認資料を重ねることで、前向き審査の余地が生まれます。
鍵は、対象請求を特定し、契約→発注→納品→検収→請求→過去入金の流れを一本線で示すことにあります。
| 観点 | 成立に近づく要素 | 成立が難しい要素 |
|---|---|---|
| 債権の確実性 | 検収条件が明確・履行が進捗 | キャンセル自由・検収未了・仕様変更多発 |
| 実在の証拠 | 契約/注文/納品/検収/請求が一貫 | 発注書のみ・証憑分散・不一致あり |
| 入金実績 | 同一先からの定期入金履歴 | 初回単発・遅延の前歴あり |
| 契約条項 | 譲渡禁止なし・相殺条項が限定的 | 譲渡禁止や強い相殺条項が存在 |
将来債権と確定債権の違い
理解の出発点は、「将来債権」と「確定債権」の違いです。将来債権は、今後の完了や検収が条件となる見込み段階の請求権。
発注書のみの状態はこれに該当し、金額や期日が記載されていても変更・キャンセルの余地が残ります。
確定債権は、契約に基づく履行が完了し、検収・納品等の要件を満たして請求可能になった段階。請求書・納品書・検収書などの証憑で裏づけられ、相手先が支払義務を負います。
ファクタリング会社が重視するのは後者で、実在性と回収可能性を客観資料で示せるかどうか。
たとえば制作会社のサイト改修なら、発注書に加え完了報告、検収メール、ステージングURLの合意確認、請求書ドラフトまで揃えると、債権の確度が大きく高まります。
【違いの要点】
- 将来債権=発生前提(未確定)→変更・キャンセル余地あり
- 確定債権=履行・検収済み(確定)→請求権が具体化
- 重視資料:将来は進捗・合意、確定は請求・検収・入金実績
成立しやすいケースと最低要件
発注書“単体”は難しくても、条件が整えば前進できます。成立しやすいのは、与信の厚い企業や公共系との継続取引で、検収条件が明確なケース。
対象請求を一件に絞り、第三者にも分かる履行状況をセットで提示できれば、可能性は高まります。
たとえば卸売で毎月同量の定期発注があり、今月分は既に納品済みで、検収メールと入庫記録がそろう例は、請求発行前でも一定の確度を示せます。
最低要件は、取引の合意、履行・検収の確認、相手先の支払実績が“線でつながる”ことです。
- 対象請求の特定(相手先・金額・期日・注文番号)
- 履行・検収の証跡(納品書/検収書/受領記録/検収メール)
- 入金実績の裏づけ(通帳の過去入金・取引履歴)
- 契約条項の確認(譲渡禁止なし・相殺条項は限定)
難しいケースと回避のポイント
難易度が上がるのは、初回単発で過去入金がない、検収条件が曖昧、キャンセルや仕様変更が多い、あるいは譲渡禁止特約や強い相殺条項が存在する場合。
制作・建設の出来高案件や、納品後に長い検査期間がある取引も、請求確定まで時間がかかり厳しめ評価になりがちです。
このような場面では、対象請求の選び直しや、証憑厚みの追加で“確度”を底上げするのが現実的。
具体的には、発注書に加え受領サイン、引渡しプロトコル、検収メール(日時・宛先・件名)のPDF化などを揃え、金額・期日・注文番号にハイライトを付ければ整合性が伝わります。
支払先切替に合意が得られるなら、3社間(通知・承諾)へ移行して条件改善を狙うのも有効です。
| 難しくなる要因 | 具体例 | 回避・改善のポイント |
|---|---|---|
| 初回・単発取引 | 過去入金なし・履歴不明 | 別の継続先の請求に切替/入金履歴を提示 |
| 検収の不明確さ | 受領連絡が口頭のみ | 検収メール・受領書・入庫記録を取得・保存 |
| キャンセル・減額 | 仕様変更・返品が多い | 最終検収後の請求を対象化/相殺発生の余地を確認 |
| 契約制約 | 譲渡禁止・強力な相殺条項 | 承諾書の取得/相殺対象外覚書/別請求の選定 |
| 回収不確実性 | 支払遅延の前例 | 3社間へ変更し支払先切替で透明化 |
必要書類の揃え方と提出順序

審査を短縮し条件を良くする近道は、「対象請求を軸に、時系列で一直線につなぐ」こと。最初に対象請求を1〜3件へ限定し、同じ案件の契約→発注→納品→検収→請求→入金実績の順で束ねます。
続いて、金額・支払期日・注文番号など“判断に使う箇所”へハイライトを入れ、ファイル名とフォルダ構成を統一。
提出順は、概要→証憑一式→補助資料→確認メモが分かりやすいです。メールやSaaS画面はPDF化してヘッダー(日時・宛先)を残します。
再提出は条件悪化につながるため、最初の提出品質を高めるのが最短です。
| 段階 | 主な書類 | チェック観点 |
|---|---|---|
| 概要 | 対象一覧・枚数・合計金額 | 相手先・期日・金額の整合 |
| 証憑 | 契約/発注/納品/検収/請求 | 番号・日付・数量の一貫性 |
| 実績 | 通帳入金ページ・明細 | 入金元名義・金額・周期 |
| 補助 | 本人確認・条文抜粋 | 譲渡禁止・相殺条項の有無 |
一件一式のセット化と整理手順
「一件一式」は、対象請求を核に必要書類を時系列で束ねる考え方です。まず対象請求を特定し、同じ注文番号(案件名)で契約→発注→納品→検収→請求→入金の書類を収集。
フォルダは「00_概要」「10_契約・発注」「20_納品・検収」「30_請求」「40_入金実績」「90_補助」に分け、各PDFは通し番号と相手先・注文番号・金額・期日を含むファイル名に統一します。
審査で見る箇所(期日・金額・注文番号・入金元名義)へ蛍光マーカーを入れ、差異や例外は注記で理由を明確化。ここまで整えると、不要な往復が減り、条件提示までが早まります。
- 対象請求は1〜3件に限定して深掘り
- フォルダ分割:概要→契約→納品→請求→入金→補助
- ファイル名:通し番号_相手先_注文番号_金額_期日.pdf
- ハイライト:金額・期日・注文番号・入金元名義
エビデンス突合と提出フォーマット
突合の基本は「同一番号・同一金額・同一期日が、各書類で連続して現れる」こと。
契約/発注の注文番号が、納品書・検収書・請求書に貫通しているか、請求金額が納品数量×単価で裏づけられるか、請求期日が支払サイトと一致するかを確認します。
通帳は対象先の入金ページを期間連続で提示し、該当入金に下線や付箋を付けます。メール証跡は件名・宛先・日時が読める形でPDF化し、「どの金額に対応する連絡か」をひと言追記。
提出フォーマットはPDFを基本に、全体像を一目で把握できる一覧(スプレッドシート体裁)を添えると親切です。
| 書類 | 突合ポイント | フォーマット例 |
|---|---|---|
| 発注書 | 注文番号・数量・単価 | PDF化+該当行に下線 |
| 納品/検収 | 受領日時・数量一致 | PDF化+検収印影の拡大 |
| 請求書 | 金額・期日・相手先名 | PDF化+金額・期日にハイライト |
| 通帳 | 入金元名義・金額・周期 | 連続ページ+対象入金に付箋 |
| メール | 件名・宛先・日時・合意 | PDF化+該当箇所に注記 |
- 一覧は「相手先/注文番号/金額/期日/証憑ファイル名」を1行で揃える
- SaaS画面はタイムスタンプが見える解像度で保存
- 機微情報はマスキングし、理由を別紙に明記
NG例と再提出を避ける工夫
再提出の典型は、金額・期日・番号の不一致、証憑の欠落、画像トリミングでヘッダー情報が消えているなど“確認不能”の状態です。
とくに、メールやSaaSのスクリーンショットで時刻や宛先が見えない、通帳の銀行名・口座名義が写っていない、請求書の内訳が読めない等は審査が止まります。
回避するには、提出前のセルフレビュー表で、三点照合(注文番号・金額・期日)と入金実績の対応をチェック。再提出は条件悪化につながるため、「最初の提出で決め切る」姿勢が結局は最短です。
- 請求書と発注書の金額・数量が一致しない
- 通帳の切り抜きで口座名義・入金元が不明
- メール証跡に日時・宛先・件名が写っていない
- 複数案件の書類が混在し対象が特定できない
- 三点照合:注文番号・金額・期日を全書類で一致確認
- 連続性:発注→納品→検収→請求→入金が時系列で追えるか
- 可読性:解像度・ハイライト・注記で第三者にも伝わるか
- 個人情報:マスキングの妥当性と理由の記載
- 最終棚卸し:対象外書類の除去とファイル名統一
審査・手数料と選び方の基本

手数料は「回収の確実性」「事務負担」「資金滞留期間」で概ね決まります。審査では、対象請求が事実か、売掛先が期日どおりに支払うか、契約制約(譲渡禁止・相殺条項など)がないかを確認。
ここが強ければ手数料は下がり、弱ければ上がる構造です。さらに、通知・登記の要否、入金スキーム(2社間/3社間)、書類完成度で事務負担が変わり、総費用に跳ねます。
表面の「何%」だけでなく、初期費用・送金手数料・登記や郵送実費・最低手数料、再提出の往復に伴う時間コストまで含めて比較を。
まずは対象請求を1〜3件に絞り、契約→発注→納品→検収→請求→入金の証跡を一直線で提示できる状態にすると、不確実性が下がり交渉余地が広がります。
- 対象請求を特定し、証憑を一件一式で提出
- 売掛先の過去入金(通帳)を期間連続で提示
- 契約条項の確認(譲渡禁止・相殺条項の有無)
- 2社間/3社間は自社体制に合わせて選択
2社間/3社間の影響と違い
2社間は売掛先に知らせず、自社に入金された後でファクタリング会社へ精算する方式。秘匿性とスピードは高い一方、回収コントロールが自社側にあるため条件は厳しめになる傾向です。
対抗要件補完として債権譲渡登記を求められるケースもあり、手数料以外のコストや開示負担が乗る可能性があります。
3社間は売掛先に通知・承諾を取り支払先を切替える方式で、回収見込みが明確な分、買取率や留保が安定しやすい反面、先方の稟議や調整時間を要します。
選択は、秘匿性・スピード・工数・相手先の理解度のバランスで。返品が多い業態では、3社間や一部留保で不確実性を吸収し、総合条件を最適化する設計が有効です。
| 観点 | 2社間(非通知) | 3社間(通知・承諾) |
|---|---|---|
| 回収確実性 | 自社精算のため不確実性やや高め | 売掛先から直接入金で確実性高め |
| 手数料傾向 | 上振れしやすい | 安定しやすい |
| スピード | 早い(通知不要) | 先方承認の時間が必要 |
| 秘匿性 | 高い | 低い(周知が前提) |
| 実務負担 | 自社で精算・消込が必要 | 入金先切替で消込が簡素化 |
- 秘匿性重視・即日志向→2社間が適合しやすい
- 条件安定・運用簡素化→3社間が適合しやすい
償還請求条項とリスク把握
「償還請求条項」は、想定外が生じた際に申込側へ買戻し等を求める範囲を定める重要部分。たとえば不払い、相殺の発生、返品・減額、表明保証違反(虚偽・二重譲渡・反社関与など)で発動することがあります。
範囲が広いほどファクタリング側のリスクは小さく条件は出やすい一方、申込側のキャッシュフロー不確実性は高まります。
逆に限定的・なしなら審査は厳格に。実務では、発動事由・上限・期間・通知期限を読み合わせ、保険・保証・登記・通知などの補完策とセットで、許容度のバランスを設計します。
| 項目 | 確認ポイント | 実務への影響 |
|---|---|---|
| 発動事由 | 不払い・相殺・返品・争訟・表明保証違反 | 範囲が広いほど申込側の負担が増加 |
| 金額上限 | 全額/部分上限・期間制限 | 最大損失額を把握できる |
| 通知期限 | 発生からの通知・対応期限 | モニタリング体制が必要 |
| 補完策 | 保険・保証・登記・通知の組合せ | 手数料とリスクの最適化に寄与 |
- どの事由で、いつまで、いくらまで償還が必要か
- 表明保証の内容(真実性・独占譲渡・反社排除)
- 相殺・減額の扱いと対象外の取り決め可否
- 通知・登記・保険で代替できる範囲
相見積もりと条件比較の基準
相見積もりは、手数料だけでなく運用負荷とリスク配分を見える化する工程です。前提を揃えるため、同じ対象請求・同じ証憑セット・同じ希望入金日で各社に提示。
回答は買取率に加え、「費用内訳」「入金スケジュール」「必要書類」「通知・登記の要否」「償還条項の範囲」「追加費用(送金・登記・最低手数料など)」まで横並びで比較します。
拮抗する場合は、継続時の枠拡張、複数請求の束ね割、オペ支援(テンプレ・ヘルプデスク)の有無と品質で差がつきます。
最終的には、自社の消込フローに当てはめ、実装コストを含む総費用で意思決定を。
| 比較軸 | 確認内容 | 評価の観点 |
|---|---|---|
| 価格 | 買取率・手数料・追加費用の内訳 | 表面%でなく総額・実質年率で比較 |
| スピード | 提出→条件提示→着金の目安 | 資金繰りサイクルと整合 |
| リスク | 償還条項・相殺・譲渡禁止の扱い | 想定外時の負担と上限が明確か |
| 運用 | 必要書類・通知/登記の要否 | 社内工数と秘匿性のバランス |
- 前提統一:対象請求・提出セット・入金希望日を固定
- 費用分解:手数料%・留保・登記・送金・最低手数料を可視化
- スケジュール:条件提示~着金までの所要と稟議負荷を確認
- リスク配分:償還・相殺・返品の扱いと上限を明確化
- 運用影響:通知・登記・消込工数と秘匿性を評価
- 「何%」ではなく「いくら受け取れるか」で判断
- 初回は対象請求を絞り、証憑精度で条件を引き上げる
- 3社以上で比較し、実務サポートの質も加点
契約条項と違法スキーム注意

可否や条件は、書類精度だけでなく「契約条項」にも大きく左右されます。
影響が大きいのは、債権譲渡を制限する条文(譲渡禁止特約)、売掛先が他債権と相殺できる条文(相殺条項)、検収条件や支払サイトの取り決め、そして表明保証・反社排除・二重譲渡禁止などの遵守条項。
内容次第で、通知・承諾の取得、3社間への切替、対象請求の見直しなど運用調整が必要です。登記や通知も「常に必須」ではなく、スキームやリスク許容度で使い分けます。
なお、外見が似ていても性質が異なる違法スキーム(給与ファクタリングなど)には関与しないことが重要。
以下で実務影響の大きい論点を整理します。
| 条項・論点 | 実務への影響 | 確認・対応の要点 |
|---|---|---|
| 譲渡禁止特約 | 第三者譲渡が制限され承諾が必要 | 条文有無を確認/承諾書や例外規定で対応 |
| 相殺条項 | 支払時に減額・相殺の可能性 | 範囲・発動条件を把握/相殺対象外覚書を検討 |
| 検収・支払サイト | 債権確定時期・着金時期に直結 | 検収成立の要件・期日を証憑で裏づけ |
| 表明保証・遵守 | 違反で償還請求・停止のリスク | 二重譲渡禁止・反社排除・真実性維持 |
| 通知・登記 | 対抗力・秘匿性・コストに影響 | 2社間/3社間の運用に合わせ選択 |
譲渡禁止特約・相殺条項の確認
譲渡禁止は、売掛金の第三者譲渡を禁じる(または制限する)条文です。強い場合は承諾書やスキーム変更が前提に。
相殺条項は、別件の未払い・損害・違約金等を理由に支払額を差し引ける規定で、範囲が広いほど回収額のブレが増えます。
実務では、基本契約・個別契約・注文裏面・約款の該当条文を読み合わせ、対象請求に関係する箇所を抜粋して提示。
譲渡禁止でも、例外規定(金融機関等への譲渡容認)があれば前進できますし、承諾書や相殺対象外覚書で実務リスクを低減できます。大切なのは「対象請求を特定し、条項の影響を具体化する」ことです。
- 譲渡禁止の有無と例外規定(金融機関等)
- 相殺条項の範囲(違約金・瑕疵・別件損害の扱い)
- 検収成立の要件(誰が・何で・いつ確定)
- 条文抜粋を添付し、対象請求と紐づけて説明
通知・登記の要否と実務留意点
通知(承諾を含む)と登記は、対抗力や回収確実性を高める主要な手段。3社間は支払先切替の通知・承諾により回収見込みが明確で、条件が安定しやすい一方、先方稟議や情報共有の負荷があります。
2社間は秘匿性とスピードに強みがある反面、回収不確実性を織り込むため条件が上振れしがちで、対抗要件補完として登記を用いる場面も。
登記は権利関係の公示で優先順位を確保できる一方、コストと開示負担が発生します。選択は、先方との関係性、必要な着金スピード、社内の消込体制との相性で判断。
いずれの方式でも、発注→納品→検収→請求→過去入金の整合度を上げるほど、交渉余地が広がります。
- 3社間:通知・承諾で確実性↑/稟議・時間コスト↑
- 2社間:秘匿性・スピード↑/条件上振れ・登記要請あり
- 登記:優先順位の確保に有効/コスト・開示の負担
- 判断軸:関係性・スピード・社内オペの三点均衡
給与ファクタリングの回避策
「給与の早期現金化」をうたう給与ファクタリングは、見た目は売掛金の資金化に似ても、実質は高コストの貸付と判断されやすい取引で、トラブル事例が多い領域です。
賃金は強い保護が及ぶため、事業者向けファクタリング(事業の売掛債権の譲渡)と同列に扱えません。資金繰りが逼迫しても、給与債権を対象とするスキームには関与しないのが安全。
代替として、事業の売掛債権に基づく正規のファクタリング、公的資金繰り支援、税・社保の納付猶予制度など、適法で透明性の高い選択肢を検討しましょう。
判断に迷ったら、対象が「事業の売掛金」か「個人の給与」かをまず切り分けるのが出発点です。
- やめる:給与ファクタリング(個人の給与を対象)
- やめる:正体不明の高料率“即日現金化”広告への申込
- 代替:事業の売掛債権に基づく正規のファクタリング
- 代替:公的支援・納付猶予・条件変更の活用
まとめ
発注書“のみ”は例外で、確定性と証拠の厚みが成否を分けます。不要書類は省きつつ、請求書・納品/検収・通帳などを一件一式で整え、2社間/3社間、償還条項、通知・登記の要否を事前確認。
最後に相見積もりで手数料・入金日・追加費用を数値比較。最短で安全に資金化へ進む実務手順が把握できます。