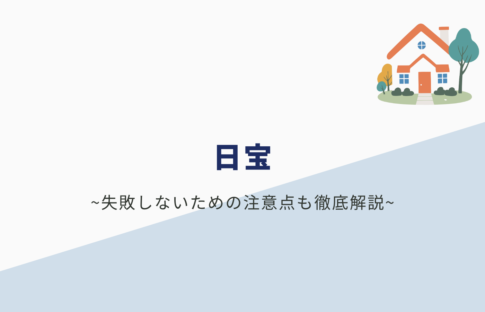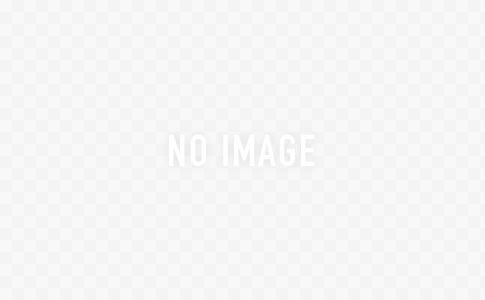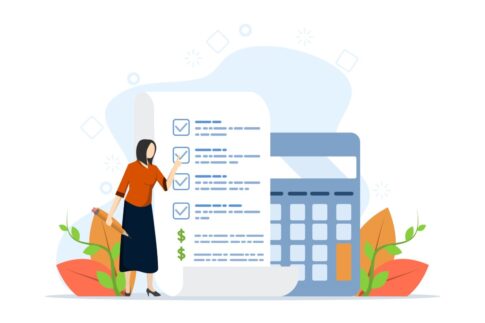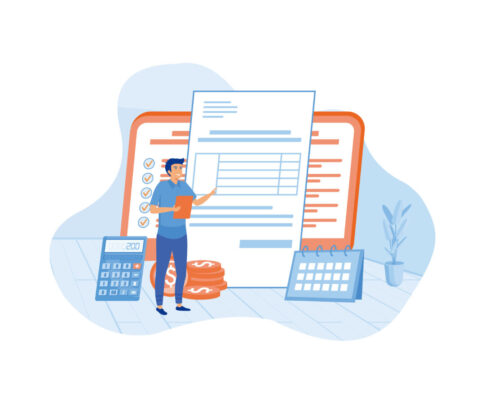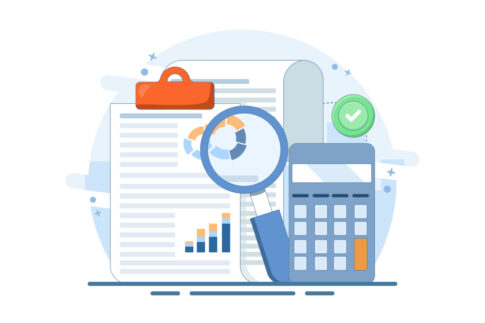返済条件の調整(リスケ)期間でも、資金ショートを避ける打ち手として検討できるのがファクタリングです。これは融資ではなく売掛債権の売却であり、見られるのは自社より相手先の信用です。
本稿では、利用可否の考え方、2社間/3社間の違い、費用感・入金スピード・提出物に加え、不動産担保・ABL・各種保証など代替策を客観比較。安全運用に必要な勘所を絞って整理します。
リスケ中の資金調達の基本

リスケは資金繰りの呼吸を取り戻す手段である一方、新規融資のハードルが上がりやすい現実があります。そこで候補に入るのが、借入以外で現金化する方法です。
代表格が売掛金の現金化であるファクタリングで、資金の源泉や審査の焦点が融資と大きく異なります。
本章では、リスケ中に押さえる視点として、各手段の性質・評価されるポイント・資金化の速度を俯瞰します。
たとえば、銀行は返済原資(利益・キャッシュフロー)を重視しますが、ファクタリングは主に売掛先の信用力を評価します。こうした「評価軸の差」を理解しておくと、無理のない選択がしやすくなります。
| 手段 | 性質 | 審査・速度の目安 |
|---|---|---|
| 銀行融資 | 借入(負債増) | 事業の収益力・返済原資を重視/実行は中〜長め |
| ノンバンク | 借入(負債増) | 財務・信用の評価/実行は中程度 |
| ファクタリング | 売掛債権の売買 | 売掛先の信用重視/最短で即日もあり得る |
| ABL | 在庫・売掛等の担保化 | 担保価値と回収性の確認/中程度 |
| リースバック等 | 資産売却+賃貸 | 資産評価と賃料負担の妥当性/中程度 |
リスケの意味と主な制約ポイント
リスケは、金融機関との合意で返済条件(期間、返済額、元金据置など)を見直す取り組みです。狙いは「資金ショート回避」と「再建のための時間確保」。
しかし、条件変更期間は新規の実行が抑制されやすく、定期的なモニタリング提出も求められます。
例えば「毎月100万円を6か月利息のみ」にすれば短期改善は可能ですが、信用回復まで追加調達は限定的になりがちです。
ゆえに、リスケは終着点ではなく「改善計画とセット」で効果を発揮します。具体的には、資金繰り表の共有、売上回復・粗利改善・固定費圧縮、税・社保の滞納整理などを同時並行で進める設計が必要です。
- 見直し対象:返済期間・返済額・元金据置などの条件
- 期間中は新規実行が難化、試算表・資金繰り表の提出が前提
- 延滞・約定違反は信用低下に直結、合意順守が大前提
- 売上・粗利・固定費の改善計画とセットで運用
- 税・社保の整理は優先、分納合意を計画に反映
銀行融資が難しい理由
リスケ中に銀行が慎重になるのは、返済原資の不確実性が高まり、内部格付・与信判断が厳格化されるためです。
銀行は「事業キャッシュ=返済原資」を最重視します。赤字や営業CFの不足、資金繰りの乱れが見えると、新規貸出は抑制されがちです。
さらに、条件変更は「当面は約定通り返せない」サインでもあり、限度の見直しや担保・保証の追加要求につながる場合があります。
例えば、営業CFが月50万円、既存返済が80万円の局面では、DSCR上も不足が明白です。この状態で借入を重ねれば将来負担が増し、再生可能性を損なう恐れがあります。
そのため、計画の実行と数字の回復が示されるまでは、新規実行は見送りとなりやすいのです。
- 営業CFや粗利の不足は与信を厳格化させる要因
- 条件変更履歴は返済能力の弱さのシグナル
- 税・社保の滞納や買掛遅延は強い警戒材料
- 担保・保証での保全不足は実行リスクを増加
- 新規借入が既存計画を阻害する可能性
経営改善計画と資金繰り表の準備
リスケ下での調達は「資金用途」と「返済原資の再生時期」を数字で示すことが要諦です。実務の要は、実行可能な改善計画と、短サイクルで更新する資金繰り表。
計画では、現状課題(粗利率低下、固定費肥大、在庫回転悪化、与信管理の甘さ)を分解し、売上の再現性、粗利率の回復策、固定費削減、不要資産売却、取引条件の見直し(値上げ・ロット・サイト短縮)を担当者×期限で落とし込みます。
資金繰りは13週など週次で管理し、入出金の山谷を早期に可視化。例えば回収前倒し10日で当座資金が改善する場合もあります。
金融機関と共有し、達成度のモニタリングまで設計すれば、外部調達の説得力が上がります。
- 売上見通しは受注残・見積・契約などで根拠付け
- 粗利改善は価格改定・歩留まり・仕入条件の数値化
- 固定費は即時と中期に分解し、効果発現時期を明記
- 資金繰りは週次の入出金・期末残・警戒ラインを設定
- 税・社保の分納を反映し、再滞納を回避
- 四半期ごとに実績レビューと施策更新を徹底
ファクタリングの可否と仕組み

ファクタリングは未回収の売掛金を第三者へ譲渡して資金化する取引です。借入ではない「債権の売買」のため、リスケ中でも選択肢となり得ます。
審査の主眼は、自社の格付よりも「売掛先の支払能力・実績」。売掛先の与信に問題がなければ、条件は組み上がりやすくなります。
一方、対抗要件(通知・承諾または譲渡登記)の整備、請求・入金フロー変更、譲渡禁止条項の確認など実務の留意点は多いです。
手数料は債権額や回収期日までの残日数、2社間/3社間の別で変動します。判断は「譲渡の適法性」「二重譲渡の防止体制」「資金繰り谷を安全に越えられるか」を、具体の帳票で検証することが基本です。
| 項目 | ポイント | リスケ中の観点 |
|---|---|---|
| 性質 | 売掛債権の譲渡(借入ではない) | 負債増を伴わない資金化 |
| 審査軸 | 売掛先の信用・取引実績 | 赤字期でも売掛先次第で可 |
| 対抗要件 | 通知・承諾/債権譲渡登記 | トラブル回避の中核要件 |
| 手数料 | 債権額・残日数・スキーム | 期日基準で費用対効果を評価 |
売掛債権の売買と法的位置づけ
ファクタリングは将来受け取る売掛金を移転し、その対価を受け取る仕組みです。融資と異なり「返済」ではなく「債権の移転」で資金化します。
第三者に主張可能にするには、売掛先への通知・承諾、もしくは債権譲渡登記など対抗要件が不可欠。譲渡禁止・制限条項がある場合は、契約に沿った承諾取得が必要です。
二重譲渡防止、請求・入金口座の整合、金額・期日・相手先の特定など、帳票レベルの突合も重要です。
会計上は借入計上ではなく譲渡対価の受領として扱いますが、リスク移転の態様で処理が分かれることもあるため、最終仕訳は専門家の助言に従うのが安全です。
- 契約・請求で相手先・金額・期日を特定
- 譲渡禁止・制限条項の有無を確認し、必要なら承諾
- 対抗要件の整備(通知・承諾/譲渡登記)
- 入金口座・請求フロー変更を当事者間で合意
- 重複担保・二重譲渡の有無を点検
審査の焦点|売掛先の信用重視
評価の中心は売掛先の支払能力と実績です。自社が赤字・リスケ中でも、売掛先が安定し、遅延なく継続関係が確認できれば、資金化の可能性は高まります。
逆に、与信が弱い、請求額のブレが大きい、検収証憑が薄い、などはマイナスです。具体的には、売掛台帳や成因資料(注文・契約・納品・検収・請求)、入金消込、支払サイトや遅延履歴で、債権の実在と回収見込みを立証します。
加えて、二重譲渡防止、反社・公序良俗のチェック、税・社保の状況など基本的コンプライアンスも確認対象。
審査の速度は、資料の整合度と売掛先情報の入手容易性に比例します。平時から証憑を整備しておくことが、いざという時の近道です。
- 売掛先与信:規模・業績・遅延の有無・取引年数
- 成因の一貫性:注文〜納品〜検収〜請求が一本線
- 入金実績:消込・相殺や値引の有無・サイト安定性
- 集中度:特定先依存が高いとリスク増
- コンプライアンス:二重譲渡防止と適正性の確認
2社間・3社間の違いと実務
2社間は「利用企業↔ファクタリング会社」の取引で、売掛先への通知は原則行いません。入金は一旦自社に入り、そこから精算。
開示を避けやすい反面、回収リスクを負うため費用は高めに出やすい傾向です。3社間は「利用企業・ファクタリング会社・売掛先」で通知・承諾を行い、売掛先から直接入金。
事務は増えますが、回収の明確化により費用は抑えやすくなります。選択は、先方との関係、開示許容度、資金化までの時間、費用水準、社内体制を総合判断。
どちらでも二重譲渡防止、請求・入金フロー整合、対抗要件の整備は必須です。
| 観点 | 2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング |
|---|---|---|
| 通知・承諾 | 原則不要(非開示運用) | 売掛先へ通知・承諾を取得 |
| 入金フロー | 売掛先→自社→ファクタリング会社 | 売掛先→ファクタリング会社(直送金) |
| 費用傾向 | 高め(回収リスクを織込) | 低め(回収明確化) |
| スピード | 短期で進めやすい | 通知・承諾分のリードタイムが必要 |
| 向く場面 | 開示を避けたい、急ぎの資金化 | 費用を抑えたい、長期の安定運用 |
費用・入金速度・必要書類の目安

「いくら・いつ・何を出すか」を先に固めると、無駄な往復が減ります。費用は表面料率だけでなく、振込・登記・郵送などの周辺費用まで含めた総コストで評価。
入金の速さは、売掛先情報の把握しやすさと、提出資料の整合度に左右されます。必要書類は、注文〜納品〜検収〜請求の連続性を示す成因資料に、売掛台帳・入金消込・会社情報を添えるのが基本。
リスケ中は「資金使途」と「短期資金繰り表」を同封すると妥当性が伝わります。
全体像を以下に簡潔にまとめます。
| 観点 | 見るポイント | 実務的な目安 |
|---|---|---|
| 費用 | 手数料+振込・登記・郵送等の周辺費用 | 残日数・売掛先信用・2社間/3社間で変動 |
| 速度 | 成因資料の整合・売掛先情報の入手性 | 整っていれば短期、齟齬があると延伸 |
| 書類 | 注文〜納品〜検収〜請求の一貫性、台帳・消込 | 不足は代替証憑や説明資料で補完 |
手数料相場と総コストの考え方
費用は「売掛金額」「回収までの残日数」「2社間/3社間」「売掛先信用」などで決まります。相見積りでは、料率だけでなく振込・登記・郵送・早期買取の割増等を合算した総コストで比較しましょう。
残日数が短いほどリスクが下がり条件は良化しやすく、継続利用で与信が安定すると滑らかになることも。
リスケ下では資金使途が“谷越え”に限定されているか、調達後に資金繰りが改善するかが焦点です。資金繰り表に「いつ・いくら・何に使い、どの時点で改善するか」を記し、効果を定量で示します。
- 料率+振込・登記・郵送など周辺費用を合算
- 残日数と売掛先信用で条件は変わる
- 2社間は高め、3社間は低めの傾向
- 単発より継続・分散で条件が安定
- 資金繰り表で調達効果を定量化
入金までの流れと最短スピード
スピードは「資料の整合」と「売掛先確認の容易さ」でほぼ決まります。成因が明確で書類が揃っていれば、審査→契約→対抗要件の整備が滑らかに進みます。
注文書なし・検収不明瞭・金額の度重なる変更は時間を要します。2社間は通知が原則不要で短縮しやすい一方、3社間は通知・承諾や振込先変更などの事務が増えるため、事前準備が速度を左右します。
最短を目指すなら、帳票の事前整備、社内承認・押印・郵送のリードタイム短縮が有効です。
- 申込み・ヒアリング(使途・必要額・期日)
- 成因資料提出(注文・契約・納品・検収・請求)
- 審査・与信(売掛先の支払実績・債権の同定)
- 見積・条件合意(金額・手数料・入金日・方式)
- 契約・対抗要件(通知・承諾/譲渡登記)
- 譲渡対価の送金(入金)
- 回収・精算(3社間は売掛先→ファクタ会社へ直送金)
申込み時に用意する基本書類
提出物は「債権の実在」と「回収見込み」を示すものが中心です。成因は注文〜請求を一本線で示し、売掛台帳・入金消込で支払規律を補強。
会社側は登記事項・代表者確認、決算や試算表、通帳明細などを用意します。3社間では売掛先の通知・承諾が必要となる場合があります。
リスケでは、金融機関との合意や資金繰り表・使途内訳を付すと、判断が速まります。
- 成因資料:注文/契約・納品・検収・請求の一式
- 債権管理:売掛台帳・入金消込・基本契約の該当条項
- 会社情報:履歴事項全部証明・印鑑証明・定款該当箇所
- 本人確認:代表者の本人確認資料・印鑑(または電子署名)
- 財務資料:直近決算・試算・主要口座の入出金明細
- 対抗要件:通知・承諾(3社間)/譲渡登記関連
- 補足:資金繰り表・使途内訳・リスケ合意の概要
リスケ中の代替手段の比較

新規融資が難しい局面では、「スキームの切り替え」「担保評価の活用」「保証で返済を平準化」といった代替も比較検討します。
主な選択肢は、不動産担保ローン、ABL(動産・売掛の担保化)、信用保証協会の借換系(条件変更改善型借換保証)、伴走前提の保証(経営改善サポート保証)など。
見た目は同じ調達でも、審査観点・書類・資金用途適合性・返済の平準化余地が異なります。「資金谷の深さ・期間」「返済原資の回復見込み」「差し入れ可能な担保・証憑」から当てはめ、過度な債務増や短期の自転車操業を避けましょう。
要点を以下に整理します。
| 手段 | 概要 | リスケ中の観点 |
|---|---|---|
| 不動産担保ローン | 土地・建物を担保に調達 | 担保余力・順位・評価の妥当性が鍵。返済原資の裏付けも必要 |
| ABL | 在庫・機械・売掛等の担保化 | 資産評価とモニタリング体制が前提。使途の妥当性を確認 |
| 条件変更改善型借換保証 | 条件変更中債務の借換・平準化 | 計画と伴走・モニタリングが前提。返済条件を整えやすい |
| 経営改善サポート保証 | 改善計画の実行資金を保証付で調達 | 認定支援機関の関与と継続フォローが条件。計画実行が前提 |
不動産担保ローンの可否と留意点
可否は不動産の評価(実勢・収益・積算)と抵当順位・残債で大きく左右されます。担保余力が十分で返済原資の見通しが示せれば、リスケ中でも検討余地はあります。
ただし、抵当が厚い・収益が不安定などは厳しい条件になりがち。使途は在庫回転改善や受注増対応など「谷越え」に合理的であることが望ましく、固定費を恒常的に増やす投資は慎重に。
評価書・公図・登記簿・固定資産税通知、賃貸ならレントロールや修繕計画まで整え、返済後の姿を定量で説明します。
繰上返済・違約金の有無、登記・保険・印紙等の諸費用も総コストに含め、資金繰り表へ反映します。
- 実勢・収益・積算の評価軸と既存抵当の順位・残債を把握
- 使途は“谷越え”の合理性を資料で立証(受注・在庫・入金計画)
- 返済後DSCRを試算し、資金繰りへ反映
- 登記・保険・印紙・事務手数料まで総コストで判断
- 途中解約・違約金、団信・火災保険の条件を確認
ABL(動産担保融資)の要件と流れ
ABLは在庫・機械・売掛など事業資産を担保に資金を得る方法です。評価とモニタリング(在庫回転・売掛回収)を前提に「資金が運転を一巡させるか」を数値で確認できます。
リスケ中でも、資産の実在・換価・回収可能性が高く、台帳や検収・消込が整っていれば検討余地あり。
売掛ABLは残高×掛目で限度を算定し、月次レポートで見直す運用が一般的。機械・在庫中心なら現物確認・保険付保・棚卸管理が重要。使途は運転資金や仕入前払いなど、短サイクルの回転改善に適します。
- 対象資産の確定(在庫・機械・売掛)と資料収集
- 評価・掛目設定(換価性・回転率・毀損リスク)
- 契約・担保設定(譲渡・登記・譲渡禁止条項の確認)
- 実行・モニタリング(月次レポート・限度見直し)
- 回収・返済(資産回転に応じた返済で平準化)
条件変更改善型借換保証
信用保証協会の保証で、条件変更中の既存債務を借換え返済条件を整える枠組みです。複数債務の一本化や期間延長で、短期の資金繰り圧迫を和らげます。
利用時は、金融機関・保証協会と共有する改善計画(売上・粗利・固定費の施策、実行時期、モニタリング体制)の策定が前提。
使途や対象債務の範囲は制度要件に従う必要があります。借換だけでは本質解決とならないため、回収改善・在庫圧縮・価格見直し等の打ち手とセットで運用します。
- 条件変更中の債務を借換え、返済条件を平準化
- 改善計画とモニタリング体制の整備が必須
- 使途・対象範囲は制度要件を事前確認
- 収益・CF改善と併用して効果を最大化
- 金融機関・保証協会と定例レビューを実施
経営改善サポート保証
改善計画と伴走支援を前提に、必要資金を保証付で調達する仕組みです。認定支援機関等が計画策定とフォローに関与し、実現性を高めます。
使途は売上回復に直結する運転・小規模改善投資・仕入前倒しなど、計画に沿った範囲。リスケ中の活用では、既存条件変更と矛盾しない返済スケジュール・CF計画の整合が重要。
提出資料は現状分析、KPI、数値計画(損益・資金繰り)、体制整備、外部支援の関与内容など。趣旨は「資金と改善の同時推進」であり、定例モニタリングと計画アップデートまで設計すると実効性が高まります。
| 観点 | 概要 | 実務の着眼点 |
|---|---|---|
| 計画 | 外部支援を伴う実現性の高い改善計画 | KPI・施策・期限を明確化し、週次/月次で管理 |
| 資金使途 | 計画に即した運転・小規模改善投資 | 入出金と回収見込みを資金繰りに反映 |
| 体制 | 伴走・定例レビュー・是正の枠組み | 未達時の代替策・コスト圧縮策を事前設計 |
安全利用の注意点とリスク管理

ファクタリングは借入ではありませんが、契約や運用を誤れば費用膨張や法的紛争の火種になります。
特に、貸付に近い実態の「偽装ファクタリング」、同一債権の「二重譲渡」、譲渡禁止条項の失念、請求・入金フロー変更時の混乱、そして調達を重ねる「自転車操業」には注意が必要です。
安全運用には、名目ではなく支払条件の中身、対抗要件(通知・承諾/登記)の整備、社内の債権管理、資金繰りモニタリングを一体で設計することが要点。
主なリスクと兆候、予防策は次表の通りです。
| リスク分類 | 典型的な兆候 | 先回りの対策 |
|---|---|---|
| 契約リスク | 名目は買取でも定額返済・遅延損害金など貸付的条項 | 本文の支払条件を精査、年率換算で総コスト比較 |
| 法的・登記 | 譲渡禁止の未確認、通知・承諾や登記の未整備 | 条項確認と対抗要件整備、専門家の確認 |
| 運用・実務 | 口座変更周知不足・消込の遅れ | 手順書の整備、締日運用の徹底 |
| 資金繰り | 高コストの継続・調達額の増加 | 13週資金繰りで閾値設定、停止基準・代替策を事前決定 |
偽装ファクタリングの見分け方
見た目は買取でも実態が貸付に近い契約は要注意です。
売掛入金の有無に関係なく定額返済を義務付ける、過大な遅延損害金・違約金、対抗要件を取らず返済義務だけ負わせる、審査料・紹介料の先払い、料率だけ強調し年率換算を出さない——いずれも警戒シグナル。
契約は見出しではなく本文で確認し、入金フローと支払条件が買取スキームに合致しているかを確かめます。
複数社で相見積りを取り、総コスト(手数料+諸費用)を残日数で年率換算し、粗利率と横並び比較しましょう。判断が難しいときは中立の専門家レビューが安全です。
- 売掛入金に無関係な毎月固定の返済義務
- 遅延損害金・違約金が過大で貸付的条項が多い
- 通知・承諾や登記を取らず返済義務のみ負わせる
- 審査料・紹介料の先払い要求、手数料の過大化
- 実質コストの年率換算を避け表面料率のみ提示
二重譲渡など違法リスクの回避
同一債権を複数へ譲渡する二重譲渡は重大リスクです。基本・個別契約の譲渡条項を確認し、必要に応じ売掛先の承諾を取得。
金融機関のABLや総合根保証など既存の担保・譲渡の有無を社内台帳・登記・金融機関照会で棚卸します。
3社間は通知・承諾(確定日付が望ましい)、2社間は譲渡登記で第三者対抗力を確保。請求・入金先の変更と消込手順は標準化し、周知徹底で誤振込や未通知を防ぎます。
返品・値引・相殺が起こる取引では、成因の保全と差額調整手順(通知・合意書式)を先に用意しておくと安心です。
- 譲渡禁止の有無を確認し、必要なら承諾取得
- 既存の担保・譲渡(ABL等)の棚卸・記録
- 通知・承諾または譲渡登記で対抗要件を確保
- 請求・入金・消込のフローを標準化し一斉周知
- 売掛台帳の締日運用で二重管理を防止
- 返品・相殺時の差額処理と証憑保全を定型化
自転車操業回避と停止基準の設定
「回すための調達」を続けると費用が積み上がり抜け出せません。まず13週資金繰りで期末残や未達時の代替策を可視化し、調達目的を“谷越え”に限定します。
実効コストが粗利率へ接近・上回る局面は注意。売上増・粗利改善が乏しければ、追加調達より回収前倒し・在庫圧縮・固定費削減を優先します。
調達比率(売上対資金化割合)や平均サイト、売掛集中度を定例でモニタリングし、悪化が続けば自動停止基準を起動。停止後は制度融資・保証や価格・条件見直しなど構造的打ち手に切り替えます。
- 年率換算の実効コストが粗利率に接近
- 調達比率が上昇(売上の伸びなしに増加)
- 13週資金繰りで期末残が警戒ラインを連続割れ
- 回収遅延の常態化、平均サイトの延伸
- 税・社保の分納計画崩れと滞納再発
まとめ
ファクタリングは“融資ではない”ためリスケ中でも選択可。ただし鍵は売掛先の信用と費用妥当性です。2社間/3社間の差、必要書類、入金速度を比較し、譲渡禁止や二重譲渡を回避。
並行して不動産担保・ABL・保証制度を検討し、資金繰り表と改善計画に落とし込めば、無理のない調達と返済が実現します。