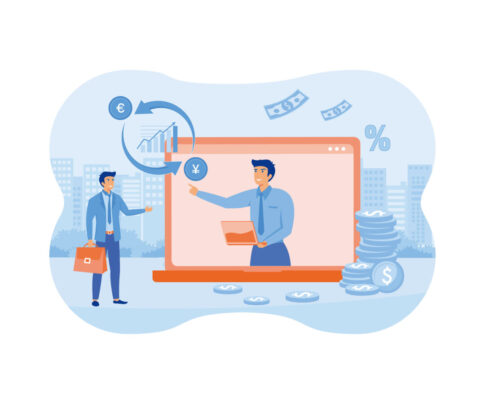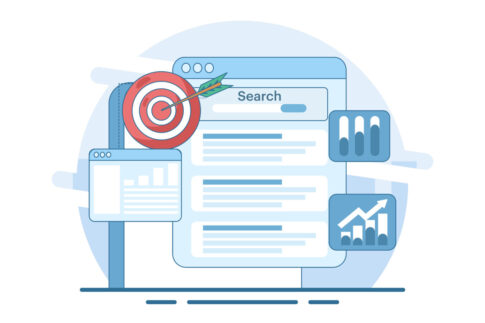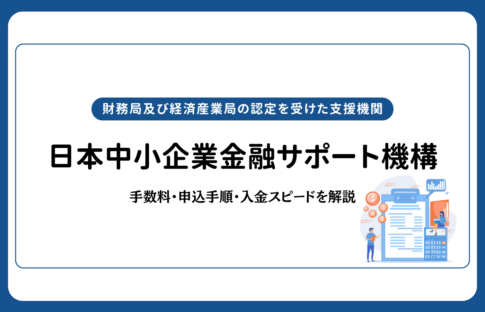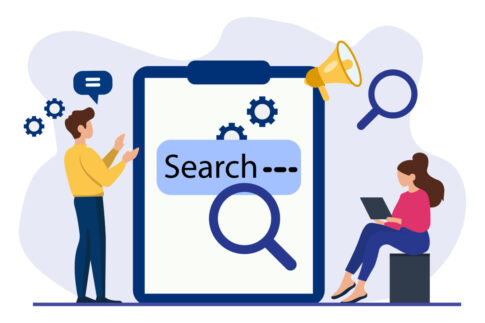ファクタリングとでんさい割引は、どちらも「将来入ってくるはずのお金」を前倒しで現金化する手段ですが、仕組みや手数料、リスクの持ち方が大きく異なります。
本記事では、でんさい割引の基本と電子記録債権の仕組み、ファクタリングとの違い、手数料・割引率の比較ポイント、資金繰り表を使った使い分けの考え方までを分かりやすく整理します。銀行融資が難しい中小企業でも、自社に合った資金調達方法を客観的に選べるようになることを目指した内容です。
目次
ファクタリングとでんさい割引の基礎

ファクタリングとでんさい割引は、どちらも「将来受け取る予定の代金を前倒しで資金化する」手段ですが、前提となる債権の種類や、法律上の位置づけが異なります。
金融庁はファクタリングを「事業者が保有している売掛債権等を、期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」であり、法的には債権譲渡(売買)と整理しています。
一方、「でんさい」は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が取り扱う電子記録債権であり、手形・売掛債権等の問題点を克服した新しい金銭債権と説明されています。
電子記録債権制度は、中小企業の資金調達を円滑化する目的で創設され、電子債権記録機関の原簿に「発生」「譲渡」などの記録を行うことで効力が生じる仕組みです。
でんさいを銀行が期日前に買い取るのが「でんさい割引」で、従来の手形割引に近い位置づけの取引とされています。
一方、ファクタリングは請求書ベースの売掛債権を対象とすることが多く、銀行以外の専業事業者も参入している点が特徴です。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| ファクタリング | 売掛債権等をファクタリング会社に売却し、手数料を差し引いて期日前に資金化する取引。法的には債権譲渡。 |
| でんさい | でんさいネットが取り扱う電子記録債権。手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した金銭債権と定義。 |
| でんさい割引 | 保有しているでんさい(電子記録債権)を、銀行等が期日前に割引料を差し引いて買い取る取引。手形割引に近いスキーム。 |
この章では、まず「でんさい割引とは何か」「電子記録債権と売掛債権の違い」「資金調達手段としての位置づけ」という基礎的な論点を整理していきます。
でんさい割引の基本的な意味
「でんさい割引」とは、企業が受取側として保有しているでんさい(電子記録債権)を、支払期日より前に金融機関が買い取り、その際に割引料(利息相当額)を差し引いて資金化する取引をいいます。
三菱UFJ銀行などの説明では、「でんさい」はでんさいネットが取り扱う電子記録債権であり、手形・振込に代わる決済インフラであること、受取企業は割引や譲渡によって資金調達ができることが示されています。
電子記録債権そのものは、「商品売買等により生じた金額を指定日に支払うことを約束する金銭債権」であり、手形・売掛債権の問題点(紙の管理負担、譲渡の煩雑さ、債権譲渡禁止特約など)を克服する目的で制度設計されています。
でんさい割引は、この電子記録債権をベースに、銀行が割引料を受け取る代わりに、期日前に資金を提供する点で、従来の手形割引と類似した性質を持ちます。
割引のイメージとしては、例えば以下のように整理できます。
- 企業Aが企業Bに商品を販売し、支払条件として「でんさい」を受け取る(支払期日は60日後)。
- 企業Aは、仕入・人件費支払のため早めに資金が必要になり、自社の取引銀行にでんさい割引を申し込む。
- 銀行は信用・期日・金額等を審査し、所定の割引料を差し引いた金額を企業Aに支払う。
- 支払期日には企業Bから銀行へ支払いが行われ、銀行はでんさいの権利を行使する。
- 対象は「でんさいネット上の電子記録債権」であり、紙の手形ではない。
- 銀行等が割引料(利息相当)を差し引いて期日前に資金化する仕組み。
- 従来の手形割引と似た位置づけだが、記録・管理は電子的に行われる。
このように、でんさい割引は「電子化された手形割引」に近いイメージで捉えると分かりやすく、電子記録債権の仕組みを活かして、従来の手形よりも柔軟で安全な資金調達を目指すスキームといえます。
電子記録債権と売掛債権の違い
電子記録債権は、電子記録債権法に基づき創設された新しいタイプの金銭債権で、「手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した金銭債権」と位置づけられています。
一方、売掛債権は、中小企業庁の説明では「企業が取引の相手先に対して商品やサービスの提供を行ったことにより、その代金を請求することができる権利」と定義されています。
両者の主な違いは、「管理方法」と「譲渡・担保利用のしやすさ」にあります。売掛債権は契約書・請求書・納品書等の紙やデータを組み合わせて管理し、譲渡や担保に入れる際には債務者への通知や承諾が必要になるケースもあります。
また、契約に「債権譲渡禁止特約」が付いていると、譲渡や担保利用が制約されることがあります。
これに対し、電子記録債権は、電子債権記録機関(でんさいネットなど)の「記録原簿」に発生・譲渡等を記録することで効力が生じます。
電子記録債権のメリットとして、中小企業庁の資料では以下の点が挙げられています。
- 電子記録により債権の存在・帰属が可視化される。
- 電子記録債権の譲渡は、債務者への通知等が不要(でんさいネット利用の場合)。
- 売掛債権の電子記録債権化により、譲渡禁止特約を付けられない取り扱いとされ、譲渡が容易になる。
- 分割や統合がしやすく、管理コストの低減が期待できる。
| 項目 | 電子記録債権と売掛債権の違い(概要) |
|---|---|
| 成立・管理 | 売掛債権:契約書・請求書等に基づき個別管理/電子記録債権:記録機関の原簿に電子記録 |
| 譲渡のしやすさ | 売掛債権:譲渡禁止特約や債務者への通知が障害になり得る/電子記録債権:譲渡禁止特約なし、記録変更で譲渡可能 |
| 資金調達での利用 | 売掛債権:ファクタリング・ABL(売掛債権担保融資等)で活用/電子記録債権:でんさい割引・担保利用など |
- 売掛債権は「取引に伴う請求権」、電子記録債権はそれを電子化・制度化した金銭債権という位置づけ。
- 電子記録債権は記録機関の原簿で管理され、譲渡・割引が手続きとして簡素化されている。
- 売掛債権の電子記録債権化により、債権譲渡禁止特約の制約がなくなり、中小企業の資金調達がしやすくなることが期待されている。
このように、電子記録債権は「売掛債権や手形の電子化・制度化」として理解すると分かりやすく、そのうえでファクタリングやでんさい割引といった商品に展開されている、と捉えることができます。
でんさい割引とファクタリングの位置づけ
でんさい割引とファクタリングはいずれも「将来の入金を前倒しする」資金調達手段ですが、金融インフラ・法的性質・利用主体に違いがあります。
金融庁はファクタリングを「売掛債権等の売買(債権譲渡)」と定義し、偽装ファクタリング(実質は高利の貸付)に注意を呼びかけています。
一方、でんさい割引は、電子記録債権法に基づく電子記録債権を対象に、銀行等が割引を行う取引であり、銀行の貸出業務の一類型として位置づけられます。
中小企業庁の資料では、電子記録債権(でんさい)を活用した資金調達は、「手形や売掛債権担保融資(ABL)のデメリットを解消しつつ、中小企業の資金調達の多様化・円滑化を図る手段」として整理されています。
一方、売掛債権ファクタリングは、売掛債権担保融資保証制度やABLと並ぶ「売掛債権を活用した資金調達」の一種であり、不動産担保に依存しない調達手段として推進されています。
整理すると、両者の位置づけは次のようなイメージになります。
- でんさい割引:電子記録債権(でんさい)を対象にした、銀行中心の割引取引。電子的な手形割引に近い。
- ファクタリング:売掛債権を対象にした、銀行・専業事業者による買取(債権譲渡)取引。2社間・3社間、リコース有無などバリエーションがある。
- 共通点:いずれも「取引から生じた債権」を活用して資金調達する手段であり、中小企業の運転資金確保に用いられる。
- でんさい割引は「電子記録債権+銀行」の世界で、決済インフラと一体のサービス。
- ファクタリングは「売掛債権+金融機関・専業業者」の世界で、スキームや事業者の多様性が大きい。
- どちらも不動産担保に頼らない資金調達だが、インフラ・法的性質・コスト構造が異なるため、比較検討が必要。
この位置づけを理解しておくと、「自社が持っているのは紙の手形か、請求書ベースの売掛金か、電子記録債権か」「どの金融インフラを使っているか」に応じて、でんさい割引とファクタリングのどちらを中心に検討すべきかを整理しやすくなります。
でんさい割引の仕組みと特徴

でんさい割引を理解するには、「でんさいそのものの仕組み」と「割引取引としての流れ」を分けて押さえると分かりやすくなります。
でんさい(電子記録債権)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)が扱う電子記録債権で、全国銀行協会が100%出資する電子債権記録機関が、記録原簿への電子記録を通じて発生・譲渡などを管理する仕組みです。
電子記録債権制度は、中小企業の資金調達の円滑化等を目的として創設された新しい金銭債権であり、手形や売掛債権が抱えていた紛失・盗難リスクや二重譲渡リスク、譲渡禁止特約といった課題を克服することが狙いとされています。
一方、でんさい割引は、受取企業が保有しているでんさいを、支払期日前に金融機関が買い取る取引で、期日までの利息相当額(割引料)を差し引いた金額が入金されます。
一般的な流れとしては、商取引の結果としてでんさいを受け取った企業が、取引銀行に割引を申し込み、銀行が審査のうえ、でんさいネット上で譲渡記録を行い、割引料控除後の金額を振り込むというステップです。
なお、でんさいはインターネットバンキング等を通じて利用することが前提となり、参加金融機関(銀行・信用金庫・信用組合など)を通じて全国的に利用可能な社会インフラとして整備されています。
こうした特徴から、でんさい割引は「手形割引を電子化したような仕組み」でありつつ、電子記録ならではの分割・譲渡の柔軟性や管理コストの低さといった利点を持つ一方、事前の契約・審査や手数料負担などの点も踏まえて検討する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| インフラ | 全国銀行協会出資の「でんさいネット」が電子記録債権を記録・管理する社会インフラ。 |
| 対象債権 | 商取引により発生した電子記録債権(でんさい)。紙の手形・売掛債権の電子化版。 |
| 割引取引 | 受取企業が保有するでんさいを支払期日前に金融機関が買い取り、割引料を差し引いた金額を支払う。 |
でんさいネットと電子記録債権の概要
でんさいネットは、全国銀行協会が100%出資する電子債権記録機関で、電子記録債権(でんさい)を記録・流通させる全国規模の社会インフラを提供しています。
企業がでんさいを利用する際は、取引金融機関のインターネットバンキングや窓口を通じて、発生記録請求・譲渡記録請求などの手続きを行い、それが記録原簿に記録されることで、債権の発生や譲渡の効力が生じます。
電子記録債権とは、電子債権記録機関が調製する記録原簿への電子記録を、その発生・譲渡等の効力要件とする金銭債権であり、既存の手形債権や指名債権(売掛債権等)とは別の新たな金銭債権として法的に位置づけられています。
その背景として、紙の手形や売掛債権は、紛失・盗難・二重譲渡リスク、譲渡禁止特約による資金調達制約、作成・保管コストなどの問題を抱えており、電子記録債権制度はこれらの問題を解決し、中小企業の資金調達の円滑化を目的に創設されました。
でんさいネットが取り扱う「でんさい」は、こうした電子記録債権制度に基づく債権であり、手形と同様の利用方法を採用しつつ、記録・譲渡・割引などを電子的に行えるように設計されています。
例えば、1本のでんさいを分割して一部を他社に譲渡したり、一部だけを割引に出すことが可能であり、柔軟な資金調達や資金移動に対応できます。
- 電子記録債権は、記録原簿への電子記録が発生・譲渡の要件となる新しい金銭債権。
- でんさいネットは全国銀行協会出資の電子債権記録機関で、全国規模のインフラとして稼働。
- でんさいは、手形に近い使い方を維持しながら、分割・譲渡・割引を電子的に行える柔軟な仕組みを備える。
このように、「電子記録債権」という法制度と、「でんさいネット」というインフラの上に成り立っているのが、でんさいおよびでんさい割引です。
まずは、この土台を押さえておくと、後述する割引の流れやメリット・デメリットの理解がスムーズになります。
でんさい割引の手続きと流れ
でんさい割引の基本的な流れは、手形割引に似ていますが、手続きの多くをインターネットバンキング上で完結できる点が特徴です。
会計ソフトベンダーの解説などでは、一般的なステップとして、①商取引後に納入企業がでんさいを受け取る、②納入企業が取引銀行にでんさい割引を申し込む、③銀行が審査する、④審査承認後、でんさいネットに譲渡記録請求を行う、⑤譲渡記録が成立すると、銀行が割引料を差し引いた金額を納入企業に振り込む、という流れが示されています。
でんさいネットのパンフレットによると、でんさいの発生自体は、支払企業(債務者)が発生記録請求を行い、でんさいネットが記録を行う「債務者請求方式」が基本ですが、受取企業が発生記録請求を行う「債権者請求方式」も用意されています。
割引の場面では、受取企業が保有するでんさいについて、割引を希望する金額を指定して分割割引することも可能であり、700万円のでんさいのうち300万円だけを割引に出し、残り400万円を保有する、といった柔軟な運用ができます。
ただし、でんさい割引を利用するには、事前に取引金融機関での利用申込・審査・契約が必要であり、審査では利用者の財務状況や経営状態、取引先の信用力などが総合的に評価されます。
また、金融機関によっては、インターネットバンキング(ビジネスダイレクト)の契約が前提となるほか、割引手数料や事務手数料が発生します。
- 商取引後、受取企業がでんさいの発生記録通知・譲渡記録通知を受ける。
- 受取企業が取引銀行にでんさい割引を申し込み、銀行が審査を行う。
- 審査承認後、でんさいネット上で譲渡記録が行われ、銀行が割引料控除後の資金を振り込む。
- 必要に応じて、でんさいを分割し、一部だけを割引に出すことも可能。
このように、でんさい割引は「慣れてしまえば手続きはシンプル」ですが、初回利用時には金融機関との契約・審査やインターネットバンキング環境の整備が必要になる点を踏まえた準備が重要です。
でんさい割引のメリット・デメリット
でんさい割引のメリットとして、まず挙げられるのが「電子化による安全性・効率性」です。
電子記録債権(でんさい)は、電子的記録により債権を発行・管理するため、紙の手形や売掛債権に比べて紛失・盗難・偽造のリスクが低く、書類保管コストも不要になります。
また、でんさいネットは全国の銀行・信用金庫・信用組合等が参加するインフラであり、相手先企業の取引金融機関を意識せずに利用できる点も利便性の高い特徴です。
資金調達の観点では、でんさいは電子記録債権として譲渡・割引がしやすく設計されており、債権譲渡禁止特約の問題を回避しつつ、売掛債権をベースにした資金調達ができる点が、中小企業の資金繰り改善につながるとされています。
また、手形サイト短縮の動きとも相まって、60日前後のサイトを持つ取引をでんさい化し、必要に応じて割引に出すことで、資金繰り平準化に活用できます。
一方、デメリット・注意点もあります。電子記録債権(でんさい)を利用するには、事前に金融機関への利用申込・審査・契約が必要であり、信用力が十分でない企業は、そもそもでんさいの利用開始が認められない可能性があります。
また、手形と同様に手数料がかかるほか、取引先もでんさいを利用している必要があるため、相手先が未対応の場合は活用範囲が限られます。
小口取引では、電子化・手数料のコストに対してメリットが薄いケースもあるとされています。
- メリット:紛失・偽造リスクの低減、保管コスト削減、全国の金融機関で利用可能で資金調達の柔軟性が高い。
- メリット:売掛債権の電子記録化により、譲渡・割引がしやすく、中小企業の資金調達の多様化に寄与する。
- デメリット:利用開始には金融機関での審査・契約が必要で、信用力により利用できない場合がある。
- デメリット:取引先もでんさい利用が前提、小規模取引ではコストメリットが出にくい。
このように、でんさい割引は「電子化された安全・効率的な割引手段」である一方、利用開始のハードルや取引先の対応状況、コストとのバランスを見ながら導入を検討する必要があります。
後続の章で扱うファクタリングとの比較や、自社の資金繰り状況を踏まえ、どの場面ででんさい割引を活用するのが適切かを整理していくことが重要です。
ファクタリングとでんさい割引の比較

ファクタリングとでんさい割引は、どちらも「将来入金されるはずの債権を早めに現金化する」という点では共通していますが、審査の考え方・手数料水準・貸倒れリスクの持ち方が大きく異なります。
電子記録債権(でんさい)は、電子債権記録機関の記録原簿への記録を発生・譲渡の要件とする新しい金銭債権であり、事業者、とくに中小企業の資金調達の円滑化を目的に創設されました。
でんさい割引は、この電子記録債権を銀行等に期日前に譲渡し、割引料を差し引いたうえで資金化する取引です。
一方ファクタリングは、売掛債権(請求書ベースの債権)をファクタリング会社に譲渡し、手数料控除後の金額を受け取るスキームで、2社間/3社間・リコース/ノンリコースなど複数の形態があります。
ファクタリング会社は銀行だけでなく専業ノンバンクも多く、スピードや柔軟性の高さと引き換えに、割引率(手数料率)はでんさい割引より高めに設定されるのが一般的です。
両者を比較するときは、①審査基準と利用しやすさ(どこまで信用力が求められるか)、②手数料・割引率水準(実質コストの違い)、③償還請求権とリスク分担(貸倒れ時に誰が責任を負うか)の3つを軸に整理すると、自社に向いた手段が見えやすくなります。
| 比較軸 | でんさい割引 | ファクタリング |
|---|---|---|
| 対象 | 電子記録債権(でんさい) | 売掛債権(請求書ベース) |
| 主な提供主体 | 銀行など金融機関 | 銀行+専業ファクタリング会社 |
| 手数料水準 | おおむね1.5〜5.5%程度 | 2社間:8〜18%、3社間:2〜9%が目安 |
| 審査 | 融資扱いで銀行審査が中心 | 売掛先重視で比較的柔軟(事業者による) |
| 貸倒れ時の責任 | 原則として利用者に償還義務あり | ノンリコース契約なら原則償還なし |
審査基準と利用しやすさの違い
審査の観点では、でんさい割引は「融資扱い」であることが大きなポイントです。
電子記録債権割引(でんさい割引)は、電子記録債権を期日前に金融機関に譲渡し割引料を引いた分の現金を得る取引ですが、各行の説明や専門記事では、でんさい割引は融資に準じた扱いであり、売掛先企業と利用者(受取側企業)の信用力を総合的に見て審査するとされています。
具体的には、
- 利用者企業の財務内容(自己資本比率・債務超過の有無・借入状況)
- 売掛先企業の業績や支払実績
- 取引実績の期間・取引金額の規模
- でんさいネットの利用実績(発生・決済に問題がないか)
といった点が、銀行審査の対象になります。そのため、既にメインバンクとの取引実績がある企業や、一定以上の信用力を持つ企業にとっては利用しやすい一方、創業間もない企業や赤字決算が続く企業にとっては、利用開始のハードルがやや高くなります。
これに対し、ファクタリングは「売掛債権の売買」であり、金融庁の注意喚起でも「貸金業ではなく債権譲渡」と明記されていますが、経済的に貸付と同様の機能を有するものは貸金業に該当し得るとしています。
正規のファクタリングでは、審査の対象は主に売掛先の信用力と売掛債権の内容であり、利用者側が赤字であっても、売掛先が上場企業や公的機関など信用力の高い相手であれば利用できるケースが少なくありません。
- でんさい割引:銀行の融資審査に近く、「利用者+売掛先」の両方の信用力を重視。既存取引がある企業向き。
- ファクタリング:売掛先の信用力重視で、利用者側が赤字でも利用余地がある事業者も多い。
- 創業間もない企業や赤字企業は、まずファクタリングから検討し、将来的にでんさい割引も選択肢に入れる流れが現実的。
このように、審査の厳しさ・利用しやすさは、「銀行との関係性」と「売掛先の信用力」のどちらをより重視するかで変わってきます。
手数料・割引率水準の比較ポイント
手数料・割引率の水準は、両者の大きな違いです。中小企業支援サイトや金融機関系の解説によると、ファクタリングの手数料(割引率)は、2社間ファクタリングで8〜18%、3社間ファクタリングで2〜9%程度が相場とされています。
一方、電子記録債権割引(でんさい割引)の手数料相場は、年利換算でおおむね1.5〜5.5%程度と紹介されており、銀行による手形割引に近い水準です。
この数字だけを見ても、「でんさい割引<ファクタリング」という関係が明らかですが、実際の負担感を比較するには、以下の点もあわせて見る必要があります。
- でんさい割引:割引料は年利ベースで設定され、残存日数に応じて日割り計算される(例:年利3%・残存90日など)。
- ファクタリング:売掛金額に一定%の手数料を乗じる「一回のディスカウント」として扱われることが多く、同じ%でも期間によって年率換算の負担が変わる。
- 両者とも、発生記録手数料・送金手数料等の「固定費」が別途かかる場合がある。
例えば、
- でんさい割引:額面100万円、残存90日、割引料年利3%とすると、割引料はおおよそ100万円×3%×90日÷365≒約7,400円。
- ファクタリング:同じ100万円の売掛金を手数料10%でファクタリングすると、手数料は10万円。
といった差が生じるため、「コストを極力抑えたい」「銀行審査を通過できる」という前提があれば、でんさい割引の優位性は大きいと言えます。
一方、審査の柔軟性やスピードを重視する場合は、手数料が高くてもファクタリングのほうが使いやすい場面もあります。
- でんさい割引:年利1.5〜5.5%程度が目安。期間を考慮した利息型の割引。
- ファクタリング:2社間8〜18%、3社間2〜9%程度が目安。期間に関係なく1回のディスカウントとして扱われやすい。
- 総コストを比較するには、「同じ100万円を同じ日数だけ前倒しした場合の負担」で並べて試算する。
このように、手数料だけを切り出すのではなく、「金額×期間」で実質年率を意識しながら比較することが重要です。
償還請求権とリスク分担の違い
貸倒れリスクの持ち方も、両者の大きな違いです。ファクタリングは「売掛債権の売買」であり、原則としてノンリコース(償還請求権なし)であるため、ファクタリング会社が売掛金を回収できなくても、利用者は弁済義務を負わない形が基本とされています。
ただし、契約によってはリコース(償還請求権あり)とされているケースもあり、契約書の確認が不可欠です。
一方、でんさい割引は、手形割引と同様に「償還請求権がある」のが原則です。銀行等がでんさいを割引した後、支払企業が期日に決済できない場合には、割引を利用した企業に対して弁済を求めることができます。 つまり、
- ファクタリング(ノンリコース型):売掛先の倒産・未払リスクをファクタリング会社に移転できる(その分手数料が高い)。
- でんさい割引:割引を受けても、最終的な未回収リスクを利用者が負う(手数料は相対的に低い)。
という違いがあります。
- 「売掛先が倒産したらどうするか」という問いに対する答えが違う。
- リスクを外出ししたい場合は、ノンリコース型ファクタリングが候補(ただしコスト高)。
- リスクは自社で負う前提で、コストを抑えたいならでんさい割引が候補。
このリスク分担の違いを踏まえると、「売掛先の信用力」と「自社のリスク許容度」によって選択が変わります。
売掛先が大企業や公的機関で倒産可能性が低いと判断できる場合は、でんさい割引でコストを抑える選択が理にかないます。
一方、売掛先の集中度が高い・財務内容が読みにくいといった場合には、コストを払ってでもノンリコース型ファクタリングでリスクを移転する、という判断も選択肢になります。
資金調達に悩む中小企業の活用パターン

中小企業が「ファクタリング」と「でんさい割引」のどちらを使うべきかを考える際には、単に手数料だけでなく、「自社と取引先の信用力」「取引形態(手形・でんさい・売掛金)」「資金繰りのパターン」を整理することが重要です。
中小企業庁は、売掛債権や手形を活用した資金調達(ABLや電子記録債権など)が、不動産担保に依存しない資金調達手段として有効である一方、資金繰り実績と予定を踏まえた計画的な活用が必要と指摘しています。
また、経済産業省は、約束手形の廃止スケジュールに合わせて「銀行振込」と「でんさい」を代替手段として推奨しており、製造業や建設業など手形文化の根強い業種に対して、でんさいへの切り替えを促しています。
一方で、売掛金そのものをファクタリング等で流動化することも、売掛金活用の一手段として紹介されており、「電子記録債権(でんさい)」「売掛債権ファイナンス(ファクタリング・ABL)」は、中小企業の資金調達を多様化・円滑化するための並列的なメニューとして位置づけられています。
この章では、「でんさい割引が向く企業と条件」「ファクタリングが適するケース」「資金繰り表を前提にした使い分け」の3つの観点から、代表的な活用パターンを整理します。
| 視点 | 検討ポイント |
|---|---|
| 取引形態 | 手形・でんさい決済が中心か、請求書ベースの売掛金決済が中心か。 |
| 信用力 | 自社と取引先の信用力、銀行との取引実績、電子記録債権利用の可否。 |
| 資金繰り | 資金不足が一時的か慢性的か、繁忙期と閑散期のキャッシュフローの山谷。 |
でんさい割引が向く企業と条件
でんさい割引が向いているのは、「でんさいによる決済が既に取引先と定着している」「取引銀行との関係があり、一定の信用力がある」タイプの中小企業です。
でんさいネットの説明では、でんさいは「全銀行参加型で構築され、中小企業の資金調達を円滑にするため、手形的に利用できる」決済インフラとして位置づけられており、支払期日には自動的に支払企業の口座から受取企業の口座へ決済される仕組みです。
電子記録債権を用いた資金調達について、中小企業庁は「売掛債権や手形のデメリットを解消しつつ、中小企業の資金調達の多様化・円滑化を促進するもの」と評価しており、特に売掛債権の電子記録債権化により、譲渡禁止特約を付けられない取り扱いとされることで、譲渡や割引が容易になると説明しています。
でんさい割引が向く条件を整理すると、次のようになります。
- 取引先との決済に、でんさい(電子記録債権)を利用している、または今後切り替える予定がある。
- メインバンク等との取引実績があり、融資や手形割引の利用歴がある程度ある。
- 売掛先の信用力が高く、期日決済に大きな不安がない(倒産リスクが相対的に低い)。
- 資金不足は一時的で、残存サイトもある程度読める(例:60日以内など)。
- 手形文化からの移行を進めている製造業・建設業等で、でんさい決済が増えている企業。
- 銀行との信頼関係があり、電子記録債権割引の枠組みを活用できる企業。
- 倒産リスクよりも、コストの低い短期資金調達を重視したい企業。
このような企業にとって、でんさい割引は「銀行金利に近いコストでの短期資金調達」が可能になるため、まず検討すべき選択肢になります。
ファクタリングが適するケース整理
ファクタリングは、売掛金そのものを対象とした資金調達手段であり、電子記録債権や手形を使っていない取引にも適用できる点が強みです。
経済産業省・中小企業庁は、売掛金の活用(流動化)を通じた資金調達の多様化を推奨しており、売掛債権担保融資保証制度やファクタリングなどが、不動産担保に頼らない調達方法として位置づけられています。
ファクタリングが適するケースとして、代表的なものは次の通りです。
- 決済は請求書ベースの掛取引が中心で、でんさいや手形を使っていない。
- 創業間もない、直近で赤字決算が続いているなどの理由で、銀行融資やでんさい割引の利用が難しい。
- 売掛先が上場企業・大手企業・官公庁など信用力の高い先で、売掛金自体の回収リスクが低い。
- 急な支払いや「今週・来週の資金ショート」を埋めたいなど、スピードを重視したい場面。
ファクタリングは手数料が高めになる一方で、「利用者が赤字でも、売掛先が優良であれば利用できる」「担保や保証人が不要なサービスが多い」「最短即日などスピーディに資金化できる」といったメリットがあります。
- 銀行融資やでんさい割引の審査が通りにくいが、売掛先は優良な企業である。
- 短期的な資金ショートが発生しており、スピードを最優先したい。
- 請求書ベースの売掛金が大きく、売掛債権を活用した資金調達を検討したい。
ただし、金融庁は「ファクタリングを装った違法な貸付」に関する注意喚起を行っており、債権額に比べて著しく低額な買取代金や、実質的な償還義務を伴うスキームには注意が必要です。
ファクタリングが適している場面かどうかを見極めるとともに、契約内容が健全かどうかを確認することが欠かせません。
資金繰り表を用いた使い分け例
でんさい割引とファクタリングを「どのように使い分けるか」を検討する際には、資金繰り表を作成して、月ごとの入金・出金のタイミングと残高の推移を見える化することが有効です。
中小企業庁の資金繰り支援パンフレットや「中小企業の会計」ツール集では、資金繰り実績表と資金繰り予定表を通期で作成することで、資金不足が予想される時期を事前に把握し、早めに資金調達策を検討することが推奨されています。
資金繰り表を前提にした使い分けの簡易例は、次のように整理できます。
- 通常時:売掛金やでんさいの回収タイミングと、仕入・人件費・税金などの支払タイミングを資金繰り表で確認し、期中の必要運転資金を銀行融資やでんさい割引で賄う。
- 繁忙期・成長局面:売上が急増して売掛金が膨らむ一方、銀行融資の枠が追いつかない場合に、売掛金の一部をファクタリングで前倒しすることで、仕入や外注費を確保する。
- 一時的なショート:決算や税金支払などで一時的に資金不足が想定される場合、でんさい割引枠の範囲で対応し、それでも不足するときに限定的にファクタリングを併用する。
- 1. 過去6か月の資金繰り実績と今後6か月の予定を資金繰り表にまとめる。
- 2. 資金残高がマイナスになりそうな月と原因(売掛サイト・大口支払など)を特定する。
- 3. でんさい・手形がある部分は「でんさい割引」で、請求書ベースの売掛金は「ファクタリング」で補えるかを検討する。
- 4. 銀行融資・公的支援(保証付き融資など)も含めた組合せで、最小コストで資金不足を解消できる案を比較する。
このように、資金繰り表をベースに「どの月に、どのくらい、どの債権を前倒しするか」を決めておくことで、でんさい割引とファクタリングを場当たり的ではなく、計画的に使い分けることができます。
結果として、手数料負担を抑えながら、資金ショートのリスクも減らすことが可能になります。
でんさい割引とファクタリング選択時の注意点
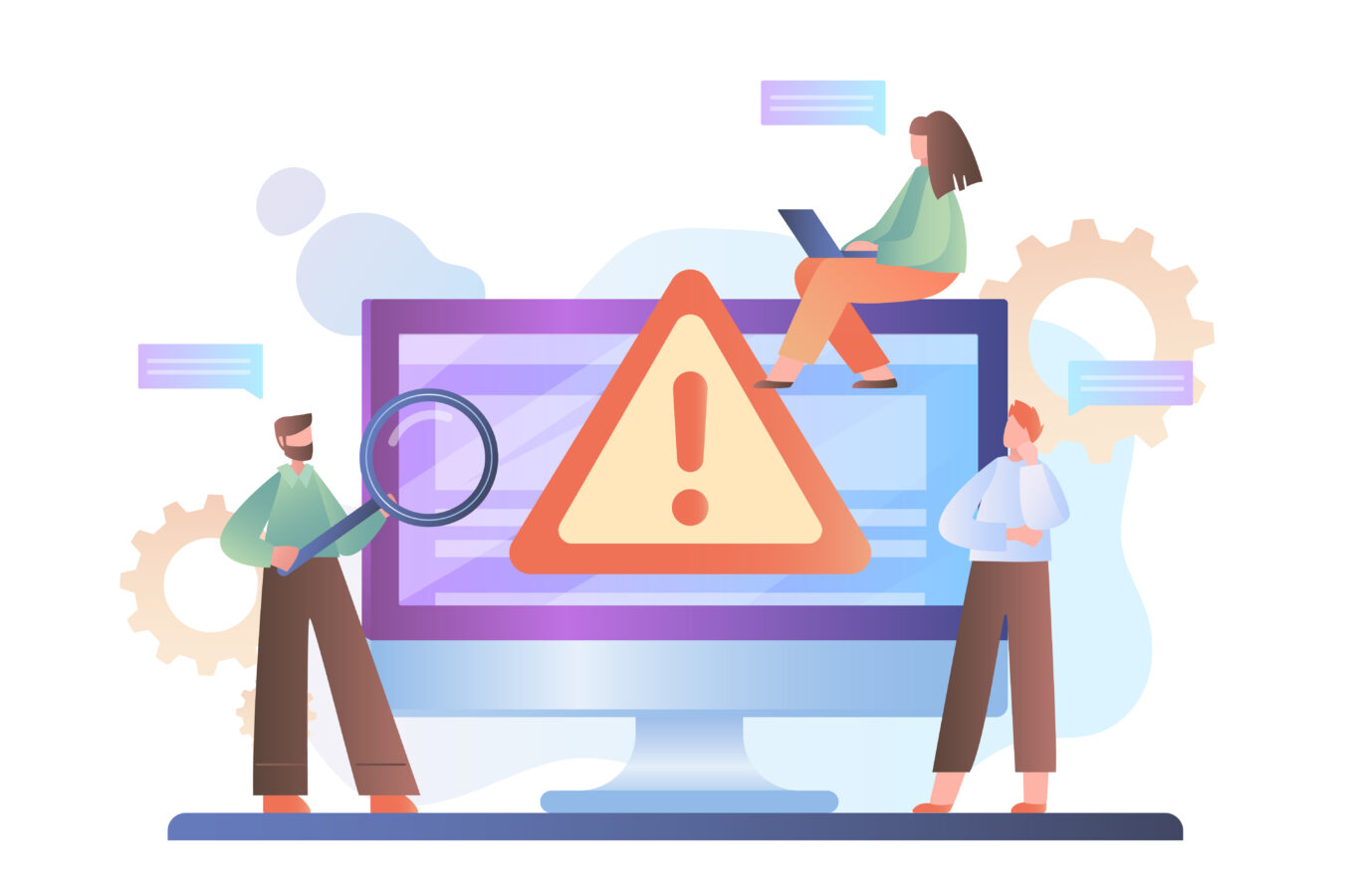
でんさい割引とファクタリングはいずれも中小企業の資金繰りを支える手段ですが、割引率・手数料水準やリスクの持ち方を誤ると、かえって資金繰りを悪化させてしまうおそれがあります。
金融庁は「高額な手数料・大幅な割引率のファクタリングの利用には十分注意してください」とする注意喚起を公表しており、売掛債権等を譲渡して資金調達を行う際、高額な手数料や大幅な割引率による契約は多重債務につながる危険性があると警告しています。
一方、電子記録債権(でんさい)は、中小企業等の資金調達環境の整備を目的に導入された制度であり、電子的手段による債権譲渡等を通じて資金調達の円滑化を図るものとされています。
でんさい割引は手形割引に近い仕組みで比較的低い金利水準が期待できますが、銀行審査や償還リスクを伴います。
このように、「コスト」「リスク」「審査・利用条件」がそれぞれ異なるため、単に「早くお金が欲しい」という理由だけで選ぶのではなく、客観的な注意点と確認事項を押さえたうえで選択することが重要です。
| 確認軸 | 主な注意ポイント |
|---|---|
| 割引条件 | 相場から大きく外れた高割引・高手数料になっていないか |
| スキームの適法性 | 偽装ファクタリングや違法な貸付に該当しないか |
| 相談先 | 金融機関や専門家、公的窓口への相談を行っているか |
極端な割引条件・高手数料への注意点
極端に高い割引率・高手数料は、短期的には資金が入っても、中期的には資金繰り悪化や多重債務につながるリスクがあります。
金融庁は、高額な手数料や大幅な割引率によるファクタリング契約を締結すると、資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性があるとして、経営者に注意を促しています。
一般的な目安として、公開情報ではファクタリングの手数料(割引率)は、2社間で8〜18%前後、3社間で2〜9%前後といったレンジが示されることが多く、一方ででんさい割引や手形割引は年利1〜数%台に収まる水準で紹介されています。
売掛金100万円について、手数料30%で60日間のファクタリングを利用すると、受取額は70万円となり、粗利率が低い事業では利益をほぼ食い尽くしてしまう可能性があります。
年率換算すると60〜100%を超える水準になることもあり、銀行融資やでんさい割引と比べて非常に高コストです。
【極端な条件で特に注意したい例】
- 2社間ファクタリングで手数料30%前後を提示される。
- 「審査が緩い代わりに手数料は高め」「どこよりも高く買い取るが、その分手数料も高い」と説明される。
- 具体的な手取り額や総コストの試算を示さず、「◯%〜」という下限のみ強調する。
- 必ず「請求書額100万円のとき、手取りはいくらか」で比較する。
- 手数料+諸費用を合計し、資金を前倒しする日数で年率換算してみる。
- でんさい割引や銀行融資と比べて、極端に高いコストになっていないかをチェックする。
割引率だけでなく、買取率(掛目)や事務手数料、送金手数料などを含めた総コストを数字で把握し、必要であれば複数のサービスや金融機関から見積もりを取り、客観的な比較を行うことが重要です。
偽装ファクタリングと違法スキームの確認
偽装ファクタリングとは、形式上は売掛債権の譲渡(ファクタリング)と称しつつ、実態としては高利の貸付であり、貸金業登録のない業者による違法なヤミ金融に該当するスキームを指します。
金融庁は、いわゆる「給与ファクタリング」について、個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し、実質的に貸付を行う行為は貸金業に該当すると明言し、無登録業者の違法性に注意喚起しています。
事業者向けの偽装ファクタリングでも、「債権額に比べ著しく低額な買取代金」「回収リスクを買い手が負わず売主に買戻し義務を負わせる」「高額な手数料を事実上の利息として徴収する」といった特徴が共通して見られます。
違法・不適切なスキームを見分ける際には、次のような観点から確認することが有効です。
- 契約の実態
- 売掛先が倒産・不払いになった場合でも、理由を問わず利用者が全額買い戻す義務を負う。
- 契約書上は「債権譲渡」となっているが、条文を読むと元本+高利息を返済する金銭消費貸借に近い構造になっている。
- 事業者の属性
- 貸金業登録番号の表示がなく、登録の有無を尋ねても明確な回答が得られない。
- 「借金ではありません」「ブラックでもOK」「審査なし」など、金融庁が危険性を指摘する誘い文句を用いている。
- 売掛先が支払えない場合でも、常に利用者が全額負担する契約(ノンリコースと称しつつ実質フルリコース)。
- 年率換算すると出資法の上限を大きく超えるような負担になっている。
- 「借金ではない」と強調しつつ、返済スケジュールや遅延損害金の設定が貸付そのものになっている。
こうした特徴が見られる場合は、条件の妥当性以前に、スキーム自体が違法または極めて不適切である可能性が高いため、契約前に必ず金融庁・日本貸金業協会・弁護士などに相談し、その業者との取引を避けることを含めて検討する必要があります。
金融機関・専門家への相談と比較検討手順
でんさい割引やファクタリングの利用を検討する際には、自己判断だけで決めず、金融機関や専門家、公的な相談窓口を活用しながら比較検討を進めることが推奨されます。
金融庁は、高額な手数料のファクタリングや悪質な取立てに関する相談先として、金融サービス利用者相談室、多重債務相談窓口、警察相談専用電話(#9110)などを案内しており、違法・不適切な取引が疑われる場合は早めに相談するよう呼びかけています。
一方、中小企業庁や経済産業省は、認定経営革新等支援機関や商工会・商工会議所を通じて、中小企業の資金繰りや資金調達に関する相談窓口を設けており、売掛債権や電子記録債権を活用した資金調達の選択肢についても助言を行っています。
比較検討の基本的な手順としては、次のように進めると整理しやすくなります。
- 1. 自社の資金繰り表を作成し、「いつ」「いくら」不足しそうかを明確にする。
- 2. 自社の売掛構成(でんさい・手形・売掛金)と取引先の信用力、銀行との取引状況を整理する。
- 3. メインバンクなどに相談し、でんさい割引・手形割引・短期融資・売掛債権担保融資などの条件を聞く。
- 4. ファクタリング会社からも見積もりを取り、買取率・割引率・諸費用・リコースの有無を確認する。
- 5. 各手段について、「100万円を◯日間前倒しした場合の手取り・総コスト・年率換算」を並べて比較する。
- 6. 不安があれば、認定支援機関や弁護士・税理士などに契約内容の妥当性を相談する。
- 銀行・ファクタリング会社・公的機関など、複数の窓口から情報を集める。
- 数字(手取り額・総コスト・年率換算)で比較し、「なんとなく安そう」に頼らない。
- 契約書のリスク条項(償還義務・違約金)を理解できない場合は、必ず専門家に確認してもらう。
このように、でんさい割引とファクタリングを安全に選択・活用するためには、「極端な条件を避ける目」と「スキームの適法性を確かめる目」、そして「第三者の助言を求める習慣」の三つを持つことが重要です。
まとめ
ファクタリングとでんさい割引は、どちらも売掛金や電子記録債権を活用した資金調達手段ですが、「何を現金化するか」「誰が貸倒リスクを負うか」「費用の出方」が異なります。
でんさい割引は銀行取引や与信が前提となる一方、ファクタリングはスピードと柔軟性に優れますがコストは高くなりがちです。
本記事で整理した、割引率・手数料の相場、償還リスク、活用が向くケース、極端な割引条件や偽装ファクタリングへの注意点を踏まえ、まずは自社の資金繰り表と売掛構成を確認したうえで、複数の金融機関・サービスの見積もりを比較しながら、無理のない調達方法を選ぶことが重要です。