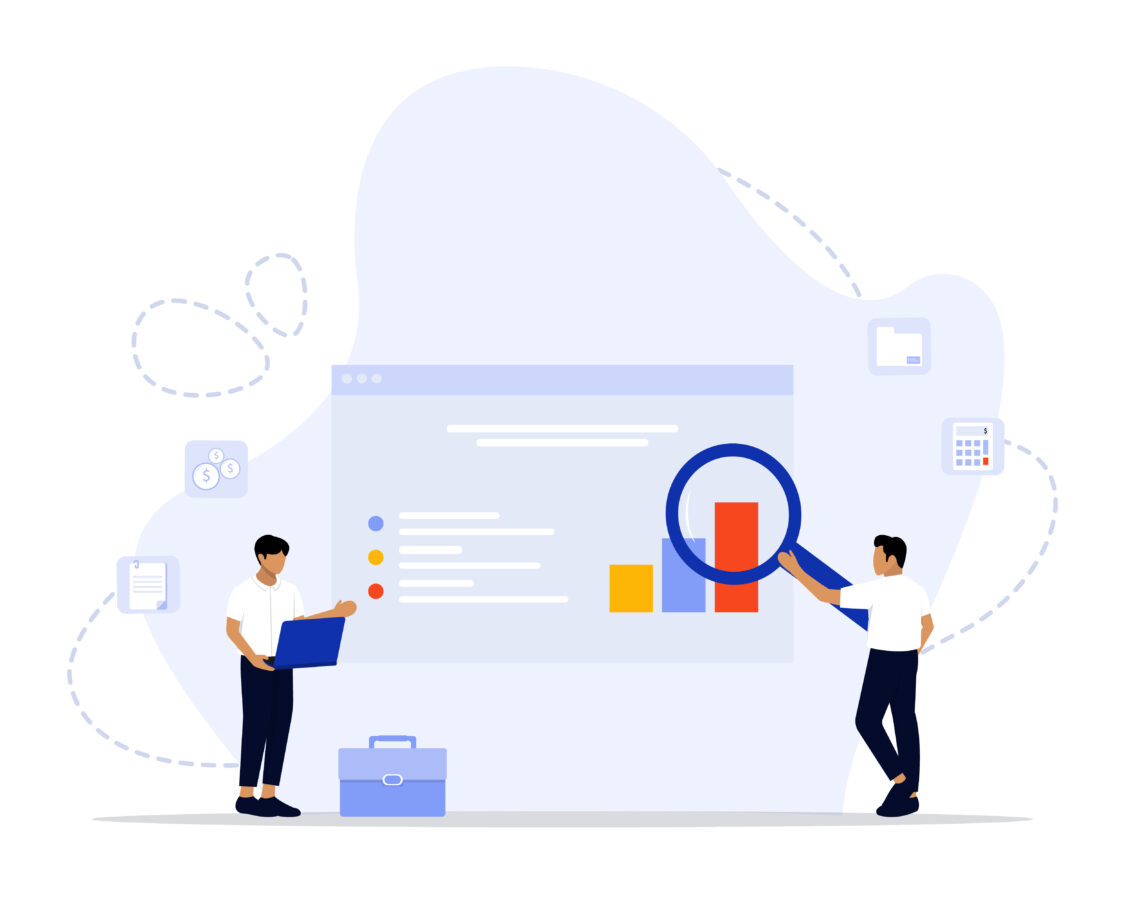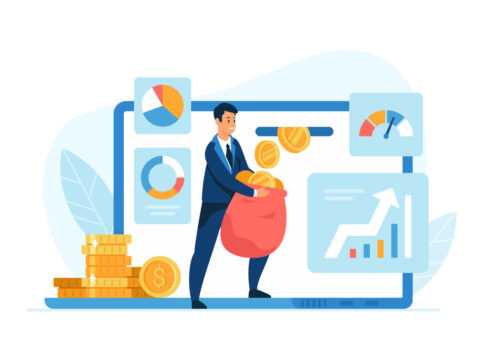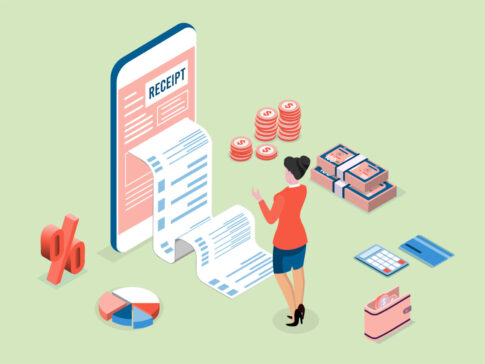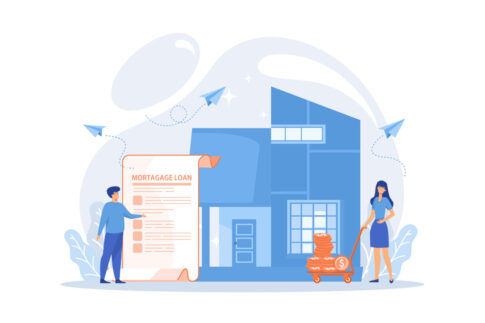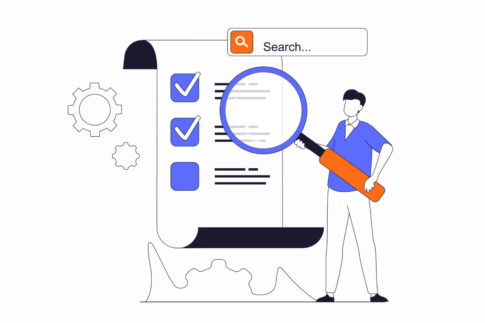長い支払サイトで資金繰りが逼迫しがちな建設業。その打開策として注目されるのが「即日ファクタリング」です。本記事では、売掛債権を当日現金化する仕組み、2社間・3社間別の手数料相場、安全なサービス選定ガイドライン、導入ステップまでを一次情報中心に網羅。
銀行融資を待たずに運転資金を確保し、工事進行や外注費の支払いを滞らせない実践的メリットを解説します。
目次
ファクタリングとは?建設業が即日資金調達できる仕組み
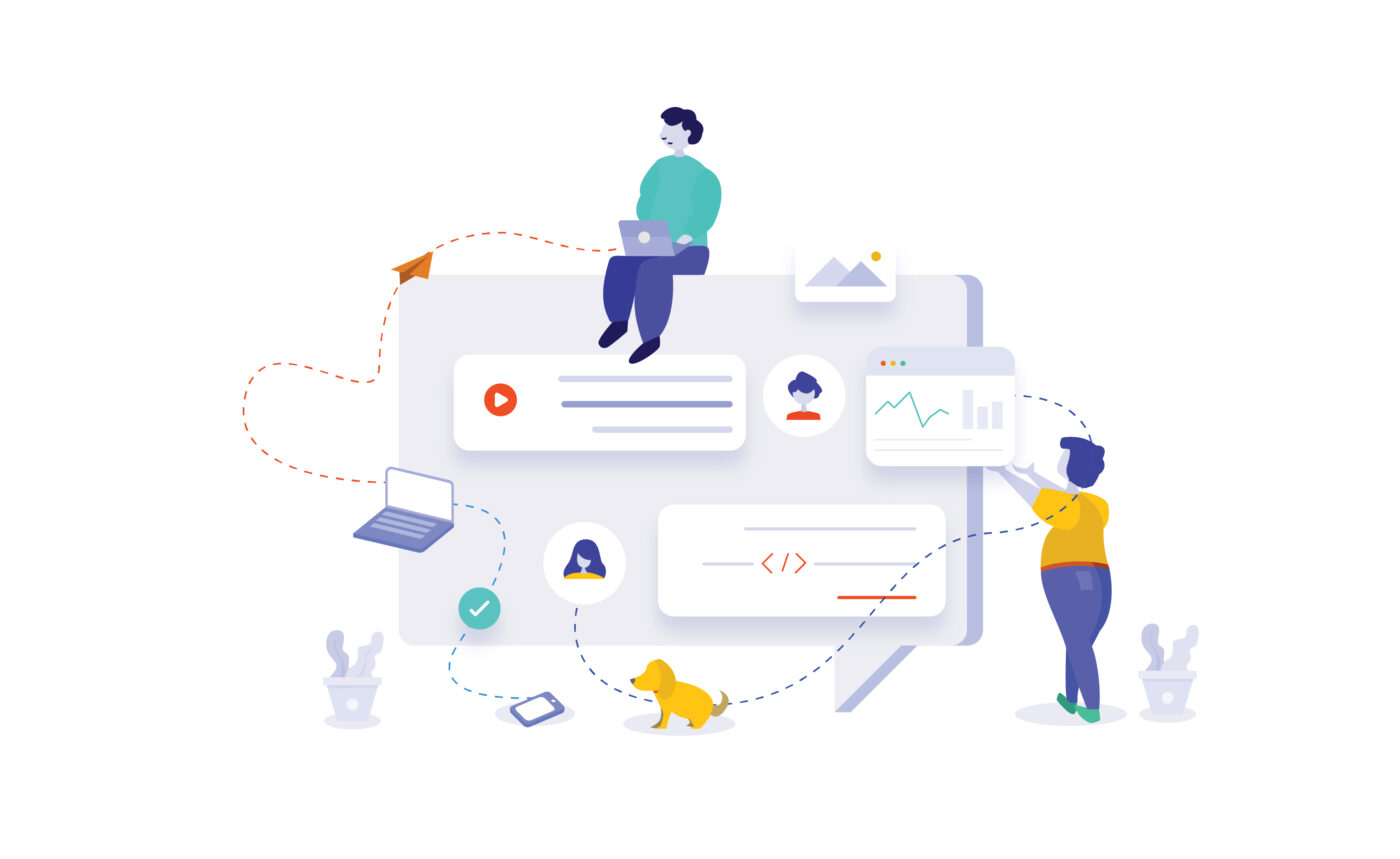
建設業では、完成後の代金が入金されるまで数か月を要する長期支払サイトが一般的です。その間に材料費や外注費が先行して発生するため、キャッシュフローが枯渇しやすいのが実情です。
ファクタリングは、この「未回収の請求書(売掛債権)」を金融機関や専門会社に売却し、資金を前倒しで受け取るサービスです。銀行融資と異なり、審査は債務者(取引先)の信用力を重視するため、赤字決算や税金滞納があっても利用しやすいのが特徴です。
中小企業庁の資金繰り支援ガイドでも、短期の資金需要に対応する手段としてファクタリングを紹介しています。さらに近年はオンライン完結型のサービスが増え、最短即日で入金可能なスキームが整いつつあります。
工事中の資金ショートを防ぎ、外注先への支払い遅延や材料購入ストップを避けるための実務的な選択肢として注目されています。
- 借入金ではないため負債計上されず、銀行与信枠に影響しにくい
- 売掛先の与信が高いほど手数料が抑えられ、即日入金も可
売掛債権を現金化する基本手順
ファクタリングの申し込みは、原則として「請求書が確定している工事案件」が対象になります。
サービスを利用する際は、請求書だけでなく工事請負契約書や発注書の写しを用意しておくと審査がスムーズに進みます。ここではオンライン型サービスを想定した標準的な流れをまとめます。
【手順】
- Webフォームから会社情報・取引先情報・請求書をアップロードする
- ファクタリング会社が取引先の信用力を確認し、買取額と手数料率を提示
- 条件を承認後、電子契約または対面で債権譲渡契約を締結
- 即日〜翌営業日に買取代金が指定口座へ入金
- 売掛金の入金期日に取引先がファクタリング会社へ支払い、取引完了
2社間と3社間の違いと即日性への影響
請求書買取の方式は「2社間」と「3社間」の2種類があります。違いを理解することで、希望するスピードとコストのバランスを取りやすくなります。
| 項目 | 2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング |
|---|---|---|
| 取引先への通知 | 不要(非通知) | 必要(譲渡通知または承諾) |
| 手数料率 | 5〜15%程度 | 1〜5%程度 |
| 入金スピード | 最短即日 | 2〜3営業日 |
| 信用リスク | 取引先未払い時に償還請求あり | 取引先支払い義務明確でリスク低 |
電子記録債権(でんさい)による取引の拡大
電子記録債権(でんさい)は紙の手形に代わるデジタル債権で、オンラインで譲渡・割引が可能です。建設業でも「でんさいネット」を利用した支払いが増加しており、ファクタリング会社が電子記録債権を即日買取するサービスも登場しています。
紙手形の郵送や裏書が不要なため、事務負担と郵送コストを大幅に削減できる点がメリットです。一方で、システム利用料や登録手数料が発生するほか、誤登録時の訂正に時間を要する場合があります。
- 利用には取引先も「でんさいネット」への参加登録が必要
- 登録ミスを防ぐため、取引先名や支払期日を必ず再確認する
建設業がファクタリングを選ぶ理由とメリット・デメリット

建設業では、工事完了から請求書発行、さらに取引先の支払期日までに平均60〜120日を要します。その間に資材費や下請けへの支払いが先行し、黒字倒産のリスクが高まります。銀行融資でつなぐ方法もありますが、決算書審査や担保設定に時間がかかり「すぐに現金が欲しい」というニーズには対応しづらいのが実情です。
こうした背景から、請求書を売却して即日現金化できるファクタリングが注目されています。とくに2社間ファクタリングは取引先へ通知しないため関係性を損ねにくく、前払い金制度のない公共工事や民間工事でも柔軟に活用できます。
一方で、手数料が銀行利息より高いことや、債権譲渡登記で外部に資金繰り状況が露見するリスクも無視できません。導入の可否は「資金ショートの回避が優先か」「コストを抑えたいか」という経営判断に直結します。
【メリット・デメリット】
- メリット:
・担保・保証人不要で当日現金化でき、工期遅延を防げる
・負債計上されないため銀行与信枠を温存できる
・赤字決算や税金滞納があっても利用審査に通りやすい - デメリット:
・手数料が取引額の5〜15%(2社間)と高めに設定される
・債権譲渡登記が必要な場合、取引先に資金難と受け取られるおそれ
長期支払サイトが招く資金繰り課題
建設業の支払サイトは、元請→協力会社→職人へと多重構造になっているため、一次請負が120日、二次請負が150日と伸びるケースも珍しくありません。
その間に公共料金や社会保険料の納付、材料費の値上がりが重なると、受注量が増えるほどキャッシュアウトが先行し、いわゆる「売上成長倒産」に直面します。
さらに手形決済の場合、期日まで現金化できず、裏書譲渡も取引先の信用に影響を与えるため利用しにくいのが実情です。ファクタリングはこうした時間差を埋める即効性の高い資金調達手段として機能し、未払い賃金トラブルや部材納入の停滞を防ぎます。
【資金繰り悪化の主な要因】
- 長期サイトによる売掛金滞留額の増大
- 材料高騰による仕入コストの先行負担
- 公共工事の出来高払いに伴う入金遅延
- 追加工事発生時の一時的キャッシュアウト
即日入金スピードと手数料相場を数値で比較
ファクタリングのコスト構造は「スキーム」と「取引先の信用力」で大きく変動します。以下の早見表は、中小建設業者が1,000万円の請求書を売却した場合の平均値をまとめたものです(手数料率は各社公開データの中央値)。
| スキーム | 入金までの目安 | 手数料相場 |
|---|---|---|
| 2社間 | 申込み当日〜1営業日 | 5〜15%(平均8%) |
| 3社間 | 2〜3営業日 | 1〜5%(平均3%) |
2社間は非通知でスピードが優れる一方、未回収リスクが高いため手数料が上がります。3社間は取引先の承諾が必要で時間を要しますが、支払確約が得られる分だけ低コストです。
自社が「即日着金を最優先」するか、「コスト削減を重視」するかで最適解が変わるため、複数社へ同時見積もりを取り入金スケジュールとコストをシミュレーションすることが欠かせません。
債権譲渡登記や信用リスクなど注意点
ファクタリング契約では、一定額を超える買取や継続利用の場合、債権譲渡登記が求められることがあります。登記費用は取引額に関係なく約7,000円(登録免許税+オンライン申請手数料)ですが、登記情報は誰でも閲覧可能なため、元請や金融機関に資金繰り難を推測されるリスクがあります。
また、2社間スキームでは取引先が倒産・支払拒否した場合、ファクタリング会社からの償還請求により自社負担が発生する点にも注意が必要です。事前に契約書の「買取債権の遡及責任条項」を確認し、リスクの所在を明確にしておきましょう。
- 債権譲渡登記の要否・費用と情報開示範囲
- 償還請求(リコース)条項の有無
- 手数料率以外の事務手数料・印紙代など付随コスト
- 取引先からの問い合わせ対応フロー
スキーム別の費用・入金スピード比較【早見表】

建設業で利用されるファクタリングは、大きく「2社間」と「3社間」の2スキームに分かれます。どちらを選ぶかで手数料率や着金までのスピードが大きく変わるため、「今日は材料代を払いたい」「来週の給与資金を確保したい」など自社のキャッシュフロー計画に合わせた選択が欠かせません。
ここでは主要ファクタリング会社の公開データをもとに、平均的なコストと入金目安を整理しました。2社間は非通知で利用しやすい反面、未回収リスクが高く手数料が上振れしがちです。
一方、3社間は取引先の承諾が必要な分スピードは劣るものの、支払確約が得られるため低コストで資金化できます。サービス選定時は、手数料率だけでなく「資金が必要なタイミング」と「リスク許容度」をセットで比較すると失敗を防げます。
| スキーム | 手数料相場 | 最短入金目安 |
|---|---|---|
| 2社間 | 8〜20%(中央値12%) | 申込み当日〜翌営業日 |
| 3社間 | 1〜9%(中央値4%) | 2〜3営業日 |
2社間ファクタリングの平均手数料・必要書類
2社間ファクタリングは取引先へ譲渡通知を行わないため、関係維持を優先する建設会社に人気があります。
ただしリスクが高いぶん手数料は3社間より高めに設定され、買取額の8〜20%が一般的です。とくに一次下請けで売掛先が中小企業の場合は数字が上振れしやすく、事前に複数社で見積もりを取ることが重要です。
審査時に求められる書類は少なく、オンライン型サービスでは「請求書PDFと通帳コピー」で完結するケースもあります。以下の表に、平均手数料帯と主要書類の組み合わせをまとめました。
| 提出書類 | ポイント |
|---|---|
| 請求書 | 工事名・入金期日が確定しているもの。電子データ可 |
| 工事請負契約書 または注文書 |
成因資料として提出。金額・工期・契約当事者を確認 |
| 直近の通帳コピー | 取引先からの入金実績を確認し、信用補完に使用 |
| 身分証明書 | 代表者または個人事業主の場合は運転免許証など |
3社間ファクタリングのコストと審査ポイント
3社間ファクタリングは、取引先が債権譲渡に同意することで未回収リスクが大幅に下がり、手数料は1〜9%に圧縮されます。また、買取限度額が高く設定される傾向にあるため、1件あたり数千万円規模の大型案件にも向いています。
ただし、取引先が譲渡通知を承認しない場合は利用できず、公共工事など契約変更が煩雑な現場では手続きが停滞しやすい点に注意が必要です。
審査では「取引先の財務内容」と「過去の支払遅延履歴」が重視されるため、取引先が上場企業や官公庁であれば、手数料の下限付近まで交渉できる可能性があります。
- 手数料:大手ゼネコン請求の場合は1〜3%台まで低減するケースも
- 入金スピード:通知・承諾手続きが電子化されていれば2営業日で着金
- 審査書類:請求書・契約書に加え、発注者側の承諾書を提出
- メリット:登記不要で済むケースが多く、外部に資金繰りを知られにくい
- デメリット:承諾を得るプロセスで社内稟議が長期化するリスク
建設業特化サービス(注文書対応型・前払い型)の特徴
建設業の実務では、まだ請求書が発行できない工事序盤でも資金が必要になる場面が多々あります。そのギャップを埋めるのが「注文書対応型」や「前払い型」と呼ばれる建設業特化サービスです。
注文書対応型は、発注段階の注文書を根拠に買取判断を行うため、材料購入費や着手金を即日確保できる点が魅力です。一方、前払い型は出来高に応じて段階的に資金を受け取る方式で、長期工期案件のキャッシュフローを平準化できます。
- 請求前でも資金化できるため、材料高騰局面でも機動的に発注可能
- 工事進行割合に応じた分割入金で、資金使途を工程別に管理しやすい
これら特化型サービスでは、注文書の真正性や工事進捗を示す工程写真の提出が求められることがあります。導入時は現場管理体制や工程管理ソフトとの連携可否を確認し、提出書類のデジタル化を進めておくと審査が短縮されます。
さらに、公共工事では出来高払い制度と併用することで、手数料を抑えながら安定的に資金を確保することも可能です。
安全なファクタリング会社の見極め方

ファクタリングは即日で資金を得られる半面、手数料の不透明さや取引条件の偏りによるトラブルが少なくありません。特に建設業では取引額が高額になるため、契約先の信頼性は資金繰り以上に重要です。
まず前提として確認したいのが、中小企業庁の「資金繰り支援ガイドライン」および金融庁が定める貸金業法の適用範囲です。業法に基づき登録を受けた業者は、手数料率や契約条件の開示が義務付けられています。
さらに、債権譲渡登記の要否や償還請求条項(リコース)の有無が明示されているかどうかで、万が一の支払遅延時に自社が負担するリスクを把握できます。
複数社から見積もりを取得し、提示された手数料率だけでなく「内訳」と「遡及責任の範囲」を比較することで、適正価格を判断しやすくなります。
- 貸金業登録番号をホームページで公開しているか
- 手数料率の内訳(買取手数料・事務手数料など)が明示されているか
- 債権譲渡登記や償還請求の条件が契約書で明文化されているか
中小企業庁ガイドラインと貸金業法のチェックリスト
中小企業庁は2023年に「中小企業向けファクタリング活用に関するガイドライン」を公表し、利用者保護の観点から7つの確認事項を示しました。
貸金業法では、資金提供を伴う債権買取事業者に対し登録と監督が義務付けられています。以下のチェックリストを満たしているかを事前に確認することで、法令順守度合いを把握できます。
| 確認項目 | ガイドライン要点 | 実務確認方法 |
|---|---|---|
| 登録確認 | 貸金業者登録番号の掲示義務 | 金融庁データベースで番号照合 |
| 手数料開示 | 総手数料と内訳を契約前に提示 | 見積書の内訳欄を保存 |
| 契約書交付 | 債権譲渡登記・償還請求の有無を明示 | 条項番号を確認し不明点は質疑 |
登録番号・手数料開示・契約書確認の必須ポイント
安全性を見極めるうえでまず着目すべきは「金融庁登録番号」です。登録の有無は直接金融庁サイトで調べられ、番号が一致しない場合は利用を避けるべきです。
また、見積書の手数料欄に「買取手数料◯%」「事務手数料◯円」など内訳が明示されていない場合は、後から追加請求が発生するリスクがあります。契約書では償還請求条項の範囲と債権譲渡登記の要否を必ず確認しましょう。
とくに2社間ファクタリングで登記が必要な場合、取引先や金融機関に資金繰りが伝わる可能性があります。登記不要を選ぶか、登記情報の範囲と公開期間を短縮できるかを交渉することがポイントです。
- 登録番号は「第◯◯号」と末尾まで記載されているか確認
- 見積書の総費用=手数料率×請求額+事務手数料+登記費用で計算
- 契約書の償還責任条項に「ノンリコース」と明記されているかチェック
小規模事業者持続化支援など公的制度との併用可否
ファクタリングを導入する中小建設業者は、国の「小規模事業者持続化補助金」や地方自治体の利子補給制度と組み合わせて資金負担を軽減できます。
ただし、補助金は「負債性資金調達とみなされる取引」が対象外となる場合があるため、事前に事務局へファクタリング契約書を提示して適否を確認することが重要です。
金融機関の保証付き融資と同時に利用する場合は、譲渡登記により保証契約が制限されるケースもあるため、取扱銀行へ相談しておくとトラブルを防げます。
- 補助金交付要領で「債権譲渡取引」の可否を確認
- 地方自治体の利子補給制度はファクタリング手数料を補填対象としない例が多い
- 銀行保証付き融資がある場合、譲渡登記の優先順位を事前調整
導入手順とモデルケース

ファクタリングを実際に導入する際は「準備→申込→着金→運用改善」という4段階を押さえることで、手数料と時間のロスを最小限に抑えられます。特に建設業は請求金額が大きく、追加工事や出来高払いが絡むため、書類の不備があると審査が長引きかねません。
まずは請求書・工事契約書・決算書の最新データをデジタル化し、PDFで即提出できる体制を整えておくことが重要です。
次に、オンライン完結型サービスを選ぶことで、担当者の移動時間や押印手続きを削減し、スピード着金を実現できます。
また、着金後は資金の流れを可視化し、どの工程で再度資金が不足するかを早期に把握することで、ファクタリングの再利用タイミングを計画的に設定できます。以下の流れを参考に、自社のキャッシュフロー計画に組み込んでみましょう。
【導入手順】
- 必要書類をスキャンしクラウド保存
- 複数社に同時見積もりを依頼し、手数料と着金スピードを比較
- 条件を確定後、電子契約で債権譲渡契約を締結
- 着金後は資金使途を工程別に管理し、再利用時期をシミュレーション
事前準備(請求書・工事契約書・決算書)のチェックリスト
スムーズに審査を通過するためには、提出書類に漏れがないかを確認することが最短着金への近道です。
特に公共工事やJV案件では契約形態が複雑になるため、成因資料として「注文書」と「工事請負契約書」の両方が求められるケースがあります。以下のチェックリストを参考に、申込前に書類を整理しましょう。
【チェックリスト】
- 請求書:工事名・締切日・支払期日が明記され、電子押印または取引先印があるか
- 工事請負契約書:契約当事者・金額・工期が一致しているか
- 注文書または発注書:増減工事分を含めた最新金額になっているか
- 決算書:直近期の貸借対照表・損益計算書をPDF化済みか
- 通帳コピー:取引先からの入金実績が確認できるページを選択したか
- 身分証明書:代表者の運転免許証またはマイナンバーカードを用意したか
これらをクラウドストレージにまとめて保管しておけば、ファクタリング会社から追加提出を求められても即応でき、結果として手数料の交渉余地も広がります。
オンライン申込〜資金着金までのタイムライン【年商5,000万円例】
年商5,000万円・請求書額300万円の中小建設業者がオンライン型2社間ファクタリングを利用した場合を想定し、申込から着金までの具体的な所要時間をまとめました。
| 工程 | 具体的な作業 | 要時間 |
|---|---|---|
| 書類提出 | Webフォームに会社情報登録・PDFアップロード | 30分 |
| 審査 | 債務者与信と書類突合(自動スコアリング) | 2時間 |
| 見積提示 | 手数料8%・買取額276万円で提示 | 1時間 |
| 電子契約 | クラウドサインで契約締結・即時送信 | 30分 |
| 振込手続き | ネットバンキングで送金指示 | 1時間 |
| 合計 | 申込〜着金まで | 約5時間(最短) |
このように書類が揃っていれば、午前中に申込を完了させ午後には着金を確認できるスピード感が実現します。なお、3社間スキームの場合は取引先承諾が入るため+1〜2営業日を見込んでおくと良いでしょう。
導入後の資金繰り改善シミュレーションと再利用タイミング
ファクタリングで得た資金を漫然と消費すると、次の資金ショートを早めてしまう恐れがあります。導入後はキャッシュインとキャッシュアウトを工程別に可視化し、再度資金が不足するタイミングを予測することが肝要です。
- 着金資金276万円を材料費150万円・外注費100万円・予備費26万円に配分
- 出来高70%時点で再度請求書発行→次回ファクタリング申込を事前予約
- 入金期日と給与支払日を照合し、運転資金ショートをゼロに
実務では、工期が3か月を超える案件で中間請求が立てられない場合、工程50〜60%時点で再利用を前提に動くと資金が途切れにくくなります。
また、複数案件を同時進行する場合は「高手数料でも即日着金が必要な案件」と「低手数料で余裕を持って申込む案件」を分け、平均手数料を圧縮するポートフォリオ運用が効果的です。
財務担当者は毎月のキャッシュフロー計画にファクタリング活用枠を設定し、利用実績と手数料推移をモニタリングすることで、銀行融資やリースとの最適バランスを継続的に見直しましょう。
まとめ
建設業向け即日ファクタリングの仕組み・費用・リスクを一次情報ベースで整理しました。当日入金を実現しつつ信用低下を防ぐ選定チェックリストと導入手順を提示しているため、手数料や登記コストを把握したうえで最短ルートで資金繰りを改善できます。
さらに小規模事業者持続化支援との併用可否や電子記録債権の活用も押さえ、導入後の再利用タイミングもシミュレーションで確認できます。