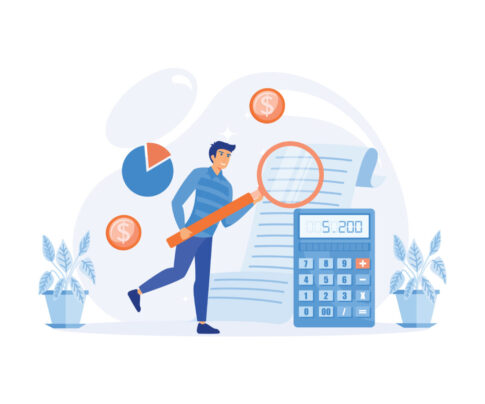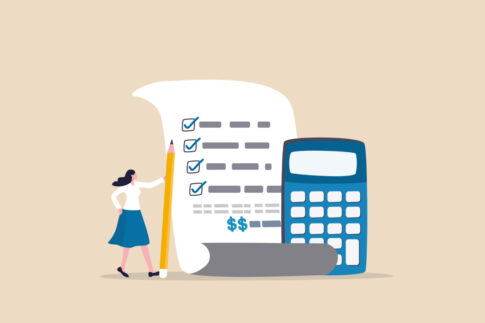公庫融資を検討しても、「必要書類が多くて何から集めるべきか」「創業と運転資金で提出物はどう違うか」「審査で見られるポイントは」「税金・社保の遅れは影響するのか」など不安になりがちです。
この記事では、公庫融資の共通書類と資金使途別の追加書類、提出から面談までの流れ、登記事項証明書や見積書の集め方、創業計画書と資金繰り表の作り方、記載ミスを防ぐチェック、相談先の使い分けまでを整理します。
必要書類の全体像

公庫融資の必要書類は、大きく「申込者の確認」「事業の状況」「資金使途の根拠」の3グループに分けて考えると整理しやすいです。
共通書類で本人・会社情報や直近の業況を確認し、創業・運転資金・設備資金など目的に応じて追加書類で根拠を補います。書類が多く感じるのは、単に枚数が多いからではなく、数字や説明が複数の書類でつながっている必要があるためです。
たとえば運転資金で「仕入が先、入金が後」の理由を説明するなら、請求・入金サイクルが分かる資料と資金繰り表が整合していることが重要になります。
準備は「取り寄せに時間がかかるもの」から着手するのが基本です。登記事項証明書などの公的書類、見積書・契約書など相手先が関わる書類は後回しにすると全体が遅れやすいです。
提出後に追加資料を求められることもあるため、最初から「根拠資料を一式で出す」発想で揃えると手戻りを減らせます。
- 共通書類→資金使途別の追加書類の順で棚卸しする
- 取り寄せに日数がかかる公的書類から先に動く
- 数字の整合を優先し、根拠資料をセットで揃える
- 資金繰り表で「いつ・いくら必要か」を先に確定する
共通書類の一覧ポイント
共通書類は、申込者本人(または法人)と事業実態、直近の業況を確認するために用意します。具体的には、本人確認、法人なら登記情報、事業の収支や税務申告に関する書類が中心になります。
個人事業主は確定申告書がベースになり、法人は決算書や試算表などで業況を示します。ここで重要なのは、提出書類の数字が矛盾しないことです。
たとえば申告書の売上と通帳入金が月次で一致しないのは入金サイトの関係で自然な場合がありますが、その場合は請求の締日と入金日が説明できるようにしておきます。
また、自己資金を示す必要がある場合は、見せ金と誤解されないよう、通帳で残高の推移が説明できる状態にします。
直前に大きな入金がある場合は、その原資(貯蓄、退職金、贈与など)を説明できないと確認が増えやすいです。
| 分類 | 例と確認ポイント |
|---|---|
| 本人・事業確認 | 本人確認、法人の登記情報など。氏名・住所など記載の一致を確認します。 |
| 業況確認 | 申告書・決算書・試算表など。直近の状況が説明できるようにします。 |
| 取引確認 | 通帳の入出金、売掛・買掛の状況など。入金サイトの説明材料にします。 |
資金使途別の追加書類
追加書類は、資金使途(借入金を何に使うか)を裏付けるために用意します。設備資金なら見積書や契約書など「支払先・金額・支払時期」が分かる資料が中心です。
運転資金なら、売上入金までのつなぎであることや、在庫増・外注費増などの理由を説明できる資料が重要になります。
創業の場合は、創業計画書などで事業の内容、売上の作り方、必要資金の内訳を示し、数字の根拠を補強します。
例として、厨房機器の購入に2,000,000円が必要なら、見積書で金額と納期、支払条件を示し、導入後に売上や原価がどう変わるかを計画に落とします。
運転資金で「売掛入金が翌々月、仕入は当月末払い」のために不足するなら、請求書や取引条件、資金繰り表で不足ピークを示し、必要額と必要期間を整合させます。
- 資金使途が曖昧で、必要額の根拠が確認できない
- 見積や契約が未確定で、支払時期が読めない
- 運転資金の必要期間が説明できず、金額が過大に見える
- 計画と資金繰り表がつながらず、返済見通しが不明確になる
電子申請の注意点
公庫融資は申込み方法が複数あり、電子申請を利用できる場合もありますが、書類の提出が不要になるわけではありません。
電子化によって提出の手間は減ることがありますが、添付ファイルの形式、容量、画像の判読性など、別の注意点が出ます。
特に、通帳写しや契約書などは、ページ抜けや解像度不足があると差し戻しや追加提出になりやすく、結果として時間が延びることがあります。
また、電子で提出すると「後で差し替える」ことが難しい場合があるため、提出前に最新版か、署名・押印や記載内容に誤りがないかを確認します。
資金繰りが逼迫している場合は、提出後の追加依頼にすぐ対応できるよう、元データや補足資料(見積の内訳、売上根拠、入金サイト説明など)を手元に揃えておくと安心です。
- 添付ファイルの不足(ページ抜け、両面の見落とし)がない
- 数字や記載が読める解像度で保存できている
- 提出書類が最新版で、記載ミスや不一致がない
- 追加依頼に備えて根拠資料を整理している
申込み手順と提出時期

公庫融資は、書類を出して終わりではなく、提出後に面談(ヒアリング)や追加資料の提出を経て審査が進みます。
そのため、提出時期は「資金が必要な日」から逆算して決めることが重要です。たとえば、月末の支払いに間に合わせたい場合、提出がギリギリだと面談日程が取れず、審査が進みにくくなることがあります。
設備資金のように見積や契約の確定が必要なケースでは、発注・納品・支払のスケジュールも絡むため、資金使途の資料が揃う時点を見込んで動きます。
また、提出後に追加資料が出るとスケジュールが延びやすいので、初回提出で「根拠資料をセットにして出す」意識が有効です。
資金繰り表で不足月を示し、必要額と必要期間を説明できる状態にしておくと、面談での確認事項が減りやすく、手戻りを抑えられます。
- 資金が必要な日から逆算し、面談と追加資料の余裕を確保する
- 資金使途の根拠資料を初回からセットで提出する
- 資金繰り表で不足月と不足額を説明できる状態にする
- 提出後の追加依頼に備え、元資料と補足資料を整理する
提出から面談までの流れ
一般的には、申込み書類の提出後に内容確認が行われ、面談で事業内容や資金使途、返済計画などがヒアリングされます。面談では、書類の数字を暗記するよりも、数字の前提と根拠資料を説明できることが重要です。
たとえば、運転資金なら「なぜ今月資金が不足するのか」「不足はいつまで続くのか」を、入金サイトと支払予定から説明します。設備資金なら「何を買うか」「いつ支払うか」「導入効果は何か」を、見積書と計画でつなげます。
スケジュールのイメージとして、設備投資で来月15日に支払いがある場合、見積書の確定と提出、面談日程の確保、審査結果の連絡、契約手続までを見込む必要があります。
提出後に見積が変更になると再提出が必要になることもあるため、金額や支払条件が確定してから提出する方が手戻りを減らせます。
| 段階 | 確認されやすい内容 |
|---|---|
| 書類提出 | 必要書類の過不足、数字の整合、資金使途の明確さ |
| 面談 | 事業内容、売上の根拠、資金不足の理由、返済の見通し |
| 追加確認 | 見積の内訳、入金実績、通帳の追加ページなど補足資料 |
準備の優先順位の決め方
準備の優先順位は「時間がかかるもの」と「審査の根拠になるもの」から決めるのが合理的です。公的書類(登記事項証明書など)や、取引先が関わる書類(見積書・契約書・発注書など)は、手配してから手元に届くまで日数がかかりやすいため先に動きます。
次に、計画書や資金繰り表のように、自社で作成するが整合が重要な資料を作ります。最後に、提出用に体裁を整え、記載ミスや不足がないかを確認します。
具体例として、運転資金で「月末に外注費800,000円、入金は翌月末」という状況なら、資金繰り表で不足月と不足額を確定し、請求書や入金実績で入金サイトの根拠を揃え、必要額と必要期間を説明できる形にします。
これが曖昧だと、面談での追加質問が増えやすく、結果として時間が延びます。
- 公的書類や取引先書類など、取り寄せに時間がかかるものから着手する
- 資金使途の根拠(見積・契約・請求サイクル)を先に固める
- 計画書と資金繰り表を作り、必要額と返済見通しをつなげる
- 最後に記載ミスと不足を一括で点検する
追加提出が出る場面
追加提出は、書類が足りない場合だけでなく、「説明を補強するため」に求められることがあります。典型例は、売上見込みの根拠が弱い、資金使途の内訳が曖昧、通帳や入金実績の確認が必要、見積書の内訳が不足している、などです。
創業の場合は実績が少ないため、見積・受注見込み・販路の説明資料などが求められやすくなります。
運転資金では、売掛金の入金サイトや支払条件が確認できる資料が追加で求められることがあります。
追加提出が出ると、提出準備と確認に時間がかかり、面談後の審査が止まりやすくなります。回避策として、初回提出で「根拠資料をセットで出す」こと、そして想定問答に合わせて補足資料を用意しておくことが有効です。
- 売上予測や受注見込みの根拠資料が不足している
- 資金使途が「運転資金一式」などで内訳が曖昧
- 通帳のページが不足し、入出金の流れが確認できない
- 見積書の内訳が粗く、支払条件や納期が読み取れない
書類の集め方と作成ポイント

公庫融資の書類準備は、単に「提出物を揃える」だけでなく、審査で問われやすい論点(資金使途の妥当性、返済見通し、事業の継続性)を一つのストーリーとして説明できる形に整えることが重要です。
具体的には、資金使途を裏付ける見積・契約、売上や粗利の根拠、資金繰り表で示す不足月と必要額が矛盾なくつながっている状態を目指します。
また、書類は「取り寄せるもの」と「作成するもの」に分かれます。登記事項証明書などの公的書類は取得に時間がかかることがあるため先に動き、計画書や資金繰り表など自社で作成する資料は、提出前に数字の整合を十分に点検します。
書類の完成度は、面談の質問数や追加提出の有無にも影響するため、初回提出で根拠資料をセットにして出すと手戻りを減らせます。
- 取得に時間がかかる公的書類と相手先書類を先に手配する
- 資金使途の根拠(見積・契約・支払条件)を固める
- 創業計画書と資金繰り表を同じ前提で作り、矛盾を消す
- 提出前に通帳・申告書・計画の数字を突合して整合を取る
登記事項証明書の取得手順
登記事項証明書は、法人の基本情報(商号、所在地、代表者、目的など)を確認するために用いられる公的書類です。
申込みに必要な場合は、提出時点での情報が最新であることが求められるため、申込みが近づいてから取得すると安心です。
取得は法務局で行い、窓口だけでなくオンライン請求や郵送受け取りが可能な場合もあります。取得方法によって受け取りまでの日数が異なるため、面談日程から逆算して手配します。
注意点は、登記情報が現状と一致しているかです。たとえば、移転や代表者変更をしたのに登記が未了の場合、書類上の情報と実態が食い違い、追加確認が増えやすくなります。
また、融資申込みの内容(事業内容や資金使途)と会社目的が大きくズレているように見えると、説明が必要になることがあります。書類を取る前に、会社情報の変更予定がないかも確認しておくと手戻りを減らせます。
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 取得方法の選択 | 窓口・オンライン・郵送のうち、受け取り期限に合う方法を選びます。 |
| 必要通数の確認 | 提出先や追加提出に備え、必要通数を確認します。 |
| 内容チェック | 商号・所在地・代表者・目的などが現状と一致しているか確認します。 |
見積書契約書の揃え方
見積書や契約書は、資金使途の根拠として重要な資料です。設備資金では特に、何を購入し、いつ、いくら支払うのかが明確であることが求められます。
見積書は金額だけでなく、内訳(機器代、工事費、設置費、保守費など)、納期、支払条件(前払・分割・納品後など)が読み取れる形が望ましいです。契約書がある場合は、契約金額や支払スケジュールが見積と一致しているか確認します。
実務の例として、店舗の内装工事で3,000,000円が必要な場合、着手金30%、中間30%、引渡し40%など支払が分割になることがあります。
このとき、資金繰り表に支払日を反映し、借入金の入金タイミングが支払に間に合うように計画します。
見積が未確定の状態で提出すると、金額変更や再提出が起きやすいため、可能な範囲で内容を固めてから提出するのが安全です。
- 見積の内訳がなく、何にいくら使うかが分からない
- 支払条件や納期が記載されておらず、資金の必要時期が不明
- 見積と契約で金額や名義が一致していない
- 付帯費用(設置費、保守費など)が抜けている
創業計画書の根拠づくり
創業計画書は、実績が少ない段階でも「どうやって売上を作り、いくら利益が残り、返済できるか」を示す資料です。根拠づくりの基本は、売上を計算式で説明し、根拠資料で補強することです。
たとえば、月商は「客単価×客数」「商談数×成約率×平均単価」などで組み立て、客数や成約率は過去の職務経験、副業実績、受注見込み、見積案件数などと結び付けます。
例として、月の商談10件、成約率30%、平均単価200,000円なら、月商は600,000円です。ただし開業初月から同水準は難しい場合があるため、初月は半分、3か月目から通常水準といった立ち上がりを月別に置きます。
費用も同様に、固定費(家賃、通信、保険)と変動費(仕入、外注)を分け、売上が下振れしたときに止められる支出があるかを示すと、計画の現実性が上がります。
- 受注見込みや見積一覧(顧客名を伏せた形でも整理)
- 職務経験や過去実績(提供できるサービス範囲の根拠)
- 販路計画(紹介、Web、訪問などの獲得手段)
- 単価の根拠(相場、見積例、料金表)
資金繰り表の作り方
資金繰り表は、入金と支払いのタイミング差を見える化し、いつ資金が不足するかを示す表です。公庫融資では、運転資金の必要額や必要期間の説明に直結するため、月次で作ると整理しやすいです。
作り方は、月初残高を置き、入金(売掛入金、現金売上など)と支出(仕入、外注、家賃、人件費、税金・社会保険料、借入返済など)を並べ、月末残高を計算します。
例として、売掛入金が翌々月末、外注費が当月末の場合、売上が増えるほど売掛金が増えて現金が拘束され、資金不足が先に出やすくなります。
この不足ピーク月と不足額を示し、その穴を埋めるために借入が必要だと説明します。
提出時は、計画書の売上・経費と資金繰り表が同じ前提で作られているかを必ず確認し、納税月や賞与月などの大口支出も入れておくと現実的です。
| 作成項目 | ポイント |
|---|---|
| 入金 | 売上計上ではなく入金日で記載し、入金サイトを反映します。 |
| 支出 | 固定費と変動費に分け、支払日が集中する月を把握します。 |
| 不足額 | 資金が割れる月とピーク不足額を示し、必要額と必要期間につなげます。 |
| 整合 | 計画書・見積・通帳などの数字と矛盾がないか確認します。 |
審査目線の書類チェック

公庫融資の審査では、書類が揃っているかだけでなく「数字がつながっているか」「前提が現実的か」「返済が継続できるか」が確認されます。
提出書類は、申告書・決算書・試算表などの過去実績と、創業計画書や資金繰り表などの将来見通しが混在するため、整合が取れていないと追加確認が増えやすいです。
特に、資金使途(何に使うか)と必要額、必要期間の説明が曖昧だと、金額が過大に見えることがあります。
審査目線での準備は「根拠→数字→資金繰り→返済」の順で確認すると整理しやすいです。売上の根拠が明確で、費用の増減理由が説明でき、資金繰り表で不足月が示され、返済計画に無理がない形になっていれば、面談での説明も一貫します。
- 売上の根拠資料があり、計算式で説明できる
- 資金使途の内訳と支払時期が見積・契約と一致している
- 資金繰り表で不足月と不足額が示され、必要額と一致している
- 返済後も資金残が維持できる前提になっている
売上根拠の示し方基準
売上根拠は「希望」ではなく、計算式と裏付け資料で示すことが基本です。創業の場合は実績がないため、月商を「客単価×客数」や「商談数×成約率×平均単価」で組み立て、客数や成約率の根拠を、見積案件、受注見込み、紹介ルート、過去の職務経験などと結び付けます。
既存事業の運転資金なら、直近の売上推移を起点に、増減の理由(新規販路、値上げ、季節要因など)を説明します。
例として、Web制作で平均単価300,000円、月の商談10件、成約率30%なら月商は900,000円です。ただし、初月から同じ水準は現実的でない場合があるため、初月は半分、3か月目から通常水準といった立ち上がりを月別に置くと前提が明確になります。
売上が増える計画なら、外注費や仕入、人件費など関連費用も同じ月から増える形にして、資金繰り表とつなげます。
| 根拠の種類 | 示し方の目安 |
|---|---|
| 件数根拠 | 商談数、問い合わせ数、既存顧客数、紹介ルートなどを整理します。 |
| 単価根拠 | 料金表、見積例、相場感、過去の取引実績などで説明します。 |
| 成約根拠 | 過去の成約率、経験値、提案プロセスの現実性を示します。 |
返済計画との整合チェック
返済計画は、利益が出るかだけでなく、返済後も資金が残るかで見られやすいです。ここで重要なのは、損益計画(利益)と資金繰り表(現金)の違いを埋めることです。
売上は計上されても入金は後になることがあり、費用は計上と支払いがずれることがあります。返済計画が利益だけを前提にしていると、納税月や仕入増の月に資金が割れる可能性が出ます。
例として、月の利益が200,000円あっても、売掛金が増えて入金が遅れる月は現金が減りやすいです。
そこに毎月の返済80,000円と、四半期の納税200,000円が重なると資金が不足することがあります。
資金繰り表に返済額と大口支出を入れ、月末資金残が最低ラインを割らないかを確認します。返済期間を延ばして月々を抑えるか、資金使途を見直して必要額を最適化するかなど、整合が取れる形に調整します。
- 利益は出る計画だが、売掛回収までの資金拘束が織り込まれていない
- 納税・社保・賞与など大口支出月が資金繰り表に入っていない
- 借入金の入金時期と支払時期がずれ、資金が足りない月が出る
- 返済額を下げるために期間を延ばし、総返済負担が増える
税金社保の確認ポイント
税金や社会保険料の状況は、信用面と資金繰りの両面で確認されやすい項目です。未納や遅れがある場合は、隠すのではなく、対象(税目・保険料)、金額、発生時期、原因、相談状況を事実ベースで整理します。
遅れがあるときは、分納や猶予などの相談を進め、支払い見通しを資金繰り表に反映して返済と両立できる形にします。
また、税・社保は「まとめて支払う月」があるため、資金繰り表に入れていないと返済余力が過大に見えやすいです。
たとえば、消費税や所得税、社会保険料の支払いが集中する時期に、運転資金の借入と返済が重なると資金が詰まりやすくなります。
税・社保の支払い予定を入れたうえで、資金が割れない返済計画になっているかを点検します。
- 未納がある場合の対象と金額、発生時期の整理
- 相談状況(分納等の方向性)と支払計画の整理
- 資金繰り表への反映(支払月を落とす)
- 再発防止策(支払優先順位、固定費見直し、回収改善)
記載ミス防止の注意点
記載ミスは、審査の印象を下げるだけでなく、確認に時間がかかりスケジュールが延びる原因になります。
多いのは、氏名・住所・事業所所在地の不一致、金額の転記ミス、税抜税込の混在、提出書類の年度違い、見積と計画の金額不一致などです。
特に、計画書・資金繰り表・見積書は数字が連動するため、どこか一つでもズレると説明が崩れます。
防止策として、提出前に「共通情報の統一」と「数字の突合」を行います。たとえば、売上・粗利・固定費の前提が計画書と資金繰り表で一致しているか、借入金の入金月と支払月が合っているか、返済額が資金繰り表に反映されているかを点検します。
最後に、通帳や申告書など一次資料と照合し、客観的に説明できる状態に整えます。
| ミスの種類 | 防止の観点 |
|---|---|
| 基本情報 | 氏名・住所・代表者名・口座名義などを全書類で統一します。 |
| 金額 | 税抜税込、単位、転記ミスを見直し、見積・計画・資金繰りで突合します。 |
| 年度・期 | 提出する期の書類が最新か、欠落がないかを確認します。 |
| 添付漏れ | ページ抜けや両面の見落としがないか、提出前に一覧で確認します。 |
個人事業主と創業の提出注意

個人事業主や創業期の申込みでは、法人や既存事業より「実績の裏付け」が薄くなりやすい分、書類の整合と説明の筋がより重視されます。
特に開業前は、決算書や十分な入金実績がないため、創業計画書の根拠資料(見積、受注見込み、販路、経験)と、必要資金の内訳(設備・運転資金)を丁寧に揃える必要があります。
開業後は、申告書や売上の実績資料が出てくる一方、入金サイトのズレや季節要因で数字がぶれやすく、説明不足だと追加確認が増えがちです。
また、個人事業主は家計と事業のお金が混在しやすく、返済原資の説明が曖昧になりやすい点に注意が必要です。
資金繰り表で入金と支出を整理し、生活費と事業費を分けて管理できる状態にしておくと、審査側の理解が進みやすくなります。
- 開業前は計画の根拠資料を厚くし、開業後は実績との整合を取る
- 自己資金は通帳で推移を示し、原資を説明できる状態にする
- 家計と事業の支出を区分し、返済原資を明確にする
- 不足月と必要額を資金繰り表で示し、必要期間を説明する
開業前後の書類の違い比較
開業前は「実績がない」ことを前提に、事業の実現可能性と資金使途の妥当性を計画で示します。売上の根拠は、客単価・件数・成約率などの計算式に落とし、受注見込みや見積案件、販路の具体性で補強します。
設備資金がある場合は見積書で支払先・金額・支払時期を示し、運転資金が必要なら入金までのつなぎ期間と不足額を資金繰り表で説明します。
開業後は、売上や入金の実績が出てくるため、直近の状況を説明できる資料が重要になります。一方で、開業直後は月次の振れ幅が大きく、売上計上と入金が一致しないこともあるため、請求締日と入金日、支払日の関係を整理しておきます。
例として、開業後3か月は月商が200,000円→600,000円→900,000円と伸びている場合、立ち上がりの要因(販路が整った、紹介が増えたなど)を説明し、資金繰り表にも反映させます。
| 区分 | 開業前 | 開業後 |
|---|---|---|
| 中心資料 | 創業計画書、見積・契約、資金繰り表 | 申告・実績資料、通帳入出金、直近の売上推移 |
| 売上根拠 | 計算式と見込み資料で補強 | 実績推移+増減理由の説明 |
| 注意点 | 根拠が薄いと追加確認が増えやすい | 入金サイトのズレや季節変動の説明が必要 |
自己資金の証明方法
自己資金は、資金管理の状況や、事業に投入できる余力を示す材料として扱われやすいです。証明の基本は、通帳等で残高と入出金の推移を示し、資金がどのように形成されたかを説明できる状態にすることです。
直前に大きな入金がある場合は、原資が説明できないと確認が増えやすいため注意が必要です。
例として、自己資金500,000円を用意している場合、通帳で数か月以上の残高推移が確認できれば説明がしやすいです。
一方、申込み直前に500,000円が入金されていると、借入や一時的な資金移動と誤解される可能性があるため、資金の出所(貯蓄、退職金、贈与など)と、返済義務の有無を含めて説明できる準備が重要です。
自己資金は金額だけでなく、見せ方で評価がぶれやすいので、推移が分かる形に整えます。
- 申込み直前の大口入金の原資が説明できない
- 複数口座を行き来しており、残高推移が追いにくい
- 生活費の引出が多く、事業投入可能額が見えない
- 資金の一部が借入で、自己資金と混同される
家計と事業の区分ポイント
家計と事業の区分は、資金繰りの説明と返済の見通しに直結します。混在していると、売上入金があっても生活費で消え、返済原資が不明確に見えやすくなります。
区分の基本は、口座を分けるか、少なくとも事業用口座から生活費を定額で振り替えるなど、資金の流れを固定化することです。
例として、毎月の生活費を200,000円に定め、事業用口座から生活用口座へ毎月一定日に振り替える運用にすると、事業側に残る資金が把握しやすくなります。
さらに、支払サイトが長い業種では、入金が遅れる月に生活費を取りすぎると資金ショートにつながりやすいので、資金繰り表で最低残高の目安を置き、割り込まないように管理します。
- 事業用と生活用の口座を分ける、または生活費を定額振替にする
- 家賃・保険・通信など固定費を事業費と生活費で整理する
- 税・社保の支払い月を資金繰り表に入れて資金残を確認する
- 返済原資がどこから出るかを資金繰り表で説明できる形にする
相談先の使い分け目安
創業・個人事業主の申込みは、計画作成、税務、資金繰り、制度要件の確認が同時に必要になることが多いため、相談先を役割で分けると効率的です。
申込み書類の書き方や要件確認は窓口、創業計画書や資金繰り表の作成は支援機関、税金・社会保険料の整理は税理士や関係窓口、といった形です。
相談前に、必要資金の内訳、見積・契約の状況、売上の根拠資料、資金繰り表、自己資金の通帳推移を揃えておくと、どの部分が不足しているかが明確になり、追加提出や修正の手戻りを減らせます。
- 必要資金の内訳(支払先・金額・支払時期)
- 見積書・契約書・受注見込み資料
- 創業計画書の前提(単価・件数・成約率など)
- 資金繰り表(向こう6〜12か月)
- 自己資金の通帳推移と原資の説明メモ
まとめ
公庫融資の必要書類は、本人・会社確認の共通書類に加え、創業や運転資金など資金使途に応じた追加書類が求められるため、提出時期から逆算して優先順位を付けて準備することが重要です。
審査では売上根拠と返済計画の整合、資金繰り表での資金不足理由、税金・社保の状況が確認されやすいので、根拠資料を揃えて説明できる形にします。
開業前後で書類が変わる点にも注意し、早めに窓口や専門家へ相談して手戻りを減らします。