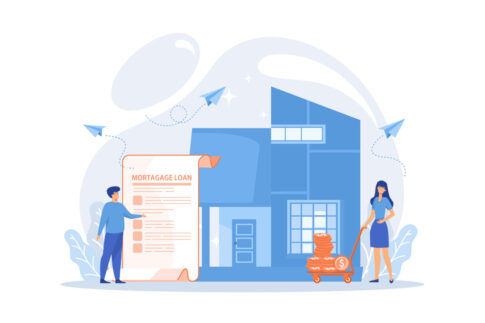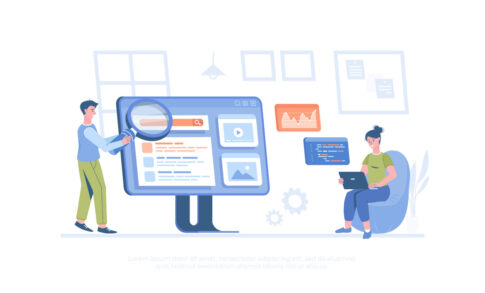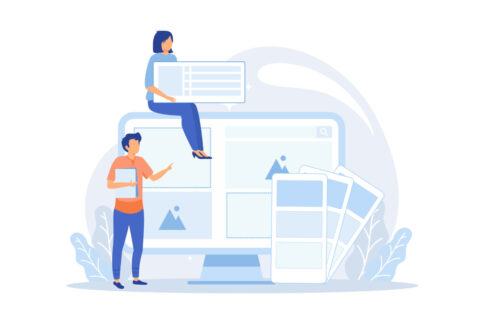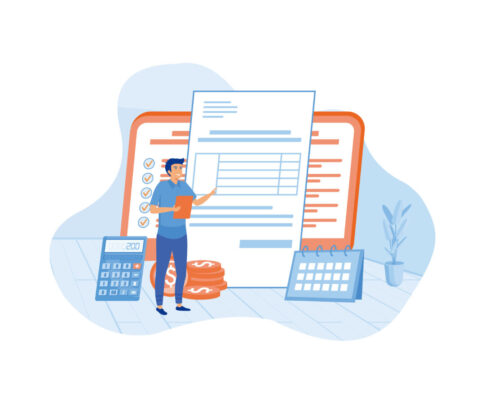訪問看護はレセプト入金が月1〜2回で資金ギャップが生じがちです。一方、請求債権は条件を満たせばファクタリングで早期資金化できます。
本記事では、対象債権と請求先(支払基金・国保連)の整理、2社間/3社間の違い、承諾・代理受領の手順、手数料・付帯費の比較、返戻時の是正までを実務目線で平易に解説します。
訪問看護ファクタリング基礎

訪問看護の売掛金は、医療保険の「訪問看護療養費」および介護保険の「訪問看護費(居宅・総合事業等を含む)」に基づく請求債権です。請求は月次で行い、審査(点検・返戻対応)後に支払されます。
金銭債権であること、提供・記録・請求の要件を満たし金額が特定されていることが、ファクタリング(債権譲渡)で資金化する前提です。
初出注釈:買取率=請求額に対する入金割合(%)、手数料率=請求額に対する費用割合(%)、掛け目=与信上の取扱上限(買取対象割合)、返戻=審査過程での差し戻しです。
訪問看護は医療・介護の双方を扱うため、請求先(支払基金・国保連)と制度区分を整理し、月次の入金サイト(目安30〜60日)を資金繰りに反映します。
2社間(事業者とファクタリング会社)か、3社間(請求先を関与させ代理受領・承諾を取得)のいずれかは、請求先の運用・承諾可否・事業者の開示方針で判断します。
| 区分 | 実務の要点 |
|---|---|
| 医療保険 | 訪問看護療養費。主な請求先は支払基金(協会けんぽ・組合健保等)と国保連(国保・後期)。 |
| 介護保険 | 訪問看護費・加算。請求先は国保連。利用者負担分(1〜3割)は別回収。 |
| 資金化前提 | 提供記録・指示書・計画書・請求データの整合で金額確定。返戻未解決部分は対象外になり得ます。 |
- 医療/介護の請求先と請求締切の特定
- 返戻の有無・率と是正フローの把握
- 入金サイト(30〜60日)を資金繰りに反映
- 2社間/3社間の選択方針を事前決定
対象債権と請求先整理要点
対象は、提供済みサービスに対する診療報酬・介護報酬の請求債権です。医療保険の訪問看護(特別訪問看護指示書を含む)は支払基金または国保連が審査・支払し、介護保険の訪問看護は国保連が審査・支払します。
利用者負担分(自費1〜3割)は別回収であり、ファクタリングの対象外とする運用が一般的です。
公費負担医療や医療・介護連携加算等が混在する場合は、請求先・支払日が分かれるため、回次・区分・金額の特定が重要です。
対象外になりやすいのは、未提供・未記録・返戻未解決・不備のある請求で、金額が確定していない状態です。割当(掛け目)は返戻率や過去の差異率に依存し、返戻率が高い場合は買取対象額が抑制されます。
- 請求先整理:医療=支払基金/国保連、介護=国保連、利用者負担=別回収
- 区分管理:医療と介護で請求データ・様式・支払日が異なる
- 対象外例:返戻未解決分、未記録・未署名、指示書期限切れ
- 返戻が発生し金額未確定の請求分
- 医師の訪問看護指示書の不備・期限失効
- 利用者負担分・自費分のみの請求
- サービス提供記録と請求量の不一致
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要書類(例) | 訪問看護指示書、計画書・報告書、提供記録、レセプトデータ、請求書、返戻通知 |
| 特定事項 | 回次、区分(医療/介護)、金額、請求日、支払予定日、返戻有無 |
入金サイクルと時系列の把握
時系列は「提供→月次締切→審査→支払」です。一般的に、当月提供分を翌月10日前後に請求し、審査・点検を経て翌月末〜翌々月初に支払われる運用が多く、入金サイトは概ね30〜60日です。
返戻が生じると再請求の分だけ資金化が遅延します。資金繰りでは、請求先ごとの支払日、介護・医療のズレ、返戻率を織り込み、実行日(ファクタリング実行)を逆算します。
指標例:実質コスト=(手数料+付帯費)÷受領額、実質年率(参考)≒(実質コスト÷サイト日数)×365。
例:請求1,000万円、手数料2.0%、付帯費5万円、サイト45日なら、実質コスト約2.56%、年率目安約20.8%です。
短期資金の橋渡しとしては妥当でも、返戻が多いと掛け目が下がるため、是正フローを併走させます。
- M月:サービス提供・記録整備
- M+1月10日:請求データ提出(医療/介護)
- M+1月:審査・返戻対応(必要時)
- M+1月末〜M+2月初:支払・入金確認
| 観点 | 着眼点 | 資金繰りの対応 |
|---|---|---|
| サイト短縮 | 3社間・承諾・代理受領で入金経路を明確化 | 審査安定で手数料低位・実行スピード向上 |
| 返戻管理 | 返戻率・差異率のモニタリング | 是正期限・再請求日を台帳管理 |
| 区分差 | 医療と介護の支払日差 | 回次別に別建てでキャッシュフロー計画 |
2社間/3社間の仕組み比較
2社間は、事業者とファクタリング会社のみで契約し、請求先への通知を行わず、入金は従来どおり事業者口座に受けて清算する方式です。
秘匿性・スピードに利点がありますが、返戻や回収遅延のリスクは事業者側の管理に依存し、掛け目が控えめになる傾向です。
3社間は、請求先(支払基金・国保連・保険者等)に譲渡通知・承諾を経て代理受領や支払先固定を行う方式で、入金経路が明確になり二重払い抑止・審査安定に優れます。
もっとも、請求先の運用上、承諾・代理受領の取扱いに差があるため、実務適合性を事前に確認します。
選定基準は、①承諾可否と所要期間、②返戻率・差異率、③必要資金の緊急度、④開示方針(対外秘か開示許容か)です。
| 項目 | 2社間 | 3社間 |
|---|---|---|
| 速度・秘匿 | 速い・秘匿性高い | 承諾取得に日数・開示前提 |
| 掛け目 | 返戻・遅延の影響を受けやすく控えめ | 入金経路明確で安定しやすい |
| コスト | 通知・登記等の付帯費は抑制されやすい | 承諾・登記等の付帯費が発生しやすい |
| 運用適合 | 請求先を巻き込まないため内部完結 | 請求先運用に依存、事前確認が必須 |
- 請求先の承諾・代理受領の可否と様式を事前確認
- 返戻率が高い場合は3社間で掛け目改善を検討
- 緊急度が高い場合は2社間でつなぎ、後日是正
- 通知・登記・承諾の特定事項(回次・金額・期日)を統一
申込から入金までの実務手順

訪問看護のファクタリングは、月次請求(医療=支払基金/国保連、介護=国保連)を前提に、申込→審査→契約→対抗要件(確定日付通知/債権譲渡登記)→請求提出→入金確認→清算の順で進めます。
対象は提供済みかつ金額が特定された請求債権で、返戻(審査差戻し)が残る部分は対象外になり得ます。
2社間はスピード重視で、入金後に清算する運用が中心です。3社間は承諾・代理受領等で入金経路を固定できる一方、請求先の運用上、第三者受領や口座変更に制約がある場合があるため事前確認が不可欠です。
資金繰りは、入金サイト(概ね30〜60日)と承諾・登記の所要日数を織り込み、実行日(資金化日)から逆算して準備します。
| 工程 | 主担当・主要書類 | 目安・要点 |
|---|---|---|
| 申込・審査 | 事業者/ファクタ会社・基本資料、反社誓約、請求データ | 返戻率・差異率・区分(医療/介護)を開示 |
| 契約 | 基本契約書・個別契約書 | 買取率・手数料・対象回次を特定 |
| 対抗要件 | 確定日付通知/債権譲渡登記事項証明書 | 二重払い抑止、所要数営業日 |
| 請求提出 | レセプトデータ、請求書、提供記録 | 締切順守、返戻是正の同時進行 |
| 入金・清算 | 支払通知、入金明細、消込資料 | 差異照合、清算・計上・保管 |
承諾・代理受領の準備
承諾・代理受領は、請求先(支払基金・国保連・保険者等)の運用で可否や手順が異なります。
第三者口座への支払や受領委任を認めない扱いもあるため、事前に「可能な方式(2社間/3社間)」「必要様式・記載事項」「反映時期(口座固定のタイミング)」を確認します。
承諾が得られない場合は、2社間で入金後清算の設計に切り替え、回次・金額・支払予定日の特定を精緻化して掛け目(買取対象割合)を安定させます。
対抗要件は、確定日付付きの譲渡通知、または動産債権譲渡登記を採用し、二重払いの余地を塞ぎます。
- 可否確認:請求先の取扱い(第三者受領・口座変更の可否)
- 方式選択:不可→2社間/可→3社間で入金経路を固定
- 書式整備:委任状・通知・承諾の特定事項(回次・金額・期日)
- 時期管理:反映締切と入金サイトを資金繰りに連結
必要書類と記載特定の要点
実務で整える書類は、審査・契約・対抗要件・請求・清算にまたがります。記載は「契約番号(あれば)・区分(医療/介護)・回次・金額・請求日・支払予定日・口座情報」を統一表記にし、返戻通知は回次別に保管します。
提供記録・訪問看護指示書(医療)、計画書・報告書、レセプトデータは、請求内容と数量・日数が一致していることが前提です。
| 項目 | 内容(例) |
|---|---|
| 審査資料 | 直近6〜12か月の請求・入金推移、返戻率、区分別ボリューム、反社誓約 |
| 契約書類 | 基本契約書・個別契約書(買取率・手数料・対象回次・清算条件) |
| 対抗要件 | 確定日付付き譲渡通知、または債権譲渡登記事項証明書 |
| 請求・証憑 | 訪問看護指示書、提供記録、レセプトデータ、請求書、返戻通知 |
| 清算・保存 | 支払通知、入金明細、消込表、保管台帳(案件別ファイル) |
返戻発生時の運用是正
返戻(審査差戻し)は資金化額とタイミングに直結します。返戻が多いと掛け目が低下し、対象額が圧縮されます。
例:請求1,000万円、掛け目90%、返戻率5%の場合、対象額=1,000万円×(90%−5%)=850万円。
是正は「原因の可視化→様式・記載の統一→再請求期日の固定→台帳化」の順で行います。返戻理由の多くは、指示書の有効期間切れ、提供記録と請求量の不一致、加算要件の証憑不足、区分誤り(医療/介護)です。
2社間では返戻分が後日清算に回るため、回次別に対象外管理を行い、3社間でも承諾の対象範囲(回次・金額)と齟齬がないかを突合します。
- 原因分類:様式不備/要件不足/区分誤り/入力ミスを分離
- 再発防止:記載テンプレの統一、指示書期限の自動管理
- 台帳管理:返戻率・再請求日・対象外額・是正完了日を記録
- 掛け目改善:3か月移動平均で返戻率低下を提示し条件交渉
審査と条件比較
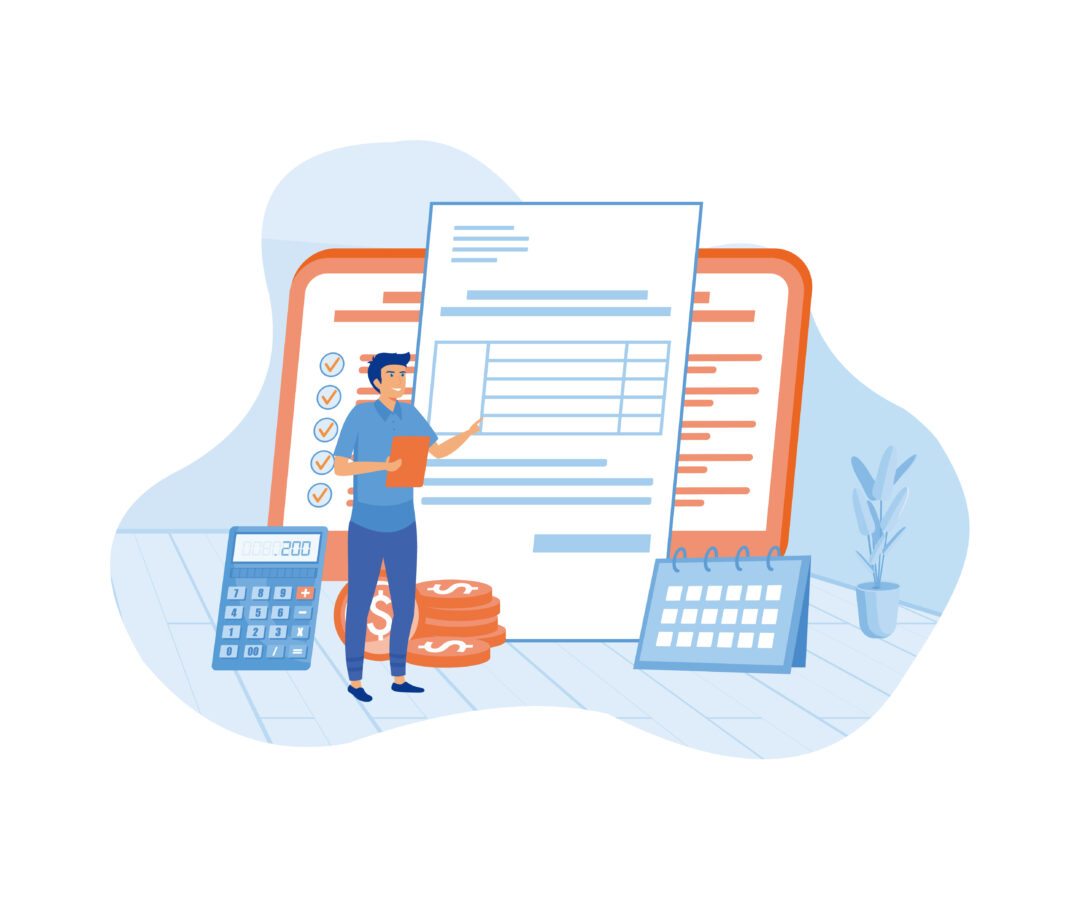
訪問看護のファクタリング条件は、①手数料(%)と付帯費の合計、②掛け目=買取対象割合(%)、③入金サイト=請求から入金までの日数、④スキーム(2社間/3社間)で決まります。
初出注釈:買取率=請求額に対する入金割合、実質コスト=(手数料+付帯費)÷受領額、実質年率(参考)≒(実質コスト÷サイト日数)×365です。返戻率(審査差戻し割合)が高いほど掛け目は抑制され、条件は上振れしやすくなります。
比較では「見かけの手数料率」ではなく、入金サイトと付帯費を含む実質コストと、掛け目・回次(医療/介護・保険種別)の組合せで横並びに評価します。
3社間で承諾・代理受領・対抗要件(確定日付通知/登記)が整う案件は、入金経路が明確になり、料率・掛け目ともに安定しやすい傾向です。
| 比較観点 | 実務の見方 |
|---|---|
| 手数料・付帯費 | 料率だけでなく登記・確定日付・郵送・振込等の費用を合算 |
| 掛け目 | 返戻率・差異率・回次特定の精度で変動(区分別に設定) |
| 入金サイト | 医療/介護で支払日がずれるためサイト別に年率換算 |
| スキーム | 2社間=迅速・秘匿/3社間=安定・入金経路明確 |
- 実質コスト=(手数料+付帯費)÷受領額で横並び比較
- 掛け目・回次・区分(医療/介護)を分けて評価
- サイト別に年率換算して時間価値を可視化
- 3社間は承諾・対抗要件・口座固定の三点セットで安定化
手数料と付帯費の内訳整理
費用は「基本手数料(請求額×手数料率)」に「付帯費」を加えた総額で判断します。付帯費には、振込手数料、確定日付取得費(内容証明等)、動産債権譲渡登記関連費(申請・証明書)、郵送・書類発行費、システム手数料などが含まれます。
2社間は付帯費が抑えやすい一方、3社間は承諾・登記等で発生しやすく、ただし入金経路の明確化により掛け目が改善し、総合的に条件が安定することが多いです。
比較時は、費用の「誰が・いつ負担するか」も明確にし、実行前に見積もりで金額レンジを確認します。
- 用語注:手数料率=請求額に対する費用割合(%)。
- 用語注:付帯費=登記・確定日付・郵送・振込等の諸費用。
- 用語注:受領額=請求額−手数料−付帯費(概算)。
- 前提:請求1,000万円、手数料2.0%、付帯費5万円、入金サイト45日
- 手数料=200,000円、受領額=9,750,000円 → 実質コスト≒2.56%
- 実質年率(参考)≒(2.56%÷45日)×365≒約20.8%
- 示唆:同率でも付帯費・サイトで負担は大きく変動
掛け目・入金サイト設計
掛け目(買取対象割合)は、回次の確度と返戻率、2社間/3社間、対抗要件(通知・登記)で決まります。
概念式は「買取対象額=請求額×掛け目−返戻見込み額」。返戻率が高いと掛け目は抑制され、対象額が減少します。
入金サイトは一般に30〜60日で、サイトが長いほど時間価値の影響で実質年率は高く見えます。
設計の要は、①医療・介護の支払ズレを台帳管理、②回次単位で掛け目を分け、③3社間(承諾・代理受領・口座固定)で入金経路を明確化し、④通知・登記のタイミングを締切に合わせて前倒しすることです。
| サイト | 資金繰り設計の要点 | 年率の目安(手数料2.0%) |
|---|---|---|
| 30日 | 迅速回収。2社間でも年率上振れは小さめ | 約24% |
| 45日 | 標準。登記・承諾を並行、締切に同期 | 約16% |
| 60日 | 長期。付帯費の比率上昇、分割実行も検討 | 約12% |
- 掛け目は「回次×区分(医療/介護)」で別管理
- 返戻率の移動平均(3か月)で掛け目交渉の根拠化
- 3社間+対抗要件で入金経路を固定し、掛け目安定
- サイト長期化時は分割実行・代替資金の併用を検討
審査基準と返戻率の影響
審査は「売掛先の支払確実性」と「請求の事務確度」の2本柱です。
訪問看護では、①回次・区分(医療/介護)の特定、②訪問看護指示書・提供記録・レセプトの整合、③返戻率・差異率の水準、④2社間/3社間と対抗要件の整備、⑤反社・コンプライアンス体制、が主な評価軸です。
返戻率が高いと、掛け目の引下げ、留保条件の付与、再請求入金後の清算など、条件は厳格化します。
改善には、返戻理由の類型化(様式不備/要件不足/区分誤り/入力ミス)と、テンプレ・点検表の標準化が有効です。
| 審査項目 | 確認資料・指標 | 条件への影響 |
|---|---|---|
| 売掛先確実性 | 支払基金・国保連の支払実績、支払サイクル | 高いほど料率低下・掛け目上振れ |
| 事務確度 | 回次特定、指示書・提供記録・レセプトの整合 | 整うほど差異リスク低下・審査安定 |
| 返戻率 | 直近6〜12か月の返戻率・再請求回数 | 高いほど掛け目抑制・留保条件の付与 |
| スキーム・対抗要件 | 3社間、通知・登記の有無、口座固定 | 整備済みで二重払い抑止、条件安定 |
- 返戻理由を類型化し、記載テンプレを更新
- 指示書期限・加算要件を台帳で自動管理
- 回次・区分・金額・支払予定日の表記を統一
- 3か月移動平均の改善実績で掛け目・料率を交渉
小規模の資金繰り設計

小規模の訪問看護事業では、月次請求(医療=支払基金/国保連、介護=国保連)の入金までに30〜60日程度の時間差が生じやすく、運転資金の設計が安定運営の要になります。
基本は、①固定費(人件費・家賃・車両等)と②変動費(消耗品・通信・移動)の見積、③入金サイトと返戻率を加味した回収見込み、④不足分を埋める調達手段(ファクタリング/公的融資/自己資金)を時系列で組み合わせることです。
運転資金の目安は「必要運転資金=月間支出×(入金サイト日数÷30)」と置き、返戻が想定される場合は「返戻控除率」を差し引きます。
例:月間支出400万円、入金サイト45日、返戻控除3%なら、必要運転資金≒400万円×1.5×(1−0.03)=582万円程度です。
小規模では人員の増減がキャッシュに直結するため、回次別(医療/介護)に請求・入金のタイムラインを置き、資金化の実行日を逆算して決めます。
| 項目 | 設計ポイント |
|---|---|
| 固定費 | 常勤・非常勤人件費、賃料、車両、保険、システム |
| 変動費 | 消耗品、衛生材、通信・燃料、出張旅費 |
| 入金サイト | 30〜60日を目安に区分(医療/介護)別に管理 |
| 返戻率 | 直近平均を控除して保守的に資金見積 |
- 回次(医療/介護)ごとの請求・入金カレンダー化
- 返戻率の移動平均で掛け目・資金化額を保守見積
- 固定費は12か月見通し、変動費は件数連動で計画
- 不足分は資金化日から逆算して調達手段を選択
立上げ〜初回入金の資金差
新規開設期は、提供開始から初回入金までのギャップが最大化しやすく、特に常勤看護師の給与や賃料が先行します。
一般的な時系列は「開設準備→提供開始→初回請求→審査→初回入金」で、提供開始から入金まで45日前後を想定すると、少なくとも1.5か月分の運転資金を確保する設計が安全です。
必要資金の概算は「初期必要資金=月間固定費×1.5+初期投資(車両・機器)−補助・助成受給額」で置き、返戻が多い想定ならさらにバッファを上乗せします。
例:月間固定費300万円、初期投資200万円、助成金50万円、サイト45日なら、初期必要資金≒300万円×1.5+200万円−50万円=600万円です。
資金化を併用する場合は、請求締切・対抗要件の整備に間に合う回次から実行し、初回は医療・介護のうち入金の早い区分を優先してキャッシュインの前倒しを図ります。
- 初回請求までは売上ゼロ前提で固定費をフル計上
- 返戻発生前提で資金バッファを10〜15%上乗せ
- 資金化は回次・区分を限定し、書類精度を最優先
- 入金確認後は消込・計上までワンセットで運用
- 実務の工夫:提供記録・指示書・レセプトを同日内に突合し、請求締切前の差異をゼロに近づけます。
サテライト開設と費用管理
サテライト(出張所・分室)の追加は、訪問圏の拡大や移動時間の削減に寄与しますが、短期的には固定費を押し上げます。
費用管理は、①立上げ固定費(賃料・什器・回線)、②人件費(常勤・非常勤・オンコール)、③車両・移動費、④システム・セキュリティの4群に分解し、訪問件数の増分で吸収できるかを月次損益で試算します。
資金繰りでは、サテライト開設月のキャッシュアウトを分割(リース・割賦・補助活用)し、入金サイトを加味した運転資金を別枠で確保します。KPIは「1件あたり限界利益=単価−変動費」「稼働率」「1日訪問件数」「移動時間比率」です。
| 費用区分 | 主な内容 | 資金繰り対策 |
|---|---|---|
| 立上げ固定費 | 賃料敷金、什器、通信回線、初期工事 | 分割・リース化、助成・補助の適用確認 |
| 人件費 | 常勤・非常勤、オンコール手当 | 件数連動シフト、単価・移動効率で吸収 |
| 移動・車両 | 燃料、駐車、車両リース | 拠点配置で移動時間を削減し変動費を抑制 |
- 開設後3か月の損益計画で黒字化時期を可視化
- 1件あたり限界利益が固定費増を上回る水準か
- 移動時間削減が人件費・燃料費に与える効果の試算
- 初期投資は分割前提、運転資金は別枠で確保
公的融資との使い分け基準
ファクタリングは「売掛債権の譲渡による早期資金化」で、返済は当該回収で完結します。公的融資(例:政策金融公庫)や保証付き融資は「借入」で、元利返済が発生し、金利・保証料が費用です。
使い分けは、①資金の性質(橋渡し/成長投資)、②必要タイミング(即時/中長期)、③総費用(年率換算と期間総額)、④貸借対照表への影響(負債増の許容度)で判断します。
短期の運転資金や回次ごとのギャップ解消はファクタリングが適合しやすく、設備更新・人員増強・新規拠点などの長期資金は公的融資が向きます。
併用する場合は、回次資金はファクタリングで平準化し、固定費増や設備は低金利の融資で賄う二段構えが効果的です。
| 観点 | ファクタリング | 公的融資等 |
|---|---|---|
| 用途 | 短期運転・回次の橋渡し | 設備・採用・拠点等の中長期 |
| スピード | 承諾・対抗要件整備で比較的短期 | 審査〜実行まで中期、計画書が必要 |
| 費用観 | 手数料+付帯費(年率高めに見えやすい) | 金利・保証料(総額は低位になりやすい) |
| BS影響 | 売掛金減少・現金増(負債計上なし) | 負債増・自己資本比率に影響 |
- 不足が一時的:回次限定でファクタリングを選択
- 固定費増・投資案件:公的融資で長期返済に設計
- 併用時:年率換算・総費用・BS影響で三点比較
- 資金調達は入金カレンダーから逆算して申し込み
レセプトと法令要点
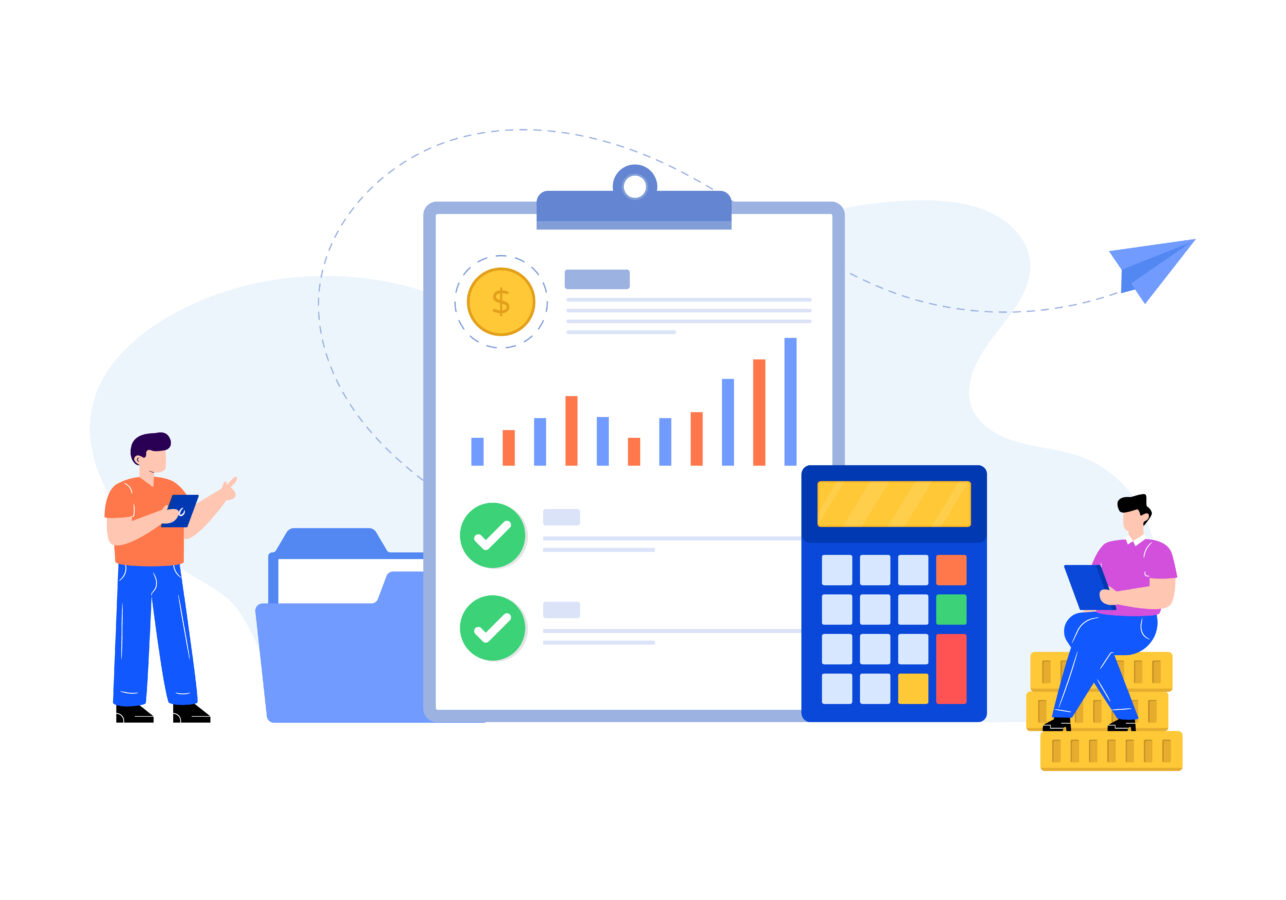
訪問看護の請求は、医療保険と介護保険で制度と手順が異なります。医療保険の訪問看護療養費は、保険者区分に応じて支払基金または国保連が審査・支払を行い、介護保険の訪問看護費は国保連が一元的に扱います。
いずれも月次請求・審査・支払の流れで、返戻がある場合は再請求となります。ファクタリングの観点では、請求先(債務者)の特定、回次・区分(医療/介護)の明確化、支払日サイクルの把握が前提です。
医療側では訪問看護指示書等に基づく提供記録の整合、介護側ではケアプラン・サービス提供票等の整合が金額確定の根拠になります。
電子請求の普及により伝送・到達時刻が明確化され、台帳管理と組み合わせることで、回次ごとの資金化計画(実行日・入金予定日)の精度を高められます。
| 領域 | 要点 |
|---|---|
| 医療保険 | 訪問看護療養費。支払基金/国保連が審査・支払。指示書・提供記録の整合が前提。 |
| 介護保険 | 訪問看護費。国保連が審査・支払。ケアプラン・提供票等との整合が前提。 |
| 資金化 | 請求先と支払日を特定し、回次単位で金額確定。返戻分は対象外になり得る。 |
- 請求区分(医療/介護)と請求先(支払基金/国保連)を回次で特定
- 返戻の有無・率を台帳化し、対象額と時期を保守見積
- 電子請求の到達・受付情報を証憑として保存
- 審査・支払日サイクルを資金化計画へ反映
支払基金と国保連の違い
医療保険の請求は、被用者保険等の多くを支払基金が、国民健康保険や後期高齢者医療等の一部を国保連が扱います。介護保険の訪問看護は国保連が一元的に取り扱います。
両者は審査基準や様式の骨格は共通するものの、受付締切や支払日、連絡票・返戻通知の形式が異なる場合があります。
資金化では、どちらが債務者となるかで対抗要件の書式・記載特定(回次・区分・金額・支払予定日)の運用が変わります。
回次ごとに「医療(支払基金/国保連)」と「介護(国保連)」を分けて台帳管理し、支払日のズレを前提にキャッシュフローを組み立てます。
| 項目 | 支払基金(医療) | 国保連(医療/介護) |
|---|---|---|
| 対象 | 被用者保険等の医療レセプト | 国保・後期(医療)、介護保険の請求全般 |
| 請求 | オンライン/紙。月次締切・伝送 | オンライン/紙。都道府県ごとに締切・到達日が規定 |
| 支払 | 審査後に月次支払 | 審査後に月次支払(医療・介護で支払日が異なることあり) |
| 返戻 | 返戻通知で再請求 | 返戻通知で再請求(区分別に管理) |
- 受付締切・支払日の違いを回次台帳に反映
- 返戻通知の様式差はテンプレで吸収
- 資金化書類は債務者名・区分・回次を統一表記
- 医療と介護で入金日がズレる前提で見込現金残高を管理
療養費・訪看指示書の関係
医療保険の「訪問看護療養費」は、医師の訪問看護指示書に基づく提供に対して請求する費目で、計画書・報告書・提供記録等と整合して金額が確定します。
一般の「療養費(償還払い)」という用語は、患者がいったん立替えた費用を後日請求する制度を指す場合があり、混同しない運用が必要です。
訪問看護では、通常の指示書に加え、状態に応じて特別訪問看護指示書(短期集中的な訪問を可能にする指示)が用いられることがあり、期間や要件に沿った提供・記録が求められます。
ファクタリングでは、指示書の有効期間内で提供されたサービスに基づくレセプトのみを対象とし、指示書不備・期限切れ・提供記録不整合がある請求は対象外または留保となるのが一般的です。
- 用語注:訪問看護指示書=医師が訪問看護の内容・期間を指示する文書。
- 用語注:訪問看護療養費=医療保険で請求する訪問看護の費目。
- 用語注:特別訪問看護指示書=短期集中的訪問を認める指示(期間制限あり)。
- 有効期間・頻度・内容が提供記録と一致
- 計画書・報告書の記載と算定要件が整合
- 回次・区分・金額を請求データに正確反映
- 不整合・返戻は原因別に是正し再請求
| 確認項目 | 記載・証憑の要点 |
|---|---|
| 指示書 | 期間・内容・頻度の特定、署名・日付、特別指示の有無 |
| 提供記録 | 日時・内容・所要時間・署名、加算要件の根拠 |
| 計画・報告 | 目標・評価・モニタリング、変更履歴 |
電子請求と証憑管理の実務
電子請求(オンライン請求・介護伝送)では、伝送・受付・到達の時刻情報が残るため、請求の実施証跡として活用できます。
実務は、①区分(医療/介護)別に締切・到達期限を台帳で管理、②返戻通知・審査結果電文を回次別に保存、③提供記録・指示書・計画書・報告書・請求データの突合を月次で実施、④入金後は支払通知・通帳明細で消込、の順で標準化します。
保存期間は、医療の診療録等は一定期間の保存が求められ、介護のサービス提供記録等も保存期間が定められています。
加えて、会計・税務書類は税法上の保存が必要になります。いずれも「最小限の利用・権限管理・廃棄手順の文書化」を徹底し、外部委託がある場合は守秘契約とアクセス管理を明確化します。
| 区分 | 主な証憑 | 保存・管理の要点 |
|---|---|---|
| 医療(訪看) | 指示書、計画書・報告書、提供記録、レセプト、返戻通知 | 診療録等の保存期間に従い保管。改訂履歴・到達時刻を保持 |
| 介護(訪看) | ケアプラン、提供票、実績票、請求データ、返戻通知 | 介護記録の保存期間に従い保管。様式・通番・版管理を統一 |
| 会計・税務 | 支払通知、入金明細、消込表、請求書控、領収書 | 税法上の保存期間を適用。電子帳簿保存の要件に沿って保管 |
- 締切・到達・審査結果・支払日の時系列を台帳化
- 回次単位で医療/介護を分けて保存・突合
- 返戻は原因別にタグ付けし、是正期限を設定
- アクセス権限・保存期間・廃棄手順を文書化
まとめ
訪問看護のファクタリングは、①対象債権の特定②承諾・代理受領③対抗要件(通知/登記)④請求・入金確認の順で運用します。費用は手数料と付帯費を含む実質で比較し、入金サイトと掛け目を資金繰り表に反映します。
返戻が多い場合は是正後に回次を限定。短期の橋渡しはファクタリング、長期資金は公的融資を基本に使い分けましょう