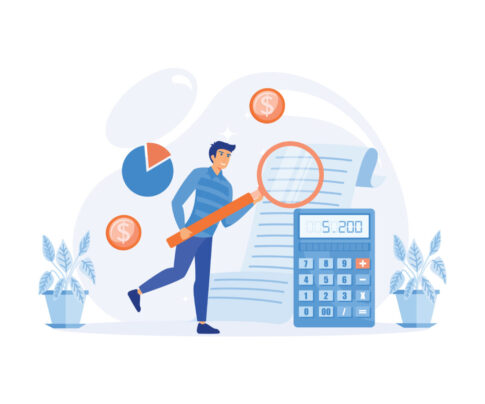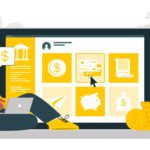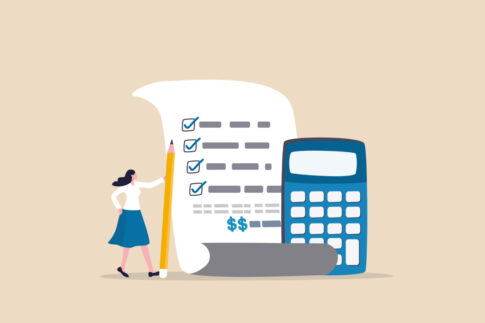公庫融資を検討するとき、「自己資金はどれくらい必要か」「通帳で出所をどう見られるか」「見せ金と疑われないか」「必要書類が足りるか」と不安になりがちです。資金繰りが厳しい局面では、銀行融資の審査が通りにくい、ノンバンクは条件が不安、税金や社保の遅れが影響しないかも気になります。
この記事では、公庫融資における自己資金要件の考え方、目安の見方、出所確認のポイント、通帳や資金移動の準備、贈与や借入が混ざる場合の注意点、不足時の対策、申込みから実行までの流れを整理します。
目次
自己資金要件の基礎知識

公庫融資(日本政策金融公庫の創業向け融資)では、自己資金の「金額」だけでなく、「いつから、どのように積み上げた資金か」「創業資金の使い道と整合しているか」が見られやすいです。
自己資金は、創業に必要な資金の一部を自分で負担できることを示す材料であり、返済負担を抑える意味もあります。
制度によっては、創業資金総額に対して一定割合以上の自己資金を確認できることが要件として示される場合がありますが、要件の適用範囲や見られ方は、利用する融資メニューや申込者の状況で変わります。
まずは「創業資金の総額」「自己資金で支払う部分」「借入で賄う部分」を分け、通帳等で説明できる状態に整えることが基本です。
- 自己資金の定義:自分で自由に使える資金かどうか
- 形成の経緯:直前の不自然な入金がないか
- 資金使途との整合:設備・運転資金の支払計画に合っているか
- 書類整備:通帳履歴や資金移動の説明ができるか
自己資金の意味と範囲
自己資金は、一般に「創業時点で自分が拠出でき、返済義務のない資金」として扱われやすいです。代表例は、長期間の貯蓄や、既存事業の利益留保、資産売却で得た現金などです。
一方、直前に誰かから借りたお金や、短期間だけ口座に入れてすぐ戻すような資金移動は、自己資金としての説明が難しくなりがちです。
贈与や親族からの援助は、状況によって扱いが分かれるため、贈与契約書や振込記録など「返済不要であること」「出所が説明できること」を準備しておくと整理しやすいです。
自己資金として説明できる範囲はケースで変わるため、通帳の入出金履歴と合わせて、資金の成り立ちを一貫して説明できる形にしておくことが重要です。
| 区分 | 例と注意点 |
|---|---|
| 自己資金にしやすい | 継続的な貯蓄、利益の積み上げ、資産売却で得た現金(入出金の根拠が示せる) |
| 説明が必要 | 贈与・援助金(返済不要の根拠、振込記録、経緯の説明が必要になりやすい) |
| 注意が必要 | 直前の借入、短期の資金移動(自己資金とみなされにくいことがある) |
要件の目安の見方
自己資金要件の「目安」は、単純に「いくらあれば十分」と決め打ちするより、「創業資金総額のうち、自己資金でどこまで負担できるか」で捉えると現実的です。
制度によっては、創業資金総額の一定割合以上の自己資金が確認できることが要件として示される場合があります。
例えば、創業資金総額が500万円(設備300万円・運転200万円)なら、自己資金の割合が一定水準に届いているかを確認し、借入に頼りすぎない計画になっているかを点検します。
ただし、自己資金が多ければ良いという単純な話ではなく、自己資金を使い切って運転資金が残らない計画は、融資実行前後で資金ショートを招きやすいです。
目安はあくまで入口で、事業計画(売上の根拠、費用の見込み、入金・支払サイト)と資金繰り表に落として「月次で資金が回るか」まで確認することが大切です。
- 自己資金を初期費用に使い切ると、運転資金が不足しやすい
- 必要資金の算定が甘いと、自己資金があっても追加資金が必要になりやすい
- 要件は融資メニューや状況で変わり得るため、申込み時点の案内確認が前提
資金使途との関係注意点
自己資金は「通帳にある金額」だけでなく、「何に充てる予定か(資金使途)」とセットで見られやすいです。
設備資金なら、見積書や発注書に基づき、自己資金で支払う部分と借入で支払う部分を分け、支払日までに資金が用意できるかを確認します。
運転資金なら、開業後の売上入金が安定するまでの家賃・人件費・仕入などを想定し、自己資金の残し方が重要になります。
例えば、開業月は売上が立っても入金が翌月以降になりやすいため、自己資金を「初期費用+数か月分の固定費」の両方に配分できるかを検討します。
資金使途が曖昧だと、必要額の根拠が弱くなり、結果として説明の手戻りが増えやすいので、支払予定と入金予定を簡単でもよいので表にして整理しておくと進めやすいです。
- 設備資金は見積書ベースで、自己資金と借入の支払タイミングをそろえる
- 運転資金は「入金が遅れる期間」を想定し、自己資金を残す配分を検討する
- 資金使途が曖昧なまま申込むと、追加説明や追加資料が増えやすい
審査で見られる自己資金

自己資金は「いくらあるか」だけでなく、「どうやって貯めたか」「返済不要か」「申込内容の資金使途と矛盾がないか」が見られやすいです。
特に創業期は決算実績が少ないため、自己資金の形成過程が事業への準備状況や計画性の裏付けとして扱われることがあります。
例えば、開業資金として300万円の自己資金を示すなら、直近だけでなく過去の入出金の流れの中で無理なく形成されたこと、開業費や設備の支払い時期に合わせて資金が確保できることを説明できる状態が重要です。
- 形成の自然さ:毎月の積立など継続性があるか
- 出所の明確さ:給与・事業収入・資産売却など根拠が示せるか
- 返済義務の有無:借入が混ざっていないか
- 資金使途との一致:設備・運転資金の支払い計画に合うか
出所確認のポイント
出所確認は、自己資金が「自由に使えるお金」かつ「返済不要の資金」と説明できるかを確かめるために行われます。
基本は通帳の入出金履歴で、給与振込や事業収入の入金、毎月の積立、資産売却代金の入金などが一貫して追えるかがポイントです。
資産売却で形成した場合は、売買契約書や入金明細など、入金の根拠を合わせて整理すると説明が通りやすくなります。
贈与・援助がある場合も、誰から・いつ・いくら・返済不要かを示せる資料があるほど、確認が短く済みやすいです。
| 出所 | 確認で用意したい根拠の例 |
|---|---|
| 貯蓄 | 通帳の継続した積立履歴、給与入金と残高推移 |
| 事業収入 | 入金の根拠(売上の入金履歴、帳簿との整合) |
| 資産売却 | 売買契約の内容、入金明細、資金が口座に入った流れ |
| 贈与・援助 | 振込記録、経緯メモ、返済不要であることの説明材料 |
見せ金が疑われる例チェック
見せ金とは、審査の場で自己資金を多く見せる目的で、短期間だけ資金を入れて残高を作るように見える状態を指します。
実際に意図がなくても、動きが不自然だと疑われやすく、追加説明や追加資料が増える原因になります。
例えば、申込み直前に大きな入金があり、すぐ別口座へ移す、親族からの入金があって短期間で返しているように見える、現金入金が多いのに根拠が示せない、といったケースです。
こうした動きがある場合は、事実関係を時系列で整理し、資金の性質(贈与・売却代金など)と根拠資料を添えて説明できる形に整えることが重要です。
- 申込み直前の高額入金があり、入金理由が説明しにくい
- 短期間で入金と出金が往復し、残高だけが一時的に増えている
- 現金入金が多く、売却や収入などの根拠が提示できない
- 親族等からの入金があるが、返済不要かどうかが不明確
通帳履歴の見せ方注意点
通帳は「残高があること」よりも「形成の流れが読めること」が重要です。提出・提示の場面では、直近だけ切り取らず、一定期間の推移が分かる範囲で用意し、自己資金として使う予定額がどこにあり、いつ支払いに充てるのかを説明できるようにします。
例えば、設備の手付金を来月末に50万円支払う予定なら、その時点で口座に残る見込みが分かるよう、資金繰り(入金・出金予定)と合わせて整理するとスムーズです。
複数口座を使っている場合は、資金が散らばって見えやすいので、「自己資金口座を一本化して見せる」「口座間の移動は理由と日付をメモする」など、第三者が追える形にしておくと確認が長引きにくくなります。
- 一定期間の推移が分かるように用意し、残高だけの提示にしない
- 口座間の資金移動がある場合は、理由・日付・金額を時系列で説明できるようにする
- 支払い予定(設備・開業費)と自己資金の残高推移が矛盾しないように整理する
必要書類と準備ステップ
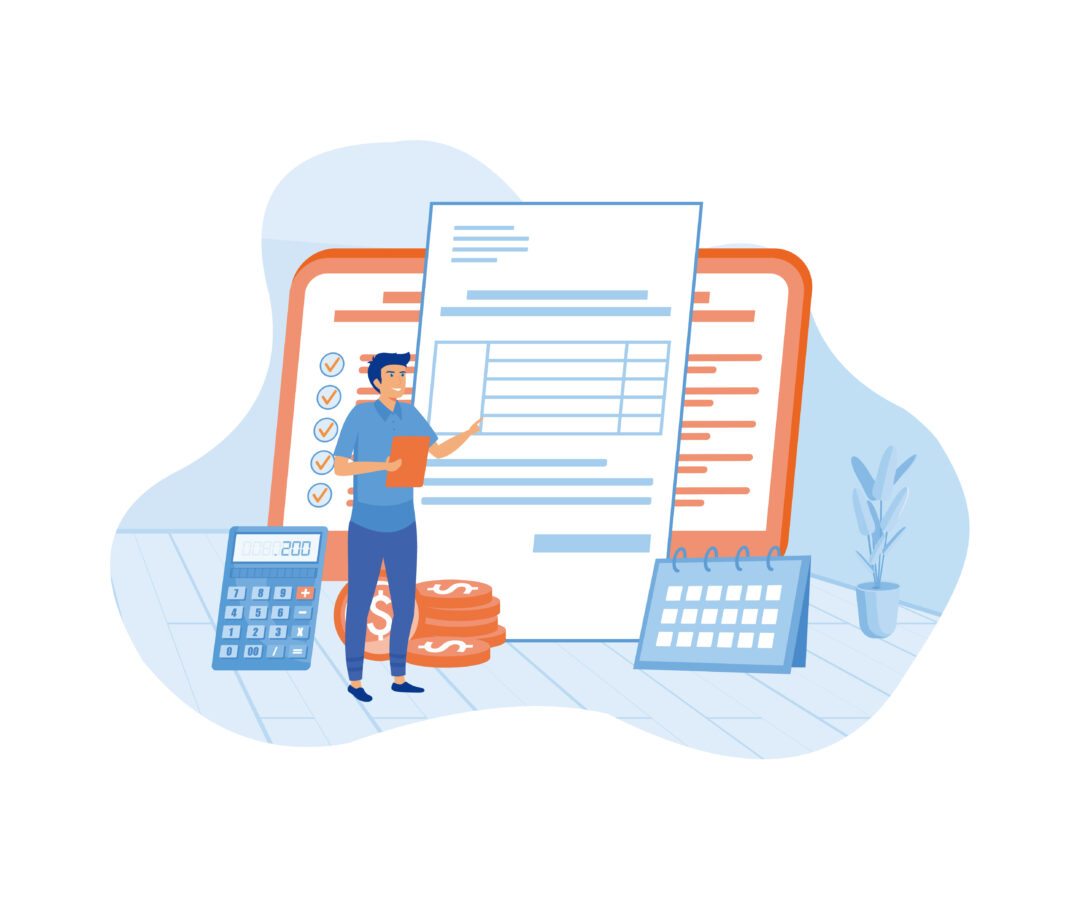
公庫融資の自己資金は、口頭で「あります」と言うだけでは足りず、通帳などの書類で裏付けて説明することが前提になります。
準備のポイントは、自己資金の残高だけでなく、形成の経緯や出所、資金使途との整合が第三者に追える形になっているかです。
例えば、設備購入で自己資金200万円を充当する計画なら、見積書・発注書・支払予定日と、自己資金口座の残高推移が矛盾しないように整えます。
資金繰りが厳しいときほど口座間の移動や一時的な入金が増えがちなので、申込み前に「どの口座のどの資金が自己資金か」を決め、時系列で説明できる状態にしておくと手戻りを減らしやすいです。
- 自己資金として示す口座と金額を決め、資金を散らさない
- 資金使途(設備・開業費・運転資金)の支払予定を日付付きで整理する
- 通帳の入出金に説明が必要な箇所を先に洗い出す
- 根拠書類は「入金の理由」と「支払いの予定」を両方そろえる
通帳コピー準備のコツ
通帳コピーは、自己資金の形成が自然であることを示すための基本資料です。直近の残高ページだけでは形成過程が見えにくいため、一定期間の入出金が分かる範囲で用意し、給与入金や積立の履歴、まとまった入金がある場合はその根拠まで追える形にします。
例えば、半年以上かけて毎月5万円ずつ積み立てたなら、入金と残高推移が分かるページをそろえることで説明が簡潔になります。
また、自己資金が複数口座に分散していると、合計は十分でも見え方が複雑になりやすいです。申込み前に、自己資金として示す口座を可能な範囲で集約し、口座間の移動を減らすと確認がスムーズになりやすいです。
印刷物を提出する場合は、ページ抜けや日付の欠落があると追加提出になることがあるため、必要範囲を漏れなくそろえることが重要です。
| 準備項目 | コツの目安 |
|---|---|
| 対象期間 | 残高だけでなく形成が追える期間を用意し、直前だけに偏らない |
| 入金の根拠 | 高額入金がある場合は売却・賞与など理由を説明できる資料もセットにする |
| 口座の整理 | 自己資金口座を決め、分散を減らして見え方を単純化する |
| 抜け漏れ | ページ抜けや日付欠落がないよう、必要範囲を一括でそろえる |
資金移動の説明目安
資金移動が多いと、自己資金の形成が分かりにくくなり、「一時的に残高を作ったのでは」と誤解されやすくなります。
誤解を避けるには、資金移動を時系列で整理し、「誰から、いつ、いくら、何のために動いたか」を説明できる状態にしておくことが重要です。
例えば、定期預金を解約して普通預金へ移した、家族口座から生活費精算をした、資産売却代金が別口座に入って移した、などは合理的な理由になり得ますが、説明がないと伝わりにくいです。
実務では、通帳の該当行に付せんやメモを付けるのではなく、別紙で「日付・金額・移動元・移動先・理由」を簡潔にまとめ、関連する根拠書類(解約明細、売買契約、振込控えなど)を添えると整理しやすいです。
- 資金移動は日付・金額・理由を時系列で一覧化する
- 移動の根拠になる資料(解約明細、振込控え等)を添える
- 申込み直前の大きな入金・移動は、理由と性質を特に明確化する
贈与・借入混在の注意点
自己資金の中に贈与や借入が混在すると、「返済義務のない自己資金はいくらか」が不明確になり、確認が長引きやすくなります。
贈与や援助は、返済不要であることと出所が説明できれば、自己資金の形成として説明できる場合がありますが、借入は原則として返済義務があるため、自己資金とは性質が異なります。
この2つが同じ口座で混ざっていると、自己資金の額の見せ方が複雑になるため、可能なら入金を分けて管理し、内訳が追える形にするのが現実的です。
例えば、親族から100万円の援助を受けた一方で、別の親族から50万円を一時的に借りた場合、通帳上は合計150万円の増加に見えても、自己資金として説明できるのは100万円に限られる可能性があります。
申込み前に、資金の性質ごとに区分し、返済の有無・条件を説明できる形で整理しておくことが重要です。
- 贈与・援助は返済不要である根拠と出所を説明できるようにする
- 借入は自己資金と混同せず、返済条件と資金使途を別枠で整理する
- 同一口座で混ざる場合は、内訳が追えるよう時系列と根拠資料を整える
自己資金が不足のとき対策
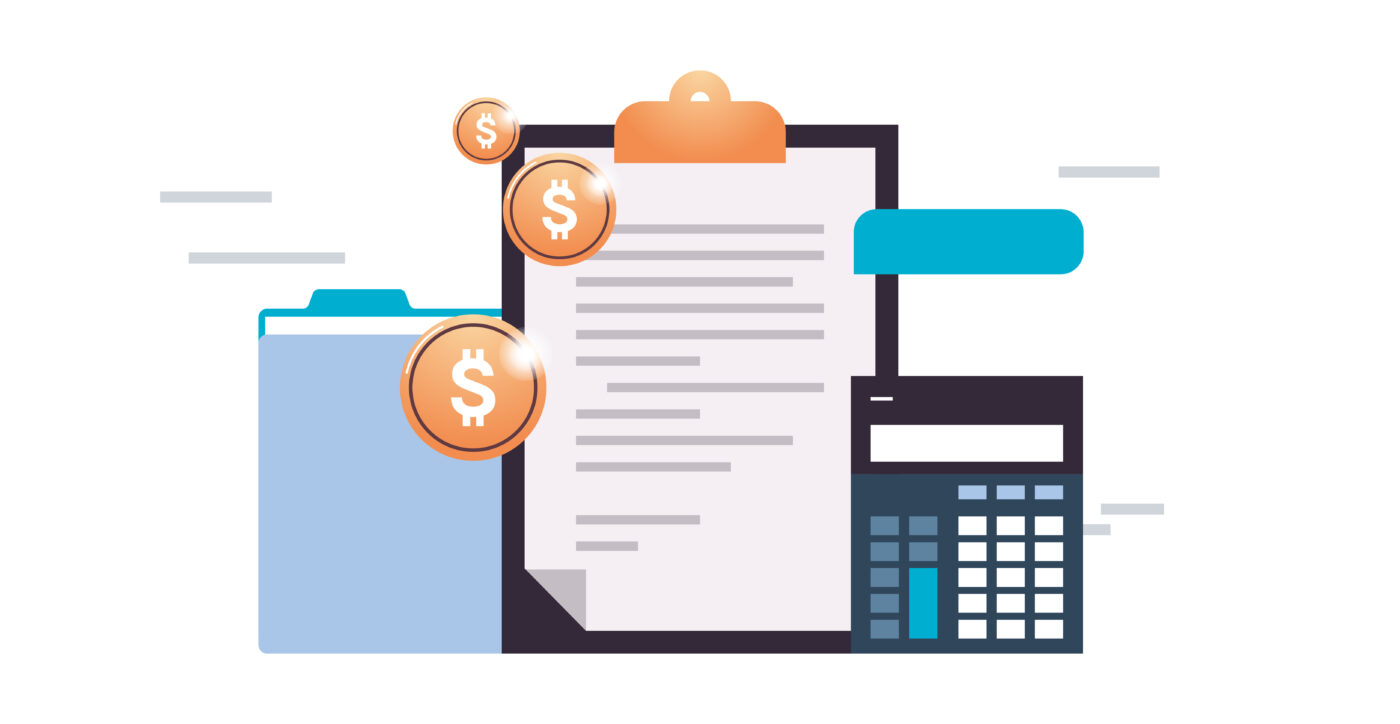
自己資金が不足している場合でも、すぐに諦めるのではなく「必要資金の再点検」「自己資金の配分の見直し」「不足額の説明のしかた」を整えることで、計画の現実性を高めやすくなります。
自己資金は多いほど安心材料になりやすい一方、自己資金を用意するために無理な資金移動をすると、形成の経緯が不自然に見え、追加確認が増える要因にもなります。
まずは、設備・開業費・運転資金の内訳を見直し、支払時期を含めて「本当に今必要か」「段階的に投資できないか」を整理します。
そのうえで、資金繰り表を作成し、売上入金が安定するまでの期間を想定して、月次で資金が枯れない計画になっているかを確認するのが基本です。
- 必要資金の内訳を再点検し、設備と運転資金を分けて考える
- 自己資金の配分を見直し、運転資金を残す設計にする
- 不足額を明確化し、借入で賄う部分の根拠を示す
- 支援機関を活用し、計画と書類の整合を第三者目線で点検する
不足額の決め方ポイント
不足額は「借りたい金額」から決めるのではなく、「資金使途の合計」と「自己資金で賄える範囲」の差額から決めるのが基本です。
特に創業期は、必要資金の見積りが甘いと、融資実行後に追加資金が必要になりやすいので、設備・開業費は見積書で裏付け、運転資金は固定費と変動費を分けて見積もります。
例えば、創業資金が合計600万円(設備350万円、開業費50万円、運転200万円)で、自己資金が200万円なら、単純な差額は400万円です。
ただし、自己資金を設備の頭金に充てるのか、運転資金に残すのかで、借入額の妥当性と資金ショートのリスクは変わります。
決め方のポイントは、支払時期と入金時期を前提に、資金繰り表で最も資金が薄くなる月(最低残高)を確認し、その谷を埋める金額にすることです。
| 項目 | 不足額算定の考え方 |
|---|---|
| 設備・開業費 | 見積書や契約に基づき、支払日と金額を確定する |
| 運転資金 | 家賃・人件費など固定費と、仕入など変動費を分けて月次で見積もる |
| 自己資金 | 返済不要で自由に使える資金に絞り、口座と金額を明確化する |
| 借入額 | 差額だけでなく、資金繰り表の最低残高を基準に妥当性を確認する |
運転資金の配分事例
自己資金が限られる場合は、設備投資に自己資金を使い切らず、運転資金を残す配分が重要になります。
創業直後は売上が発生しても入金が遅れやすく、固定費は毎月発生します。例えば、飲食店の開業で、内装・厨房機器に自己資金を全額投入してしまうと、開業後の家賃・人件費・仕入の支払いが回らず、黒字でも資金ショートすることがあります。
配分の一例として、自己資金200万円がある場合に、設備の頭金に120万円、開業費に30万円、運転資金として50万円を確保するなど、当面の支払いに耐える余力を残す考え方が有効です。
運転資金は「何か月分」という表現だけでは曖昧なので、家賃・人件費・水道光熱などの固定費合計と、入金までのタイムラグを踏まえて、最低限必要な月数を資金繰り表で確認します。
- 売上は立っても入金が遅れ、支払いが先行して資金が底をつきやすい
- 仕入や外注の支払いが滞り、営業継続に影響が出やすい
- 追加借入や条件の悪い資金調達に頼りやすくなる
支援機関の活用法
自己資金が不足している局面ほど、第三者の支援を使って計画の精度を上げることが有効です。代表的な相談先として、商工会・商工会議所、よろず支援拠点、認定経営革新等支援機関などがあります。
これらは、事業計画の前提(売上・粗利・固定費)の妥当性、資金使途の整理、資金繰り表の作り方、必要書類の不足チェックなどで役立つ場合があります。
例えば、自己資金200万円で創業資金600万円を計画する場合、資金繰り表の最低残高がマイナスにならないか、売上の立ち上がりが遅れた場合の調整策(固定費の抑制、仕入の調整、販促計画の見直し)を一緒に点検できます。
申込み前に計画の矛盾をつぶしておくと、面談での追加質問が減り、手続きが進めやすくなります。
- 支援機関でできること:事業計画の整合確認、資金繰り表の作成支援、必要書類の点検
- 活用のコツ:見積書・通帳・売上根拠など手元資料を持参し、数字で相談する
- 申込前の目的:不足額の妥当性と、運転資金の安全余力を第三者目線で確認する
創業期の申込み準備

創業期は決算実績が少ないため、自己資金の形成過程と事業計画の整合が、審査での説明材料になりやすいです。
準備段階では、自己資金の金額を示すだけでなく、通帳の履歴で「いつ・どのように積み上げたか」を説明できる形にし、創業資金の使い道(設備・開業費・運転資金)と支払時期を日付ベースで整理します。
さらに、売上の根拠と費用の前提をそろえ、資金繰り表で最低残高がマイナスにならないかを点検すると、面談での手戻りを減らしやすくなります。
- 自己資金:形成の経緯と出所を通帳で追える状態
- 資金使途:見積書・契約書・支払予定日の整理
- 資金繰り:売上入金の遅れを織り込んだ月次の残高推移
形成ストーリーの作り方
形成ストーリーは、自己資金が「返済不要で、無理なく積み上がった資金」であることを伝えるための説明です。
ポイントは、直近だけを切り取らず、一定期間の残高推移を示しながら、入金理由が説明できる材料をそろえることです。
例えば「毎月の給与から5万円ずつ積立」「賞与の一部を貯蓄」「資産売却代金を入金」など、通帳の動きと一致する説明にします。
申込み直前に大きな入金がある場合は、根拠資料を添えて時系列で説明できる形に整えると誤解を避けやすいです。
| 要素 | 用意したい材料の目安 |
|---|---|
| 積立の継続 | 毎月の入金・残高推移が分かる通帳履歴 |
| まとまった入金 | 賞与・売却・退職金など入金理由の根拠(明細等) |
| 資金移動 | 口座間移動の理由と日付・金額の一覧(簡単なメモで可) |
| 使途との整合 | 自己資金で支払う予定(手付金等)と残高推移の一致 |
事業計画との整合チェック
自己資金の説明ができても、事業計画の数字と資金使途が噛み合っていないと、資金需要の妥当性が弱く見えやすいです。
整合チェックでは、売上の根拠(単価・件数・契約見込み)と費用(固定費・変動費)を整理し、支払いと入金のタイミングを資金繰り表に落として、資金が薄い月が出ないかを確認します。
特に創業直後は入金が遅れやすいので、自己資金を初期費用に使い切らず、運転資金を残す配分になっているかが重要です。
- 設備に自己資金を使い切り、運転資金が残らない
- 売上は計画しているが、入金時期が資金繰り表に反映されていない
- 見積書の金額と申込金額、支払時期の前提がずれている
- 固定費が高いのに、売上立ち上がりが弱い前提になっている
申込から実行までの流れ
創業期の申込みは、相談から実行までに資料作成と確認が重なるため、スケジュール管理が重要です。
特に、設備の支払日や物件契約日が先に決まっている場合は、実行時期が遅れると資金繰りに直結します。
申込み前に、自己資金の提示資料、資金使途の根拠、事業計画、資金繰り表をそろえ、面談での質問(売上根拠、費用、入金サイト、自己資金の出所)に一貫して答えられる状態にしておくと手続きが進めやすくなります。
- 事前整理:資金使途・自己資金・資金繰り表を一本化して準備
- 相談・申込:必要書類を提出し、資金需要と計画の筋道を説明
- 面談・確認:自己資金の出所、売上根拠、支払予定の整合を確認
- 条件提示:融資額・返済期間などの条件を確認し、計画と再照合
- 契約・実行:実行日を確定し、支払いスケジュールに間に合うか最終確認
まとめ
公庫融資の自己資金は、単に金額の多寡だけでなく、形成の経緯や出所が説明できるかが重要になりやすく、通帳履歴や資金移動の整合が審査のポイントになります。
要件の目安は資金使途や事業計画とセットで考え、見せ金と疑われる動きや贈与・借入の混在は事前に整理して書類で説明できる状態にします。
自己資金が不足する場合でも、必要額の決め方や運転資金の配分を見直し、支援機関の活用も含めて準備を進めることで、申込みから実行までの手戻りを減らしやすくなります。