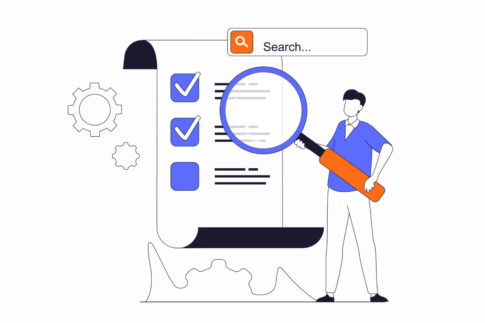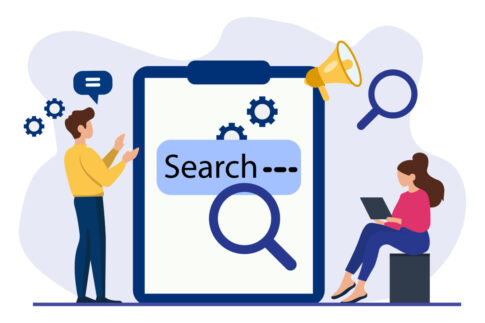運送業で資金繰りが厳しい——まず整えるべきは現金残高の見える化と制度の正しい理解です。
本記事は資金繰り表の作成、公庫・保証協会・セーフティネットの仕組み、借換えや条件変更の進め方、標準運賃と燃油サーチャージ導入までを整理。実務に使える要点とチェック表を簡潔に示します。
症状見極めと資金繰り表整備

資金繰りが厳しいと感じたときは、原因が「一時的な入出金のズレ」なのか「採算悪化の恒常化」なのかを切り分けることが出発点です。
運送業では、燃料単価の上振れ、通行料・整備費の増加、車両リースや保険料の固定的負担、売掛金の入金遅延が同時に起きやすく、体感だけでは実態をつかみにくいです。
まずは週次の資金繰り表で、手元資金→当週入金→当週出金→週末残高の流れを見える化します。継続的に更新すれば、入金サイトの長さや季節変動、特定荷主の遅延傾向、燃油の増減などが数値で把握できます。
月次だけでなく13週の先読み(四半期相当)を併用すると、納税や車検など一時的な大型出金の山も事前に織り込めます。
可視化の目的は「足りない」の把握ではなく、「いつ・いくら・なにが原因で」不足が生じるかを特定し、対策(回収前倒し、支払い調整、資金調達、価格転嫁)を順序立てて選ぶことにあります。
| 区分 | 記載例(週次フォーマット) |
|---|---|
| 期首残高 | 前週末の現金・預金残高 |
| 入金 | 売掛回収、雑収入、保険金等 |
| 出金 | 燃料・オイル、通行料、整備・部品、車両リース、保険料、給与・外注、社会保険、税金、地代家賃 等 |
| 期末残高 | 期首+入金−出金(翌週の期首へ連結) |
資金繰り表の基本用語と作成
資金繰り表は「いつ・いくら現金が動くか」を示す運転資金の台帳です。用語の要点は次のとおりです。
期首残高は週の始まりの現預金、入金は売掛回収など現金の流入、出金は燃料費や給与など現金の流出、期末残高はその差し引きです。
作成時は会計上の「売上・費用」ではなく、あくまで現金主義で記録する点が重要です。運送業の特徴として、売上から入金までのサイトが長い一方、燃料や通行料など日々の即時出金が多いことがあります。
そこで、荷主別の入金予定を明細で置き、出金は固定と変動を分けると、ズレの原因が見えます。初回は前月の通帳・請求書・明細から実績を転記し、翌週以降に差分を反映するだけで精度が上がります。
【作成ステップ】
- 対象期間を決める(週次+13週先読みを推奨)。
- 期首残高を確定し、通帳残高と一致させる。
- 荷主別の回収予定を日付・金額で並べる。
- 出金は「固定(リース・保険・家賃等)」と「変動(燃料・外注等)」に分類。
- 週末に実績で上書きし、翌週へ繰り越す。
- 売掛は荷主別・案件別で予定日を明記
- 燃料・通行料はカード締め日と引落日を分けて管理
- 特別出金(税金・車検・保険年払い)は事前に週次へ分解して見込み計上
手元資金の安全水位と算定
「安全水位」は、入金のズレや突発出金があっても支払いを止めないための最低限の現金水準です。
絶対的な公式はありませんが、運送業では入金サイトが長めなことを踏まえ、固定費(給与・リース・保険・家賃等)と、最低限発生する変動費(燃料・外注等)をベースに、入金までの平均日数をカバーする日数分の現金を確保する考え方が実務的です。
まず自社の荷主構成と入金条件(末締め翌月末払い等)を洗い出し、平均回収日数を把握します。次に、固定費の月額と、最低運行に必要な燃料等の支出を週次で見積もり、入金までの期間に相当する金額を安全水位の目安に置きます。
安全水位を設定したら、資金繰り表の週末残高が下回るタイミングを事前に検知し、回収前倒しや支払い調整、調達手段の検討を前広に行います。
| 項目 | 把握方法 | メモ |
|---|---|---|
| 平均回収日数 | 請求日と入金日の差を荷主別に平均 | 「末締め翌々月」など長い先があるか確認 |
| 固定費 | 給与・リース・保険・家賃等の月額合計 | 支払日ベースで週次へ按分 |
| 最低変動費 | 最低運行本数の燃料・外注を試算 | 繁忙・閑散で幅をもたせて見込む |
- 安全水位は「自社の入金条件×最低運行コスト」を基準に設定します。
- 月次だけでなく週次で点検し、下回る見込みが出たら早期に対策を検討します。
売掛回収と燃油支出の可視化
資金繰り悪化の多くは、売掛金の遅延と燃油支出の膨張が同時進行で起きることにあります。まず売掛は「請求→承認→入金」の各段階で滞りがないかを可視化します。
配車表・伝票・運行管理データと請求書の紐づけを定型化し、荷主別の回収予定カレンダーを作ると、遅延の早期察知が可能です。
燃油は単価の変動だけでなく、車両ごとの燃費、アイドリング比率、ルート選定による通行料とのトレードオフを指標で管理します。
カード払いは「利用日」と「引落日」がずれるため、資金繰り表では締め日・引落日を分けて入力します。これにより、実態より遅れて資金が減る「見込み違い」を防げます。
【KPIの例】
- 売掛回転日数、入金遅延件数(荷主別)
- 燃料単価(仕入先別)、平均燃費(km/L)
- アイドリング率、空車率、通行料/走行距離
- 入金前のリマインド送付(支払予定日の数営業日前)
- 検収差異の即日照合(伝票・GPS・荷姿写真)
- 長期遅延は与信見直しや回収条件の再協議へ
公的融資・保証の仕組みと選択基準

資金繰りが厳しい局面では、「誰が資金を貸すのか」「誰がリスクを負うのか」を理解すると選択が速くなります。
日本政策金融公庫(以下、日本公庫)は国の直接融資で、審査から実行まで公庫の窓口で完結します(国民生活事業/中小企業事業などの区分あり)。
一方、信用保証協会付融資は民間金融機関からの借入に保証協会が保証を付ける仕組みで、返済不能時は協会が代位弁済して資金繰りを下支えします。
セーフティネット保証は一般保証と別枠で利用でき、原則100%保証(5号は原則80%)が用意され、突発的な売上悪化時の選択肢になります。
運送業では入金サイトが長く、燃料・通行料など即時出金が多いので、「着金までの速さ」「返済期間の柔軟さ」「別枠の有無」を基準に、直貸し(日本公庫)と保証付(民間+協会)を並行検討するのが現実的です。最新の制度詳細は日本公庫・中小企業庁・保証協会の公式情報で確認してください。
| 比較軸 | 日本公庫(直接融資) | 信用保証協会付融資 |
|---|---|---|
| 窓口 | 日本公庫の支店で申込・審査・実行 | 取引金融機関で申込、保証協会が審査 |
| 仕組み | 公的金融機関が直接貸付 | 金融機関が貸付、協会が保証(代位弁済) |
| 特徴 | セーフティネット貸付等の制度枠あり | 一般保証80%、セーフティネットは原則100%・別枠 |
| 枠 | 制度ごとに限度額を設定 | 保証限度額は制度により別枠設定 |
日本政策金融公庫の融資区分
日本公庫の融資は大別して「国民生活事業(個人・小規模)」「中小企業事業(中堅の中小企業)」「農林水産事業」に分かれます。
運送業では、開業間もない個人事業・小規模法人は国民生活事業、車両台数や売上規模が大きい法人は中小企業事業が入口になりやすいです。
いずれも直貸しのため、返済計画と資金繰り表、荷主構成、入金サイト、車両更新計画など、実態に基づく説明が重要です。景気・災害など外部要因で一時的に業況が悪化した場合は「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」等で、運転資金の長期化や据置期間の設定などが検討できます。
該当する事業区分と制度条件を公庫サイトで確認し、支店への相談予約→必要書類の準備→申込という順に進めるとスムーズです。
- 国民生活事業:個人・小規模向け。小口・機動的な資金繰りに適合。
- 中小企業事業:中堅向け。大型の更新投資・長期資金も視野。
- セーフティネット貸付:外的要因で悪化時の資金繰り安定に活用。
- 直近の試算表・決算書、資金繰り表(週次+13週先)
- 荷主別の入金条件一覧(末締め・翌月末払い等)
- 車両リース契約・保険料・通行料など固定費の内訳
信用保証協会付融資の構造
信用保証協会付融資は、借り手・金融機関・保証協会の三者で成り立ちます。申込は金融機関で行い、並行して保証協会が審査します。
保証承諾後に金融機関が実行し、万一返済が滞ると協会が代位弁済します。現在は「責任共有制度」により、一般保証では金融機関も一定割合のリスクを負担(通常80%保証)し、協力して伴走支援を行う仕組みです。
一方、自然災害等に起因する4号や、経済危機に対応する危機関連保証などのセーフティネット保証は、一般保証と別枠で原則100%保証が用意され、平時よりも資金を調達しやすく設計されています。
詳細な枠や必要手続は、全国信用保証協会連合会・中小企業庁・各保証協会の最新案内で確認しましょう。
| 当事者 | 役割の要点 |
|---|---|
| 借り手 | 金融機関で申込。必要書類の提出・返済計画の提示。 |
| 金融機関 | 審査・実行・伴走支援。一般保証では一部リスクを負担。 |
| 保証協会 | 保証審査・保証決定・代位弁済。セーフティネットは別枠運用。 |
- 保証料率は業況・担保・期間等で変動(金融機関へ最新を確認)
- 条件変更・返済猶予は早めの相談が前提(資金ショート前)
- 保証の利用は信用情報に記録。将来の借入余力も踏まえて設計
セーフティネット保証と対象業種
セーフティネット保証は、中小企業信用保険法に基づく経営安定関連保証(1〜8号)と、危機関連保証に区分されます。
4号(自然災害等)や危機関連は原則100%保証、5号(業況悪化業種)は原則80%保証とされ、いずれも一般保証とは別枠で利用できます。
5号の対象業種は四半期ごとに経済産業省が指定し、市区町村長の認定を受けてから金融機関・保証協会へ申込みます。運送業が対象に含まれるかは時期で変わるため、最新の「指定業種一覧(四半期ごと)」で日本標準産業分類の該当有無(例:道路貨物運送関連)を必ず確認してください。
指定期間内に市区町村へ認定申請すれば、申請後の実行が期間外でも対象となる場合があるなど、手続要件も公式で確認しましょう。
- 5号:経産省の「対象業種一覧」告知とPDFを確認
- 4号・危機関連:中小企業庁の制度概要と自治体の認定窓口を確認
- 申請順序:市区町村で認定→金融機関・保証協会へ申込み
公庫・保証協会の申請手順と必要書類
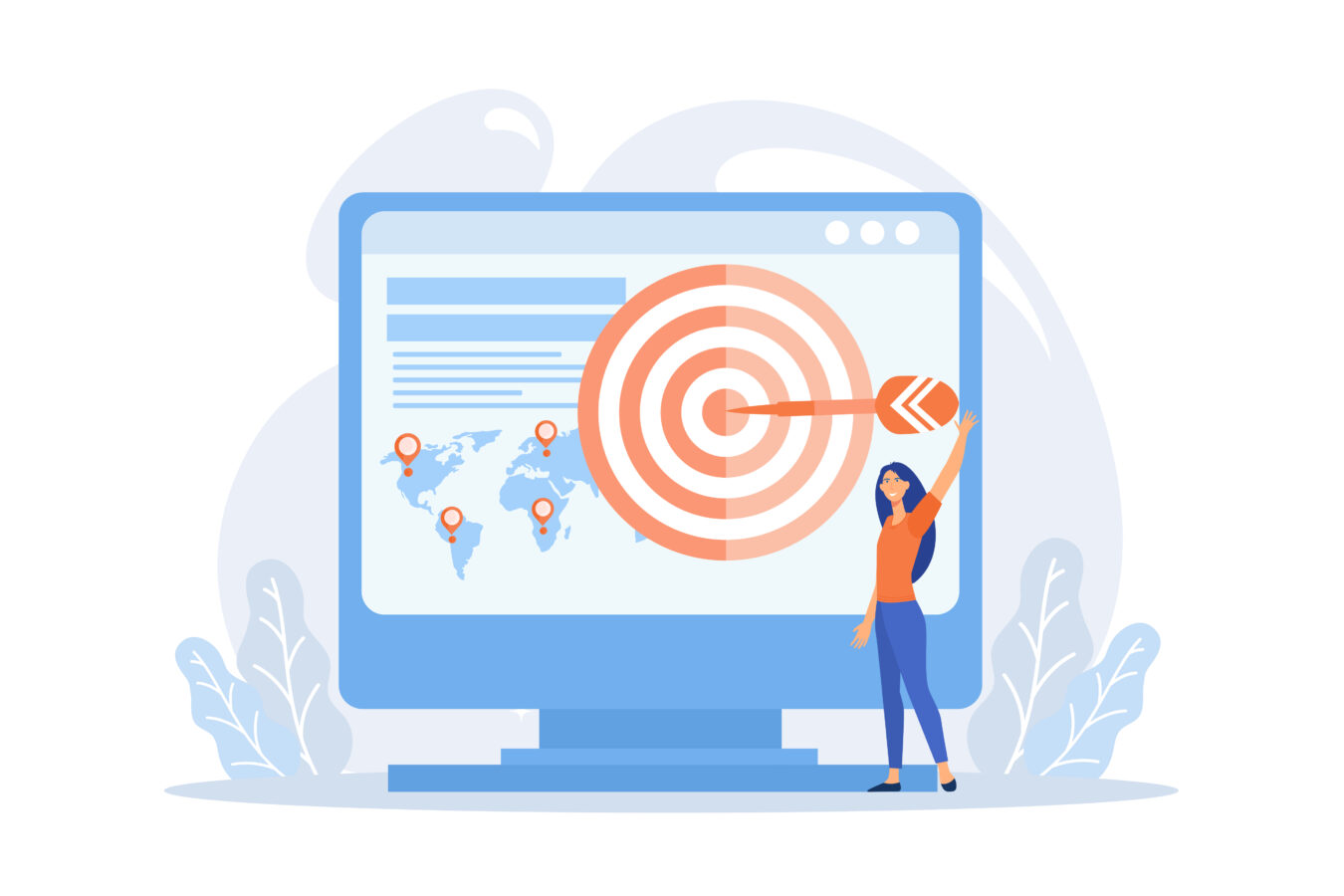
公的支援で資金繰りを立て直すには、「どの窓口に何を持参し、どんな順番で動くか」を最初に固めます。日本政策金融公庫(直貸し)は、公庫の支店やオンラインから申込ができ、必要書類の様式も公開されています。
信用保証協会付融資は、金融機関経由または保証協会窓口のどちらからでも申込でき、審査は保証協会と金融機関の双方で行われます。
セーフティネット保証を使う場合は、まず市区町村の認定(5号・4号など)を先に受け、その認定書を持って金融機関または保証協会へ進むのが原則です。地域で運用が異なる点もあるため、最新の手順・様式は各公式ページで必ず確認しましょう。
| 区分 | 主な窓口 | 事前手続・ポイント |
|---|---|---|
| 日本政策金融公庫 | 公庫支店/インターネット申込 | 様式公開済・オンライン可。必要書類は制度により追加あり。 |
| 保証協会付融資 | 取引金融機関/保証協会 | 保証協会と金融機関が審査。手順・様式は地域で差異あり。 |
| セーフティネット保証 | 市区町村→金融機関/保証協会 | 先に市区町村の認定取得(認定書を添付して申込)。 |
相談予約から申込までの流れ
まず資金使途と必要額・時期を整理し、申込先の候補(公庫/保証協会付)を決めます。日本公庫は支店相談のほかインターネット申込が可能で、フォームに沿って基本情報と書類を提出します。
保証協会付は、取引金融機関の窓口で融資と保証の同時申込をするか、保証協会に直接相談して申込書を受け取る二つの入口があります。
セーフティネット保証を利用する場合は、市区町村での認定が先行手続です。いずれも、面談時に資金繰り表と返済計画を用意しておくと審査がスムーズです。
- 資金使途・必要額・希望時期を整理(運転/設備、据置の要否など)。
- 日本公庫の相談予約・オンライン申込、または金融機関/保証協会へ相談。
- 必要書類を準備し、申込(保証協会付は銀行審査と保証審査)。
- 面談・追加資料提出(資金繰り表、見積書、契約予定など)。
- 可決後、契約・実行(セーフティネットは認定書の有効期限に注意)。
法人・個人の必要書類
必要書類は制度・地域で一部異なりますが、共通する中核は「直近の確定申告書・決算書」「事業計画・資金繰り表」「身分・資格を示す書類」です。
日本公庫では、原則として最近2期分の確定申告書/決算書の提出が求められ、オンライン申込時はPDFでの提出に対応しています。
保証協会付でも、決算書等に加え、セーフティネット利用時は市区町村の認定書が必要です。以下は代表例です(地域・制度で変わるため、最終は各公式の案内で確認してください)。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 確定申告書・決算書(最近2期分) | 損益・貸借・勘定科目内訳等を一式で。未申告は取扱いが異なるため各制度の規定に従います。 |
| 試算表・売上台帳 | 最新の業況把握に使用。月次推移があると説明しやすい。 |
| 事業計画書・資金繰り表 | 資金使途、返済原資、据置の要否、13週予測などを記載。 |
| 登記事項証明書/本人確認書類 | 法人は履歴事項全部証明書、個人は運転免許等。 |
| 見積書・契約予定書類 | 設備・車両更新など資金使途の裏付けに使用。 |
| セーフティネット認定書 | 5号・4号等の利用時に添付(市区町村で事前取得)。 |
事業計画と資金繰り表の評価
審査では「資金使途の妥当性」「返済原資の確度」「資金ショート回避の実現性」が一貫して見られます。事業計画では、荷主構成と入金条件、標準運賃や燃油サーチャージ等の価格転嫁策、車両の稼働計画(休車・更新含む)を論理的に示します。
資金繰り表は現金主義で作成し、13週の先読みで大型出金(税・車検・保険年払い)を織り込むと据置期間や返済期間の根拠になります。
返済能力の指標としては営業CFや債務返済余力(DSCR:年間キャッシュフロー÷年間元利支払)などが重視されますが、数字の前提(単価・本数・燃費・回収日数)を説明できるかが合否を分けます。
- 資金使途と回収の対応関係(運転なら回転短縮策、設備なら増収・省コストの根拠)
- 価格転嫁とコスト管理(標準運賃・燃油サーチャージ、燃費・通行料のKPI)
- 資金繰りの先読み(13週予測、据置期間の根拠、代替案の用意)
返済条件の見直しと借換え手順

資金繰りが厳しくなったときは、返済を止める前に「条件変更(リスケ)」と「借換え・一本化」のどちらが実態に合うかを整理します。
運送業は入金サイトが長く、燃料・通行料の即時出金が重いため、元金据置や返済期間の延長で月次負担を下げるだけで持ち直す場面も多いです。
一方で、複数の高金利・短期借入が混在しているなら、一本化で返済日をそろえ、平均金利を下げる選択肢が現実的です。いずれも延滞が出る前の早期相談が前提で、保証協会付融資では保証人(協会)の同意が必要になります。
費用(保証料・事務手数料・担保再設定費・違約金)と、実行までの時間軸を資金繰り表に落とし込み、着金まで耐えられるかを併せて確認しましょう。
| 場面 | 主な手続・選択肢 | 実務のポイント |
|---|---|---|
| 直近の支払が逼迫 | 条件変更(元金据置・期間延長) | 延滞前に相談/据置中の運転資金不足に注意 |
| 高金利・短期が多い | 借換え・一本化(返済日統一) | 平均金利と総支払額、諸費用を比較 |
| 保証付が多い | 保証協会の同意手続 | 別枠の可否・保証料率・担保差替の要否を確認 |
- 資金繰り表で「不足の時期と額」を確定(13週先まで)。
- 取引金融機関・日本公庫のどちらへ何を相談するかを決める。
- 必要書類(決算書・資金繰り表・返済計画・見積等)を準備。
- 条件変更/借換えの影響を試算(毎月負担・総支払額・費用)。
- 面談→審査→契約。実行時期を資金繰りに反映し運行計画も調整。
返済猶予と条件変更の相談
返済猶予は、一定期間「元金のみ据置」または「返済期間の延長」で月次の資金流出を抑える方法です。売掛回収のズレや一時的な費用増が主因で、数か月の回復見込みがあるときに適合します。
相談時は、遅れの原因と回復シナリオ(価格転嫁・運行効率化・固定費見直し等)を、資金繰り表と事業計画で具体化することが重要です。
保証協会付融資では、金融機関と保証協会の双方が判断するため、早めに連絡し、必要な追加資料(受注証明、荷主との協議経過など)を整えておくと進行が速くなります。
延長だけでは総支払額が増える可能性もあるため、据置後の返済水準で再度資金ショートが起きないかを必ず試算します。
- 資金繰り表(週次+13週):不足発生日と不足額の根拠
- 回復策の裏付け:単価改定・燃費改善・外注見直しの効果見込み
- 希望条件の幅:据置期間、延長年数、毎月返済の許容レンジ
- 猶予は「当面の流出抑制」、延長は「平準化」。どちらも恒久策ではない点を理解します。
- 延滞後より延滞前の相談の方が選択肢は広がります。
複数借入の借換えと一本化
複数の短期・高金利・返済日の異なる借入が並立している場合は、一本化で「支払日の集中」「重複費用の発生」「資金繰りの読みづらさ」を解消できます。
運送業ではカード系運転資金や短期借入が増えがちで、引落日が月内に点在すると資金の谷が深くなります。
借換えでは、既存借入ごとの残高・金利・残存期間・担保/保証の有無・違約金の有無を整理し、一本化後の条件と比較します。保証協会付が含まれる場合は、同協会の同意や「内枠借換(同一保証枠内)」「別枠取扱」の可否を事前に確認します。
総支払額は伸びても、毎月の資金繰りが安定し、配送計画やドライバー稼働に集中できるメリットがあるかを実務で評価します。
| 項目 | 確認内容 | メモ |
|---|---|---|
| 残高・金利 | 各借入の残高と実質年率 | カード系は実質負担が高い場合あり |
| 返済日 | 月内の引落集中日・バラつき | 一本化でピーク平準化を狙う |
| 担保・保証 | 根抵当/物上保証、保証協会の関与 | 差替・再設定費用と手続時間を考慮 |
| 費用 | 保証料・事務手数料・違約金 | 回収できる効果(利息削減・遅延防止)と比較 |
- 既存借入の台帳化(残高・金利・返済日・担保保証・期限前償還条件)。
- 一本化後の条件案を取得(金融機関/日本公庫)。
- 月次負担・総支払額・費用を比較し資金繰り表へ反映。
- 保証協会・担保権者の同意や差替手続を事前確認。
- 実行日を入金・支払サイクルに合わせ、引落集中を回避。
金利・返済期間見直しの判断
金利引下げや期間延長の可否は、「月次キャッシュの改善」と「総支払額の増加」を天秤にかけて判断します。期間を延ばせば毎月の支払いは軽くなりますが、利息は増えやすくなります。
反対に、短縮や金利引下げが実現できれば総支払額は抑えられますが、月次負担が増える場合があります。
実務では、年間の返済余力(営業キャッシュフロー÷年間元利支払)を確認し、少なくとも計画上は1を上回る水準を目指すと資金ショートの再発を避けやすくなります。
また、据置期間終了後の返済額や、燃料・保険の見直し効果、標準運賃・燃油サーチャージの導入状況を前提に織り込み、無理のない返済曲線を設計します。
- 金利交渉は「取引状況・担保・保証・財務改善の実績」を示して進めます。
- 期間延長は総支払額の増加を伴う可能性があるため、更新投資や車両維持計画と併せて検討します。
- 変動金利の場合は上昇リスクを資金繰り表で感応度分析しておきます。
- 延滞後の相談は選択肢が狭まるため、兆候段階で早期連絡
- 諸費用(保証料・手数料・担保再設定・違約金)を必ず総額で比較
- 保証付は協会の同意が必要なケースがあるため、手続時間を見込む
標準運賃と燃油サーチャージ導入

標準運賃と燃油サーチャージは、原価上昇を可視化し、荷主と合意形成するための「共通言語」です。国土交通省は標準的な運賃を告示し(距離制・時間制・加算項目の考え方を例示)、2024年の見直しでは運賃水準の引上げや荷役対価の加算明確化等を示しました。
燃油サーチャージについても、標準的運賃の解説・Q&Aで設定の考え方が整理され、告示・通達に沿う形で算式や適用方を定められます。
まず自社の運行実態(車種・走行距離・荷待ち・荷役・回送)を棚卸しし、標準運賃の枠組みで原価と対価の対応関係を説明できる資料を整えましょう。
次に、サーチャージは「基準燃料価格」「改定トリガー(例:一定変動幅)」「算定係数」「請求書での明示」を事前に取り決め、定期レビューのルールを合意します。
これにより、継続的な価格協議(価格交渉促進月間など)でも論点を共有しやすく、過度な値下げ圧力や不当な据え置きの抑止にもつながります。
| 段階 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 準備 | 原価/KPIの整理、標準運賃と適用方の理解 | 距離・時間・加算(荷待ち/荷役等)の切り分け |
| 設計 | 標準運賃の社内基準、燃油サーチャージの枠組み案 | 基準燃料価格・改定幅・適用対象の定義 |
| 協議 | 荷主と根拠資料で合意形成 | 見積・契約・請求での明示、定期レビューを規定 |
標準運賃の算定根拠と協議
標準運賃は、距離制・時間制に加えて、荷待ち・荷役・付帯業務などの加算を組み合わせる考え方です。国土交通省の告示・解説資料・適用方の参考様式を使うと、どの工程に、どの対価が対応するかを荷主に説明しやすくなります。
実務では、(1)走行距離と運転時間の二軸を分解し、(2)荷待ちや積卸し、附帯作業の発生頻度と所要時間を明示し、(3)回送や特殊車両・繁忙期等の割増の要否を確認、という順で根拠を整えます。
見積は標準運賃の項目構成に沿って「見える化」し、契約書・注文書に反映、請求書でも内訳を維持することで、後日の価格交渉時にも説明がぶれません。
2024年見直しの趣旨(荷役対価の加算明確化等)を引用しつつ、自社のKPIと併せて提示すると合意が得られやすくなります。
- 走行・待機・荷役・回送を分解し、標準運賃の項目にマッピング。
- 項目ごとに数量(km/時間/回数)と根拠(運行データ)を整備。
- 見積・契約・請求で同じ内訳を明示し、定期レビューを規定。
- 標準運賃の解説/Q&A・適用方(参考例)の該当ページを添付
- 実走行データ(テレマ・伝票)とKPI(燃費・空車率)の抜粋
- 繁忙/閑散や車型別の代表ケース(距離・時間・加算)
燃油サーチャージ導入と明示
燃油サーチャージは、燃料価格の変動を運賃に反映させるための仕組みです。標準的運賃のQ&Aでは、サーチャージの設定・見直しに関し、基準燃料価格や改定の判断基準を定めて継続的に適用する考え方が示されています。
導入時は(a)基準燃料価格の定義(例:公表指標の月次平均)、(b)改定トリガー(一定幅・一定期間の変動等)、(c)算定係数(燃料コスト感応度)、(d)適用対象(貸切/混載・車型・地域など)を事前に決め、(e)見積・契約・請求書でサーチャージを独立項目として明示します。
国交省のプレス・解説も、燃料高騰分を適正に転嫁しうる枠組み整備を打ち出しているため、定期レビューのルールと改定履歴の保管をセットにすると実務が安定します。
| 項目 | 取り決め例 | 運用の要点 |
|---|---|---|
| 基準燃料価格 | 公的指標の月次平均を採用 | 指標名・参照サイト・反映月を契約に明記 |
| 改定トリガー | ±X円/L または ±Y%以上 | 頻繁な微調整を避け、四半期レビュー等で反映 |
| 算定方法 | 差額×係数×(距離/時間 等) | 算式は告示/Q&Aに沿って整合性を確保 |
| 明示方法 | 見積・契約・請求で独立行として記載 | 適用期間・係数・指標値・改定履歴を記録 |
下請法・独禁法と価格転嫁
価格交渉や転嫁の妨げになる行為は、独占禁止法の「優越的地位の濫用」や下請代金支払遅延等防止法(下請法)の「買いたたき」に該当するおそれがあります。
公正取引委員会の指針は、受注者が公表資料等に基づいて適切なタイミングで転嫁を求め、交渉記録を作成・保管することを推奨しています。
中小企業庁は毎年3月・9月を「価格交渉促進月間」とし、フォローアップ調査と指導・助言を行っています。
運送委託のような継続取引で「スポット扱い」を理由に協議なく据え置くことも問題視されうる旨が明記されており、標準運賃・サーチャージの根拠を示して定期協議することが防御線になります。自治体や支援機関の相談窓口も活用しつつ、合意形成と記録保存を習慣化しましょう。
- 価格協議の拒否・不当な据え置きは独禁法/下請法リスク
- 交渉記録(日時・参加者・根拠資料)を双方で作成・保管
- 価格交渉促進月間に合わせ、定期レビューと改定ルールを運用
まとめ
資金繰り悪化時は、(1)資金繰り表で現状把握→(2)公庫・保証協会・セーフティネットの適用確認→(3)借換え・条件変更の相談準備→(4)標準運賃・燃油サーチャージで価格転嫁の検討、の順で対応。
本文のチェック表と必要書類を活用し、誤解を避けて安全に手続きを進めましょう。