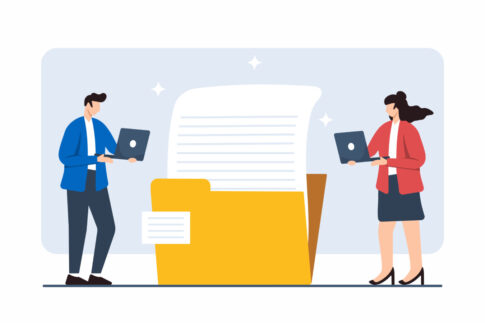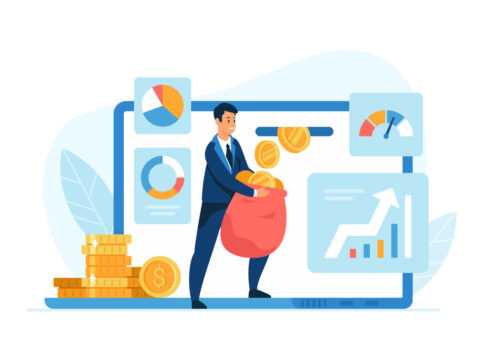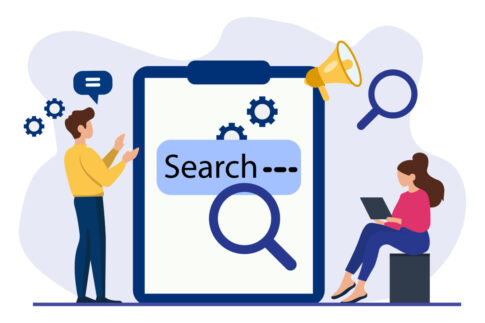「ファクタリング会社を選びたいけれど、そもそも何を比較すれば良いのか分からない」「安全性や手数料が不安」という中小企業は少なくありません。
本記事では、ファクタリング会社の役割や銀行系・独立系・オンライン型の違い、2社間・3社間スキーム、中小企業向け・フリーランス向け・医療介護特化など会社タイプ別の特徴を整理します。あわせて、手数料相場や入金スピード、安全性の見極め方、自社に合う会社を絞り込むチェックポイントまで客観的に解説します。
目次
ファクタリング会社の基礎知識

ファクタリング会社は、企業が保有する売掛金(売掛債権)を買い取り、一定の手数料を差し引いて資金を前倒しで支払う金融サービスを提供する事業者です。
中小企業支援機関の解説でも、ファクタリングは「売掛金をファクタリング会社に売却して現金化する資金調達手法」と位置付けられており、融資とは異なり貸借対照表上は債権の売却として扱われる点が特徴とされています。
現場レベルでは、ファクタリング会社は主に次のような役割を担います。
- 利用者(資金調達したい企業)から請求書や契約書などを預かり、売掛金の実在性を確認する
- 売掛先(取引先)の信用力や支払実績を審査し、買取の可否や手数料率・買取率を決定する
- 契約締結後、売掛金額から手数料を差し引いた金額を短期間で入金する
- 支払期日に売掛先から売掛金を回収し、必要に応じて回収事務も代行する
スキームとしては、売掛先に債権譲渡を通知する「3社間ファクタリング」と、利用者とファクタリング会社だけで完結させる「2社間ファクタリング」に大別されます。
3社間では売掛先からファクタリング会社に直接入金されるためリスクが小さく、手数料が低く抑えられやすい一方、3者の合意が必要で資金化までに時間がかかる傾向があります。
2社間は売掛先に知られずに資金調達しやすい半面、ファクタリング会社の回収リスクが高く、その分手数料が高めになりやすいという整理が一般的です。
なお、金融庁は「ファクタリング全般を直接規制する専用法はない」一方で、ファクタリングを装った違法な貸付けや高額手数料に対する注意喚起を行っており、契約内容によっては貸金業法等の適用対象になり得ることを指摘しています。
利用者側としては、こうした制度背景も踏まえたうえで、後述する安全性の確認や業者選定のポイントを押さえておくことが重要です。
| 当事者 | ファクタリング会社との関係 |
|---|---|
| 利用者企業 | 売掛金を譲渡し、手数料控除後の資金を受け取る |
| 売掛先企業 | 3社間ではファクタリング会社へ直接支払い、2社間では従来通り利用者へ支払い |
| ファクタリング会社 | 売掛金の審査・買取・回収を行い、その対価として手数料を得る |
ファクタリング会社とは何をする企業か
ファクタリング会社の中心的な役割は、「売掛金の買取(または保証)を通じて、企業の資金繰りを支えること」です。
中小企業支援機関の解説では、ファクタリングは売掛金を早期現金化することで、入金サイトが長い取引や売上の急増局面でも運転資金を確保しやすくするサービスとされています。
利用者から見ると、銀行融資とは別枠で資金を確保でき、売掛先の信用力を活用して資金調達できる点が特徴です。
ファクタリング会社が実務で行う主な業務は、役割ごとに分けると次のとおりです。
- 審査業務:売掛先の信用調査(財務内容・支払実績・業界動向など)や、請求書・契約書に基づく債権の実在性確認
- 契約・スキーム設計:買取型(売掛金の譲渡)か保証型(売掛金保証)か、2社間か3社間か、ノンリコースかリコースかなどの条件整理
- 資金供給:請求書額面に対する買取率(例:90〜100%)と手数料率を決定し、利用者の口座へ入金
- 回収・管理:支払期日に売掛先から売掛金を受け取り、必要に応じて回収事務や入金消込を行う
金融庁の情報によれば、ファクタリング自体を包括的に規制する専用法はありませんが、ファクタリングを装いつつ実質的には高金利貸付を行っている事案については注意喚起がなされており、そのような場合は貸金業法等の規制対象となる可能性があるとされています。
これは「ファクタリング会社であれば必ず問題がある」という意味ではなく、契約内容によっては融資と同等の法的評価を受けうる、という制度的な位置付けを示したものです。
利用者としては、ファクタリング会社が提供しているのが
- 売掛金の早期買取を行う「買取型ファクタリング」なのか
- 売掛金の回収不能時に一定割合を補償する「保証型ファクタリング」なのか
- あるいは別の金融商品なのか
を見極め、契約書に記載されたスキームとリスク分担を理解しておく必要があります。
の章で触れるように、同じ「ファクタリング会社」でもサービス内容や法的性格が異なる場合があるため、「何をしている会社なのか」を最初に整理しておくことが、安全な利用につながります。
- 売掛金やその回収を引き受け、企業の資金繰りを平準化する
- 売掛先の信用力を前提に審査・スキーム設計・資金供給を行う
- 契約内容によっては、買取型・保証型など法的な性格が異なる
- 制度上は専用法はないが、ケースによっては貸金業規制の対象となり得る
銀行系・独立系・オンライン型の違い
ファクタリング会社は、運営母体や提供チャネルによって大きく「銀行系」「独立系(ノンバンク系)」「オンライン型・クラウド型」に分けられ、それぞれ強みと注意点が異なります。
ファクタリング専門サイトなどでも、銀行系は低手数料・高い信頼性、独立系はスピードと柔軟性、オンライン型は小口・少書類・非対面対応に強みがあると整理されています。
まず銀行系ファクタリングは、銀行やそのグループ会社が提供するサービスで、3社間ファクタリングを中心に、大口の売掛金を対象とした案件を取り扱うことが多いとされています。
審査に時間はかかりますが、ノンバンクや独立系と比べて手数料が低めに設定される傾向があり、信用力の高い売掛先との取引に向いています。
一方で、数千万円以上の大口案件が中心で、中小企業や個人事業主にとっては利用しづらいケースもあると指摘されています。
独立系(ノンバンク系)ファクタリング会社は、銀行グループに属さない事業者が運営するもので、最短即日などスピードに優れ、中小企業・個人事業主・フリーランス向けの少額取引にも対応しやすいのが特徴です。
その一方で、ファクタリング業の開業自体には許認可が不要であることから、独立系のなかには、高額な手数料を設定する業者や、金融庁が注意喚起しているような「偽装ファクタリング」に該当し得る業者も含まれる可能性が指摘されています。
利用にあたっては、後述のとおり会社情報や実績、説明の透明性を確認することが重要です。
オンライン型・クラウド型ファクタリングは、申込から審査・契約・入金までをオンラインで完結できるサービスで、会計データや請求書データと連携して少額の売掛金をスピーディーに資金化できることが多いとされています。
最近の解説では、2社間ファクタリングで「最短即日入金」「少額(数十万円〜)対応」といった特徴を持つサービスも紹介されており、特にフリーランスや小規模事業者が小口の資金ニーズを埋める際に活用されるケースが増えています。
これらの違いを整理すると、次のようなイメージになります。
| タイプ | 主な特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 銀行系 | 3社間中心・大口案件が多い/審査に時間がかかるが手数料は低め/親会社が金融機関で信頼性が高い | 売掛先が大企業で、数千万円規模の資金を比較的低コストで調達したい企業 |
| 独立系(ノンバンク系) | 中小・小規模向け/審査が柔軟でスピード重視/手数料は銀行系より高め/業者間の質の差が大きい | 銀行融資が難しい、少額〜中口の資金を迅速に調達したい中小企業・個人事業主 |
| オンライン型・クラウド型 | 少額・短期の2社間案件に強み/Web完結・書類少なめ/フリーランス・小規模事業者向けのサービスが多い | 数十万〜数百万円程度のスポット資金が必要なときに、スピードと手軽さを重視したい事業者 |
- 「手数料の低さ」や「信頼性」を重視するなら銀行系を優先候補にする
- 「スピード」や「利用のしやすさ」を重視するなら独立系・オンライン型を中心に検討する
- 独立系・オンライン型を利用する場合は、会社概要・実績・説明の透明性を必ずチェックする
- 自社の規模と資金ニーズに合ったタイプを選び、過不足のない組み合わせを意識する
ファクタリング会社の主な種類

ファクタリング会社は、提供しているスキーム(2社間・3社間)と、主に想定している利用者層(中小企業・フリーランス・医療介護機関など)によって性格が大きく分かれます。
2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社だけで契約を完結させる方式で、売掛先に通知せずに資金調達したいニーズを想定したサービスが中心です。
一方、3社間ファクタリングは、売掛先にも債権譲渡を通知し、売掛金をファクタリング会社に直接支払ってもらう方式で、取引先との関係も含めたスキーム設計が前提になります。
また、利用者層に応じて、一般の中小企業向けのほか、個人事業主・フリーランス専用の小口ファクタリング、診療報酬・介護報酬に特化した医療介護ファクタリングなど、業種・報酬の種類に特化した会社も存在します。
これらの専門特化型は、対象となる債権(請求書・診療報酬明細・介護給付費明細など)の事務フローや支払元(支払基金・国保連合会・自治体など)に詳しいことが多く、一般的な売掛金ファクタリングとは審査の視点や必要書類が異なるのが特徴です。
| 分類軸 | 主なタイプ |
|---|---|
| スキーム | 2社間ファクタリング(通知なし)/3社間ファクタリング(通知あり) |
| 利用者規模 | 一般的な中小企業向け/スタートアップ・小規模事業者向け/フリーランス向け |
| 業種特化 | 医療・介護(診療報酬・介護報酬)/建設・運送・人材派遣など特定業種にフォーカスしたサービス |
2社間・3社間対応と取扱いスキーム
2社間ファクタリングは、利用者(資金を受け取る企業)とファクタリング会社の2者間で契約を結び、売掛先には債権譲渡を通知しないスキームです。
実務では、利用者が売掛先から売掛金を受け取り、その一部をファクタリング会社に支払う形や、指定口座への入金を前提に回収を管理する形が採られます。
売掛先との関係性に配慮しやすく、申込から入金までが比較的短期間で完了しやすいことから、「急ぎで資金が必要」「取引先に知られたくない」といったニーズに対応したサービスが多くなっています。
3社間ファクタリングは、利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者が関わるスキームで、売掛先に対して債権譲渡通知を行い、売掛金をファクタリング会社に直接支払ってもらう形が基本です。
売掛先の了承を得る必要があるため、導入や説明に一定の手間はかかるものの、ファクタリング会社から見ると回収ルートが明確なため、2社間と比べて手数料率が低く抑えられる傾向があります。
大口案件や長期的な利用を前提としたサービスでは、3社間スキームを前提とする会社も少なくありません。
また、買取型(売掛金そのものを買い取る)か、保証型(万一の未回収時に一定割合を保証する)かによっても、ファクタリング会社のリスクの持ち方や契約の仕組みが変わります。
買取型は、請求書額面から手数料を差し引いた金額が前倒しで入金されるシンプルな構造で、資金調達ニーズに直接応える一方、保証型は売掛金の回収リスクを部分的に軽減する保険的な機能が強く、取引全体のリスク管理を重視する会社が取り扱うことが多いです。
- 2社間は「売掛先に知られにくい」「スピード重視」だが、手数料は高めになりやすい
- 3社間は「売掛先への通知・協力」が前提だが、手数料は抑えやすい
- 買取型は資金調達色が強く、保証型はリスクヘッジ色が強い
- 自社の目的(資金繰り優先か、リスク管理優先か)に合わせてスキームを選ぶことが重要
中小企業向け・フリーランス向け・医療介護特化
ファクタリング会社の多くは「中小企業向け」を標榜していますが、実際にはターゲットによってサービス設計が細かく分かれています。
一般的な中小企業向けファクタリング会社は、製造業・卸売業・建設業・運送業など、企業間取引で売掛金が発生する幅広い業種を対象にしており、取扱金額も数百万円〜数千万円規模が中心です。
審査では、売掛先の信用力や取引実績、請求書・契約書・納品書などの書類整備状況が重視されます。
一方、フリーランス向けファクタリング(いわゆる「フリーランスファクタリング」)は、Web制作・ライター・デザイナー・エンジニアなど個人事業主を対象に、数十万〜数百万円程度の請求書をオンラインで資金化できるサービスとして提供されるケースが多くなっています。
勤怠データや業務委託契約書、クラウドソーシング・エージェントからの報酬明細といった資料をもとに審査を行い、最短即日〜数営業日で入金する仕組みが一般的です。
医療介護特化型のファクタリング会社は、診療報酬債権や介護報酬債権を専門に扱います。
診療報酬は診療月の翌々月以降に支払基金・国民健康保険団体連合会から入金されるなど支払サイクルが決まっているため、そのタイムラグを埋める目的で病院・クリニック・歯科医院・訪問看護ステーション・介護事業者向けのファクタリングサービスが提供されています。
審査では、レセプト(診療報酬明細書)や診療報酬の過去入金実績が重視され、売掛先は公的な支払機関であることから、通常の売掛金ファクタリングと比べて債権の信用度が高いと評価されやすい一方、制度や請求フローに関する専門知識が求められる領域です。
これらを踏まえ、自社の立場と照らし合わせると、次のような整理ができます。
- 製造・卸・建設・運送などの一般的なBtoB企業:中小企業向けの買取型ファクタリング会社が候補
- 個人事業主・フリーランス:少額・オンライン完結型のフリーランス特化サービスを中心に検討
- 病院・クリニック・介護事業者:診療報酬・介護報酬に特化した医療介護ファクタリング会社を優先候補にする
- 複数の債権タイプを併用する場合:各債権の特性に応じて、一般型と特化型を組み合わせることも選択肢
手数料・入金スピードで見る比較ポイント

ファクタリング会社を比較するうえで、多くの利用者が最も気にするのが「いくら引かれるのか(手数料)」と「いつ入金されるのか(スピード)」です。
一般的な売掛金ファクタリングでは、2社間ファクタリングの手数料相場はおおむね8〜20%、3社間ファクタリングは1〜9%程度とされており、2社間の方が高くなりやすいことが複数の業界解説で示されています。
一方、診療報酬など公的機関が支払元となる医療系ファクタリングでは、0.2〜0.8%/月や0.8〜2%など、一般の売掛金ファクタリングよりかなり低めの手数料が提示されている例もあります。
入金スピードについては、オンライン型の2社間サービスでは「最短30分〜数時間で入金」とする会社もあれば、銀行系や3社間スキームでは2〜5営業日程度を要するケースも見られます。
また、買取可能額の上限も会社により異なり、10万円〜1億円、1万円〜、上限なし(過去7億円までの実績あり)など、金額レンジの違いがサービス選びに直結します。
つまり、「安い会社=常にベスト」ではなく、自社の売掛金額・資金が必要なタイミング・売掛先の性質に応じて、手数料とスピードのバランスを見ながら比較することが重要です。
| 比較軸 | 押さえておきたいポイント |
|---|---|
| 手数料相場 | 2社間8〜20%、3社間1〜9%前後が一般的。診療報酬などは1%前後と低め。 |
| 入金スピード | オンライン2社間は最短30分〜数時間、銀行系3社間は数営業日程度が目安。 |
| 買取可能額 | 数万円〜数百万円中心の小口特化から、上限なし・数億円まで対応する会社まで幅広い。 |
| 追加費用 | 手数料以外に、事務手数料・登記費用・振込手数料が発生する会社もある。 |
手数料相場と見積もり確認のコツ
手数料を比較する際は、まず「自社の案件が相場のどのゾーンに入るのか」を把握することが出発点になります。
複数の解説によれば、2社間ファクタリングの手数料はおおむね8〜18%、高いところで20%程度、3社間ファクタリングは1〜9%が一般的な範囲とされています。
これを大きく上回る見積もりが出てきた場合は、「単に高いのか」「売掛先リスクや少額・短期など、条件面での理由があるのか」を確認する必要があります。
一方で、オンライン型のクラウドファクタリングや大手企業が提供するBtoB早期支払いサービスでは、案件や売掛先によっては1〜5%といった低水準の手数料が提示されている例もあります。
診療報酬・介護報酬ファクタリングは、売掛先の信用度が高く未回収リスクが小さいため、0.2〜0.8%/月や1%前後といった水準が目安とされるケースもあり、一般の売掛金ファクタリングと比べて明らかに相場が異なります。
見積もりを取る際の実務的なコツとしては、次のような手順が有効です。
- 自社の案件が「2社間/3社間」「一般売掛金/診療報酬・介護報酬」など、どの相場帯に属するかを事前に把握する
- 複数社に同一条件(売掛先・金額・支払サイト)で見積もりを依頼し、「手数料率」「買取率」「その他費用」の3点を一覧化する
- 手数料率だけでなく、事務手数料・登記費用・振込手数料などを含めた「総コスト」で比較する
- 前倒し日数と利用回数を踏まえ、実質年率のイメージと年間総コストを簡単に試算しておく
また、「相場よりかなり安い」場合も注意が必要です。あまりに低い手数料をうたっている場合、別名目の費用が後から加算される、買取条件が非常に限定的、あるいは償還請求権付き(未回収時に利用者が全額負担)でリスクが重い、といった可能性もあります。
契約書や重要事項説明で、「いつ・どの条件のときに、いくら差し引かれるのか」を最後まで確認してから判断することが、安全な会社選びの前提になります。
入金スピード・上限額・審査基準の違い
入金スピードは、ファクタリング会社のタイプとスキームによって大きく異なります。オンライン完結型のサービスでは、「最短30分〜2時間で入金」「審査最短15分」など、即日資金化を前面に出している会社が複数存在します。
一方、銀行系ファクタリングや3社間スキームでは、売掛先の了承や社内審査プロセスが必要なため、申し込みから入金まで2〜5営業日程度を要するケースが多いとされています。
買取可能額の上限も会社ごとに幅があり、オンライン小口特化型では「1万円〜数百万円」、中小企業向け一般ファクタリングでは「10万円〜上限なし」や「100万円〜1億円」、大手事業者では「3万円〜7億円までの実績」といった例も見られます。
自社の売掛金規模に対して上限が十分かどうかを確認しないと、「審査は通ったが、必要額の半分しか資金化できない」といったミスマッチが起こり得ます。
審査基準については、銀行系や大口案件向けのファクタリングでは、利用者企業の財務内容や業歴も重視される一方、独立系やオンライン型の多くは「売掛先の信用力」と「請求書の実在性」「取引実績」に軸足を置いて審査する傾向が強いとされています。
つまり、直近の決算が赤字であっても、売掛先が上場企業・大企業で支払実績が安定していれば、一定の条件で利用できる余地がある一方で、売掛先が新規取引先・与信情報の少ない企業である場合は、手数料増額や買取額の制限といった条件が付く可能性があります。
入金スピード・上限額・審査基準を比較する際には、次のような視点で整理すると分かりやすくなります。
- 「いつまでに・いくら必要か」を資金繰り表で具体化し、即日か数日以内かで候補を切り分ける
- 自社の売掛金額と、各社の買取可能額レンジ(最小〜最大)を照らし合わせる
- 自社よりも売掛先の信用力が重視されるタイプか、自社の財務内容が重視されるタイプかを確認する
- スピードを優先する場合でも、手数料と審査基準(過度な条件や償還条項)のバランスを必ず確認する
このように、「手数料が安い会社」だけでなく、「必要なタイミングに間に合うか」「必要な金額をカバーできるか」「自社と売掛先の与信に合った審査スタイルか」を含めて比較することで、自社にとって実務的に使いやすいファクタリング会社を選びやすくなります。
安全なファクタリング会社の見極め方

ファクタリング自体は、中小企業の資金繰りを支える有効な手段ですが、一部には「ファクタリング」を名乗りながら実質は高金利の貸付を行う業者も存在します。
金融庁は、「債権額に比べて著しく低い買取代金」「買戻し義務が実質的に付いている」などのケースは、貸金業登録のない業者による違法な貸付に当たるおそれがあるとして注意喚起を行っています。
日本貸金業協会も「偽装ファクタリング」として、買主が回収リスクを負わず、債権回収できない場合に買戻しを強要するスキームは、実態は貸付であり、無登録業者であればヤミ金融に該当すると警告しています。
安全なファクタリング会社を見極めるには、「誰が運営しているか」「どのような団体・制度に基づいているか」「契約内容や料金体系が透明か」といった基本情報の確認が欠かせません。
業界には、一般社団法人オンライン型ファクタリング協会や一般社団法人日本ファクタリング業協会など、一定のガイドラインや苦情受付窓口を設けている業界団体も存在しますが、公的機関ではなく自主規制団体である点も理解しておく必要があります。
| 確認すべき観点 | 具体的なチェック内容 |
|---|---|
| 運営主体 | 商号・所在地・代表者名・設立年月・資本金・グループ企業などが明記されているか |
| 制度・登録 | 貸金業登録や業界団体加盟状況、苦情・相談窓口の有無などが確認できるか |
| 契約内容 | 手数料や償還請求条項などが分かりやすく説明されているか、実質が貸付に近くないか |
| 情報公開 | ウェブサイトやパンフレットで料金体系やサービス内容が具体的に開示されているか |
会社情報・実在性・業界団体加盟の確認
ファクタリング会社の安全性を判断するうえで、まず確認したいのが「会社情報」と「実在性」です。
金融庁や日本貸金業協会は、違法な金融業者への注意喚起のなかで、「所在地が不明瞭」「登録番号を詐称」「連絡先が携帯電話のみ」といった特徴を挙げ、利用しないよう呼びかけています。
ファクタリング業そのものには専用の登録制度はありませんが、貸金業に該当するスキーム(実質的に貸付と同様の機能を持つ取引)であれば、貸金業登録が必要であり、無登録であれば違法となる可能性があると金融庁は説明しています。
また、ファクタリング業界には、一般社団法人オンライン型ファクタリング協会や一般社団法人日本ファクタリング業協会といった業界団体が存在し、それぞれガイドラインの策定や会員企業一覧の公開、利用者からの苦情受付などを行っています。
これらの団体は公的機関ではありませんが、「一定の基準を満たした会員企業であるか」「協会のガイドラインに従っているか」といった点を確認する一つの目安になります。
実務上は、次のようなステップで会社情報と実在性を確認するのがお勧めです。
- 商号・所在地・代表者名・連絡先(固定電話の有無)・設立年月・資本金をウェブサイトや登記情報で確認する
- 貸金業登録が必要なスキームかどうかを税理士や専門家と整理し、必要な場合は金融庁や都道府県の登録情報を照会する
- オンライン型ファクタリング協会や日本ファクタリング業協会などの業界団体の会員一覧に記載があるか確認する
- 苦情・相談窓口の記載や、トラブル時の対応方針が開示されているかをチェックする
こうした基本情報が不十分な場合や、所在地がバーチャルオフィスのみで実態が見えない場合、会社名・代表者名で検索しても情報がほとんど出てこない場合は、慎重に検討したほうが安全です。
複数社を比較し、情報公開が整っている会社を優先候補とすることが、リスクを抑えた選び方につながります。
偽装ファクタリング・悪質業者の注意ポイント
偽装ファクタリングとは、形式上は「債権譲渡」や「ファクタリング」と称しながら、実態としては高金利の貸付に近い取引を行うスキームを指します。
日本貸金業協会は、「債権の買い取り代金が債権額に比べて著しく低額」「債権の買戻し義務があり、実質的に貸付と同じ」「貸金業登録のない業者がファクタリングを装っている」といったケースを、「ファクタリングを装ったヤミ金融」の典型例として注意喚起しています。
また、国民生活センターや各地の消費生活センターは、「借金ではない」「ブラックOK」「審査なしで即日」などの広告につられて給与ファクタリングや偽装ファクタリングを利用し、高額な手数料と強引な取り立ての被害に遭った事例を複数紹介しています。
こうした事例では、債権の買取と説明されながら、実際には元本に相当する金額を上回る返済を求められているなど、利息制限法や出資法の上限を大きく超える「ヤミ金」に該当するケースも見られます。
悪質業者を避けるためには、次のようなポイントをチェックすることが有効です。
- 「借金ではない」「ブラックでもOK」「審査なしで即日高額」などの過度な広告文句をうたっていないか
- 債権額に比べて著しく低い買取代金(例:売掛金100万円に対して入金50万円など)になっていないか
- 契約書に買戻し条項や、実質的に利用者が全ての回収リスクを負う内容が含まれていないか
- 手数料率や総支払額、遅延時の条件について、具体的な数値を明示せず「とりあえず契約を」と急がせてこないか
少しでも不審に感じた場合や、条件が複雑で理解できないまま署名を求められる場合は、その場で契約せず、必ず税理士・弁護士・公的相談窓口(金融庁金融サービス利用者相談室、消費生活センターなど)に相談することが重要です。
「早く資金が欲しい」という状況ほど判断力が鈍りやすいため、あらかじめチェックリストを用意し、どれか一つでも該当する場合は一度立ち止まる、というルールを社内で共有しておくと、偽装ファクタリングや悪質業者とのトラブルを未然に防ぎやすくなります。
自社に合うファクタリング会社選定の流れ

自社に合うファクタリング会社を選ぶときは、「なんとなく良さそうな会社に問い合わせる」のではなく、あらかじめ選定フローを決めておくと判断ミスを減らせます。
大枠の流れとしては、①自社の資金ニーズと売掛構成を整理する、②ニーズに合うタイプ(銀行系・独立系・オンライン型・業種特化型など)を仮決めし候補をリストアップする、③手数料・スキーム・入金スピード・上限額・安全性といった比較軸で絞り込む、④契約書案を入手し、税理士や専門家にも目を通してもらう、というステップで考えるのが現実的です。
特に重要なのは、「いくら足りないか」だけでなく、「いつまでに・どのくらいの頻度で必要になりそうか」「売掛先は誰か(大企業か中小か、公的機関か)」という視点まで含めて整理することです。
この情報が曖昧なままだと、手数料だけで会社を選んでしまい、自社の運転サイクルに合わないサービスを選択するリスクが高くなります。
最初に資金繰り表で不足タイミングを確認し、それに合うスキームと会社タイプを当てはめていくイメージを持つと、検討がスムーズになります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①ニーズ整理 | 金額・タイミング・頻度・売掛先の属性(業種・規模・支払サイト)を把握する |
| ②候補抽出 | ニーズに合うタイプ(銀行系/独立系/オンライン型/医療介護特化など)から複数社をリストアップ |
| ③条件比較 | 手数料率・買取率・入金スピード・上限額・スキーム・安全性を共通フォーマットで比較 |
| ④契約確認 | 条件を絞ったうえで契約書案を入手し、社内と税理士・専門家でリスクとコストを確認 |
資金ニーズ別の候補会社リストアップ
候補会社を絞り込む前に、「自社の資金ニーズに応じて、どのタイプを優先候補にするか」を決めておくと、比較の軸がぶれません。
例えば、月に1回、毎回数百万円前後の売掛金を前倒ししたい中小企業であれば、中小企業向けの独立系ファクタリング会社やオンライン型が候補になります。
一方で、年に数回、数千万円〜億単位の大口資金が必要で、売掛先が大企業の場合は、銀行系や大手グループの3社間ファクタリングが現実的です。
また、フリーランスやごく小規模な事業者で、毎月20〜100万円程度の報酬を前倒ししたい場合には、オンライン完結型のフリーランス向けサービスの方が書類負担やスピードの面で適していることが多くなります。
医療機関・介護事業者であれば、診療報酬・介護報酬を専門に扱う会社でなければ、レセプトや給付費に関する事務・制度を十分に理解してもらえず、スムーズな運用が難しくなるおそれがあります。
こうした整理を踏まえ、「金額」「頻度」「売掛先」「業種」を軸に候補会社をピックアップしていきます。
最初から1社に絞るのではなく、同じタイプの中から少なくとも2〜3社をリストアップし、次の段階で手数料・条件を比較する前提で情報収集を進めると、交渉の余地も含めて検討しやすくなります。
- 資金ニーズを「金額」「必要時期」「頻度」「期間(一時的か継続か)」に分解して整理する
- 売掛先の属性(大企業/中小企業/公的機関/個人など)と、請求書の単価帯を整理する
- 一般中小企業向け・フリーランス向け・医療介護特化など、ニーズに合うサービス領域を決める
- 各領域から、条件が合いそうな会社を2〜3社ずつピックアップし、簡単な候補一覧を作成する
比較チェックリストと専門家相談の活用
候補会社がある程度揃ったら、「比較チェックリスト」を使って条件を横並びで確認します。見るべきポイントは、単純な手数料率だけではありません。
買取率(請求書額面に対して何%前払いされるか)、前倒し日数と入金スピード、買取可能額の最低・上限金額、2社間/3社間・買取型/保証型といったスキーム、安全性(会社情報・業界団体加盟・苦情窓口の有無)、契約期間や解約条件、償還請求条項の有無など、複数の軸で確認する必要があります。
比較表は、Excelやスプレッドシートで簡単に作成できます。会社名を行、比較項目を列に並べ、各セルに数値や○×、コメントを入れていくと、「手数料は安いが上限が低い会社」「手数料は中程度だが安全性や上限に余裕がある会社」などの特徴が見えやすくなります。
この段階で、自社にとって譲れない条件(例:入金スピード、償還請求なし、最低買取額、反社チェック体制など)を明確にし、それを満たさない会社は候補から外していきます。
さらに、最終候補を2〜3社に絞った段階で、税理士や中小企業診断士、金融機関の担当者など、第三者の専門家に意見を聞くことも有効です。
特に、契約書に記載された条文(手数料計算方法、買戻し義務、債権譲渡の範囲、既存融資との関係)については、専門的な視点でリスクを確認してもらうと安心です。
「どの会社が一番安いか」だけでなく、「どの会社なら自社の財務や取引構造に無理なくフィットするか」という観点で助言をもらうことで、長期的な資金繰りの安定にもつながります。
- 手数料率・買取率・前倒し日数・入金スピード・買取上限額を一覧で比較しているか
- 2社間/3社間・買取型/保証型・償還請求の有無など、スキーム上の違いを理解したうえで選んでいるか
- 会社情報・実在性・業界団体加盟・苦情窓口の有無など、安全性に関する情報を確認したか
- 契約書案を税理士や専門家に共有し、手数料の実質コストやリスク条項について意見をもらったか
まとめ
ファクタリング会社は「どこも同じ」に見えても、スキームの種類、手数料水準、入金スピード、安全性などに大きな差があります。
まずは自社の資金ニーズ(必要金額・タイミング・期間)を整理し、銀行系・独立系・オンライン型、2社間・3社間といった軸で候補をリストアップしましょう。
そのうえで、手数料と上限額、会社情報や業界団体加盟状況、契約条件をチェックリストで比較し、必要に応じて専門家にも意見を聞きながら選定することで、過度なコストやトラブルを避けつつ、自社に適したファクタリング会社を選びやすくなります。