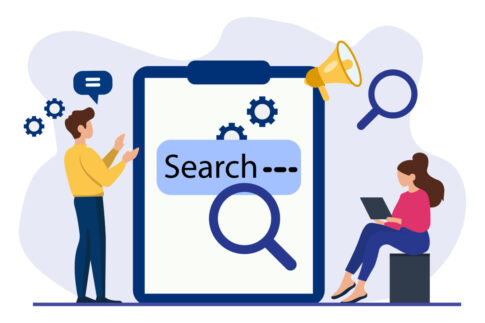「決算書なしでファクタリングは使える?」に答える実務ガイド。審査は自社ではなく売掛先の信用を重視。請求書や通帳などの必要書類、申込~入金の流れ、2社間/3社間の違い、手数料と注意点を客観的に整理。
個人事業主や赤字決算でも可能性を見極め、違法な給与ファクタリングの回避まで短時間で把握できます。
決算書なしでも使える仕組みと根拠
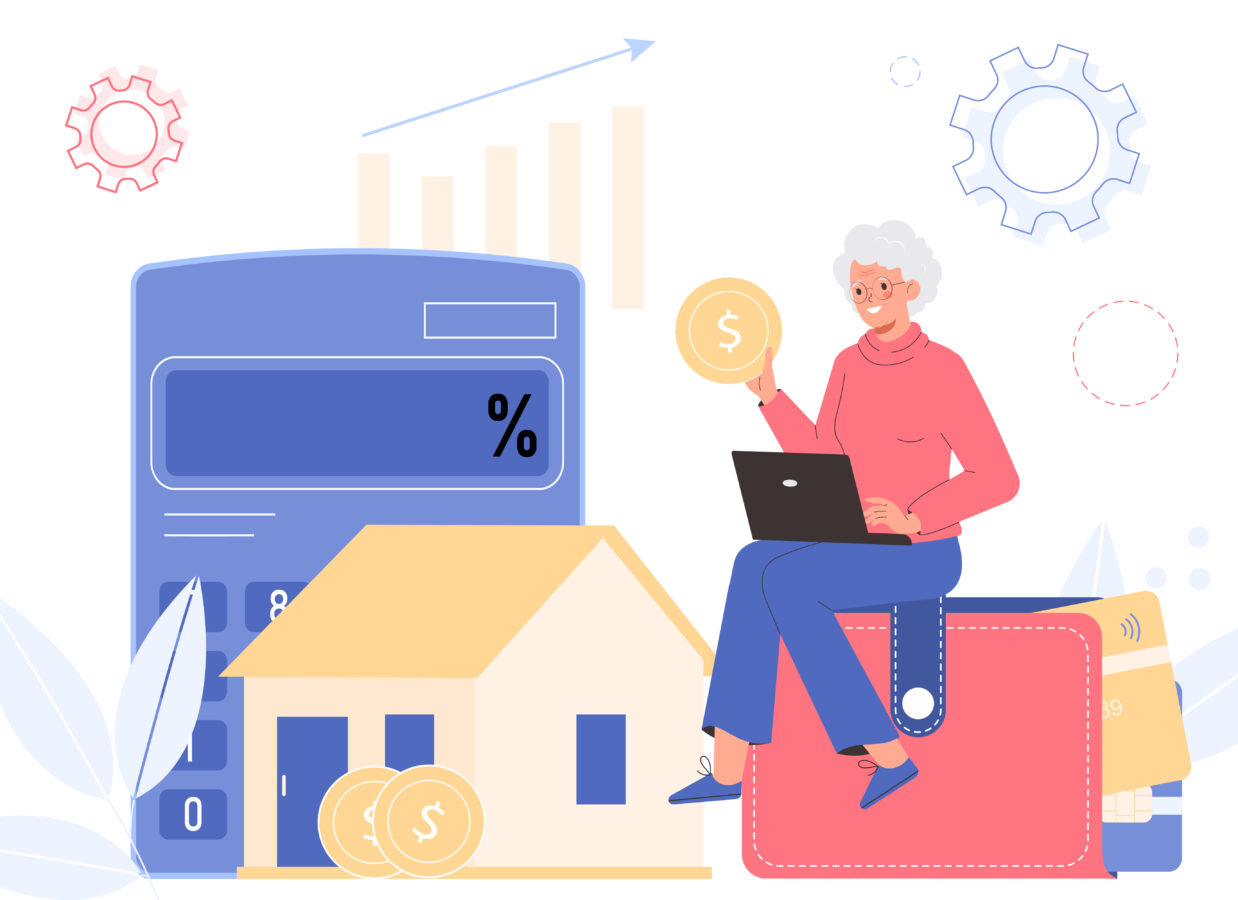
ファクタリングは、商品やサービスを納品して発生した「売掛債権」を買い取ってもらい、将来の入金を前倒しにする資金調達です。
審査の中心は申込企業ではなく、支払いを行う取引先(売掛先)の信用度と、債権が実在しているかどうかにあります。
融資のように企業の過去成績を示す決算書が絶対条件ではないのは、返済原資が「自社の将来利益」ではなく「売掛先からの入金」だからです。
たとえばイベント運営会社が毎月法人Aに請求しているケースでは、法人Aの支払実績や契約関係、請求書・納品書の整合が確認できれば、申込企業が赤字でも利用できる余地があります。
一方で、架空請求や譲渡禁止特約の存在、クレーム・返品などで債権が減る可能性があると判断されると、取引は難しくなります。
2社間(通知なし)と3社間(通知あり)で手数料や手続きが異なる点も、根拠の違いとして押さえておきましょう。
- 返済原資は売掛先の入金であり、自社決算への依存度が低い
- 審査は「売掛先の信用」と「債権の実在性・継続性」が軸
- 2社間と3社間で通知・手数料・スピードが異なる
- 譲渡禁止特約や相殺条項は成立可否に影響
審査は売掛先の信用力重視が基本
ファクタリング会社は、実際に支払いをする売掛先が「約束どおり支払うか」を最重視します。見るのは、支払遅延の有無、業歴や規模、取引実績、倒産や法的整理の兆候、そして請求書・納品書・発注書の整合です。
売掛先が安定していて、入金サイクルが明確、かつ過去の入金記録が通帳で裏づけられると、審査は前向きに進みます。
実務では、与信枠(その取引先に対して買い取れる上限)を設定し、枠内で継続利用していくイメージです。
たとえばB社に月300万円前後を継続請求し、過去6か月の入金が期日どおりである場合、与信の根拠が揃いやすくなります。
逆に、取引の発生が単発である、請求書の記載が不正確である、返品や値引きが多く債権額がブレる—といった要素は減点対象です。
| 項目 | 見るポイント | チェック方法 |
|---|---|---|
| 売掛先の信用 | 遅延履歴・業歴・支払能力 | 信用調査・官報・取引先ヒアリング |
| 債権の実在性 | 請求内容の真実性 | 請求書・納品書・発注書の突合 |
| 継続性 | 入金サイクルと過去実績 | 通帳記録・入出金明細の確認 |
| 条項の制約 | 譲渡禁止・相殺条項の有無 | 基本契約書の条文確認 |
融資と違い決算書は必須ではない
銀行融資は、返済原資を「将来の利益」と見て、申込企業の事業計画や過去の決算書を精査します。
これに対し、ファクタリングは既に発生済みの売掛債権を資金化する取引であり、焦点は「売掛先が支払うかどうか」です。
たとえば、開業2年目で直近が赤字の飲食店でも、大手ケータリング先への安定した月次請求があり、証憑が揃っていれば検討対象になります。
もちろん、決算書があるに越したことはありませんが、必須ではありません。重要なのは、請求書や契約書、納品証跡、通帳の入金履歴など、債権の確からしさを示す資料を過不足なく用意することです。
準備段階で「どの取引先の、どの請求書を対象にするのか」を絞り込み、金額・期日・入金実績を整理しておくと、審査と着金までがスムーズになります。
【主な違い】
- 焦点:融資=申込企業の信用/ファクタリング=売掛先の信用
- 原資:融資=将来利益/ファクタリング=売掛先からの入金
- 書類:融資=決算書・事業計画が中心/ファクタリング=請求書・取引証憑が中心
- スピード:融資=審査に時間/ファクタリング=証憑整備次第で短縮可
違法の給与ファクタリングに要注意
「給与債権を早期に現金化」とうたう給与ファクタリングは、実態としては手数料名目で高利の立替えを行う貸付に当たり、貸金業法や利息制限法等に抵触する違法取引として各所が注意喚起しています。
賃金は生活保障の性格が強く、法制度上も保護されています。そのため、給与を対象とするスキームはトラブルが多く、返済不能や過大な手数料請求、執拗な取り立てなど深刻な被害が報告されています。
事業者向けファクタリングと名称が似ていても、対象が「事業の売掛金」か「個人の給与」かで法的性質がまったく異なります。
資金繰りの改善を急ぐ場合でも、給与ファクタリングには手を出さず、事業の売掛債権を使った正規のファクタリングや、自治体・公的制度の資金繰り支援など、適法で透明性の高い手段を選びましょう。
- 実質は高利の違法貸付と判断されやすい
- 過大手数料・厳しい取り立てなど被害事例が多い
- 事業向けの売掛債権ファクタリングとは別物
- 公的支援や正規サービスの検討が安全
必要書類と申込から入金までの流れ

ファクタリングの審査は「売掛先が約定どおり支払うか」を見極める工程です。申込企業の決算書がなくても、請求書や通帳、契約書などで債権の実在と継続性が確認できれば前向きに進みます。
流れは、おおまかに「申込→書類提出→与信確認→条件提示→契約→入金」です。スピードを左右するのは、対象請求書の特定と証憑の整合性です。
請求金額・支払期日・入金履歴が一本の線でつながるように準備すると、やり取りが少なくなり、結果として着金も早まりやすくなります。
2社間の場合は取引先への通知を行わないぶん、債権譲渡登記を活用して対抗要件を確保するケースがあり、3社間は取引先への通知・承諾で透明性を高めるのが一般的です。
どちらを選ぶかは、手数料・スピード・開示のバランスで判断します。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 申込 | 対象請求書の概要と希望金額を連絡 | 取引先名・支払期日・金額を明確化 |
| 書類提出 | 請求書・通帳・身分確認・契約書等 | 同一取引の証憑をセットで提出 |
| 与信確認 | 売掛先の支払実績や信用状況を確認 | 遅延・返品・相殺リスクの有無を点検 |
| 条件提示 | 買取率・手数料・入金日等の提示 | 複数社で相見積もりし条件比較 |
| 契約 | 2社間/3社間・登記や通知の手続き | 条項(譲渡禁止・表明保証)を確認 |
| 入金 | 債権買取・指定口座へ送金 | 差引控除費用・入金額を事前確認 |
請求書・通帳・本人確認が中心
審査で核となるのは「請求書」「通帳(入金履歴)」「本人確認(法人・個人事業主の属性確認)」です。請求書は、売掛先名・金額・支払期日・明細が読み取れ、納品書や発注書と整合していることが重要です。
通帳は過去の入金実績を示す客観資料になり、対象取引先からの入金が定期的にあるほど評価が安定します。
本人確認は、なりすましやマネロン対策の観点から必須で、法人なら登記事項証明書や会社情報、個人事業主なら開業届や身分証の提示を求められることがあります。
これらは「過去と現在の取引の実在」を裏づける最低限のセットです。迷ったら、対象請求書を1~3件に絞り、関連する証憑をひとつのフォルダにまとめると、審査側の確認負担が下がり、条件提示までの時間短縮につながります。
【主な提出書類(例)】
- 請求書・納品書・発注書(同一取引のひも付け)
- 通帳の入出金ページ(対象取引先の入金履歴)
- 基本契約書・個別契約書(該当する場合)
- 本人確認書類(法人:登記事項証明書等/個人事業主:身分証)
- 取引先とのやり取り(注文メール、検収記録等)
取引エビデンスの例と提出方法
エビデンスは「請求の事実があり、相手が支払う見込み」を示す材料です。
典型的には、発注書・納品書・検収書・受領書・業務完了報告書、SaaSのダッシュボードや受発注システムの画面、取引先とのメールやチャットのやり取り(日時・件名・宛先が分かるもの)などが使われます。
提出時は、対象請求書ごとにフォルダを分け、契約→発注→納品→請求→入金の順に並べると、審査側が一目で流れを追えます。
画面キャプチャは解像度を確保し、必要箇所にハイライトを付けるだけで伝達精度が向上します。機微情報が含まれる場合は、契約や法令に抵触しない範囲でマスキングを行い、隠す理由をコメントで添えると誤解を防げます。
PDF化はファイル破損や改ざん検知の観点からも有効で、紙原本は万一に備えて手元保管しておくと安心です。
- 対象請求書を特定し、関連証憑を1セット化
- 金額・支払期日・発注番号にハイライトを付与
- メールはヘッダー情報(送信日・宛先)を含めてPDF化
- マスキング箇所は理由を注記し、原本は保管
債権譲渡登記の要否と注意点
債権譲渡登記は、売掛債権を第三者に対抗するための手段で、2社間ファクタリングで用いられることがあります。取引先に通知しないぶん、登記により権利関係を公示して優先順位を確保する考え方です。
一方、3社間は取引先への通知・承諾を得るため、登記を省略しても対抗力が確保されるのが一般的です。
どちらも一長一短があり、登記は開示範囲が広がる・手間と費用が発生するという現実的な負担、通知は取引先との関係性や社内承認のハードルが上がる可能性があります。
重要なのは、基本取引契約に「譲渡禁止特約」や相殺条項がないかを確認することです。
これらがあると、そもそも債権譲渡が認められない、または回収時に相殺されて買取額が減るおそれがあります。契約条項の読み合わせと、実務上のコミュニケーション設計を事前に行うと安全です。
【注意点の整理】
- 2社間:通知なしのため登記で対抗要件を補うケースがある
- 3社間:通知・承諾で対抗力を確保でき、登記省略の場面が多い
- 契約チェック:譲渡禁止特約・相殺条項の有無を確認
- 実務負担:登記はコストと開示、通知は関係性への影響に留意
個人事業主・赤字決算でも利用可否

個人事業主でも、決算書がなくても、ファクタリングは検討可能です。重視されるのは「売掛先が期日どおり支払うか」「債権(請求)の実在が証憑で裏づけられるか」です。
赤字か黒字かよりも、取引先の信用と請求~入金までの一貫性(請求書・発注書・納品書・通帳の突合)で判断されます。継続取引があり、請求金額や入金サイクルが安定しているほど前向きに評価されます。
一方、税金・社会保険の滞納や差押えリスク、契約上の譲渡禁止特約、返品・値引きが多い取引などは慎重に見られます。
実務では、対象請求書を絞り込み、関連証憑を1セット化して提示することが、審査のスピードと条件の両面で有利に働きます。
| 対象 | 可否の目安 | 留意点 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 利用余地あり | 事業実態の確認資料(開業届控え等)を求められる場合あり |
| 赤字決算 | 売掛先次第で可 | 入金履歴の安定性・取引継続性で補完 |
| 税金・社保滞納 | 不利になりやすい | 分納合意等の資料でリスク低減を説明 |
個人事業主の提出書類と実務ポイント
個人事業主の審査では、請求の真実性と事業実態の確認が要点です。核となるのは、対象請求書とそれに紐づく発注書・納品書・検収記録、そして通帳の入金履歴です。
本人確認は公的身分証で行われ、事業実態の補助資料として開業届控え、インボイス登録通知、業務委託契約書、見積書・注文書のやり取りなどを求められることがあります。
準備段階で、取引先別にフォルダを作り、契約→発注→納品→請求→入金の順で並べると整合確認が容易になります。
私用と事業用の入出金が混在していると実績の読み取りに時間がかかるため、事業用口座・決済手段を分け、請求書の番号体系・支払期日の表記を統一しておくと、審査がスムーズに進みやすくなります。
- 対象請求書を1~3件に絞り、関連証憑を1セット化
- 通帳は対象取引先の入金ページを期間連続で提出
- 事業用口座・請求番号・支払期日の表記を統一
- 開業届控え・インボイス登録通知・契約書で実態補強
赤字でも売掛先次第で利用可能
赤字は必ずしも不可ではありません。ファクタリングの焦点は返済原資となる「売掛先からの入金」にあり、申込者の損益よりも、売掛先の信用力・入金実績・契約関係が重視されます。
たとえば、安定した発注を継続する上場企業や自治体関連先への定期請求で、期日入金が続いているケースは評価が上がりやすい一方、単発案件が多い、返品・値引きが頻発する、与信の弱い先への集中が強い場合は、買取率や限度枠が抑えられがちです。
成功のカギは「どの請求を対象にするか」の選定にあります。取引履歴が長く、相手先の信用情報が安定、相殺リスクの低い請求を優先すると、手数料や条件が改善しやすくなります。
| 要因 | 評価が上がる例 | 評価が下がる例 |
|---|---|---|
| 取引継続性 | 毎月の定期請求・期日入金が継続 | 単発案件中心・入金遅延が散見 |
| 売掛先与信 | 信用調査で安定・倒産兆候なし | 業況悪化・支払遅延情報あり |
| 契約条件 | 譲渡禁止なし・相殺条項限定的 | 譲渡禁止特約あり・相殺条項が強い |
| 請求の確度 | 発注~納品~検収の証跡が明瞭 | 返品・値引きが多く債権額が変動 |
税金・社保滞納は審査で不利
税金や社会保険料の滞納があると、差押えリスクや資金管理の不安定さが懸念され、審査は不利になります。
滞納処分による預金口座・売掛金の差押えが発生すると、回収の優先順位や資金の流れが不透明になり、ファクタリングの安全性が損なわれるためです。
加えて、継続的な滞納はコンプライアンスリスクとしても評価に影響しやすい傾向があります。とはいえ、直ちに不可と断定されるわけではありません。
分納(猶予)や納付計画が成立しており、証憑で確認できる、滞納範囲が限定的で対象取引に波及しない—といった材料があれば、リスク低減の説明は可能です。申込前に現状を整理し、提出資料で透明性を確保することが重要です。
- 不利要因:差押え・相殺リスク/長期滞納の継続
- 備え:分納合意書・納付計画書・最新の納付書控えの提出
- 影響限定:対象請求先・取引に波及しない旨の説明
- 資金管理:事業用口座分離・入金フローの明確化
審査基準と落ちる典型パターン整理

ファクタリングの審査は、「売掛先が期日どおり支払うか」「請求が実在しているか」「契約上、譲渡や回収に支障がないか」を軸に総合判断されます。
申込者の損益や決算の良し悪しは副次的で、重視されるのは売掛先の信用力と、発注→納品→検収→請求→入金のつながりです。
典型的に落ちやすいのは、売掛先与信が弱い、取引が単発、請求書に不備がある、証憑がバラバラで整合が取れない、譲渡禁止特約や相殺条項が強い、滞納・差押えリスクがある、といったケースです。
たとえば新規の単発案件で、検収がメール口頭のみ、請求書の期日も曖昧、過去入金実績もない——このような案件は割引率が悪化するか、見送りとなりやすいです。
逆に、継続入金の履歴と整った証憑がそろえば、枠設定を含め前向きな打診につながります。
| 審査基準 | 見るポイント | 落ちやすい例 |
|---|---|---|
| 売掛先与信 | 遅延・倒産兆候、業況、支払姿勢 | 支払遅延の常習、業況悪化の情報 |
| 実在性・整合 | 発注〜納品〜検収〜請求の突合 | 証憑欠落、金額・期日の不一致 |
| 継続性 | 定期発注・入金履歴の安定度 | 単発案件中心、履歴が乏しい |
| 契約制約 | 譲渡禁止・相殺・通知要件 | 譲渡禁止特約、相殺条項が強い |
| 法務・リスク | 滞納・差押え、係争・クレーム | 差押え予兆、返品・値引き多発 |
売掛先与信・取引実績が弱いケース
与信の土台が弱いと、買取率は下がりやすく、場合によっては見送りとなります。
典型例は、(1)売掛先の業況悪化や遅延情報がある(2)取引が新規単発で履歴がなく、通帳に入金実績が出ていない(3)発注量や単価が月によって大きく変動し、将来の回収見込みが読みにくい、などです。
たとえば初回取引で200万円を請求しているが、契約・発注・検収の証跡が薄く、過去入金の裏づけもない場合、評価は厳しくなります。
対策はシンプルで、対象請求を「継続実績のある先」に絞り、直近6〜12か月の入金履歴を示すこと、そして注文番号や検収記録で請求の確度を補強することです。
複数の売掛先があるなら、集中しすぎない構成にすると枠設定が取りやすくなります。
- 継続実績を示す通帳ページを期間連続で提出
- 初回・単発より、既存定期請求を優先して対象化
- 注文番号・検収記録で請求の確度を補強
- 売掛先の分散で集中リスクを低減
請求書不備や虚偽申告は即NG
請求書の基本要件(相手先名、金額、品目・数量、支払期日、発行日、担当部署など)が欠けていたり、発注書・納品書・検収記録と数字や期日が一致しないと、実在性の疑義から審査は止まります。
とくに、金額の改ざん、二重請求、未納品分の先出し、過去の入金記録の加工といった虚偽は取引停止の決定打です。
SaaS画面のスクリーンショット提出時も、発注番号やタイムスタンプが分かる形で保存し、編集痕跡を残さないことが重要です。
迷ったときは、対象請求を1〜3件に絞り、関連書類を時系列で並べるだけで整合が一気に見えます。再提出が続くと条件悪化や成約遅延につながるため、最初の提出品質を高めるのが近道です。
- 請求書と発注書の金額・数量が不一致
- 未検収・返品分を含めた先走り請求
- 通帳画像のトリミング・編集痕跡
- 二重請求・名義違い・別案件の混在
譲渡禁止特約や相殺リスクの懸念
契約上の制約は、審査の可否と回収の安全性に直結します。基本取引契約に「債権譲渡禁止特約」があると、原則として第三者への譲渡ができず、承諾書の取得やスキーム変更が必要になります。
また、相殺条項が強いと、売掛先が別件の損害や未払いを理由に相殺し、回収額が減るおそれがあります。
たとえば長期保守契約で、月次請求のほかに瑕疵対応や違約金条項があり、相殺の余地が大きいと評価は厳しめです。
さらに、検収条件が「発注者の検査合格」になっている場合、検査未了や差戻しによって債権成立時期が遅れ、資金化のタイミングにズレが生じます。
申込前に契約条項を読み合わせ、必要であれば先方の承諾書や相殺しない旨の覚書の取り付けを検討すると安全です。
- 基本契約:譲渡禁止特約・通知承諾要件の有無を確認
- 相殺条項:範囲・上限・発動条件を把握
- 検収条件:検査合格や検収書の発行時点を明確化
- 対策:承諾書の取得、相殺対象外の覚書、対象請求の絞り込み
手数料の考え方と2社間・3社間の基本

手数料は「リスク・事務負担・資金回収の確度」に応じて決まります。
一般に、売掛先へ通知しない2社間は、ファクタリング会社が回収段階のコントロールを持ちにくいため、事務負担や信用リスクを織り込んだ条件になりやすい一方、スピードと秘匿性に強みがあります。
3社間は、取引先へ通知・承諾をとることで回収の見通しが明確になり、条件が安定しやすい反面、先方の社内承認や関係性への配慮が必要です。
いずれも「請求の実在性」と「入金履歴の連続性」を示すほど交渉余地が広がります。
費用は表面の手数料だけでなく、登記費用の有無、送金手数料、最低手数料、追加書類対応に伴う時間的コストなども含めて総額で評価すると、後のギャップが小さくなります。
| 観点 | 2社間 | 3社間 |
|---|---|---|
| 回収方法 | 自社入金→譲渡先へ送金 | 売掛先から譲渡先へ直接入金 |
| 通知・承諾 | 不要(非通知が基本) | 必要(通知・承諾で透明化) |
| 手数料傾向 | 高めになりやすい | 安定しやすい |
| スピード | 早い傾向 | 通知承認分の時間が必要 |
| 開示・風評 | 低い(秘匿性) | 高い(関係先に周知) |
| 登記の扱い | 対抗要件確保のため利用例あり | 通知・承諾で代替される場面多い |
2社間と3社間の違いと選び方
2社間は、売掛先に知らせずに資金化できるため、営業関係や価格交渉に影響を与えにくい点が利点です。
自社が入金を受けた後にファクタリング会社へ精算するため、運用はシンプルですが、回収不確実性が高いぶん条件は厳しめになりがちです。
3社間は、売掛先が支払い先を切り替えるため、資金の流れが明確で回収見込みも立てやすく、総合条件が安定しやすい反面、通知・承諾の社内稟議や情報共有の配慮が必要です。
どちらを選ぶかは、手数料だけでなく、先方との関係性、社内の業務設計、入金消込の体制まで含めた総合最適で判断します。
例えば新規取引の比率が高く、入金消込の工数に余裕がない場合は、通知を伴う3社間で回収フローを固定化する選択が合理的なことがあります。
| 判断軸 | 2社間が向く状況 | 3社間が向く状況 |
|---|---|---|
| 関係性配慮 | 先方に資金調達を知られたくない | 開示しても関係に影響が少ない |
| 業務設計 | 社内で精算と消込を完結できる | 入金先切替で消込を簡素化したい |
| 与信・回収 | 与信が厚い先が中心で遅延少ない | 新規や変動が多く回収を確実化したい |
| スピード | 即時性を重視したい | 通知承認の時間を許容できる |
償還請求権の有無とリスク整理
契約上の償還請求権は、売掛先の不払い等が起きたときに、申込側へ買戻しや支払を求められる可能性を意味します。
一般に、償還請求権が広いほどファクタリング会社の回収リスクは小さくなるため条件は出やすくなりますが、申込側にとってはキャッシュフローの不確実性が残ります。
一方、償還請求権が限定的または無しと定める場合は、回収不能時のリスク移転が明確になる反面、審査は厳格になりやすく、対象請求の選定やエビデンスの精度が求められます。
重要なのは、どの事由で償還請求が発動するのか、範囲と上限、通知期限、表明保証違反の扱いを条文で具体的に確認することです。
保険や保証の付帯、相手先の分散、返品や相殺の可能性が低い請求を選ぶことで、実務上のリスクは抑えられます。
- 償還請求の発動事由と範囲(不払い・争訟・相殺等)
- 金額上限や期間制限、通知期限の明記
- 表明保証違反・反社条項違反の扱い
- 保険・保証・登記などの補完策の位置付け
相見積もりと条件比較の手順
相見積もりは、手数料の妥当性だけでなく、運用負荷やリスク配分を可視化するために有効です。まず対象請求書を特定し、発注から入金までのエビデンスを1セットにして、同一条件で各社に提示します。
回答は、買取率・手数料の内訳、入金スケジュール、必要書類、登記や通知の要否、償還請求条項の範囲、追加費用の有無まで項目を揃えて比較します。
条件が拮抗している場合は、継続利用時の枠拡張や、複数請求を束ねた際の手数料レンジ、地方銀行や大手との連携の有無など運用面の提案も確認すると、総合最適の判断がしやすくなります。
最後に、社内の消込体制や請求フロー図に当てはめ、実装コストを含めた総費用で意思決定します。
- 対象請求書と比較観点を統一して提示
- 買取率・入金期日・追加費用の有無を並列比較
- 登記・通知の要否と業務影響を確認
- 償還請求条項と表明保証の範囲を精査
- 継続利用時の枠設定や手数料の変動条件を確認
- 社内運用へ落とし込み、総費用で最終判断
まとめ
ファクタリングは決算書がなくても、売掛先の信用と正確な書類があれば利用余地あり。申込前に①請求書・通帳・本人確認の整備 ②譲渡禁止特約の確認 ③手数料・入金スピードの相見積りを実施。
2社間/3社間と償還リスクを理解し、違法な給与ファクタリングは避けましょう。まずは条件を数値で比較することが近道です。