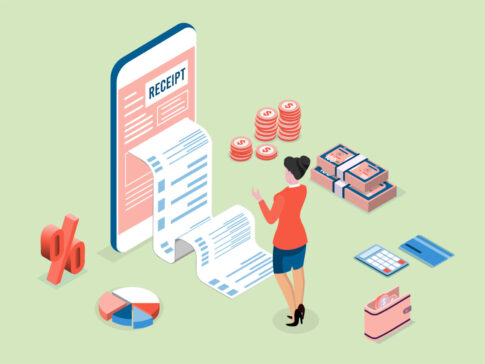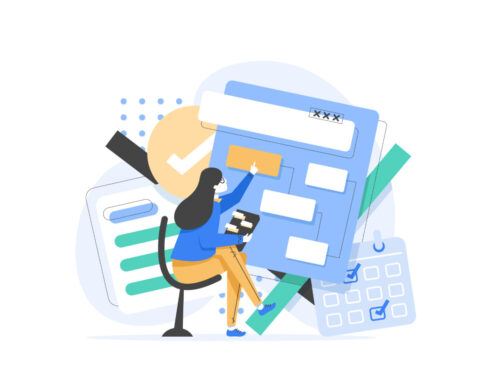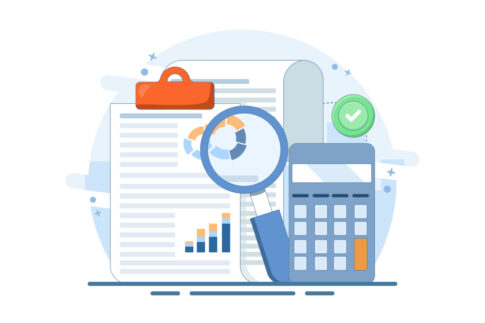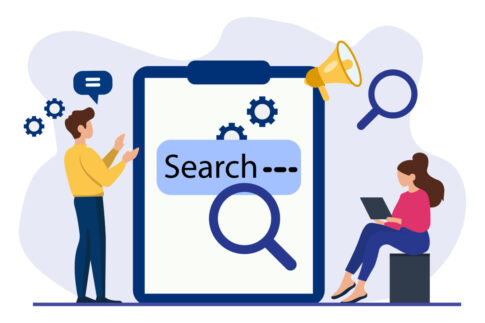公庫融資を申し込んだのに不承認になった、または「落ちる理由」が不安で申込みに踏み切れないという方は少なくありません。
資金繰りが厳しい中で、銀行審査が通るか心配、ノンバンクは安全性が気になる、税金や社保の遅れが影響しないか不安…そんな悩みに向けて、本記事では公庫融資の審査の全体像と、落ちやすい原因、面談で見られる点、必要書類と数字の整え方を整理します。資金繰り表の作り方や再申込の考え方、代替策と相談先の方向性までまとめます。
公庫融資審査の全体像

公庫融資は、資金使途(何に使うか)と返済計画(どう返すか)を中心に、事業の実現性と返済可能性を確認していく流れです。審査では、申込書類の数字だけでなく、面談での説明と整合しているかが重視されます。
特に「資金が必要な理由が具体的か」「売上・経費の根拠が示せるか」「借入後に資金繰りが回るか」を準備できるほど、判断材料が明確になります。
制度や商品は目的別に複数あるため、内容に合わない商品を選ぶと説明が弱くなりやすい点にも注意が必要です。
- 資金使途と金額の妥当性を説明できること
- 返済原資と返済計画が数字で示せること
- 書類と面談の説明が一致していること
制度と商品選びのポイント
公庫融資は、創業・新規開業、運転資金、設備資金など目的に応じて枠組みが分かれています。商品選びで重要なのは、資金使途と返済期間の整合です。
例えば、設備導入なら見積書や導入時期が明確で、投資効果(売上増やコスト減)を説明しやすい一方、運転資金は「何の支払いに」「いつまでに」「いくら必要か」を資金繰りで示せることがポイントになります。
合わない商品を選ぶと、必要書類が揃わない・説明が噛み合わないなどで評価が下がりやすいので、申込前に目的と数字を整理しておくと安心です。
| 観点 | 選び方の目安 |
|---|---|
| 資金使途 | 設備資金なら対象設備と見積・契約、運転資金なら支払い内容と必要期間を明確にします。 |
| 返済期間 | 設備は回収期間に合わせやすく、運転資金は資金繰り表で返済原資の見通しを示します。 |
| 創業性 | 創業期は実績が少ないため、受注見込みや販路、単価・粗利の根拠が重要になります。 |
申込から着金までの流れ
一般的には、相談・申込→書類提出→面談→審査→契約手続→融資実行(着金)という流れで進みます。実務でつまずきやすいのは、面談までに数字の根拠が揃っていないケースです。
例えば「運転資金300万円」と言っても、内訳(外注費、家賃、仕入、人件費など)と支払日が曖昧だと、必要性の説明が弱くなります。
逆に、請求書の入金予定と支払予定を月次で並べ、資金不足が生じる月と不足額を示せると、話が短時間で通りやすくなります。
手続き期間は状況で変動するため、資金が必要な期限から逆算して早めに動くことが重要です。
- 資金の目的と必要額を確定し、使途の内訳と支払時期を整理します。
- 必要書類を揃え、事業計画と数字(売上・経費・資金繰り)を整合させます。
- 面談では、資金使途と返済計画を事実ベースで説明し、追加資料依頼に備えます。
- 条件が固まったら契約手続きを進め、実行日と着金タイミングを確認します。
審査で確認される基本項目
審査で見られやすい項目は、大きく「事業の実現性」「返済可能性」「信用面」「資金使途の明確さ」に整理できます。事業の実現性では、売上見込みの根拠(受注・契約・見積、販路、単価と粗利の説明)が重要です。
返済可能性では、利益だけでなくキャッシュの動きが重視されるため、資金繰り表で返済原資を示すことが有効です。
信用面では、延滞や税金・社保の遅れなどがあると追加説明が必要になりやすい点に注意します。最後に、書類と口頭説明の不一致は不利になりやすいので、数値の前提を揃えておくことが基本です。
- 売上の根拠が「希望」だけだと弱く、単価・件数・成約率などの前提が必要になりやすい
- 資金使途が大まかだと、必要額の妥当性を説明しにくい
- 資金繰り表がないと、返済原資の説明が損益だけに偏りやすい
- 書類の数字と面談の説明がずれると、追加確認が増えやすい
公庫融資が落ちる主な理由

公庫融資が不承認になる背景は一つではなく、「必要性はあるが説明が弱い」「数字の整合が取れていない」「返済の見通しが立たない」「信用面の懸念が残る」などが重なって起こりやすいです。
特に多いのは、資金使途が曖昧で必要額の妥当性を説明できない、返済計画が利益計画だけで資金繰りが伴っていない、信用情報や延滞が審査上の懸念になる、そして書類・面談・実態の整合が取れないケースです。
不承認を避けるには、落ちる理由を「制度要件」ではなく「説明と証拠の不足」として捉え、事業計画・資金繰り表・使途証憑・売上根拠を同じ前提で揃えることが効果的です。
- 資金使途の説明不足(内訳・支払時期・根拠資料が弱い)
- 返済計画の弱さ(利益は出るがキャッシュが回らない)
- 信用面の懸念(延滞・税金社保の遅れなど)
- 虚偽・不一致(数字や事実関係のズレで信頼が下がる)
資金使途が曖昧なケース
資金使途が曖昧だと、必要性と金額の妥当性を判断しづらくなり、不承認の原因になりやすいです。
たとえば「運転資金300万円」とだけ記載し、何の支払いに充てるのか(仕入、外注費、家賃、人件費、広告費など)、いつ支払うのか、なぜその金額が必要なのかが説明できない状態です。
特に、赤字補填の色合いが強い申込みは、資金がどこで止まり、どう回収され、どう返済されるかが見えにくくなるため、より丁寧な説明が必要になります。
対策は、使途を「費目別×月別」に落とし込み、請求書・見積書・契約書などの証憑で裏付けることです。
例えば、外注費120万円(来月10日支払)、家賃30万円(毎月末)、広告費50万円(今月末)といった形で、支払日まで示せると説明が具体化します。
| 悪い例 | 改善の方向性 |
|---|---|
| 運転資金300万円 | 外注費120万円(支払日・請求書)、家賃30万円×2か月(契約)、仕入50万円(発注・見積)など内訳化 |
| 売上が増える予定 | 受注見込み(見積・発注)、単価×件数、成約率の根拠を添付 |
| 資金が足りない | 資金繰り表で不足月と不足額を明示し、必要期間を説明 |
返済計画が弱い場合の注意点
返済計画が弱いとは、返済の原資が利益計画だけで、現金の動き(資金繰り)まで説明できていない状態を指します。
公庫融資は返済が前提なので、月々の返済額を資金繰りの中で無理なく回せるかが重要です。例えば、損益計画では黒字でも、売掛金の回収が遅く、支払いが先行するビジネスでは、返済月に現金が不足することがあります。
よくある落とし穴は、売上を楽観的に置き、粗利率や固定費の前提が甘いケースです。例えば「月商300万円、粗利40%」と置いても、実際は粗利25%で広告費や外注費が増えると、返済原資が想定より小さくなります。
対策としては、保守的な前提で資金繰り表を作り、返済開始月からの最低残高が維持できることを示すのが有効です。
- 損益計画はあるが、資金繰り表がなく返済月の現金残高が示せない
- 売上前提が根拠不足で、単価・件数・成約率が説明できない
- 固定費の増加(人件費・家賃・外注)が計画に反映されていない
- 返済開始直後の数か月で資金残高が底をつく設計になっている
信用情報と延滞の影響目安
信用情報や延滞は、返済の確実性を判断する上で重要な材料になり得ます。ここでいう延滞は、クレジットやローンの支払い遅れなどを含み、内容によっては審査上の懸念として扱われます。
また、税金や社会保険料の支払い遅れがある場合、資金繰りが逼迫しているサインとして見られ、追加の説明や資料が必要になることがあります。
ただし、過去に遅れがあったとしても、現状が改善している、理由が整理できる、再発防止策があるなど、説明できる材料があれば評価が安定しやすいです。重要なのは、隠さずに事実を整理し、いつ・何が・どう改善したかを示すことです。
| 論点 | 影響の出方の目安 |
|---|---|
| 支払い遅れ | 遅れの程度や頻度により、返済の確実性に疑義が出やすい |
| 他社借入 | 返済負担が重いと、追加借入の余力が小さく見られやすい |
| 税金・社保 | 遅れがある場合、状況説明と改善計画が求められやすい |
虚偽や整合不一致のチェック
虚偽や整合不一致は、審査において致命的になりやすい論点です。虚偽とは、売上や取引実態、借入状況などを事実と異なる形で申告することです。
整合不一致は、意図的でなくても、書類同士の数字が合わない、面談の説明と資料が食い違う、資金使途と入出金がつながらない、といった状態を指します。
例えば、申込書では「設備資金」としながら、面談では運転資金の話をしている、見積書の金額と申込額が一致しない、売上計画の単価と見積書が矛盾する、などは不利になりやすいです。
対策は、提出前に「数字の突合」と「ストーリーの一本化」を行うことです。損益計画、資金繰り表、使途証憑、借入一覧を同じ前提で揃え、説明が一貫しているかをチェックすると、面談の受け答えも安定します。
- 申込書・事業計画・資金繰り表の前提(単価・件数・粗利率)を統一する
- 申込額と使途証憑(見積・請求)の金額を一致させる
- 借入一覧(他社借入・カード枠)を最新にし、説明とズレをなくす
- 面談で聞かれそうな論点(使途・返済・売上根拠)を一枚メモで整理する
書類と数字の準備ポイント
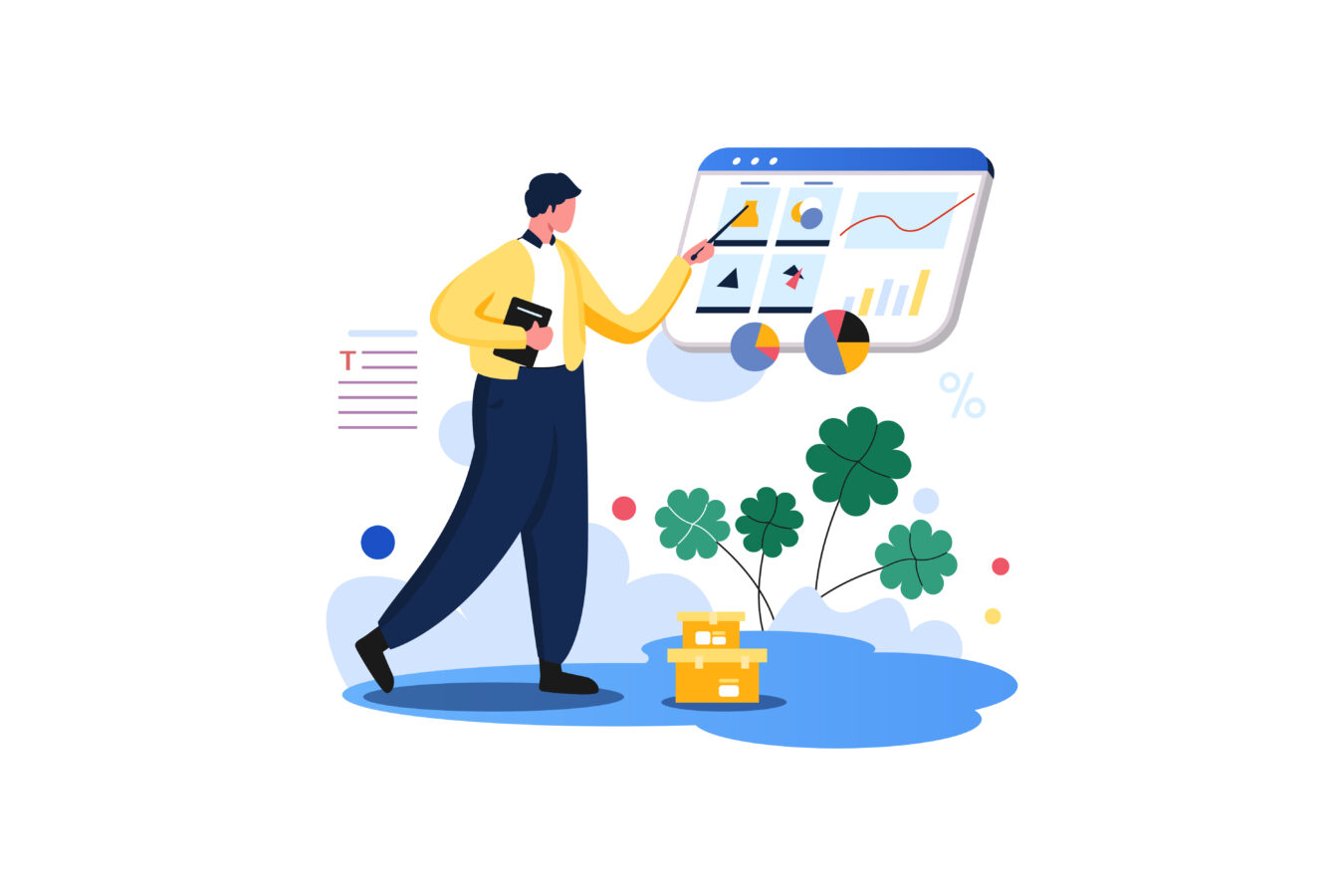
公庫融資の審査では、書類の「量」よりも、数字と説明の「整合」が重視されます。
事業計画に書いた売上が、見積・契約・販路の実態とつながっているか、資金繰り表で返済月の現金残高が維持できるか、申込額が使途証憑(見積書や請求書)と一致しているか、といった点が確認されやすいです。
逆に、計画と資料がバラバラだと、内容が良くても追加確認が増え、結果として不利になりやすくなります。
準備の基本は、損益計画(利益の見通し)と資金繰り表(現金の見通し)をセットで作り、自己資金・借入一覧・使途証憑まで同じ前提で揃えることです。
特に資金繰りに不安がある場合ほど、数字を“見える化”して説明できるようにすると面談も安定します。
- 資金使途(何に、いつ、いくら使うか)
- 売上前提(単価×件数×成約率など)
- 粗利率と固定費(外注・人件費・家賃など)
- 返済開始月と返済額を入れた資金繰りの安全ライン
事業計画の作り方ステップ
事業計画は、審査での「説明書」です。強い計画は、夢や意気込みではなく、取引の流れと数字の根拠が揃っています。
まず、何を誰にどう売るか(商品・顧客・販売方法)を整理し、次に売上の作り方を数字で示します。
例えば、月の受注10件、客単価10万円、成約率20%なら、必要な見込み客数や営業活動量も逆算できます。
さらに、原価や外注費、広告費、人件費を積み上げ、利益が出るまでの時間と赤字期間を説明します。
最後に、資金が必要な理由(立替の発生、在庫、広告先行など)を、資金繰り表の不足月と結びつけると説得力が上がります。
- 商品・サービスと顧客像、販売方法を1枚で整理します。
- 売上前提を数式化します(単価×件数×成約率など)。
- 主要コストを洗い出し、粗利と固定費の見通しを作ります。
- 黒字化までの期間と、資金が不足する月を資金繰りで示します。
- 資金使途と申込額を、見積書・請求書などの証憑で裏付けます。
試算表と資金繰り表の整え方
試算表は、直近の経営状況を示す月次の成績表で、数字の鮮度が重要です。特に売上や粗利が月ごとに変動する業種では、決算書だけだと現状が伝わりにくいため、直近月までの試算表があると説明が安定します。
一方、資金繰り表は入金と出金を月別に並べ、月末残高を予測する表です。公庫融資では「返済できるか」を見るため、資金繰り表に返済額を入れても残高が維持できることが重要になります。
例えば、入金が月末に集中し、支払いが月中に多い会社は、月末残高だけでなく月中の最低残高も薄くなりがちです。
資金繰り表は、売掛金回収の予定日と、給与・外注費・家賃・税金などの支払日を具体的に入れ、資金不足が出る月と不足額を明示すると実務で使える資料になります。
- 税金・社会保険料の支払月(納付時期が偏りやすい)
- 賞与や更新料などの臨時支出(年に数回だけ発生)
- 借入返済の返済日(入金タイミングとズレると月中が苦しい)
- 入金遅延のバッファ(予定どおり入らない月への備え)
自己資金と使途証憑のチェック
自己資金は、事業へのコミット度や資金繰りの余力を示す材料として扱われやすく、見せ方が重要です。
ここでいう自己資金は、単に口座残高があるだけでなく「いつ、どのように準備したか」が説明できることが望まれます。
突発的な入金で残高を作ると、資金の出所確認が必要になりやすいため、資金の流れを整理しておくと安心です。
使途証憑は、申込額が妥当であることを裏付ける資料です。設備なら見積書・契約書、運転資金でも外注費の請求書、仕入見積、家賃契約、広告見積などで内訳が示せると、資金使途が明確になります。
申込額と証憑の金額がズレると説明が必要になるため、内訳表を作り、端数や予備費の扱いまで整理しておくと面談で困りにくいです。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 自己資金 | 残高だけでなく準備経緯が説明できるか、資金の出所が明確か |
| 使途証憑 | 申込額の内訳が見積・請求・契約で裏付くか、支払時期が一致するか |
| 予備費 | 上振れに備える場合、根拠と金額の妥当性を説明できるか |
売上根拠と見積の示し方例
売上根拠は「受注の確度」を示す材料です。創業期や新規事業ほど実績が少ないため、見積書や発注書、契約書、商談メモ、予約台帳など、第三者とのやり取りが分かる資料が有効です。
示し方のコツは、1件ごとの資料を並べるだけでなく、合計が売上計画に一致するように「積み上げ表」を作ることです。
例えば、月の売上計画が200万円なら、A社80万円(見積提出済み・来月検収予定)、B社60万円(契約済み・月末請求)、C社60万円(継続取引・過去入金実績あり)と整理し、単価と件数が事業計画の前提と一致していることを示します。
計画を保守的に組み、未確定部分は成約率を置くなど、現実的な前提で説明すると信頼性が高まります。
- 見積・契約・発注の「確度」を分けて整理し、計画の根拠を積み上げで示す
- 継続取引は過去の入金実績を添え、単価・頻度の再現性を示す
- 未確定案件は成約率を置き、楽観的に見えない前提で計画を組む
- 売上計画と資金繰り表の入金予定が一致するように揃える
創業期と個人事業主の注意点
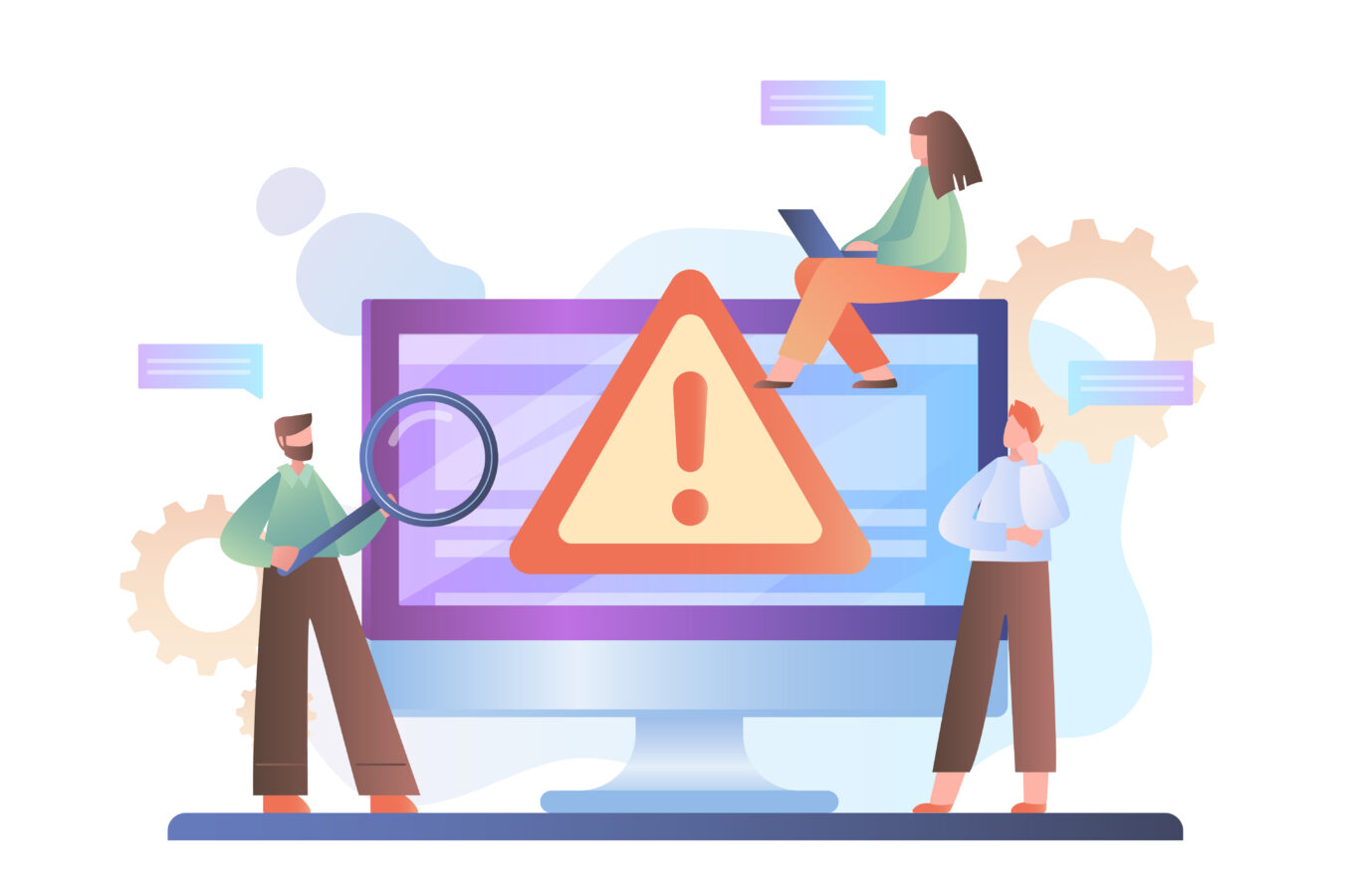
創業期や個人事業主の公庫融資は、法人よりも「数字の裏付け」と「生活と事業の線引き」が問われやすいです。
理由は、実績が短い、収入が変動しやすい、事業用と私用の支出が混ざりやすいなど、返済能力の判断材料が整理されていないことが多いからです。
審査では、申告所得や売上見込みだけでなく、家計を含めた資金繰りの安定性、税金・社会保険料の状況、他社借入を含めた返済負担が確認されやすくなります。
対策は、提出書類を早めに揃え、申告内容と実態の整合を取ったうえで、事業計画・資金繰り表・借入一覧・生活費の見積りをセットで説明できる形にすることです。
- 申告書類と売上見込みの整合(根拠資料の有無)
- 税金・社保の納付状況と資金繰りの安定性
- 他社借入を含む返済負担の全体像
- 生活費と事業費の区別ができているか
確定申告書類の準備ポイント
個人事業主の場合、確定申告書類は「収入と経費の結果」を示す基礎資料として扱われます。審査では、単年だけでなく複数年の推移が確認されることが多く、売上や所得が大きく変動している場合は理由説明が必要になりやすいです。
また、青色申告か白色申告かで帳簿の整え方や提出書類が異なるため、申告区分に合った資料を揃えることが重要です。
創業期で申告実績が少ない場合は、受注見込みや販路、単価、粗利、固定費の根拠を補う必要があります。
例えば、契約書・見積書・予約台帳・入金実績など、第三者とのやり取りが分かる資料を揃え、事業計画の売上前提と一致していることを示すと説明が通りやすくなります。
| 資料 | 準備のポイント |
|---|---|
| 確定申告書 | 直近年に加え、可能なら複数年分を揃え、前年差の説明メモを用意します。 |
| 決算書類 | 青色決算書や収支内訳書など、申告区分に応じた添付書類を揃えます。 |
| 帳簿・証憑 | 売上・経費の根拠が追えるよう、請求書・領収書・通帳明細を年度別に整理します。 |
| 売上根拠 | 契約・見積・発注などを積み上げ表で示し、計画との整合を取ります。 |
税金社保遅れの影響目安
税金や社会保険料の支払い遅れは、資金繰りの厳しさを示す要素として見られる可能性があります。審査では、納付状況の資料提出や説明を求められることがあり、遅れがある場合は追加確認が増えやすいです。
重要なのは、遅れを隠すのではなく、現状と改善計画を整理して説明できる状態にすることです。
例えば、納付が難しい時期に相談を行い、分割納付や猶予の手続きを進めている場合は、手続き状況が分かる資料を用意すると説明が安定します。
遅れが長期化している場合は、融資によって一気に解消する前に、納付計画と資金繰りの整合を取らないと再び遅れが発生しやすい点にも注意が必要です。
- 遅れを申込書や面談で曖昧にし、後から判明して説明が崩れる
- 根拠なく「すぐ解消できる」と説明し、資金繰り計画が伴わない
- 税金・社保の支払いを後回しにして、他の支出を優先してしまう
他社借入とカード枠のチェック
公庫融資の審査では、他社借入を含む返済負担が確認されます。ここでいう他社借入には、事業用ローンだけでなく、クレジットの分割・リボ払い、カードローン、個人の自動車ローンなどが含まれ得ます。
借入が多いと、月々の返済額が家計・事業のキャッシュを圧迫し、追加借入の余力が小さく見られやすいです。
対策としては、借入一覧を作り、残高・金利・毎月返済額・返済日を整理し、資金繰り表に反映させることです。
カード枠は「使っていないから関係ない」と考えがちですが、利用状況によっては説明が必要になることもあるため、現状を把握しておくと安心です。
- 借入一覧を作成し、返済負担(毎月・年間)を可視化する
- 返済日が集中している場合、資金残高が薄い時期を確認する
- リボや分割がある場合、残高と完済見込みを整理して説明できるようにする
- 事業用と個人用の借入を混同せず、用途と返済原資を区別する
生活費と事業費の区別基準
個人事業主は、生活と事業が同じ財布になりやすく、資金繰りの説明でつまずきやすいポイントです。
審査では、事業の返済原資を説明するために、生活費がどれくらい必要で、事業からどれくらい引き出すのか(生活費に回すのか)も含めて整理されることがあります。
生活費が過小に見積もられていると、返済計画が現実的でないと判断されやすいです。
対策は、事業用口座と生活用口座を分け、事業から生活へ移す金額を定額化することです。例えば、毎月の生活費として固定額を振替し、残りを事業の運転資金と返済に回す運用にすると、資金繰り表が作りやすくなります。
自宅兼事務所の家賃や通信費など、家事按分が必要な費目は、合理的な基準(面積比や利用時間など)を決めて継続し、証跡を残すことが重要です。
| 区別の観点 | 基準の例 |
|---|---|
| 口座管理 | 事業用と生活用を分け、生活費の振替額を固定して記録します。 |
| 家事按分 | 面積比・利用時間などの合理的基準を決め、毎期同じ基準で処理します。 |
| 支出の記録 | 私用混在が疑われやすい費目は、目的・相手先・日時をメモして保存します。 |
落ちた後の再申込と代替策
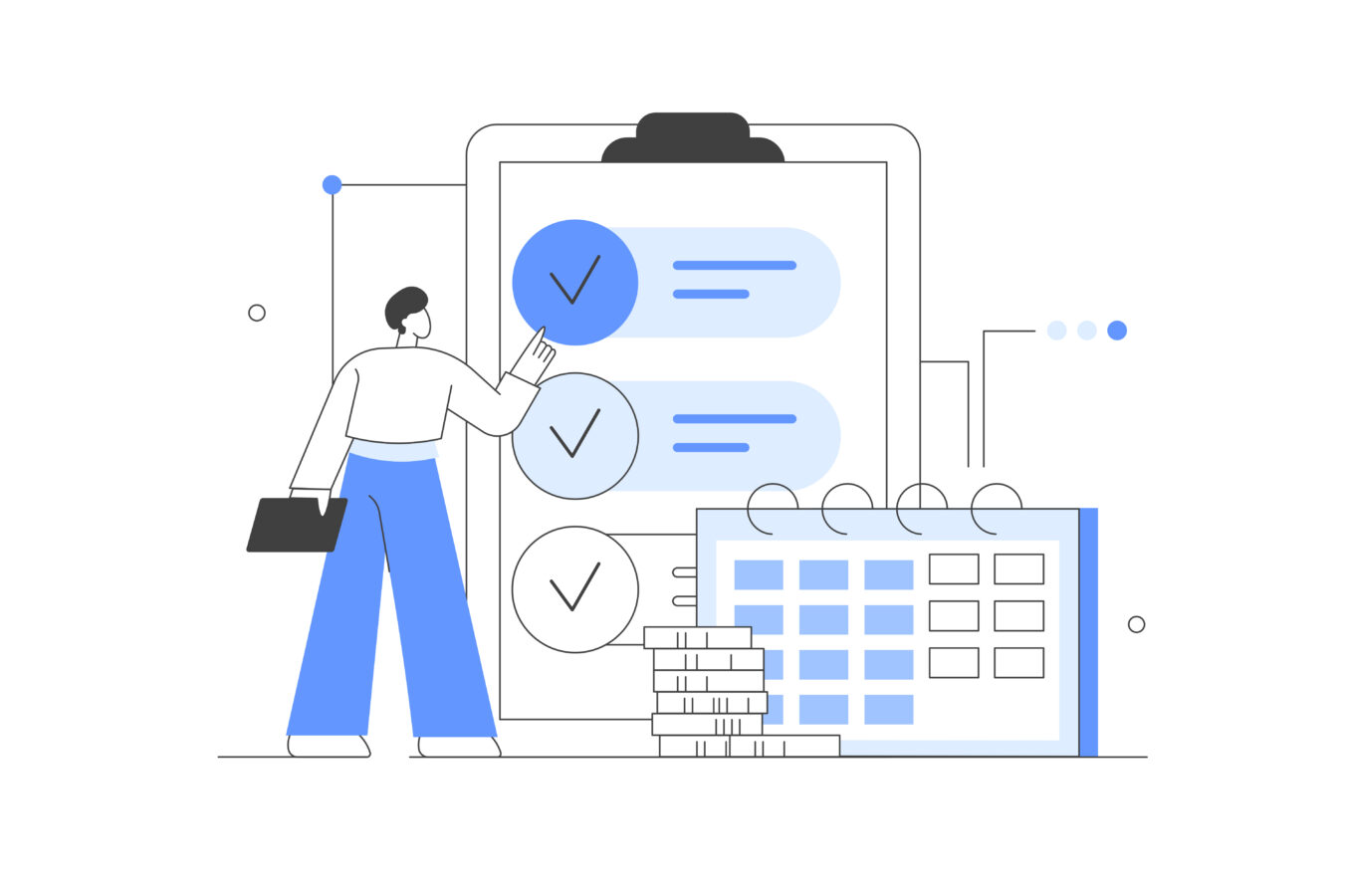
公庫融資が不承認になっても、直ちに資金調達が不可能になるわけではありません。重要なのは「なぜ落ちたのか」を推測で終わらせず、説明の弱点や資料不足、数字の整合、信用面の懸念などを具体的に洗い出し、再申込に耐える形へ整えることです。
特に資金使途や返済計画の説明が弱いケースは、資金繰り表と使途証憑を補強するだけで改善することがあります。
一方、延滞や税金・社保の遅れなど信用面の課題がある場合は、短期で解決しにくいこともあるため、代替策(保証協会付き融資、制度融資、つなぎ資金など)を併用して資金ショートを避ける発想が必要です。
再申込は「早ければ良い」ではなく、弱点が改善されたと説明できる状態で行うことが前提になります。
- 不承認の要因を「使途・返済・信用・整合」の4分類で洗い出す
- 足りない証拠資料(見積・請求・契約・入金実績)を補う
- 資金繰り表に返済を入れても回る設計へ見直す
- 資金ショート回避のため、代替策と実行までの時間を並行検討する
不承認後の確認ポイント
不承認後は、まず申込書類と面談内容を振り返り、どこで説明が弱かったかを特定します。特に多いのは、資金使途の内訳が粗い、売上根拠が弱い、返済計画が損益だけで資金繰りが示せていない、書類同士の数字がズレている、といったパターンです。
次に、客観資料で補えるかを確認します。例えば、見積書・契約書・請求書・入金履歴などを揃え、売上計画の積み上げ表を作ると説明が具体化します。
また、信用面(延滞、税金・社保の遅れ、他社借入の返済負担)が原因の可能性がある場合は、現状と改善状況を整理し、説明できる材料(支払いの正常化、分納手続きの進捗など)を揃えることが重要です。
| 分類 | 確認するポイント例 |
|---|---|
| 資金使途 | 内訳が費目別・月別になっているか、証憑と金額が一致するか |
| 返済計画 | 資金繰り表に返済を入れても最低残高が維持できるか |
| 売上根拠 | 単価・件数・成約率の前提があり、見積・契約で裏付くか |
| 信用面 | 延滞・税金社保の状況、他社借入の返済負担が整理できているか |
再申込タイミングの目安
再申込は、弱点が改善されたことを示せるタイミングで行うのが基本です。例えば、受注が増えた、入金実績が積み上がった、試算表が整った、資金使途の証憑が揃った、税金・社保の遅れを相談して計画的に解消している、といった“変化”が出てからの方が説明が通りやすくなります。
逆に、短期間で同じ内容を出し直すと、前回からの改善が示せず結果が変わりにくいことがあります。
実務では、決算・申告が終わって最新の申告資料や試算表が揃う時期、または受注や契約が確定し売上根拠が強くなった時期が、再申込の候補になりやすいです。
資金が急ぎの場合は、再申込の準備と並行して、つなぎ策を検討して資金ショートを避けます。
- 資金使途の内訳や証憑が前回と変わらず、説明が改善していない
- 売上根拠が依然として希望ベースで、積み上げ資料がない
- 税金・社保の遅れや延滞が継続し、改善状況が示せない
- 資金繰り表に返済を入れるとすぐ赤字残高になる
保証協会付き融資の比較軸
代替策の一つが、信用保証協会の保証が付く銀行融資(保証協会付き融資)です。保証が付くことで銀行側の信用リスクが一定程度カバーされ、プロパー融資より利用しやすい場面があります。
一方で、保証料が発生し、保証枠を使うため将来の資金調達余力にも影響することがあります。
比較の軸は、金利だけでなく保証料を含めた総コスト、必要書類、審査期間、資金使途の適合性です。
公庫で説明が弱かった点(使途・返済・売上根拠)を補強する必要がある点は共通なので、同じ資料整備が無駄になりにくいのがメリットです。
| 比較軸 | 見るポイント |
|---|---|
| 総コスト | 金利に加えて保証料・手数料を含めた負担で比較します。 |
| 審査と期間 | 資金が必要な期限に間に合うか、手続きの所要期間を確認します。 |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金など目的に合う枠組みかを確認します。 |
| 将来余力 | 保証枠を使うことで、今後の追加借入に影響が出る可能性を考えます。 |
つなぎ資金と相談先の選び方
資金が急ぎの場合は、再申込や代替融資を待つ間の「つなぎ資金」をどう確保するかが重要です。つなぎ策には、売掛金の回収条件見直し(分割請求や前受)、支払サイトの交渉、在庫や固定費の圧縮、短期の資金化手段などがあり、状況に応じて組み合わせます。
違法な資金移動や債務逃れに当たる行為は避け、支払遅延が出る前に早めに相談して調整することが重要です。
相談先は目的別に分けると進めやすいです。公庫・銀行は融資方針と必要資料、税理士は数字の整合と申告資料、商工会・認定支援機関は事業計画や資金繰り表の作成支援、といった役割分担が現実的です。
- 金融機関:融資の可能性、必要書類、スケジュール、代替策(保証協会等)の確認
- 税理士:試算表・資金繰り表の整備、申告内容の整合、税金社保の整理
- 支援機関:事業計画のブラッシュアップ、売上根拠の整理、資金繰り改善策の検討
- 取引先:支払サイト・分割請求・前受など、商流側での改善交渉
まとめ
公庫融資で落ちる理由は、資金使途の曖昧さ、返済計画の弱さ、書類や数字の整合不一致、信用情報や延滞、税金・社保の状況などが重なって起こりやすいです。
申込み前に事業計画の根拠、試算表と資金繰り表、自己資金と使途証憑、売上見込みの裏付けをそろえると、面談でも説明がぶれにくくなります。
創業期や個人事業主は申告資料や生活費との区別が重要で、落ちた後は理由の整理と再申込のタイミング検討が必要です。急ぎの資金はつなぎ策も含め、金融機関や専門家に早めに相談しましょう。