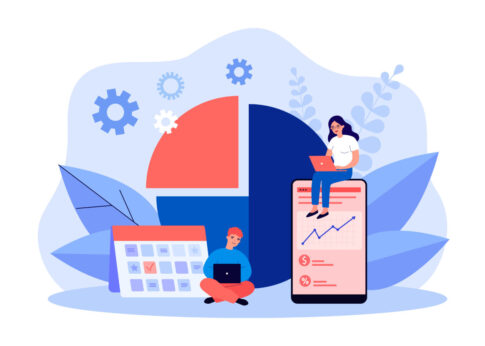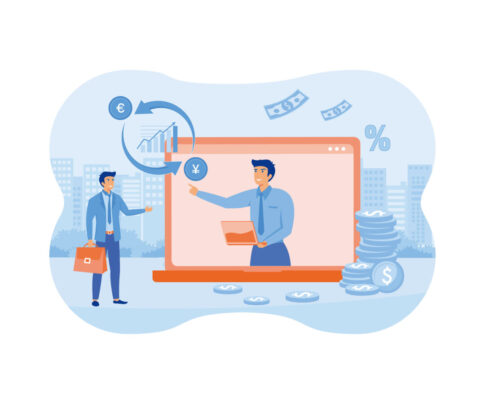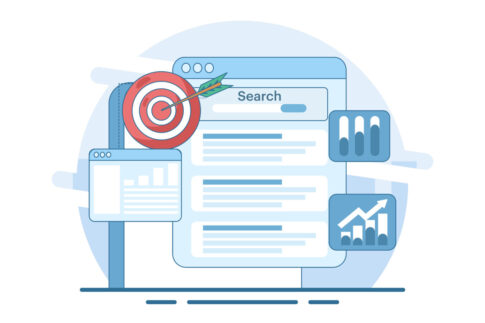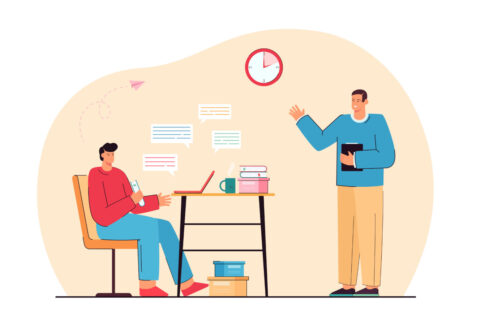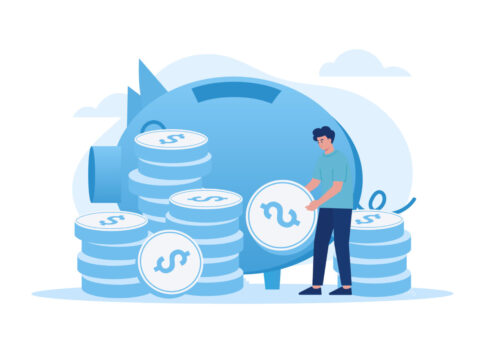ファクタリングを使うとき、「この手数料はどの勘定科目で仕訳すればいいのか」「消費税はかかるのか」「税務上いつ損金にできるのか」で迷う方は少なくありません。買取型と保証型、2社間・3社間といったスキームの違いによって、使える勘定科目や実務処理も微妙に変わります。
本記事では、ファクタリング手数料の基本的な考え方から、売上債権売却損・支払手数料などの勘定科目選択、仕訳例、消費税の課非判定、決算期をまたぐ場合の注意点までを整理し、中小企業・個人事業主でも迷わず処理できるよう解説します。
目次
ファクタリング手数料の基礎

ファクタリング手数料を会計処理するときは、「どんなスキームで利用しているか」を押さえておくことが大切です。
ファクタリングは大きく分けると、売掛債権を譲渡して資金化する「買取型」と、売掛金はそのまま保有しつつ、未回収時に補償を受ける「保証型(保証型ファクタリング・売掛保証型サービスなど)」があります。
前者は売掛金を早期に現金化することが目的、後者は売掛先の倒産リスク等を軽減することが目的で、手数料の性質と勘定科目の考え方も少し変わります。
また、買取型ファクタリングの中でも、「2社間(利用者とファクタリング会社のみ)」と「3社間(利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者)」に分かれ、2社間では売掛先に譲渡通知をせず、3社間では売掛先に通知してファクタリング会社が直接回収するのが一般的です。
手数料率は、一般に3社間の方が低く、2社間の方が高めに設定される傾向がありますが、いずれも会計上は「売掛債権をどのように評価し、その差額や手数料をどの勘定科目で処理するか」がポイントになります。
さらに、ファクタリングを利用するときには、事務手数料・債権譲渡登記費用・振込手数料などの付随コストが発生することも多く、これらを「ファクタリング手数料」と合わせて処理するのか、別勘定(支払手数料、租税公課、支払利息など)で処理するのかも実務上の論点になります。
基礎としては、次のような整理イメージを持っておくと、その後の勘定科目や税務の理解がスムーズになります。
| 区分 | ファクタリング手数料の位置付け |
|---|---|
| 買取型 | 売掛債権を譲渡して資金化する対価。売掛金の時価と受取額の差額や、支払う手数料をどう費用処理するかが論点。 |
| 保証型 | 売掛金は自社に残し、未回収時に補償を受ける対価。保証料・保険料に近い性格の費用として処理することが多い。 |
| 2社間・3社間 | どちらも基本は売掛債権の譲渡だが、リスクの取り方や手数料率が異なる。会計処理の考え方は共通部分が多い。 |
| 付随費用 | 登記費用・振込手数料・印紙などは、本体手数料とは性格が異なるため、別勘定で処理するかどうかを検討する。 |
買取型と保証型の手数料の違い
買取型ファクタリングの手数料は、「売掛債権の譲渡対価の一部」として位置付けられます。
例えば、請求書額500万円、買取率90%(買取率=請求書額面に対する支払い割合)、手数料率5%とすると、いったん500万円の売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、買取額450万円(500万円×90%)から手数料22万5,000円(450万円×5%)を控除した427万5,000円が入金されるイメージです。
この22万5,000円は、売掛金を早期に現金化するための「資金調達コスト」として認識されます。
一方、保証型ファクタリング(売掛保証型)の手数料は、売掛金自体は自社に残したまま、「取引先が倒産したときなどに一定割合を補償してもらう対価」として支払います。
信用保険や売掛保証サービスの保証料は、通常、年間の保証枠や対象売上高に対する料率(例:年1.0%など)を掛けて算出され、事故が起きても起きなくても発生する費用です。
この意味で、保証型の手数料は「リスクヘッジのための固定的な費用」、買取型の手数料は「資金繰り改善のための取引ごとの費用」と性格が異なります。
会計上の勘定科目も、この性格の違いを踏まえて検討します。買取型では、売掛債権の売却損(売却価額と帳簿価額の差額)や支払手数料として処理するケースが多く、一方で保証型では保証料・保険料・支払手数料といった勘定が候補になります。
どちらも「営業外費用」ではなく、「販売費及び一般管理費」や「営業費用」として位置付けるのが一般的かどうか、税務上の取扱いも含めて自社の方針を定めておくことが重要です。
- 買取型:売掛債権そのものを譲渡して資金化するためのコスト(取引ごとに発生)。
- 保証型:倒産・未回収リスクをカバーするためのコスト(年間で継続的に発生)。
- 性格の違いに応じて、売却損・支払手数料・保証料など、適切な勘定科目を選ぶ視点が必要。
発生タイミングと費用の内訳
ファクタリング手数料がいつ発生するか、どのような内訳で構成されるかを整理しておくことも、仕訳や税務上の判断に役立ちます。
買取型ファクタリングでは、一般に「売掛金をファクタリング会社に譲渡し、買取代金が振り込まれるタイミング」で手数料が確定します。
請求書を発行した時点では売掛金(売掛金/売上)として計上し、その後ファクタリング契約を締結して買取が実行された時点で、「売掛金の譲渡と手数料の認識」を行う流れになるのが通常です。
費用の内訳としては、主に次のような項目が挙げられます。
- ファクタリング手数料(割引料):買取額に対する◯%などとして設定されるメインの手数料。
- 事務手数料・取扱手数料:初回契約時や取引ごとに定額で課されることがある費用。
- 債権譲渡登記費用:動産・債権譲渡登記を行う場合の登録免許税や司法書士報酬など。
- 振込手数料・送金手数料:買取代金の振込に伴う銀行手数料。
- 印紙税:基本契約書・個別契約書の作成に伴い貼付する収入印紙の額。
保証型では、契約時に「年間保証料」を一括で支払うケースや、毎月・毎期の売上に応じて保証料が発生するケースがあります。
発生タイミングと期間対応の考え方(前払費用とするか、その期の費用とするか)は、契約内容や保証期間に応じて判断します。
- 買取型:買取実行時に手数料が確定するのが一般的(売掛金譲渡と同時に費用認識)。
- 保証型:契約期間に対応して保証料が発生(年払い・月払いなど)。前払処理の要否も確認する。
- 手数料本体のほか、登記費用・印紙税・振込手数料などの付随費用をどの勘定で処理するかを決めておく。
2社間・3社間で変わる費用項目
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは、スキームの違いから発生しやすい費用項目にも差があります。
2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の間だけで契約を結び、売掛先には債権譲渡の通知を行わない形態です。
この場合、売掛先からの入金は一旦利用者が受け取り、その後ファクタリング会社に支払うことが多く、ファクタリング会社側のリスクが高い分、手数料率が高めに設定される傾向があります。また、債権譲渡登記を行って対抗要件を確保するスキームでは、登記関連の費用が発生します。
3社間ファクタリングは、利用者・ファクタリング会社・売掛先の三者が関わり、売掛先に対して債権譲渡通知を行い、ファクタリング会社が直接売掛金の支払いを受ける形です。
売掛先が誰に支払うべきか明確になるため、ファクタリング会社の回収リスクは相対的に低く、その分手数料率は低めに設定されることが多いとされています。
一方、通知書の作成・送付や、場合によっては売掛先の同意取得など、事務手続きのコストが別途発生することもあります。
会計上は、どちらのタイプでも「売掛債権の譲渡」と「手数料の発生」をどう認識するかが基本ですが、2社間では売掛金の入金・支払の流れが一旦自社を経由するため、「一時的に預り金・未払金とするか、売掛金とファクタリング債務の振替で処理するか」といった実務上の判断も生じます。
3社間では、売掛先から直接ファクタリング会社へ支払われるため、自社の帳簿上は「売掛金の消滅と同時に、ファクタリングによる入金が行われたものとして整理する」形になります。
- 2社間:手数料率は高めになりやすく、登記費用などの付随コストも発生しやすい。入金・支払が一旦自社を経由するため、仕訳フローも確認が必要。
- 3社間:手数料率は低めになりやすいが、通知書作成・送付などの事務負担が増える場合がある。売掛先からの入金はファクタリング会社に直接行われる。
- どちらのタイプでも、費用項目(本体手数料・事務手数料・登記費用など)を整理し、勘定科目と仕訳パターンを事前に決めておくと実務がスムーズ。
ファクタリング手数料の勘定科目と会計処理

ファクタリング手数料の勘定科目は、取引の性質(買取型か保証型か、売掛金を「売却」とみるか「資金調達コスト」とみるか)によって複数の選択肢があります。
一般的な買取型ファクタリングでは、売掛債権の譲渡対価として「売却価額<帳簿価額」となった差額を「売上債権売却損」などの勘定で処理する方法と、受取額と請求額の差を「支払手数料」等の費用科目で処理する方法がよく用いられます。
どちらも、実質的には「売掛債権の現金化に要したコスト」を費用化する点で同じですが、損益計算書の表示区分や分析上の見せ方が変わるため、自社の会計方針としてどちらを採用するかをあらかじめ決めておくことが重要です。
また、仕訳を組む際には「売掛金の消し込み」と「手数料・売却損の計上」を同時に行うため、未収入金(ファクタリング会社に対する債権)を経由するかどうかによっても仕訳パターンが変わります。
2社間ファクタリングでは、売掛先からの入金とファクタリング会社への支払いが一時的に自社を経由することも多く、「売掛金→未収入金→現金・預金」という流れの中で手数料を切り出すイメージになります。
3社間ファクタリングでは、売掛先から直接ファクタリング会社へ支払われるため、「売掛金の消滅」と「現金・預金の入金」の関係を整理しておく必要があります。
| 論点 | 主な確認ポイント |
|---|---|
| 勘定科目 | 売上債権売却損か、支払手数料・雑損失等か、自社の方針を統一しておく。 |
| 仕訳フロー | 売掛金→未収入金→現金・預金の流れの中で、どのタイミングで手数料を費用計上するか。 |
| 表示区分 | 販売費及び一般管理費か営業外費用かなど、損益計算書上の位置付けも含めて整理する。 |
売上債権売却損で処理するケース
売上債権売却損は、売掛金や受取手形などの売上債権を帳簿価額よりも低い価額で譲渡した場合、その差額を「売上債権の売却による損失」として費用計上する勘定科目です。
買取型ファクタリングを「売掛債権の譲渡(売却)」とみる場合、ファクタリング会社から受け取る金額(買取代金)が売掛金の帳簿価額より少ないとき、その差額を売上債権売却損として処理する方法が、会計上の考え方として分かりやすいパターンの一つです。
例として、以下の前提を置きます。
- 売掛金:1,000,000円(元々の売上計上済)
- 買取額:950,000円(手数料等込みの受取額)
- 差額:50,000円(売上債権売却損として処理)
この場合、ファクタリング実行時の仕訳イメージは次のようになります。
- 借方:現金預金 950,000円/貸方:売掛金 1,000,000円
- 借方:売上債権売却損 50,000円/貸方:現金預金 50,000円
または一仕訳で、
- 借方:現金預金 950,000円/借方:売上債権売却損 50,000円/貸方:売掛金 1,000,000円
と表現することもできます。どちらも、「売掛金1,000,000円のうち、950,000円を現金化し、50,000円を売却損として費用計上した」ことを意味しています。
売上債権売却損を使うメリットは、「売掛債権の売却に伴う損失が、他の支払手数料などと区別して把握しやすい」点です。
複数のファクタリング会社や売掛債権売却を利用している場合、この勘定を使うことで「売掛債権の売却によってどの程度コストが発生しているか」を定量的に管理しやすくなります。
一方で、一般的な支払手数料と分けて管理する必要がない場合は、後述のように支払手数料で処理する選択肢もあります。
- 売掛債権を「売却」する考え方が明確な場合に採用しやすい勘定科目。
- 売掛金の帳簿価額と受取額の差額を一目で把握でき、ファクタリングのコスト管理に役立つ。
- 他の売掛債権売却(手形割引や債権譲渡など)と合わせて管理する場合にも使いやすい。
支払手数料・雑損失を使うケース
ファクタリング手数料を「売上債権売却損」ではなく、「支払手数料」や「雑損失」といった一般的な費用科目で処理するケースも少なくありません。
特に、中小企業や個人事業主の実務では、「金融機関やサービス業者への支払い」という実態を踏まえ、支払手数料にまとめて処理する方が、帳簿や試算表の見通しが良くなる場合があります。
支払手数料で処理する場合のイメージは次のとおりです。
- 請求書額:1,000,000円(売掛金)
- 買取額:930,000円
- 手数料:70,000円(内訳:ファクタリング手数料50,000円、事務手数料20,000円)
仕訳例:
- 借方:現金預金 930,000円/借方:支払手数料 70,000円/貸方:売掛金 1,000,000円
このように処理すれば、「売掛金は全額消し込み」「支払手数料としてファクタリング関連コストを一括計上」というシンプルな形になります。
ファクタリング以外にも、銀行振込手数料・カード決済手数料などを支払手数料に集約している企業では、ここにファクタリングの費用も含めることで、「金融サービス関連コスト」をまとめて管理できるメリットがあります。
一方、雑損失を用いるのは、「金額が少額であり、他の費用との区分が特に重要でない場合」などに限るのが一般的です。
雑損失は性格の異なる少額費用をまとめる勘定科目であるため、ファクタリングの利用が継続的・多額である場合には、支払手数料や売上債権売却損など、より内容を表す科目に分けた方が、管理・説明の観点から望ましいといえます。
- 支払手数料:ファクタリングを含む金融サービスの費用として一括管理したい場合に有力な選択肢。
- 雑損失:金額が少額・一時的な場合の補助的な科目であり、継続的な利用にはあまり向かない。
- 自社の管理方針(コストをどの粒度で把握したいか)に応じて、勘定科目を選び、継続して適用することが重要。
未収入金・売掛金の振替仕訳フロー
ファクタリングの仕訳では、「売掛金を直接消すか、一度未収入金に振り替えてから処理するか」が実務上の選択ポイントになります。
特に2社間ファクタリングでは、「売掛先からの入金は従来どおり自社が受け、あとからファクタリング会社に支払う」という構造になる場合があり、その際に未収入金・未払金・仮受金などの勘定を使ってフローを整理することがあります。
典型的な2社間ファクタリングの流れで、仕訳フローを例示します。
前提:
- 売掛金:1,000,000円(既に計上済)
- ファクタリング実行時の入金:930,000円
- 手数料:70,000円
- 後日、売掛先から1,000,000円が自社に入金され、その全額をファクタリング会社へ送金する。
①ファクタリング実行時(売掛金を未収入金に振替え、入金を受ける)
- 借方:未収入金(ファクタリング) 1,000,000円/貸方:売掛金 1,000,000円
- 借方:現金預金 930,000円/借方:支払手数料(または売上債権売却損) 70,000円/貸方:未収入金(ファクタリング) 1,000,000円
②売掛先からの入金時(未収入金の回収として処理)
- 借方:現金預金 1,000,000円/貸方:未収入金(ファクタリング) 1,000,000円
③ファクタリング会社への送金時
- 借方:未払金(ファクタリング会社) 1,000,000円/貸方:現金預金 1,000,000円
- (②と③を相殺して、直接現金預金の増減だけで表現する処理も可能)
実務では、②・③を一仕訳で「売掛先からの入金をそのままファクタリング会社に支払った」とみなして処理する簡略化も行われます。
重要なのは、「売掛金はファクタリング実行時に消し込まれていること」「未収入金・未払金を通じて、ファクタリング会社との債権債務関係を帳簿上明確にしていること」です。
3社間ファクタリングの場合は、売掛先からの入金が直接ファクタリング会社に行われるため、未収入金を経由せずに、「売掛金の消滅」と「ファクタリング入金」を同時に記録するシンプルな仕訳にできるケースが多くなります。
- ファクタリング実行時点で、売掛金を未収入金(ファクタリング)に振り替えておくとフローを把握しやすい。
- 2社間では、「売掛先→自社→ファクタリング会社」というお金の流れを、未収入金・未払金等で明確に表現する。
- 3社間では、売掛先からファクタリング会社への直接入金を前提に、売掛金の消滅とファクタリング入金を整理する。
ファクタリング手数料の税務・消費税取扱い

ファクタリング手数料は、会計上は費用として処理しますが、税務上も「いつ損金算入できるか」「消費税がかかるか(課税/非課税)」という2つの観点を押さえておく必要があります。
買取型ファクタリングの場合、手数料は通常、そのファクタリング取引が行われた事業年度の損金(経費)として認められるのが一般的です。
一方、保証型や長期にわたる契約では、「どの期間に対応する費用なのか」を見て、前払費用として期間按分が必要になるケースもあります。
消費税については、金融取引に該当する部分(利息や割引料など)は非課税とされますが、ファクタリングの付随サービス(事務手数料、登記手続きの代行報酬など)は、一般の役務提供として課税対象となるのが原則です。
さらに、登録免許税や印紙税そのものは消費税の対象外(不課税)である一方、それらの支払いを代行してもらう際の「代行手数料部分」は課税される、といった区分も押さえておきたいポイントです。
税務調査の場面では、「損金算入のタイミング」「課税・非課税の区分」「売上債権売却損と手数料の区分」がチェックされやすいため、契約書や請求書で内訳を確認し、帳簿上も科目と金額を整理しておくことが重要です。
| 論点 | 概要 |
|---|---|
| 損金算入時期 | 原則として、ファクタリング取引が行われた事業年度に費用計上(ただし長期契約の保証料等は期間按分の検討が必要)。 |
| 消費税区分 | 金融取引に該当する割引料などは非課税、一方で事務手数料・登記代行料などは課税取引として区分。 |
| 付随税目 | 登録免許税・印紙税自体は消費税の対象外。代行手数料部分は消費税の課税対象となる。 |
手数料の損金算入時期と留意点
法人税法の基本的な考え方では、費用は「その事業年度の益金と対応する部分を、その事業年度の損金とする」という期間対応の原則に基づきます。
買取型ファクタリングの手数料(売上債権売却損や支払手数料として処理する部分)は、通常、特定の債権を譲渡した時点でサービス提供が完了しており、その事業年度に費用が発生したと考えられるため、買取が実行された事業年度の損金として処理するのが一般的です。
一方で、保証型ファクタリング(売掛保証型)など、1年分まとめて保証料を支払うケースでは、その保証料がどの期間の取引に対応するかを意識する必要があります。
会計上、複数事業年度にわたって効果が及ぶ保証料については、前払費用として資産計上し、各事業年度に按分して費用化する処理が原則になります。
税務上も、実質的に当期の業務に対応する部分を当期の損金、それ以外を翌期以降の損金とする整理が基本です。
また、決算日近くにファクタリングを利用した場合、「手数料の発生・計上タイミング」と「入金・支払のタイミング」がずれることがあります。
発生主義(債務が確定し、金額を合理的に見積もれる時点で費用計上)に基づき、決算日までにサービス提供が完了しているか、請求書が到着しているかなども確認し、未払計上や前払計上が必要かどうかを判断します。
- 買取型の手数料は、原則として買取が実行された事業年度の損金として処理する。
- 保証型で複数年度にまたがる保証料は、前払費用として期間按分が必要になる場合がある。
- 決算直前の取引では、請求・役務提供の完了状況を確認し、未払計上・前払計上の要否を検討する。
非課税となる基本手数料の範囲
日本の消費税法では、「利子、割引料その他これらに類する対価」は、金融取引として非課税となる取引類型に含まれます。
ファクタリングのうち、売掛債権を買い取ることに伴って支払われる割引料(売掛金額と買取額の差額部分)は、一般に金融取引に係る対価と解釈されるため、消費税の課税対象とはならず、仕入税額控除の対象にもなりません。
保証型ファクタリングにおける保証料(売掛保証料)も、信用保証や信用保険と同様、「金融・保険サービス」に該当する部分については非課税取引とされるのが原則です。
ただし、各サービスの請求書には、非課税対象となる部分と、課税対象となる事務手数料などが混在して記載されているケースが多いため、請求書の内訳や契約書の記載を確認して区分することが重要です。
ここで注意したいのは、「金融取引に係る対価」として非課税になるのは、あくまで「債権の譲渡や保証そのものに対する対価」の部分であり、付随する事務処理や代行業務の料金まで自動的に非課税になるわけではないという点です。
ファクタリング会社や保証会社が請求書に「手数料(非課税)」「事務手数料(課税)」のように区分している場合、それぞれの金額を仕訳上も非課税区分/課税区分に分ける必要があります。
- 売掛債権を買い取る際の割引料(買取額と債権額の差額部分)は、金融取引に係る対価として非課税となるのが一般的。
- 売掛保証料(信用保証・信用保険に類する部分)も、金融・保険サービスとして非課税取引に区分される。
- ただし、請求書に記載された「事務手数料」「調査手数料」などは課税対象となる可能性が高く、内訳の確認が必須。
登記費用など課税取引の区分
ファクタリングに付随して発生するコストのうち、消費税の扱いが分かれやすいのが「登記費用」「専門家報酬」「振込手数料」「印紙税」などです。動産・債権譲渡登記を行う場合、法務局に納める登録免許税そのものは「国税」であり、消費税の課税対象外(不課税)です。
一方、登記申請を司法書士に依頼した場合の司法書士報酬は、司法書士による役務提供として消費税の課税対象となります。
また、登録免許税の立替金自体は不課税ですが、それに上乗せされる「立替事務手数料」部分は課税取引として扱うのが原則です。
同様に、ファクタリング会社が請求する「事務手数料」「審査手数料」「契約事務手数料」なども、一般の役務提供の対価として消費税の課税対象になります。
銀行振込に伴う振込手数料については、銀行が直接受け取る手数料は金融取引として非課税とされる一方、ファクタリング会社が「振込手数料相当額」として利用者に請求する場合、その部分は課税取引として計上する必要が出てきます。
印紙税については、消費税法上の課税取引ではないため、印紙代自体は不課税ですが、印紙購入や貼付を代行するサービスに対する手数料は課税取引となります。
実務では、請求書に「非課税」「課税」「不課税」の区分が明記されていることも多いため、これに沿って会計システム上の税区分(課税仕入・非課税仕入・対象外)を設定しておくと、仕入税額控除の計算ミスを防ぎやすくなります。
- 登録免許税や印紙税そのものは消費税の対象外(不課税)。一方、司法書士報酬や事務代行手数料は課税仕入となる。
- ファクタリング会社の「事務手数料」「審査手数料」「振込手数料相当額」などは、原則として消費税の課税対象。
- 請求書の内訳をもとに、会計システム上でも「非課税」「課税」「対象外」の区分を正しく設定し、仕入税額控除の計算に反映させる。
中小企業の勘定科目Q&A

中小企業でファクタリングを導入すると、「これは金利なのか、手数料なのか」「支払利息で良いのか、それとも支払手数料なのか」「会計ソフトにそれらしい科目が出てこない」といった実務的な疑問が出てきます。
特に、銀行借入と違い、ファクタリングは債権の譲渡(売却)や保証に対する対価であるため、表面的なイメージだけで「金利」「利息」として処理すると、決算書の見え方や税務上の区分がぶれてしまうおそれがあります。
まず押さえたいのは、買取型ファクタリングの手数料は「売掛債権を譲渡して、早期に現金化したことに対するコスト」であり、銀行借入に対する利息とは性質が異なるという点です。
そのうえで、「売上債権売却損」として処理するか、「支払手数料」などの費用科目で処理するかを、社内方針として決めておくと、仕訳や試算表の統一が図れます。
会計ソフトに専用科目がない場合の実務的な対応や、個人事業主の簡易帳簿での処理のしかたも、よくあるQ&Aとして整理しておくと、担当者が変わっても迷いにくくなります。
| Q&Aのテーマ | 押さえたい観点 |
|---|---|
| 金利との違い | 銀行利息との性格の違い、支払利息としない方がよいケース、割引料との区別 |
| ソフトの科目設定 | 既存科目を流用する場合と、補助科目・サブ科目を作る場合の考え方 |
| 個人事業主 | 簡易帳簿でも最低限押さえたい科目選択と記録方法 |
金利・割引料との違いと区別基準
ファクタリング手数料は、見た目だけ見ると「お金を前倒しで受け取るためのコスト」であり、銀行利息や手形割引料と似た印象があります。
しかし、実務上は「利息」なのか「手数料」なのかを区別しておくことが大切です。銀行借入に対する利息は、金銭消費貸借契約に基づき、借入元本に対して一定の利率を乗じて計算される対価であり、決算書上は「支払利息」として表示されるのが一般的です。
一方、買取型ファクタリングの手数料は、売掛債権を譲渡する際の値引き分(割引料)やサービス対価としての性格が強く、「借入」に対する利息とは法的・経済的性質が異なります。
区別の基準としては、次のような点を確認します。
- 契約の形式:金銭の貸付(借入)か、債権の譲渡(売買)か、保証か。
- 計算方法:借入残高×利率×期間で発生する利息か、売掛金額と買取額の差額として一度だけ発生する割引料か。
- 表示目的:財務分析上「借入コスト」として見せたいのか、「売掛債権売却に伴う費用」として管理したいのか。
この観点から、多くの中小企業では、ファクタリング手数料を「支払利息」ではなく、「売上債権売却損」や「支払手数料」として処理する方が整合的です。
利息と混在させると、銀行から見た借入実態や金融コストの把握が難しくなり、与信判断にも影響し得るため、「利息は借入に対するもの」「ファクタリングは売掛債権やサービスに対するもの」と切り分けておくと、決算書の説明性が高まります。
会計ソフトに科目がない場合の対応
市販の会計ソフトやクラウド会計では、「売上債権売却損」や「ファクタリング手数料」といった科目が最初から用意されていない場合もあります。その際に迷いやすいのが、「どの科目を選べばよいか」「新しい科目を作るべきか」という点です。
基本的な考え方としては、「既存の性格の近い勘定科目(支払手数料など)を使う」か、「元の科目を親として補助科目・サブ科目を追加する」のどちらかで整理する方法がよく採用されます。
例えば、次のような設定イメージが考えられます。
- 支払手数料の補助科目として「ファクタリング手数料」を追加し、ファクタリング関連のコストをそこで集計する。
- 特に売掛債権の売却損を把握したい場合は、新規に「売上債権売却損」科目を追加し、そこに差額を計上する。
- クラウド会計の「勘定科目のカスタマイズ」機能を使い、決算書の表示上は「支払手数料」にまとめつつ、内部管理用に細分化する。
重要なのは、「毎期同じルールで処理し、ブレを作らない」ことです。途中で科目を変えると、前年との比較や税務調査時の説明が難しくなります。
会計ソフトの初期設定どおりに処理するのではなく、自社の業種・ファクタリング利用頻度・管理したい粒度を踏まえて、税理士とも相談のうえで科目体系を決めると、後々の分析や説明がスムーズになります。
個人事業主・簡易帳簿での実務処理
個人事業主や白色申告・簡易帳簿の場合、「細かい科目を増やしすぎても管理しきれない」「会計ソフトを使わずエクセルや手書きで付けている」というケースも少なくありません。
このような場合でも、最低限「売掛金をいくら現金化し」「そのためにいくらコストをかけたか」が分かるようにしておくことが重要です。
勘定科目については、無理に専門的な科目を作らず、「売掛金」「売掛金売却損」「支払手数料」など、性格の近い科目にまとめて処理する方法が現実的です。
たとえば、個人事業主が請求書額300,000円の売掛金をファクタリングに出し、手数料15,000円を差し引かれて285,000円を受け取った場合、簡易な帳簿では次のような処理が考えられます。
- 売上発生時:借方 売掛金 300,000円/貸方 売上 300,000円
- ファクタリング利用時:借方 現金 285,000円/借方 支払手数料(または売掛金売却損) 15,000円/貸方 売掛金 300,000円
- 簡易帳簿では、「売掛金の回収額」と「ファクタリングにかかった費用」を日付ごとにメモしておく。
青色申告で複式簿記を採用している個人事業主であれば、法人と同様に勘定科目を細分化して管理することも可能ですが、「記帳負担」と「得られる情報」のバランスを見て決めることが大切です。
どの科目を使うにしても、「毎年同じ処理を継続すること」「事業用と家事費用を混在させないこと」「確定申告書の別表や収支内訳書と整合する形で集計すること」を意識しておくと、後から修正や説明が必要になるリスクを減らせます。
実務で使える仕訳例とチェックポイント

ここまででファクタリング手数料の性格や勘定科目の候補を整理しましたが、実務担当者としては「結局、日々の仕訳をどう切るか」「決算のときにどこを見ればよいか」が一番気になるポイントだと思います。
ここでは、典型的な一括買取のケースをベースに、売掛金発生→ファクタリング利用→回収・消し込みまでの流れを、仕訳ステップとして具体的に整理します。
あわせて、決算期をまたぐ場合の未払計上や前払費用の扱い、税理士とすり合わせておきたい論点をチェックリスト形式でまとめ、日々の経理処理と年次決算の両方で迷いにくい実務イメージを持てるようにすることが目的です。
まずは、売掛金を一括でファクタリングに出した場合の基本パターンを押さえたうえで、「自社は売上債権売却損で処理するのか」「支払手数料で処理するのか」といった方針を固め、その方針に沿って会計ソフトの勘定科目・補助科目・税区分を設定しておくことが、実務上の最初のチェックポイントになります。
| 場面 | 主な論点・チェックポイント |
|---|---|
| 日々の仕訳 | 売掛計上、ファクタリング実行時の仕訳、回収時の消し込み方法を統一しているか。 |
| 決算対応 | 期末時点での未払手数料・前払保証料の有無、税務上の損金算入時期を確認しているか。 |
| 方針の統一 | 科目(売上債権売却損・支払手数料など)と税区分(課税/非課税)を税理士と共有し、毎期ぶれなく処理しているか。 |
一括買取時の仕訳ステップ例
一般的な買取型ファクタリングで、売掛金をまとめて一括買取してもらうケースを想定した仕訳例です。ここでは、売掛金1,000,000円をファクタリング会社に譲渡し、買取率95%、ファクタリング手数料(割引料)が買取額の5%と仮定します。
前提:
- 売掛金(元の売上) 1,000,000円(既に売上計上済)
- 買取額:1,000,000円×95%=950,000円
- 手数料:950,000円×5%=47,500円
- 実際の入金額:950,000円−47,500円=902,500円
【パターン1:売上債権売却損で処理する場合】
ファクタリング実行時(買取実行と同時に入金されたケース):
- 借方:現金預金 902,500円/借方:売上債権売却損 97,500円/貸方:売掛金 1,000,000円
ここでは、「売掛金1,000,000円のうち、902,500円を現金化し、差額97,500円(買取割引・手数料相当)を売上債権売却損として費用処理した」と整理しています。
明細上、手数料47,500円とその他費用(事務手数料・登記費用など)50,000円を売上債権売却損にまとめているイメージです。
【パターン2:支払手数料を使う場合】
- 借方:現金預金 902,500円/借方:支払手数料 97,500円/貸方:売掛金 1,000,000円
この場合は、「売掛金は全額消し込み、差額はすべて支払手数料」として扱います。
ファクタリング以外の金融サービス費用(振込手数料、カード手数料など)と合わせて管理したい場合には、この処理の方が試算表が見やすくなることもあります。
いずれのパターンでも、社内で採用する勘定科目を1つに決め、同じスキームのファクタリングには同じ処理を継続して適用することが重要です。
- 売掛金の帳簿価額と入金額の差(=ファクタリング関連コスト)をどの勘定科目に集約するかを決める。
- 仕訳パターン(売上債権売却損か支払手数料か)を毎期統一し、途中で変えないようにする。
- 手数料の内訳(割引料、事務手数料、登記費用など)を請求書ベースで把握しておくと、税務や分析に活かしやすい。
決算期をまたぐ場合の処理と注意点
ファクタリングの利用が決算期をまたぐ場合、「手数料はいつの費用か」「未払計上や前払計上が必要か」が論点になります。
買取型ファクタリングで、決算日前に買取が実行されているのであれば、その時点でサービス提供が完了しているため、原則としてその事業年度の費用(損金)として処理することになります。
決算日をまたいで支払いが行われる場合でも、「発生主義」に基づき、決算日時点で債務が確定している金額は未払費用として計上するのが基本的な考え方です。
一方、保証型ファクタリングや売掛保証で、1年分の保証料を一括で支払うような契約では、保証期間が複数事業年度にまたがることがあります。
この場合、会計上は前払費用として資産計上し、保証期間に対応する額を各期の費用に配分する処理が原則になります(税務上も、実質的に対応する期間に応じて損金算入する考え方が基本です)。
決算時に「当期分」と「翌期以降分」を分けておくことで、翌期に費用が二重計上されるといったミスを防ぐことができます。
また、決算時点で「請求書は届いていないが、ファクタリングを利用した事実があり、手数料額が概ね確定している」ケースも想定されます。
この場合は、契約書や計算書をもとに合理的な見積額を算出し、未払計上するかどうかを税理士と相談して判断します。
- 買取型:決算日前に買取実行済みの手数料は、原則として当期の費用。未払があれば未払費用として計上する。
- 保証型:保証期間が複数期にわたる場合は、前払費用として資産計上し、期間按分するかを検討する。
- 請求書未着でも金額が確定している場合は、契約書をもとに未払計上の要否を税理士と確認する。
税理士と確認したいチェックリスト
ファクタリングの会計・税務は、スキームや契約内容によって判断が分かれるポイントが多く、「なんとなく手数料だから支払手数料で」といった処理を続けると、後で修正や説明が必要になることがあります。
そこで、導入時・決算時に税理士と共有しておきたいチェック項目を整理しておくと安心です。以下は、実務でよく議題に上がる項目です。
- スキームの確認:自社が利用しているのは買取型か保証型か、2社間か3社間か、ノンリコースかリコース付きか。
- 勘定科目方針:売上債権売却損/支払手数料/保証料など、どの科目で処理し、損益計算書上どこに表示するか。
- 消費税区分:割引料・保証料など非課税部分と、事務手数料・登記代行料など課税部分の区分方法。
- 損金算入時期:買取型の手数料をいつの事業年度の損金とするか、保証料を前払費用で期間按分するかどうか。
- 決算整理:期末時点で未払・前払・未収などが発生していないか、仕訳の洗い出しと決算整理仕訳の要否。
これらの項目をベースに、契約書・見積書・請求書を一度税理士に見てもらい、「自社としての処理方針」を決めてしまえば、その後の月次・年次処理はルールに従って機械的に進めることができます。
経理担当者が変わっても同じルールで処理できるよう、社内マニュアルや経理メモの形で残しておくことも、実務上の重要なチェックポイントです。
まとめ
ファクタリング手数料の会計処理は、「どのスキームか」「何に対する対価か」を押さえれば整理しやすくなります。
買取型なら売上債権売却損や支払手数料、保証型なら保証料に近い性格など、勘定科目ごとの位置付けを理解しておくことで、仕訳ミスや税務リスクを減らせます。
また、消費税の課非判定や損金算入時期、決算またぎの処理は、実務でつまずきやすいポイントです。本記事の仕訳例とチェックリストを参考にしつつ、最終的な判断は税理士とも共有し、自社の会計方針をあらかじめ統一しておくことが安心につながります。