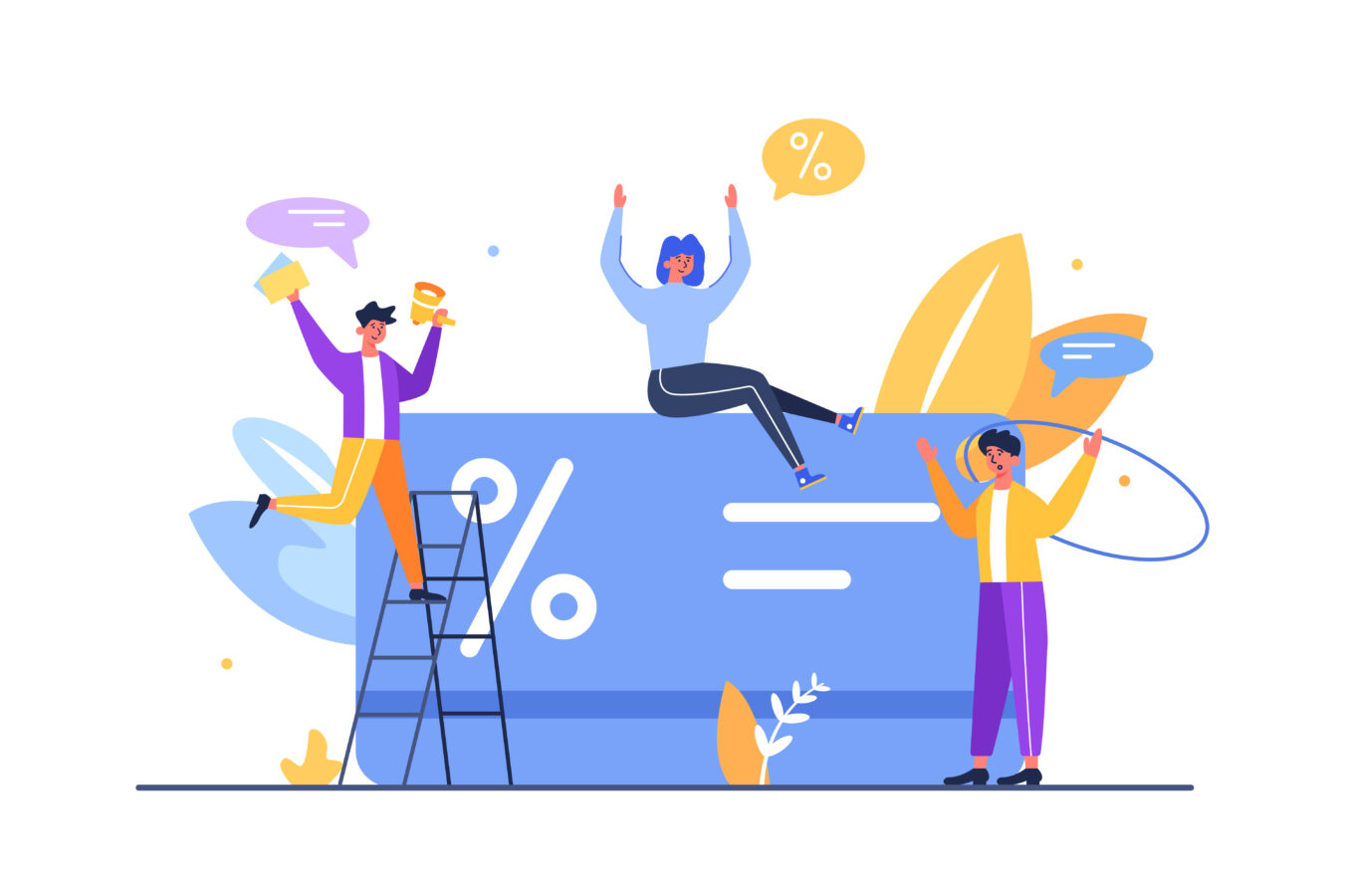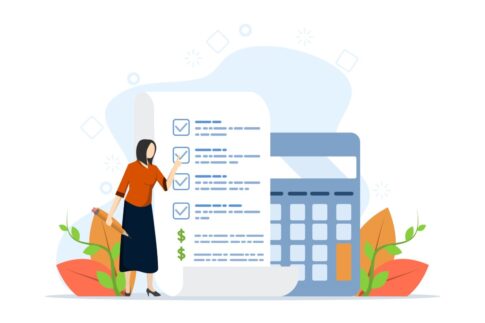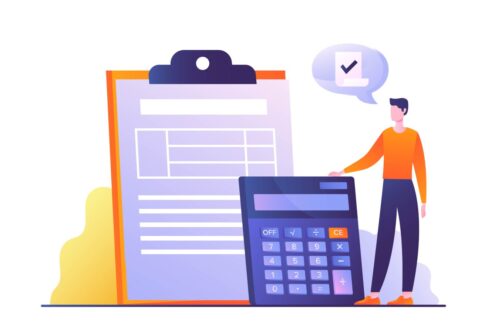ファクタリング手数料に消費税はかかるのか、仕訳はどうなるのかは、経理担当者にとって気になるポイントです。
この記事では、ファクタリング手数料が原則「非課税」とされる理由と注意したい例外、登記費用・司法書士報酬・収入印紙など周辺コストの消費税区分、具体的な仕訳例やインボイス制度との関係までを一つずつ整理します。税務調査で迷いやすい論点やチェックリストもまとめ、実務で迷わず判断できるようになることを目的としています。
ファクタリングと消費税の基本

ファクタリングは、利用者(売掛金を持つ会社)が取引先に対する売掛債権(金銭債権)をファクタリング会社に売却し、その代わりに現金を受け取る取引です。
日本の消費税法では、国内で行われる取引のうち「土地」「有価証券等」「金銭債権」「支払手段」などの譲渡は非課税取引として扱われます。
国税庁のタックスアンサーでも、「国債・株式等に加え、売掛金その他の金銭債権の譲渡」は非課税と明記されています。
この枠組みに当てはめると、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡する行為は「金銭債権の譲渡」に当たるため、基本的に消費税の課税対象にはなりません。
また、国税庁の質疑応答事例では、金銭債権を割引いて買い取る際の割引料・保証料・手数料についても「金銭債権の譲渡に対する対価」であり、非課税売上になると整理されています。
一方で、ファクタリングの利用に付随する事務手数料やシステム利用料、司法書士報酬などは、一般の役務提供と同じく課税取引に該当し、消費税の対象になります。
そのため、「ファクタリング手数料(割引料)は非課税」「周辺サービスの費用は課税」という区分を意識しておくことが大切です。
| 項目 | 消費税の扱い(原則) |
|---|---|
| 売掛金の譲渡 | 金銭債権の譲渡として非課税取引 |
| 買取手数料(割引料) | 金銭債権の譲受対価として非課税取引 |
| 事務手数料・システム利用料 | 役務提供として課税取引 |
| 司法書士報酬 | 専門サービスの対価として課税取引 |
ファクタリングの消費税区分
ファクタリング取引の消費税区分を考えるときは、「何を譲渡しているか」「どの部分がお金の貸し借りや金融取引に当たるか」を整理することが重要です。
売掛債権は金銭債権の一種であり、その譲渡は消費税法上「有価証券等の譲渡」の一部として非課税取引に含まれます。
国税庁のタックスアンサー「非課税となる取引」では、有価証券や国債等と並んで「売掛金その他の金銭債権の譲渡」が非課税と明示されています。
さらに、国税庁の質疑応答事例「金銭債権の買取り等に対する課税関係」では、ファクタリングとほぼ同じ構造の取引が前提とされ、「金銭債権を買い取る際に債権者から徴収する割引料・保証料・手数料は、その名目にかかわらず非課税売上になる」と示されています。
つまり、「売掛金を◯%引きで現金化する部分」は、消費税の観点では非課税取引として扱うのが原則です。
具体例で見ると、請求書額面100万円(うち消費税10万円を含む)を、ファクタリング会社が手数料10%で買い取る場合、利用者が受け取るのは90万円です。
この10万円は「割引料」であり、商品・サービスの提供に対する対価ではなく、金銭債権の譲渡差額として扱われるため、消費税は課されません。
- 売掛債権の譲渡=金銭債権の譲渡として非課税
- 割引料・買取手数料・保証料=原則として非課税売上
- 商品・サービスの対価ではないため、「消費」に対する課税の対象外
手数料が非課税になる理由
ファクタリング手数料(割引料)が非課税とされる理由は、「消費税は商品やサービスの『消費』に対して課税する税金であり、金融取引や資金移動そのものには課税しない」という基本的な考え方にあります。
消費税法では、非課税となる取引として「有価証券等の譲渡」が挙げられ、その中に金銭債権の譲渡が含まれます。
ファクタリングでは、利用者が持つ売掛債権をファクタリング会社が買い取り、債務者(取引先)からの支払いを受け取る権利を引き継ぎます。
このとき、額面100万円の債権を90万円で買い取るとすると、差額の10万円は「金融取引における割引差額」であり、商品やサービスの提供に対する代金ではありません。
国税庁の質疑応答事例でも、この割引差額(割引料・保証料・手数料)は、金銭債権の譲渡に係る対価として非課税と整理されています。
なお、金利や利息も「利子を対価とする金融取引」として非課税取引に分類されますが、ファクタリングの割引料も同じく「金融的な性格を持つ対価」です。
したがって、消費税の課税対象である「資産の譲渡等」(商品販売や役務提供)には含まれません。
- 消費税は「消費」に対する税であり、金融取引は原則として非課税
- 売掛金は「金銭債権」であり、その譲渡は有価証券等の譲渡として非課税
- 割引料・保証料・手数料は、債権譲渡の差額として非課税売上に分類
課税になる費用のパターン
ファクタリングの「割引料」自体は非課税ですが、取引に付随する各種費用の中には消費税の課税対象になるものがあります。
代表的なのは、事務手数料・審査料・システム利用料などの役務提供に対する対価、司法書士や税理士など専門家への報酬です。
これらは、金銭債権の譲渡そのものではなく、事務処理や専門サービスという「役務の提供」に当たるため、一般の役務と同様に課税仕入として扱います。
また、債権譲渡登記を行う場合、法務局に納める登録免許税そのものは国税であり消費税の対象外ですが、登記申請を司法書士に依頼した場合の報酬は課税取引です。
請求書上で「登録免許税」と「報酬」が区分されていなければ、どこまでが消費税の課税対象か分かりにくくなるため、明細の確認が必要です。
ファクタリング会社によっては、「買取手数料(非課税)」「事務手数料(課税)」をまとめて「手数料」と表示しているケースもあります。
この場合でも、消費税の区分は実態に応じて判断する必要があり、「割引料なのか、サービス対価なのか」を分けて考えることが求められます。
- 事務手数料・審査料・システム利用料などのサービス対価
- 司法書士報酬やコンサル料など専門家の報酬部分
- 請求書上で「非課税の割引料」と「課税のサービス料」が区分されているか
売掛金と消費税の関係
売掛金は、もともと商品の販売やサービス提供に対する「請求権」であり、その中には消費税相当額も含まれています。
たとえば、税込110万円(本体100万円+消費税10万円)で販売した場合、売掛金110万円の内訳としては「売上100万円」「仮受消費税10万円」です。
ファクタリングでこの売掛金を譲渡しても、「元の売上が課税取引であること」「10万円分の消費税を納める義務があること」は変わりません。
つまり、ファクタリングによって「売掛金を現金化するタイミング」は変わりますが、「どの売上に対してどれだけの消費税を計上するか」という点には影響しません。
課税売上としてカウントされるのはあくまで元の販売取引であり、売掛金の譲渡や割引料は非課税取引として区分されます。
一方、課税売上割合(仕入税額控除の按分計算に使う割合)を計算する際には、「非課税取引が多いと控除できる仕入税額が減る」という仕組みがあります。
金銭債権の譲渡については、国税庁の質疑応答やタックスアンサーで、「一定の金銭債権の譲渡は総売上高・課税売上高の双方から除外する」等の取扱いが示されており、再ファクタリングなど特別なケースでは個別の検討が必要になる場合もあります。
実務では、まず「元の売上の消費税処理」と「ファクタリング取引の非課税処理」を切り分けたうえで、課税売上割合に影響がある規模かどうか、必要に応じて税理士に確認する流れが安心です。
- 売掛金には元の売上の消費税相当額が含まれるが、ファクタリングしても納税義務は変わらない
- 課税売上としてカウントされるのは「販売取引」であり、売掛金の譲渡は非課税取引
- 課税売上割合への影響はケースにより異なるため、金額が大きい場合は専門家に確認する
手数料と消費税の具体例

ここからは、ファクタリング手数料と消費税の関係を、実際の数字と仕訳例で確認します。ファクタリングは「売掛金の譲渡」であり、その割引料(買取手数料)は原則として非課税取引に当たりますが、事務手数料や専門家報酬などは課税取引になるものも含まれます。
また、買取型と保証型では、手数料の性格や会計処理のイメージも変わります。
国税庁の質疑応答事例では、金銭債権の買取りに際して債権者から徴収する割引料・保証料・手数料は、名目にかかわらず「金銭債権の譲受対価」として非課税売上(非課税仕入)になることが示されています。
一方で、金銭債権の買取りとは別に提供されるサービス部分については、通常の役務提供として課税されるのが原則です。
| 区分 | 典型的な消費税の扱い |
|---|---|
| 買取型の割引料 | 金銭債権の譲受対価として非課税 |
| 保証型の保証料 | 信用保証としての金融取引で非課税となる取扱いが一般的 |
| 事務手数料・システム利用料 | 役務提供に対する対価として課税 |
| 司法書士報酬 | 専門サービスに対する対価として課税 |
買取ファクタリングの仕訳例
買取ファクタリングは、もっとも一般的なスキームです。まず通常どおり売上を計上し、その後、売掛金をファクタリング会社へ譲渡して資金化します。
国税庁の事例でも、自社の営業債権をファクタリング会社へ売却する際の仕訳例が示されており、割引料は非課税仕入として扱うことが示されています。
前提条件として、次のようなケースを想定します。
- 商品を税込110万円(本体100万円+消費税10万円)で販売し、売掛金を計上
- 後日、この売掛金110万円をファクタリング会社に譲渡し、98万円が振り込まれた(割引料12万円と仮定)
この場合の仕訳例は次のとおりです(勘定科目名は一例です)。
【①販売時】
売掛金 110万円 / 売上 100万円(課税売上)
/ 仮受消費税 10万円
【②ファクタリング利用時】
預金 98万円(対象外) / 売掛金 110万円(対象外)
ファクタリング手数料 12万円(非課税仕入) /
ここで重要なのは、②の「ファクタリング手数料12万円」が、商品やサービスに対する対価ではなく、「金銭債権を譲渡する際の差額」である点です。消費税区分としては、有価証券・金銭債権の譲渡に関する非課税仕入に該当します。
会計ソフト上は「非課税(有価証券等)」など専用の区分が用意されていることが多く、通常の非課税(家賃など)と区別しておくと、課税売上割合の計算にも対応しやすくなります。
- 売上計上時の消費税処理は通常どおり(課税売上)
- 売掛金譲渡時の割引料は「非課税仕入」として区分する
- 売掛金・預金はともに消費税の対象外(資産の区分)で処理する
保証型ファクタリングの仕訳例
保証型ファクタリングは、売掛金そのものを買い取るのではなく、「売掛金が回収できなくなった場合に一定額を保証する」タイプのサービスです。
形としては信用保証に近く、保証料は「信用の保証としての役務提供」に対する対価として、消費税法上非課税取引に区分されるのが一般的です。
保証料については、信用保証協会等への保証料が非課税取引とされることが、消費税法や質疑応答事例で示されています。
前提として、次のようなケースを想定します。
- 売掛金1,000万円について、一定割合を保証する保証型ファクタリングに加入
- 保証期間1年分の保証料として30万円を一括で支払う(保証料は非課税取引)
単純化した仕訳例は次のとおりです。
【保証料支払時(全額当期費用とするケース)】
保証料 30万円(非課税仕入) / 普通預金 30万円(対象外)
保証期間が複数期間にまたがる場合には、保証料の一部を「前払費用」や「長期前払費用」として資産計上し、各期に按分して費用化する処理も行われます。
いずれの場合も、保証料自体は消費税の課税対象外であり、仕訳上も非課税区分として扱う点がポイントです。
- 保証料は「信用の保証」に対する対価として非課税取引
- 支払時に全額費用か、期間按分で前払費用計上するかを契約内容から判断
- 買取型の割引料と同様、消費税区分は「非課税仕入」で処理する
一括で利用した場合の処理
複数の売掛金をまとめて一括でファクタリングする場合でも、基本的な考え方は変わりません。「売掛金総額」「実際に受け取る金額」「差額としての割引料(非課税)」を一括で計算し、その差額を非課税仕入として処理します。
例えば、次のようなケースを想定します。
- 売掛金A:税込330万円、売掛金B:税込220万円、合計550万円
- 2件をまとめてファクタリング会社へ譲渡し、資金化額は合計520万円
- 差額30万円が割引料(買取手数料)
この場合の仕訳例はシンプルにまとめると次のとおりです。
預金 520万円(対象外) / 売掛金 550万円(対象外)
ファクタリング手数料 30万円(非課税仕入) /
ただし、管理上は「どの売掛先分をいくら割引いたのか」を把握できるようにしておくことが望ましいため、社内の管理資料では売掛先ごとに割引料を按分するケースもあります(割合で配分するなど)。
会計帳簿上は一括金額で計上しつつ、補助簿や管理表で内訳を管理するイメージです。
保証型ファクタリングなどで「1年分の保証料を一括払いする」ケースでは、保証期間が複数期にまたがる場合、期をまたぐ部分を前払費用・長期前払費用に振り替える処理が必要になることがあります。
この場合も、保証料自体は非課税取引ですが、「どの期の費用とするか」は会計上の期間配分の問題として整理します。
- 一括で譲渡しても「総額-入金額=割引料」という構図は同じ
- 帳簿上は一括計上でも、管理上は売掛先ごとの割引額を把握しておく
- 保証料を一括で支払う場合、期間をまたぐ部分は前払費用として整理する
インボイス制度とのかかわり
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、「課税仕入の仕入税額控除」を受けるために、原則として適格請求書の保存を求める制度です。
ファクタリングのような金銭債権の譲渡は、消費税法上「非課税取引」に該当するため、インボイス制度の対象となる「課税取引」には含まれません。
したがって、ファクタリング会社が受け取る割引料については、適格請求書の発行・保存が前提となる仕入税額控除の議論とは直接関係しないのが原則です。
一方で、ファクタリングに付随する課税取引(事務手数料・システム利用料・司法書士報酬など)については、従来どおりインボイス制度の対象になります。
たとえば、ファクタリング会社から「事務手数料(課税)+割引料(非課税)」が請求される場合、事務手数料部分について仕入税額控除を受けるには、その部分が適格請求書の要件を満たしている必要があります。
また、売掛金の「もとになる売上」については、通常の課税売上としてインボイスの発行・保存が必要です。
ファクタリングを利用しても、「誰が誰に商品・サービスを提供し、消費税を受け取っているか」という構図は変わらないため、売手側は取引先(買手)に対して適格請求書を発行し、買手はそれを保存して仕入税額控除を検討することになります。
ファクタリング会社は、この課税仕入の当事者ではなく、金銭債権の譲受人という立場です。
- ファクタリングの割引料は非課税取引であり、インボイス制度の対象外
- 事務手数料・システム利用料・専門家報酬など課税部分にはインボイスが必要
- 元の売上取引については、従来どおり売手が取引先に適格請求書を発行する
登記費用・印紙税の考え方

ファクタリングを利用すると、「債権譲渡登記」と「契約書(債権譲渡契約書)」に関するコストが発生します。
これらは消費税とは別の税目(登録免許税・印紙税)であり、金額は大きくないものの、取引件数が多い企業では合計額が無視できない水準になることもあります。
まずは、①登記そのものにかかる登録免許税と情報取得の手数料、②登記手続を司法書士に依頼した場合の報酬、③契約書にかかる印紙税、という3つに分けて考えると整理しやすくなります。
登録免許税は、法務局に支払う国税であり、消費税の「課税取引」には該当しません(租税公課として処理)。
また、法務局や登記情報提供サービスが行う登記・証明業務にかかる手数料も、国が法令に基づき徴収する手数料として非課税取引に区分されます。
一方、司法書士に支払う報酬や、ファクタリング会社が独自に設定する事務手数料などは「役務提供の対価」であり、消費税の課税対象です。印紙税は、契約書や領収書など「文書」そのものに課される国税です。
ファクタリングで用いる債権譲渡契約書は、印紙税法上「第15号文書(債権譲渡または債務引受けに関する契約書)」に該当し、契約金額が1万円未満であれば非課税、1万円以上または契約金額の記載がない場合は1通あたり200円の印紙税額となります。
| 項目 | 税目・消費税上の扱い |
|---|---|
| 登録免許税 | 登記時に法務局へ納める国税。消費税の課税対象外(不課税)で、会計上は租税公課などで処理。 |
| 登記情報等の手数料 | 国等が法令に基づき徴収する手数料として非課税取引。 |
| 司法書士報酬 | 司法書士の役務提供に対する対価であり、消費税の課税取引(課税仕入)。 |
| 債権譲渡契約書の印紙税 | 印紙税法上の第15号文書。1万円未満は非課税、1万円以上または金額記載なしは1通200円。消費税はかからない。 |
債権譲渡登記費用の扱い
ファクタリングのうち、特に2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記を行うケースが多く見られます。
債権譲渡登記を行うと、同じ売掛金が二重に譲渡されるリスクや、第三者との優先順位を巡る争いを防ぐ効果があり、ファクタリング会社にとっては重要な権利保全手段です。
このとき発生する主なコストは、①登記申請時に納める登録免許税、②登記手続や書類作成を司法書士に依頼した場合の報酬、③登記事項証明書の取得費用などです。
登録免許税は、登録免許税法に基づいて法務局に納める国税であり、消費税の「課税取引」には含まれません。
一般の会計・税務解説でも、登録免許税は不課税(消費税の対象外)とされ、勘定科目としては租税公課や創立費などで処理するのが通常とされています。
また、登記事項証明書の交付手数料や登記情報提供サービスの利用料など、国が法令に基づいて徴収する手数料についても、消費税法上「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」として非課税取引に位置付けられています。
一方、司法書士に登記申請や書類作成を依頼した場合の報酬は、司法書士が提供する専門サービスに対する対価であり、消費税の課税対象です。
実務では、司法書士からの請求書が「報酬部分」と「登録免許税等の立替部分」に分かれていることが多く、報酬部分のみを課税仕入として処理し、登録免許税や登記手数料など立替経費は不課税・非課税として区分するのが一般的です。
- 登録免許税=国に納める税金で、消費税の課税対象外(不課税・租税公課)
- 登記事項証明書や登記情報提供サービスの手数料=国等の一定の事務に係る役務として非課税
- 司法書士報酬=専門サービスの対価として課税取引(課税仕入)。請求書で立替経費と区分する
司法書士報酬と消費税区分
司法書士報酬は、債権譲渡登記や登記事項証明書の取得、契約書のリーガルチェックなど、専門的な役務提供に対する対価です。
消費税法上は、「事業者が事業として対価を得て行う役務の提供」に該当するため、原則として課税取引(課税売上・課税仕入)に区分されます。
国税庁の消費税の基本通達や、登記関連の実務解説でも、登録免許税などの税金・行政手数料は不課税である一方、司法書士への報酬は課税対象である点が繰り返し示されています。
司法書士事務所からの請求書では、「報酬」と「登録免許税」「登記情報提供サービス利用料」などの立替分が区分記載されていることが多く見られます。
実務上は、報酬部分にのみ消費税が計上され、立替分は「課税対象外」として請求書内で扱われる形が一般的です。
経理処理においても、報酬部分を課税仕入として仕訳し、立替分は租税公課や支払手数料など適切な科目で、消費税区分を不課税または非課税で処理します。
ファクタリング会社経由で登記費用が請求される場合も、「司法書士報酬(課税)」と「登録免許税(不課税)」がまとめて「登記費用」と表示されていることがあります。
この場合、契約書や明細書から内訳を確認し、どこまでが課税対象の役務提供で、どこからが税金・行政手数料なのかを把握しておくことが、消費税申告の精度を高めるうえで重要です。
- 司法書士の報酬部分は「役務提供」に対する対価として課税仕入
- 登録免許税や登記手数料などの立替分は不課税・非課税として区分する
- ファクタリング会社経由の「登記費用」請求では、報酬部分と税金部分の内訳を確認する
収入印紙と印紙税の基礎知識
収入印紙は、印紙税法で定められた「課税文書」に課される印紙税を納付するための証票です。印紙税は、契約書や領収書など20種類の文書(第1号文書〜第20号文書)に対して課税され、その文書の性質と記載金額に応じて税額が決まります。
国税庁の「印紙税額の一覧表」では、ファクタリングで用いる債権譲渡契約書は第15号文書「債権譲渡または債務引受けに関する契約書」として位置付けられています。
第15号文書の印紙税額は、契約金額が1万円未満の場合は非課税(印紙不要)、1万円以上または契約金額の記載がない場合は一律200円です。
売掛債権の金額が100万円であっても1,000万円であっても、契約金額が1万円以上である限り印紙税額は1通200円となります。
金額規模に比べると印紙税コストは小さいものの、税務調査で印紙の貼り忘れが指摘されると、本来の印紙税額に加えて過怠税(原則3倍)が課される可能性があるため、確実に対応しておく必要があります。
なお、印紙税は「紙の契約書」に対して課税される税金であり、電子契約書(PDFやクラウド契約サービス等)には現行制度上課税されません。
このため、ファクタリング契約を電子契約で行えば、第15号文書に該当する内容であっても印紙税は不要という整理になります。
- 債権譲渡契約書は印紙税法上の第15号文書に該当
- 契約金額1万円未満:非課税/1万円以上・金額記載なし:200円/通
- 紙の契約書には印紙税がかかるが、電子契約書には課税されない
契約書まわりの税務チェック
ファクタリング契約書まわりでは、「消費税」と「印紙税」の2つの観点でチェックが必要です。
まず、消費税については、ファクタリング手数料(割引料)は非課税取引である一方、事務手数料やシステム利用料など役務提供分は課税取引となるため、見積書・請求書・契約書で「どの金額が非課税で、どの金額が課税か」を区分して確認します。
国税庁の消費税問答集では、金銭債権の譲渡差益・差損や割引料は非課税となる一方、別途提供されるサービス部分は課税対象とされているため、この線引きを意識することが重要です。
次に、印紙税については、契約書が印紙税法のどの号数に該当するか(ファクタリングでは第15号文書が中心)、契約金額の記載があるか、電子契約か紙契約か、を確認します。
国税庁の印紙税額一覧表では、第15号文書の印紙税額が「1万円未満非課税/1万円以上200円/金額記載なし200円」と明示されているため、この基準に沿って必要な収入印紙を貼付し、消印することになります。
また、印紙税と消費税の関係については、「印紙税の記載金額に消費税額を含めるかどうか」という論点がありますが、国税庁の解説では、第1号文書・第2号文書・第17号文書について、消費税額等を区分記載した場合の特例が示されており、第15号文書には適用されないことが明記されています。
ファクタリング契約では、契約金額に消費税が含まれているかどうかにかかわらず、1万円以上であれば印紙税額は一律200円となるため、金額確認と号数判定を確実に行うことが実務上のポイントです。
- 見積書・契約書・請求書で、「非課税の割引料」と「課税の事務手数料等」が区分されているか
- 債権譲渡契約書が第15号文書に該当するか、契約金額と印紙税額(200円)の妥当性を確認したか
- 紙契約か電子契約かを確認し、紙の場合は収入印紙の貼付漏れがないか点検したか
中小企業経理が押さえたい実務
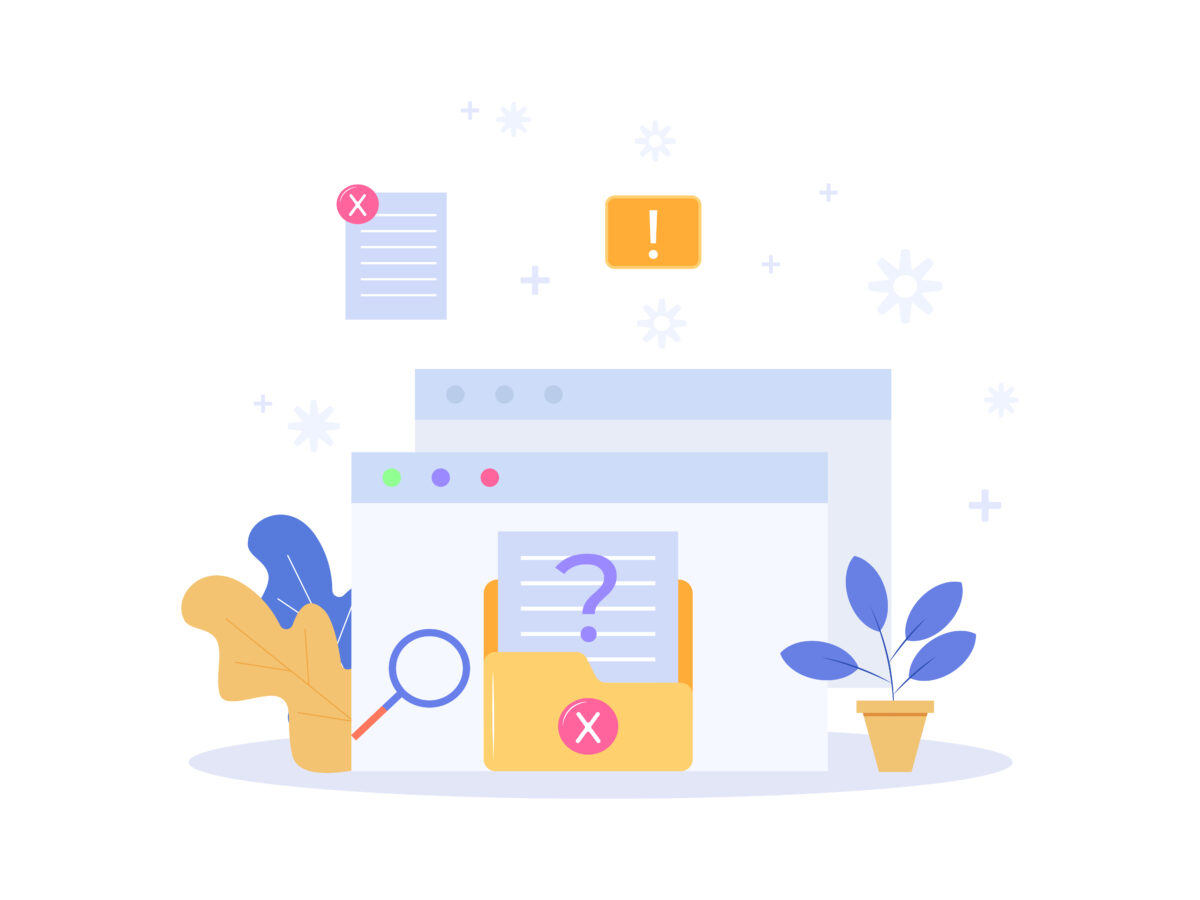
ファクタリングは「売掛金の譲渡」という金融取引であり、消費税の面では非課税取引に当たりますが、実務では「課税売上割合への影響」「非課税取引が多い場合の仕入税額控除」「勘定科目と税区分の設定」「税理士への相談内容」まで一体で考える必要があります。
特に、課税売上割合は仕入税額控除の金額を左右する指標であり、国税庁も計算方法や有価証券・金銭債権の取扱いについて詳細な解説を公表しています。
一般の事業会社が自社の売掛金をファクタリング会社に売却するケースでは、課税売上割合に与える影響は限定的です。
一方で、金融業者やファクタリング会社のように金銭債権の譲渡を繰り返す業態では、有価証券等の譲渡対価の5%を分母に含める特例や、再ファクタリング(譲り受けた売掛金をさらに譲渡する取引)に関する特別な計算方法が定められており、取扱いを誤ると仕入税額控除の計算にズレが生じます。
中小企業の経理担当者としては、①自社がどの程度ファクタリングを利用しているか、②非課税取引全体の規模、③会計ソフト上の税区分設定、④税理士へ説明できる資料の整備、といった実務的なポイントを押さえておくことが、日々の入力ミス防止だけでなく、税務調査時の説明負担軽減にもつながります。
| 実務テーマ | 押さえたいポイント |
|---|---|
| 課税売上割合 | 金銭債権の譲渡の取扱い(5%ルール、自社売掛金の除外など) |
| 非課税取引の多寡 | 95%ルールの適用可否と仕入税額控除への影響 |
| 仕訳・科目 | 「割引料=非課税」「事務手数料・報酬=課税」の切り分け |
| 税理士対応 | 契約書・明細・利用実績の一覧化と論点の整理 |
課税売上割合とファクタリング
課税売上割合は、「課税期間中の課税売上高(税抜)」を「課税期間中の総売上高(課税+輸出免税+非課税の合計)」で割った比率で、仕入税額控除の按分計算に使う重要な指標です。ここでポイントになるのが、有価証券や金銭債権の譲渡の扱いです。
消費税法施行令・基本通達では、有価証券等の譲渡対価については、その全額ではなく「対価の5%」のみを課税売上割合の分母に含める特例が定められており、頻繁に売買が行われる金融取引によって課税売上割合が過度に下がるのを防ぐ仕組みになっています。
さらに、金銭債権のうち「自社の売上の対価として発生した売掛金等」を他社に譲渡する場合(典型例がファクタリング)については、課税売上割合の計算上、その譲渡対価を分母・分子のいずれにも含めない取扱いが示されています。
これは、通常の事業会社が資金繰りのために売掛金をファクタリングに出しただけで、急に課税売上割合が大きく変動してしまうことを防ぐための配慮といえます。
一方、ファクタリング会社やクレジット会社など、他社から譲り受けた売掛金をさらに譲渡する「再ファクタリング」の場合には、譲渡対価の5%を分母に含めるなど、別の計算ルールが適用されることが国税庁の質疑応答事例で示されています。
一般の中小企業で、自社売掛金のファクタリングのみを行っている場合には、「課税売上割合には基本的に影響しない」と押さえておけば十分なケースが多いですが、取扱高が増えたり、他社債権を譲り受けるスキームを利用する場合には、個別検討が必要です。
- 課税売上割合=課税売上高÷総売上高(国税庁タックスアンサー参照)
- 有価証券・金銭債権の譲渡は原則「対価の5%」を分母に算入
- 自社の売上から生じた売掛金のファクタリングは、原則として分母・分子とも算入しない取扱い
- 再ファクタリングなど、他社から譲り受けた債権を譲渡する場合は別ルールがあるため要確認
非課税取引が多い会社の注意点
賃貸不動産収入や金融収益など、非課税取引が多い会社では、課税売上割合が下がりやすく、仕入税額控除の按分計算に影響が出ます。
課税売上割合が95%以上であれば、原則として課税仕入に係る消費税の全額を控除できますが、95%未満になると、非課税売上に対応する部分の仕入税額は控除できません。 このため、非課税取引の増減は「納める消費税の金額」に直結します。
ファクタリング自体は金銭債権の譲渡であり、非課税取引に当たります。ただし前述のとおり、自社の売上から発生した売掛金の譲渡については、課税売上割合の分母からも原則除外される取扱いがあるため、「非課税売上が増えた=課税売上割合が下がる」とは限りません。
問題になりやすいのは、売掛金のファクタリングに加え、有価証券・金銭債権の売買を繰り返す金融性の高い取引を多く行う会社や、本業とは別に土地・建物の売却(非課税または不課税)を行った場合などです。
中小企業にとっては、「自社の非課税取引はどの程度の規模か」「課税売上割合が95%を下回る可能性があるか」を早めに把握しておくことが重要です。
非課税取引が多くなりそうな年度には、個別対応方式か一括比例配分方式を採用するか、あるいは簡易課税制度を選択するかなど、消費税の計算方法そのものを見直す必要が出てくることもあります。
- 課税売上割合(95%ルール)を毎期試算し、仕入税額控除への影響を確認する
- 自社売掛金のファクタリングは課税売上割合への影響が限定的である一方、有価証券・金銭債権の売買や土地売却は影響が大きい
- 非課税取引が増える年度は、消費税の計算方法(個別対応・一括比例・簡易課税)を税理士と検討する
仕訳フローと勘定科目の選び方
中小企業の経理実務では、「売上→売掛金→ファクタリング→回収」という一連の流れを、会計ソフト上で分かりやすく管理できるようにしておくことが重要です。
基本的な流れは、①商品・サービスの販売時に「売掛金/売上・仮受消費税」を計上、②ファクタリング利用時に「預金・ファクタリング手数料(非課税)/売掛金」、③登記費用や司法書士報酬が発生した場合に「租税公課(登録免許税は不課税)」「支払手数料(司法書士報酬は課税仕入)」などで計上する、という形になります。
勘定科目は会社ごとに異なりますが、ファクタリング特有の論点を整理しやすくするために、少なくとも次のような区分を設けておくと便利です。
- ファクタリング手数料(割引料などの非課税部分)
- ファクタリング事務手数料・システム利用料(課税部分)
- 保証料(保証型ファクタリングの場合の非課税部分)
- 租税公課(登録免許税・印紙税など不課税部分)
- 支払手数料または専門家報酬(司法書士報酬など課税部分)
会計ソフトの税区分では、「非課税(有価証券等・金銭債権の譲渡)」「非課税(家賃等)」「課税仕入(10%)」など複数の非課税・課税区分が用意されていることが多く、ファクタリング手数料は「非課税(有価証券等)」グループに、事務手数料や司法書士報酬は「課税仕入」に設定するのが一般的です。
誤ってファクタリング手数料を「課税仕入」で入力してしまうと、仕入税額控除を過大に計上してしまうおそれがあるため、初期設定時に税理士と相談しておくと安心です。
- 「割引料(買取手数料)」と「事務手数料・報酬」を別勘定に分ける
- ファクタリング手数料は「非課税(有価証券・金銭債権)」の税区分を使用する
- 登録免許税・印紙税は租税公課等で不課税処理、司法書士報酬は課税仕入処理とする
- 会計ソフトの税区分は、初期に税理士と相談して設定し、運用ルールを社内で共有する
税理士へ相談するときの準備事項
ファクタリングの消費税・印紙税・会計処理は、金額やスキームによって判断が分かれる論点を含んでいます。迷った場合は税理士に相談するのが安心ですが、その際に「どの情報を持っていくか」で回答のスピードと精度が大きく変わります。
最低限準備しておきたいのは、①ファクタリング契約書(基本契約書・個別契約書)、②見積書・請求書・入金明細、③売掛金の内訳(売掛先・金額・支払サイト)、④ファクタリング利用実績の一覧(取引日・金額・手数料・スキーム)です。
加えて、課税売上割合に関する検討が必要かどうかを判断してもらうために、課税売上・非課税売上の金額、他の非課税取引(家賃・利息など)の有無もまとめておくとよいでしょう。
金銭債権や有価証券の譲渡が多い会社では、対価の5%を分母に含める特例や、自社売掛金の譲渡を分母・分子ともに含めない取扱いなど、個別の判断が必要になるケースがあるためです。
相談時には、「どのような意図でファクタリングを使っているか(スポットなのか継続なのか)」「今後も利用が増えそうか」「他の資金調達手段との組み合わせを検討しているか」といった背景情報も共有しておくと、単なる税務処理だけでなく、資金繰り全体を見据えたアドバイスを受けやすくなります。
- ファクタリング契約書・見積書・請求書・入金明細(費用内訳が分かるもの)
- 売掛金の内訳(売掛先・金額・支払サイト)とファクタリング利用一覧
- 課税売上・非課税売上・有価証券・金銭債権の譲渡額など、課税売上割合の判断材料
- ファクタリング利用の目的や今後の利用見込み(スポットか継続か)
トラブルを防ぐチェックポイント

ファクタリングは、資金繰り改善に役立つ一方で、「手数料の消費税区分」「登記費用・専門家報酬の扱い」「印紙税」など、税務処理を誤りやすいポイントがいくつかあります。
特に注意したいのは、①本来は非課税である割引料(ファクタリング手数料)に消費税を上乗せして請求している例、②見積書・請求書で課税/非課税の区分があいまいな例、③税務調査で確認されやすい印紙税や仕入税額控除の誤り、④実務上の“なんとなく”の処理がそのまま続いているケースです。
国税庁のタックスアンサーや質疑応答事例では、売掛金など金銭債権の譲渡およびその割引料は非課税である一方、登記を依頼した司法書士の報酬や事務手数料などは課税取引であることが示されています。
こうした線引きを踏まえ、ファクタリングに関する文書一式を「消費税」「印紙税」「登録免許税」の3つの観点からチェックしておくことが、トラブルの未然防止につながります。
| 確認テーマ | 主な論点 |
|---|---|
| 消費税 | 割引料(非課税)と事務手数料・報酬(課税)の区分 |
| 印紙税 | 債権譲渡契約書が第15号文書に該当し、適切な印紙が貼付されているか |
| 登録免許税 | 登録免許税(不課税)と司法書士報酬(課税)が区分されているか |
手数料に消費税を上乗せする例
ファクタリングの割引料(買取手数料)は、売掛金など金銭債権の譲渡に係る対価として、消費税法上「非課税取引」に区分されます。
国税庁の質疑応答事例では、金銭債権を割引購入する際に徴収する割引料・保証料・手数料について、「金銭債権の譲受対価」であり非課税売上になると明記されています。
にもかかわらず、実務上は「手数料◯円+消費税◯円」と、割引料部分に10%の消費税を一律で上乗せして請求しているケースも見受けられます。
このような請求書が届いた場合、利用者側がそのまま「課税仕入」として入力し、仕入税額控除を行うと、本来は非課税である割引料部分まで消費税の控除をしてしまうおそれがあります。
制度上、非課税取引については仕入税額控除の対象とならないため、税務調査で指摘される可能性がある論点です。
一方、ファクタリング会社側が「割引料」と「事務手数料」等をまとめて「手数料」と表示し、その全体に消費税をかけているケースもあります。
この場合でも、本来は割引料部分のみ非課税、事務手数料などサービス部分のみ課税が原則ですから、可能であれば明細を分けてもらい、どの部分が非課税でどの部分が課税なのかを確認することが望ましいといえます。
- 割引料(買取手数料)は金銭債権の譲渡対価であり非課税が原則
- 「手数料+消費税」となっていても、内容に応じて非課税/課税を区分する必要がある
- 請求書に疑問がある場合は、ファクタリング会社や税理士に内容の内訳を確認する
見積書・請求書の税区分の確認
ファクタリングに関する見積書・請求書では、「どの金額が非課税で、どの金額が課税なのか」が一目で分かるようになっているかが重要です。
割引料や保証料は非課税取引であり、事務手数料・審査料・システム利用料などは課税取引です。
国税庁の解説でも、金銭債権の譲渡差額は非課税である一方で、別途提供される役務については課税取引とされることが示されています。
実務上は、請求書に次のような明細があるかどうかを確認します。
- 割引料(ファクタリング手数料)◯円 【税区分:非課税】
- 事務手数料◯円 【税区分:課税・10%】
- システム利用料◯円 【税区分:課税・10%】
- 登録免許税立替分◯円 【税区分:不課税】
- 司法書士報酬立替分◯円 【税区分:課税・10%】
もし、請求書上で税区分がまとめて「課税10%」になっている場合、会計ソフトへの入力時に割引料分まで課税仕入として登録してしまうリスクがあります。
このようなときは、ファクタリング会社から内訳明細を取り寄せる、契約書の費用条項を確認するなどして、経理処理の根拠となる資料をそろえておくと安心です。
インボイス制度開始後は、課税取引について適格請求書の要件を満たしているかどうかも併せてチェックする必要があります。
- 割引料・保証料と、事務手数料・システム利用料が明細上で区分されているか
- 登録免許税や印紙税など税金立替分が、課税取引と混在していないか
- 課税部分について、適格請求書の要件(税率ごとの税込価額・税額の記載など)を満たしているか
税務調査で見られやすいポイント
税務調査では、ファクタリング特有の論点として、①割引料を課税仕入として処理していないか(仕入税額控除の過大計上)、②債権譲渡契約書の印紙税の貼付漏れがないか、③登録免許税と司法書士報酬の区分が適切か、などが確認されることがあります。
国税庁が公表している印紙税の手引きやタックスアンサーでは、第15号文書(債権譲渡契約書)の印紙税額や過怠税の取扱いが示されており、貼り忘れは調査で指摘されやすい項目です。
また、消費税については、金銭債権の譲渡に係る取引を非課税とした上で、課税売上割合の計算からどのように除外しているか、有価証券・金銭債権の譲渡対価の5%を分母に含める特例を必要に応じて適用しているか、といった点がチェックされる可能性があります。
ファクタリングの利用件数が多い会社では、税務調査前に「契約書」「請求書」「登記関連資料」「会計ソフトの仕訳・税区分」を一通り確認し、割引料を課税として処理していないか、印紙税や登録免許税が適切に計上されているかをセルフチェックしておくと、指摘リスクの低減につながります。
- 割引料(ファクタリング手数料)を誤って課税仕入で処理していないか
- 債権譲渡契約書への印紙貼付と印紙税の計上が適切か(第15号文書・200円)
- 登録免許税と司法書士報酬を区分し、消費税区分を誤っていないか
- 課税売上割合の計算において、金銭債権の譲渡を適切に扱っているか
実務で多い勘違いと見直し方法
ファクタリングに関する実務で多い勘違いは、「ファクタリング手数料も他の手数料と同じように課税」と思い込んでしまうことです。
また、債権譲渡契約書を一般の「金銭消費貸借契約書」や「継続的取引基本契約書」と同じ感覚で扱い、印紙税の号数・税額を誤って判断してしまうケースもあります。
国税庁の公表資料では、金銭債権の譲渡や第15号文書の取扱いが明確に示されているため、ファクタリングを導入したタイミングで一度整理しておくことが望ましいといえます。
見直しの第一歩は、「最近1〜2年分のファクタリング関連仕訳と証憑を抜き出して一覧にすること」です。
具体的には、①ファクタリング手数料の勘定科目・税区分、②事務手数料やシステム利用料の税区分、③登録免許税・印紙税の計上状況、④司法書士報酬の処理状況をチェックします。
そのうえで、国税庁のタックスアンサーや質疑応答事例と照らし合わせ、「非課税にすべきものを課税にしていないか」「不課税にすべきものを課税/非課税として処理していないか」を確認します。
必要に応じて、過年度分の修正申告や更正の請求の要否を税理士に相談することになりますが、まずは「どこが誤っていそうか」「金額的にどの程度の影響がありそうか」を社内で整理しておくと、相談もスムーズです。
特に、今後もファクタリングの利用が増える見込みがある会社では、このタイミングで仕訳ルールや会計ソフトの税区分設定を見直しておくことが、将来のトラブル防止につながります。
- 「ファクタリング手数料=課税」と思い込まず、割引料は非課税、事務手数料等は課税と切り分ける
- 債権譲渡契約書の印紙税区分(第15号文書・200円)を再確認する
- 過去1〜2年分の仕訳・証憑を一覧化し、税区分と税目(消費税・印紙税・登録免許税)を棚卸しする
- 誤りや不明点があれば、影響額を概算したうえで税理士に相談する
まとめ
ファクタリング手数料は、売掛金という「金銭債権の譲渡」に対する対価であるため、原則として消費税の非課税取引として扱われます。
一方で、債権譲渡登記に伴う司法書士報酬や事務手数料、システム利用料などは課税対象になる場合があり、費用ごとに区分して仕訳することが重要です。
この記事では、買取型・保証型それぞれの仕訳例、インボイス制度とのかかわり、契約書・請求書の税区分チェックのポイントを整理しました。
今後は、見積書や契約書を確認する際に「どの費用が非課税で、どの費用が課税か」を自社で整理し、必要に応じて税理士へ早めに相談することで、税務リスクと手戻りを減らすことができます。