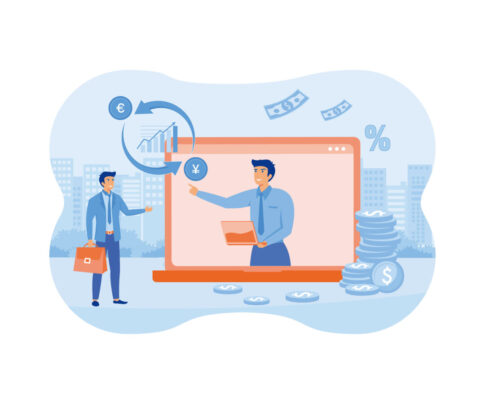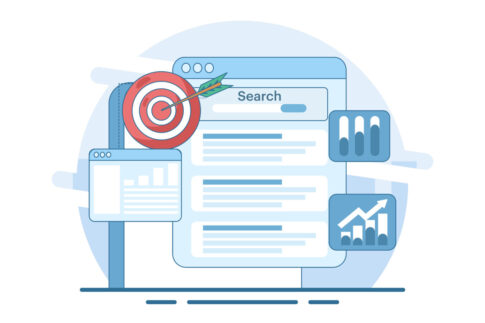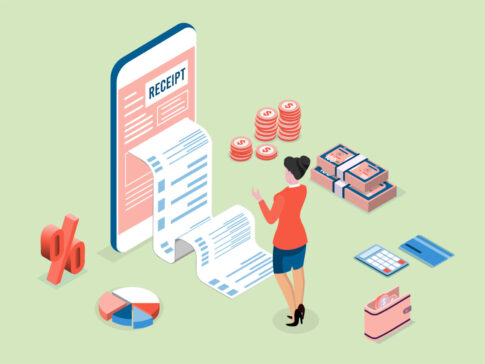ファクタリングを利用する際、「他社利用は共有されるのか」「銀行に知られて与信に響かないか」と不安に感じる企業は少なくありません。実際には、ファクタリング会社同士で共有されやすい情報、信用情報機関に登録される情報、債権譲渡登記で第三者に見える情報など、性質の異なる「情報共有」が存在します。
この記事では、その仕組みとリスク、二重譲渡防止や社内管理のポイント、銀行融資NG企業が取るべき情報開示の戦略までを整理し、安全にファクタリングを活用するための考え方を解説します。
ファクタリングと情報共有の基本

ファクタリングを検討する場面では、「この情報はどこまで共有されるのか」「銀行や他社に知られてしまうのか」という不安がよく出てきます。
ここで押さえたいのは、情報共有と信用情報は似て非なるものだという点です。
ファクタリングの審査では、申込企業の決算書や試算表、売掛先の名称・取引内容、過去の支払状況など、多くの情報が提出されますが、そのすべてが信用情報機関に登録されるわけではありません。
一方、同じグループ内の金融機関・関連会社、あるいは債権譲渡登記や支払遅延などを通じて、業界内で一定の情報が共有されやすい領域も存在します。
まずは、「誰が」「どの範囲で」「何のために」情報を使うのかを整理することが重要です。
外部との情報共有だけでなく、社内でのファクタリングに関する情報共有ルール(誰がどの売掛金を、どの会社に出したか、上限はいくらか)を整備していないと、二重譲渡や説明の食い違いを招き、結果として信用低下につながるリスクもあります。
| 情報の種類 | 主な利用・共有のイメージ |
|---|---|
| 審査用資料 | 決算書・試算表・売掛先一覧など。基本的には申込先のファクタリング会社が審査の範囲で利用。 |
| 信用情報 | 金融機関との借入・延滞等が信用情報機関に登録される領域。ファクタリング利用そのものは原則別枠。 |
| 公的情報 | 債権譲渡登記や訴訟・差押え情報など、第三者も確認し得る情報。 |
情報共有と信用情報の違い
「情報共有」と聞くと、まず思い浮かぶのが信用情報機関に登録される情報かもしれませんが、実務上はもっと広い概念です。
信用情報機関の情報とは、クレジット・ローン・カードなどの契約内容や返済状況が、定められたルールに基づいて登録・利用される仕組みを指します。
一方で、ファクタリングに関する「情報共有」は、個々のファクタリング会社の社内情報、グループ会社間の情報、業界団体や信用情報機関で扱われる法人向け情報、公示される登記情報など、複数のレイヤーに分かれています。
ポイントは、「信用情報」と「業界内の評判・取引履歴」は別物だということです。
たとえば、銀行借入の延滞は信用情報として記録される可能性がありますが、「特定のファクタリング会社で過去にトラブルがあった」という情報は、主にその会社の社内情報や契約記録の範囲にとどまることが多く、制度としての信用情報とは扱いが異なります。
逆に、債権譲渡登記や訴訟情報など、誰でも確認可能な公的情報は、結果として「取引先選定の参考情報」として広く見られることになります。
- 信用情報=信用情報機関に登録されるローン・返済情報などの制度的な情報
- 情報共有=ファクタリング会社の社内・グループ内・業界内で扱われる取引情報全般
- 登記・訴訟などの公的情報は、第三者も確認できる「開かれた情報」として扱われる
ファクタリング会社と金融機関の連携有無
「ファクタリングを使うと銀行に知られてしまうのか」という疑問はよくありますが、ここでも情報の流れを整理することが大切です。
まず、銀行グループの一員としてファクタリングサービスを提供している会社の場合、同じグループ内で一定の情報連携が行われることがあります。
これは、反社会的勢力の排除やマネーロンダリング対策、グループ全体のリスク管理といった観点から、金融業界全体で進められている枠組みです。
一方、独立系のファクタリング会社は、銀行とは資本関係のない別法人であることも多く、「利用した事実が自動的にすべての銀行へ共有される」といった仕組みがあるわけではありません。
ただし、銀行側が融資審査の過程で財務諸表・資金繰り表の提出を求めた際に、ファクタリング利用によるキャッシュフローの動きや債権譲渡登記の有無などから、事実上ファクタリング利用を把握できるケースはあります。
- 銀行グループ系ファクタリングでは、一定の情報がグループ内で共有される前提を持つ
- 独立系でも、決算書・資金繰り表・登記情報から銀行に利用が推測される場合がある
- 「どうせ知られるから隠す」のではなく、必要に応じて自ら経緯を説明できるよう整理しておく
情報共有が問題になる典型ケース
ファクタリングにおける情報共有が具体的な問題として表面化するのは、主に次のようなケースです。
- 同じ売掛金を複数のファクタリング会社に提示してしまう二重譲渡の疑いが生じたとき
- 過去に支払遅延や契約違反があり、その履歴が社内・グループ内で共有されているとき
- 債権譲渡登記や訴訟・差押えにより、取引先や金融機関が問題を認識したとき
二重譲渡は、同じ売掛債権を複数の相手に譲渡してしまう行為であり、民法上も重大なトラブルの原因になります。
このリスクを避けるため、ファクタリング会社は契約時に他社利用の有無を確認したり、債権譲渡登記や取引先への通知を通じて、優先順位や真実の譲受人を明らかにしようとします。
また、支払遅延や不誠実な対応があった場合、その情報は少なくともその会社の内部では共有され、その後の審査に影響することが一般的です。
- 売掛金を複数の先に出し、「他社での利用履歴」を隠して申し込む
- 支払遅延や契約違反が繰り返され、社内・グループ内で「要注意先」として扱われる
- 登記・訴訟情報から、取引先や銀行に資金繰り悪化が伝わってしまう
自社内での情報共有ルールの重要性
「情報共有」というと外部とのやり取りに目が行きがちですが、実務上もっとも重要なのは自社内での情報共有ルールです。
営業部門が個別にファクタリングを進めて経理に十分な情報が伝わっていなかったり、複数の担当者が別々のファクタリング会社に同じ債権を提示してしまったりすると、結果として二重譲渡や説明の食い違いを招き、信用低下につながりかねません。
社内ルールとしては、少なくとも以下のような仕組みを整えておくと安心です。
- ファクタリング利用の可否判断を行う責任者(役員・財務担当)の明確化
- 「どの売掛先・どの請求書を」「どの会社に」「いくらで」出したかを記録する台帳の整備
- 取引先・銀行に対する説明方針(必要に応じて開示する範囲)の社内合意
- ファクタリング利用は必ず財務・経理を通すフローにし、現場の個別判断にしない
- 売掛金ごとのファクタリング利用状況を一覧化し、二重譲渡を防止する
- 銀行・主要取引先に対してどこまで説明するか、方針を事前に決めておく
このように、外部との情報共有の仕組みを理解すると同時に、自社内の管理体制を整えることで、「知られたら困る」という発想から「知られても説明できる状態をつくる」という前向きな情報戦略へと切り替えていくことができます。
ファクタリング会社間の情報共有実態

「他社で使っていることはバレるのか」「一度トラブルを起こすと業界全体に共有されるのか」は、多くの利用企業が気にするポイントです。
結論から言うと、指定信用情報機関(CIC・JICC・KSC)のように、すべてのファクタリング会社が一括して情報を登録・閲覧する公式な枠組みはありません。
一方で、債権譲渡登記や業界団体・任意の信用情報サービス(日本ファクタリング信用情報機関など)を通じて、「特定の情報」は共有される実務があります。
また、各社内部での「要注意先リスト」や、同一グループ内での情報連携、債権譲渡登記の閲覧、明らかな二重譲渡・詐欺案件に関する情報交換など、私的・限定的な情報共有は少なからず行われています。
そのため、「全く何も共有されていない」という前提で安易な二重利用や偽装を行うことは極めて危険です。
| 情報の経路 | 主な内容 |
|---|---|
| 公式信用情報 | CIC・JICC・KSCなど。ファクタリング会社は原則加盟せず、直接の記録は行われない。 |
| 登記・公的情報 | 債権譲渡登記・訴訟・差押え等。申請・閲覧により第三者も確認可能。 |
| 任意の業界情報 | 日本ファクタリング信用情報機関など、加盟社間での悪質利用情報の共有。 |
| 社内・グループ内 | 各社の社内データベース、グループ金融機関との連携など。 |
他社利用がバレるケースとバレないケース
「他社でもファクタリングを使っていることは基本的に分からない」と説明されることがありますが、実務ではケースバイケースです。
一般に、同じ売掛金を別のファクタリング会社に出していない、支払い遅延やトラブルを起こしていない、といった通常の利用であれば、「A社で使っていることがB社に自動的に伝わる」仕組みはありません。
一方で、次のようなケースでは他社利用が判明しやすくなります。
- 同じ売掛金について、すでに他社で債権譲渡登記が行われている(審査時の登記チェックで判明)
- 売掛先から、「他社からも同じ請求について通知が来ている」と情報が入る
- 過去にトラブルを起こし、日本ファクタリング信用情報機関などに登録されている
複数社見積もりや、売掛先や対象債権を変えたうえでの複数社利用自体は珍しいことではありません。
ただし、「同一債権の二重利用」や「未払いを抱えたまま別会社へ新規申込み」は、登記やヒアリングの段階で発覚するリスクが高く、不誠実な利用と見なされる可能性があります。
- 未払い・トラブルを隠したまま別会社へ申し込む
- 同じ売掛債権を複数社に持ち込む(二重譲渡)
- 売掛先や登記情報から、複数社利用が一目で分かる状態になっている
債権譲渡登記・二重譲渡と情報把握
債権譲渡登記は、売掛債権が誰に譲渡されたかを法務局に記録し、第三者対抗要件(第三者に対して優先順位を主張するための要件)を備えるための制度です。
ファクタリング会社が債権譲渡登記を行うと、その情報は登記簿として法務局に保管され、一定の手続を踏めば誰でも閲覧することができます。
この仕組みは、二重譲渡の防止・発見に大きな役割を果たします。別のファクタリング会社が同じ売掛債権を対象に取引を検討する場合、登記簿を確認すれば、すでに他社の債権譲渡登記が存在するかどうかを知ることができます。
もし同一債権に複数の登記があると判明すれば、二重譲渡の疑いが強くなり、契約前に審査がストップする、または法的トラブルに発展する可能性があります。
- 登記は「誰でも閲覧できる」公的情報であり、他社が確認することもあり得る
- 同じ売掛債権に複数の登記があれば、二重譲渡が即座に疑われる
- 自社側でも、どの債権に登記が入っているかを把握し、二重利用を防ぐ管理が必要
日本ファクタリング信用情報機関の役割
日本ファクタリング信用情報機関(JFIC)は、クレジットカード等を扱う指定信用情報機関とは異なり、ファクタリング会社向けの任意の信用情報サービスです。
公式サイトによれば、JFICはファクタリング会社が審査を行う際に、悪質な利用者の情報を共有し、被害を未然に防ぐことを目的とした情報機関とされています。
一般に登録対象となるのは、例えば次のようなケースとされています。
- 支払期日になっても入金がなく、連絡も取れない
- 通帳や契約書類の偽造・改ざんが判明した
- 架空・水増しの売掛債権を持ち込んだ
- 同一債権の二重譲渡が発覚した
- 計画倒産を疑わせる大規模な詐欺的スキームがあった
加盟しているファクタリング会社は、審査時にこの情報を照会することで、過去に重大な不正やトラブルを起こした利用者を早い段階で見分けることができます。
一方で、すべてのファクタリング会社が加盟しているわけではなく、あくまで任意の仕組みである点も押さえておく必要があります。
- 重大な不正行為があれば、JFICに登録され、加盟各社の審査で共有され得る
- 登録先のファクタリング会社だけでなく、他の加盟社の審査にも影響する
- 適正な利用であれば、JFICへの登録・照会が問題になることは基本的にない
業界内で共有されやすい「ブラック情報」
公式な信用情報機関とは別に、ファクタリング業界には「ブラック情報」と呼ばれる、悪質事案に関する情報が共有されやすい文化があります。
これは、法律で定められた公的な仕組みというより、実務上の自衛手段として、各社や専門家(弁護士・コンサル等)が情報交換を行うケースがある、というイメージに近いものです。
共有されやすい情報としては、
- 明らかな詐欺・二重譲渡・架空債権など刑事事件に発展した事案
- 複数の会社で同様の問題行動(偽造・虚偽申告等)を繰り返している利用者
- 特定の業者が関与する悪質スキーム(ブローカー・仲介業者など)
が典型です。これらは、司法判断(判決・逮捕報道)や業界団体・勉強会、専門家同士の情報交換を通じて共有されることがあり、結果として該当する企業・人物は業界内で強い警戒対象となります。
- 二重譲渡や架空債権などの不正行為は、一社だけでなく業界全体から敬遠される
- 悪質な仲介業者を利用すると、自社も同列に見なされるリスクがある
- 長期的に資金調達の選択肢を残すには、短期的な違反・ごまかしを絶対に行わないことが重要
このように、公式な信用情報機関とは別に、「登記・公的情報」「任意の信用情報機関」「業界内の悪質情報」という複数のレイヤーで情報共有が存在します。
適正な範囲で利用し、二重譲渡や虚偽申告といった不正を避けることが、結果的に自社の与信と資金調達力を守る近道になります。
信用情報機関とファクタリングの関係
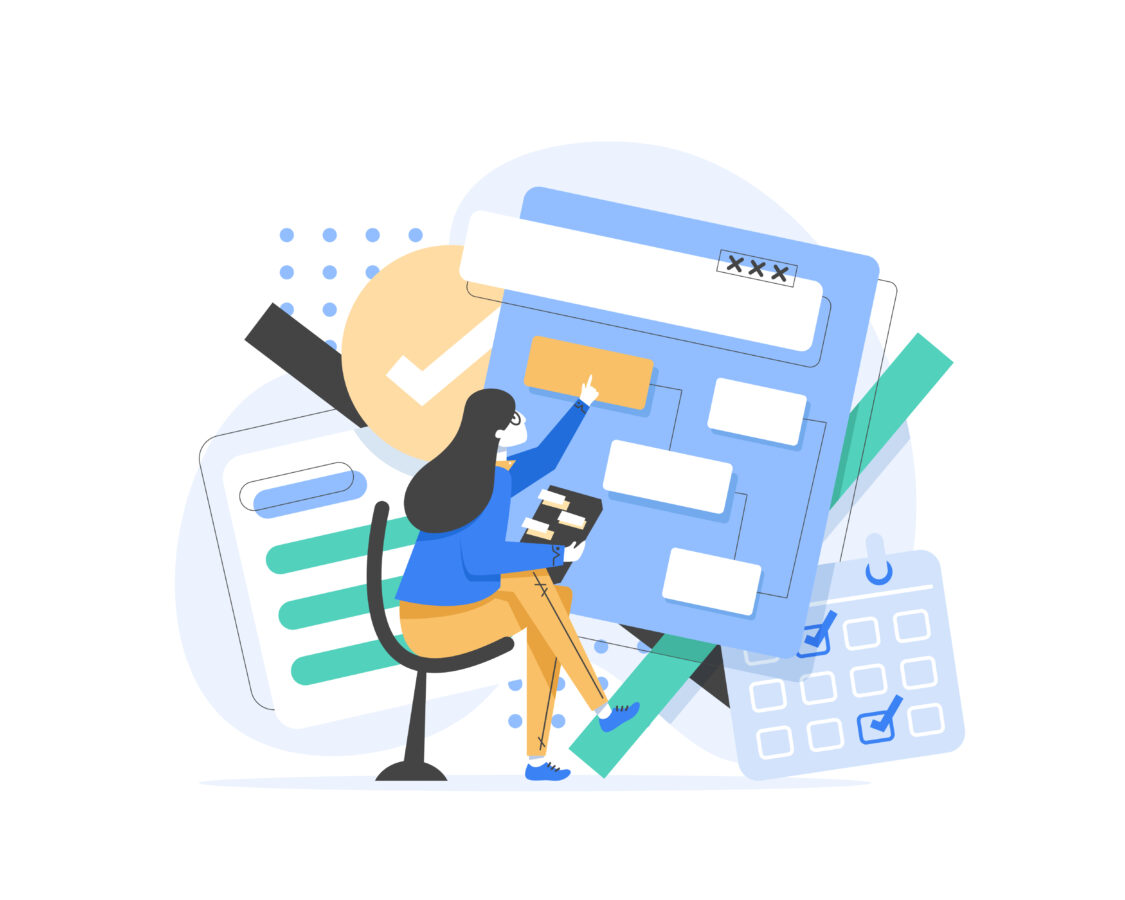
ファクタリングを利用する際、「CIC や JICC に載るのか」「銀行の与信にどう響くのか」という不安は非常に多いです。
ただし、ここではまず、指定信用情報機関(CIC・JICC・KSC)が扱う情報と、ファクタリングの情報との位置づけを切り分けて整理する必要があります。
指定信用情報機関は、主としてクレジットカード・個人向けローン・カードローン・住宅ローンなどの「個人信用情報」を扱う仕組みであり、法人や事業性融資については、全国銀行協会のシステムなど別枠で管理される領域もあります。
一方、ファクタリングは「売掛債権の譲渡」であり、法律上は金銭消費貸借(ローン)とは異なる取引形態です。
実務では、ファクタリング利用そのものが自動的に信用情報機関へ登録されるルールは一般的ではありません。
ただし、ファクタリング利用企業が同時に行っている銀行借入・保証付き融資・リスケジュールなどの情報は金融機関経由で信用情報に反映されるため、「ファクタリング+他の借入・延滞」の組み合わせで、トータルの信用力に影響する構図をイメージしておくことが重要です。
| 情報の種類 | 主な管理主体・扱われ方 |
|---|---|
| 個人信用情報 | CIC・JICC・KSC が管理。クレジットカード・個人ローン等の契約・返済状況。 |
| 事業性融資情報 | 銀行内部システム・全国銀行協会システム等で管理される法人向け情報。 |
| ファクタリング取引 | 各社の社内情報・業界系情報機関・登記情報などで個別に扱われることが多い。 |
CIC・JICC・KSCに登録される情報
CIC(指定信用情報機関)、JICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、いずれも個人のクレジット・ローン等に関する情報を登録する仕組みです。
登録される代表的な情報としては、クレジットカード契約、個人向けカードローン、住宅ローン、フリーローン、分割払い(割賦販売)などの契約内容と返済状況(入金状況、延滞、代位弁済、債務整理など)が挙げられます。
ここでのポイントは、
- 登録の主体は「加盟している金融機関・クレジット会社等」であること
- 登録されるのは主に「個人または個人事業主としての取引情報」であること
- 法人そのもののファクタリング取引は、原則としてこれらの個人信用情報とは別枠で扱われること
という点です。
法人代表者が個人保証を付けて銀行借入をしている場合、その借入の延滞や代位弁済等は、代表者個人の信用情報として CIC・JICC・KSC に登録される可能性がありますが、法人の売掛債権をファクタリングしたという事実だけで、直ちに個人信用情報が更新されるわけではありません。
- クレジットカード・カードローン・個人ローンの契約・返済状況
- 個人保証付き事業性融資の延滞・代位弁済等(代表者個人の情報として)
- 任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理情報
ファクタリング利用が信用情報に与える影響
ファクタリング取引そのものは、売掛債権の譲渡であり、「金銭の貸付契約」ではないため、指定信用情報機関の登録対象とは性質が異なります。
このため、「ファクタリングを利用した」という事実だけで、CIC・JICC・KSC の記録が増えるという仕組みは通常想定されていません。
しかし、信用情報にまったく無関係かといえばそうではありません。たとえば、
- ファクタリングを多用している結果、銀行借入の返済が遅延し、そちらが延滞情報として信用情報に登録される
- ファクタリングでしのぎつつも、最終的に法的整理(民事再生・破産)となり、その情報が代表者個人の信用情報に残る
- 個人保証付きの事業性融資で代位弁済が発生し、その原因の一つにファクタリング手数料負担の増加が含まれている
といった形で、間接的に信用情報へ影響することがあります。
- ファクタリングの多用により、他の借入の返済や税金・社保の支払いが遅れ始める
- 資金繰り悪化が進み、代表者個人を含めた債務整理に踏み切る
- 結果として、銀行・ノンバンクの借入に関する延滞・代位弁済情報が信用情報機関に記録される
このため、信用情報への直接登録有無だけに注目するのではなく、「トータルで見た資金繰りと返済能力」を踏まえた上で、ファクタリングの利用頻度・金額をコントロールすることが重要です。
延滞・代位弁済と信用情報のリスク
信用情報上の大きなマイナス要因になるのが、延滞・代位弁済・債務整理です。
延滞(61日以上や 3 か月以上など基準は機関・商品による)が発生すると、信用情報に「異動」として登録され、その後一定期間(概ね 5 年程度)にわたり、他の金融機関の審査に影響を与えることがあります。
代位弁済(保証会社が金融機関に肩代わりして支払うこと)が発生した場合も、同様に信用情報に登録されます。
ファクタリングを多用する企業の場合、
- ファクタリング手数料負担で利益・キャッシュが圧迫される
- 結果として、銀行融資やリースの返済が遅れやすくなる
- 延滞や代位弁済が発生し、信用情報にマイナス情報が記録される
という流れに陥るリスクがあります。一度信用情報に延滞等が記録されると、今後の借換えや新規借入に大きな制約が生じるため、「ファクタリングで短期を埋める→他の返済が遅れる」という悪循環を避けることが極めて重要です。
- ファクタリング利用額と手数料総額を、月次で可視化し、返済能力の範囲内か確認する
- 銀行返済・税金・社会保険料など「絶対に遅らせたくない支払」を優先順位として明確化する
- 延滞の兆候が見えたら、早期に金融機関・専門家と相談し、リスケや再建策を検討する
銀行融資とファクタリング情報共有の実務
銀行融資とファクタリングの関係では、「銀行に隠すべきか・説明すべきか」が悩みになりがちです。
実務で重要なのは、「いずれ銀行は概ね把握している」という前提に立ち、むしろ自ら経緯と目的を説明できるようにしておくことです。
銀行側は、決算書・試算表・資金繰り表・預金口座の入出金などから、売掛金の増減やファクタリングによるキャッシュフローの動きをある程度読み取ることができます。
また、債権譲渡登記を行っている場合は、登記情報から売掛金の処分状況を確認される可能性もあります。
銀行との関係構築という観点では、
- 一時的な資金ギャップを埋めるためにファクタリングを活用したのか
- 構造的な赤字・債務超過を補うためにファクタリングを常用しているのか
- 今後、銀行融資・公的支援・コスト削減などを組み合わせた再建計画をどう描いているのか
を、数字とともに説明できるかどうかが重要です。「隠しておきたい情報」を無理に隠すよりも、「現状は厳しいが、こういう計画で立て直したい。
その間のブリッジとしてファクタリングをこう使っている」という説明の方が、銀行との対話ではプラスに働きやすくなります。
- 決算書・資金繰り表にファクタリング利用の影響を正しく反映させる
- ファクタリングを「常用資金源」ではなく「再建のための一時的手段」として位置づける
- 将来的にファクタリング依存度を下げる数値計画(売上・粗利・固定費・借入構成)を示す
このように、信用情報機関とファクタリングとの関係は直接的ではないものの、ファクタリングの使い方次第で、銀行融資や個人・法人の信用力に間接的な影響を与えます。
制度の枠組みと実務の動きを理解したうえで、「どの程度まで・どの期間使うか」を戦略的に設計することが、安全なファクタリング活用の前提となります。
情報共有を前提にした安全な利用設計

ファクタリングは、本来「売掛金を使った資金調達スキーム」にすぎませんが、情報共有の観点を無視して利用すると、二重譲渡や不正利用の疑いを招き、結果として与信悪化や取引停止につながるおそれがあります。
特に、複数のファクタリング会社と取引する企業や、銀行融資NGでファクタリング依存度が高い企業では、「どの売掛金を・どの会社に・どの条件で出しているか」を社内で一元管理し、外部にどう説明するかまで含めて設計しておくことが重要です。
安全な利用設計のポイントは、①二重譲渡防止のための債権管理、②複数社見積もり・乗り換えのルール化、③反社会的勢力排除や不正検知といったコンプライアンス視点、④社内情報共有フローと承認プロセスの整備、の4点に整理できます。
これらを前提としてファクタリングを位置づけておけば、「知られたら困る取引」から「説明できる資金調達」に変えやすくなります。
| 観点 | 設計時に確認したいポイント |
|---|---|
| 債権管理 | 債権ごとの利用状況(対象会社・金額・登記有無)を台帳化しているか |
| 複数社利用 | 見積もり・乗り換え時の社内ルールや情報開示方針が決まっているか |
| コンプライアンス | 反社チェック・不正検知の体制があり、危険なスキームを排除できるか |
| ガバナンス | 誰が最終承認し、どの部署が記録・モニタリングを担うかが明確か |
二重譲渡防止と社内債権管理のポイント
二重譲渡は、同じ売掛債権を複数の相手に譲渡してしまう行為で、ファクタリング実務で最も問題視されるリスクの一つです。
悪意がなくても、社内で債権管理がされておらず、営業がそれぞれ別の会社に同じ請求書を持ち込んでしまえば、結果として二重譲渡とみなされることがあります。
これを防ぐためには、売掛債権の「単純な売掛管理」と「ファクタリング利用管理」を分けて考え、後者を専用の台帳やシステムで管理する発想が必要です。
基本的には、
- 売掛先別・請求書別に「ファクタリング利用フラグ」を付ける
- 利用先(ファクタリング会社名)、利用額、利用日、登記有無を一覧化する
- 新たにファクタリングを検討する際は、この台帳を必ずチェックする
というステップを徹底します。小規模企業であればスプレッドシートでも始められますが、担当者が変わっても分かるよう、ファイルの保管場所・更新ルールまで明文化しておくと安全です。
- 「ファクタリング利用済み売掛金リスト」を最新状態で維持しているか
- 営業・経理・財務のいずれかだけで判断せず、必ず複数部署で確認しているか
- 債権譲渡登記を行った債権について、社内台帳に登記済みの印を付けているか
複数社見積もり・乗り換え時の注意点
適正な条件を把握するために、複数のファクタリング会社から見積もりを取ること自体はよく行われます。
ただし、このプロセスでも情報管理を誤ると、「あの会社は同じ債権をあちこちに出している」「未払いを抱えたまま別の会社へ申し込んでいる」といったマイナス評価につながりかねません。
安全に複数社見積もり・乗り換えを行うには、「見積もり段階で提供する情報」と「正式申込時に提供する情報」を段階的に分けることがポイントです。
実務上は、
- 見積もり段階では、売掛先の業種・規模・サイト・概算金額など、匿名化した情報で条件感を確認する
- 正式申込先を絞ったあとに、請求書・契約書・登記状況など詳細情報を開示する
- 既に他社で利用中の債権や未払いがある場合は、隠さず事実として説明する
といった運用が望ましいです。乗り換えを検討する場合も、「既存契約をどのタイミングで清算し、新しい会社でどの債権から始めるか」を、資金繰り表と契約条件(違約金・精算条件など)に基づいて検証しておく必要があります。
- 既存ファクタリングの未払いを隠して、新規会社に申し込む
- 同一の請求書を、一度に複数社へ正式申込する(二重譲渡リスク)
- 違約金や精算条件を確認せずに乗り換え、結果的に総コストが増えてしまう
反社チェック・不正利用と情報共有リスク
金融業界全体で、反社会的勢力の排除やマネーロンダリング防止(AML)、テロ資金供与対策(CFT)が強く求められており、ファクタリング会社も例外ではありません。
そのため、多くの会社が反社チェックや不正利用検知の仕組みを整備し、必要に応じてグループ内・業界内・専門機関と情報共有を行っています。
不正なスキームや反社関与が疑われる取引は、「自社だけの問題」ではなく、業界全体のリスクとして扱われることを意識する必要があります。
利用企業の立場からは、
- 反社チェックを嫌がらず、登記簿・本人確認資料・株主構成などの開示に協力する
- 売掛債権の取引実態(契約書・納品書・検収書等)を説明できる状態にしておく
- ブローカー・仲介業者を利用する場合、その業者の信頼性をきちんと確認する
ことが重要です。疑義のある案件や、明らかに高リスクのスキームに関わると、その情報が自社だけでなく代表者個人の信用にも影響するおそれがあります。
- 取引実態の乏しい売掛債権(架空・水増し)を持ち込む
- 反社チェックで質問された事項に虚偽の回答をする
- 出所不明の仲介業者を経由したスキームに安易に乗る
社内情報共有フローとガバナンス強化
最後に重要なのが、社内での情報共有フローとガバナンス(統制)の整備です。
ファクタリングに限らず、資金調達は経営判断と直結する行為であり、「誰が・どの範囲で判断し・どう記録するか」が決まっていないと、担当者依存や属人化が進みます。
結果として、二重譲渡や未報告の負債、銀行への説明不足など、情報管理の不備が一気に顕在化することになります。
社内フローとしては、
- 営業部門が資金ニーズを感じた時点で、必ず経理・財務に相談する
- ファクタリングの検討・選定は、財務責任者(または経営陣)を含めた場で決定する
- 決定した内容(対象債権・金額・会社名・登記有無)は、債権管理台帳と資金繰り表に反映する
- 定期的に取締役会等でファクタリング利用状況・依存度をモニタリングする
といったプロセスを明文化しておくと効果的です。
- ファクタリングは「経営会議の議題」とし、利用状況を定期報告する
- 債権管理台帳・資金繰り表・決算予測を連動させ、全社で同じ数字を共有する
- 社内規程や稟議ルールに「ファクタリング利用基準」「承認フロー」を明記する
このように、「情報共有される前提」で設計しておくことで、ファクタリング利用に伴うレピュテーションリスクを抑えつつ、外部からの与信評価にも耐えられる資金調達体制を構築しやすくなります。
銀行融資NG企業の情報戦略

銀行融資を断られた企業ほど、「できれば隠したい情報」と「むしろ開示した方が信頼につながる情報」の線引きが重要になります。
ファクタリング利用やリスケ履歴をすべて伏せようとすると、決算書や預金の動き、債権譲渡登記などから矛盾が生じ、かえって金融機関の不信感を招きかねません。
情報戦略として大切なのは、「隠す」ではなく「整理して説明する」方向に舵を切ることです。
なぜファクタリングが必要になったのか、その結果として資金繰りや債務構成はどう変わったのか、今後はどう減らしていく計画なのか——これらを数値とストーリーの両面で示すことで、「苦しいが、打ち手を考えている会社」という評価を受けやすくなります。
情報戦略を考えるうえでは、次の4つの視点で整理すると分かりやすくなります。
| 視点 | 情報戦略上のポイント |
|---|---|
| 過去 | なぜ銀行融資NGになったのか(赤字・債務超過・条件違反など)の事実整理 |
| 現在 | ファクタリングや他の資金調達を含めた「今」の資金繰り構造 |
| 未来 | 再建計画とキャッシュフロー改善のシナリオ、ファクタリング依存度の減少計画 |
| 体制 | 専門家や社内のガバナンス体制を含む、計画を実行できる仕組み |
ファクタリング履歴と金融機関への説明
金融機関への説明で悩みやすいのが、「ファクタリングをどこまで話すか」です。預金推移や売掛金の残高、債権譲渡登記などから、一定規模以上のファクタリングは概ね把握されると考えた方が現実的です。
そのうえで、「なぜ導入したのか」「どのような条件で使っているのか」「今後どう減らしていくのか」を整理して伝えることが情報戦略の軸になります。
説明の際は、感情論ではなく、次のような情報を組み合わせて提示すると説得力が増します。
- 導入理由:売掛金の増加・取引先のサイト延長・コロナや災害など一時的要因 など
- 利用状況:売掛金残高に対するファクタリング利用比率、月次手数料総額
- 改善策:高コスト案件の縮小、採算性の低い取引の見直し、粗利率改善策
- 出口戦略:◯年後までにファクタリング比率を◯%以下にする、銀行融資に戻す など
- 隠すのではなく、「一時的な資金ギャップを埋めるためにどう使ったか」を具体的に説明する
- 利用額・頻度・手数料を数値で示し、「どこまでが許容範囲か」を自社でも把握していると示す
- 将来の削減計画を、売上・粗利・固定費の改善策とセットで提示する
決算書・資金繰り表で見せるべき情報
情報戦略の中心は、決算書と資金繰り表です。ここにファクタリングを含む資金調達の実態を正しく反映させないと、金融機関から見ると「どこから資金が来ているのか分からない会社」になってしまいます。
決算書では、売掛金残高の推移・短期借入金・その他流動負債の構成、手数料の費用計上状況などから、ファクタリング依存度や収益圧迫の程度が読み取られます。
資金繰り表では、「売上→売掛金→ファクタリング入金→支出」というキャッシュフローの動きが見える形にすることが大切です。
具体的には、次のような情報を「見える化」しておくと、説明がしやすくなります。
- ファクタリングを利用した売掛金の金額と比率(売掛金全体に対する割合)
- ファクタリング手数料の年間合計と、営業利益に対する比率
- 月次の資金繰り表における、ファクタリング入金と将来の入金減少の関係
- ファクタリングを減らした場合のシミュレーション(利益・キャッシュへの影響)
- ファクタリングを「その他」に埋めず、現金・売掛金・手数料への影響を分かるようにする
- 単年度だけでなく、過去数期分の推移を示し、依存度の変化を説明できるようにする
- 将来予測の資金繰り表にも、ファクタリング利用前提と削減後の両方を記載し、比較を可能にする
専門家と連携した開示・情報整理の進め方
銀行融資NGの企業では、経営者が一人で情報整理と説明戦略を考えるのは負荷が大きくなりがちです。
そこで有効なのが、税理士・中小企業診断士・弁護士などとチームを組み、「どの情報をどの順番で開示するか」を一緒に設計する方法です。
税理士は決算・資金繰り・税金の観点から、中小企業診断士は事業戦略・再建計画の観点から、弁護士は契約リスクや法的整理の選択肢の観点から、それぞれ異なる視点で必要な情報を整理してくれます。
実務の進め方の一例としては、
- まず税理士と資金繰り表・決算の整理を行い、「現在地」を把握する
- 中小企業診断士等と再建計画を作成し、「どの事業を伸ばし、どこを縮小するか」を決める
- ファクタリング契約や他の債務の内容は、必要に応じて弁護士のチェックを受ける
- そのうえで、金融機関や取引先にどの範囲まで開示し、どう説明するかをチームで決める
- 単発相談で終わらせず、3〜6か月スパンの「伴走支援」として関わってもらう
- 良い情報だけでなく、延滞・赤字・債務超過など不都合な事実も隠さず共有する
- 金融機関向け説明資料(再建計画・資金繰り計画)を専門家と共同で作成する
情報共有を味方につける与信改善ステップ
最後に、「情報共有を恐れる」のではなく、「情報共有を味方につける」という発想が重要です。
金融機関は、「何も問題がない会社」よりも、「問題はあるが、事実を開示し、改善に向けた具体的な行動を取っている会社」を支援しやすいと言われることがあります。
ファクタリング利用も、その文脈の中で位置づけ直すことが、与信改善の第一歩になります。
与信改善に向けたステップのイメージは、次のように整理できます。
- 第1段階:現状の問題(赤字・債務超過・ファクタリング依存)を正確に開示する
- 第2段階:短期(1年以内)で実行する改善策(コスト削減・不採算案件の縮小)を具体化する
- 第3段階:中期(3年程度)の目標値(自己資本比率・借入構成・ファクタリング比率など)を置く
- 第4段階:四半期・半期ごとに進捗を金融機関や専門家と共有し、軌道修正を行う
- 「知られたら困る」ではなく、「知ってもらったうえで一緒に再建を考える」スタンスを持つ
- ファクタリング利用履歴も、再建の過程でどう減らしていくかを示す材料に変える
- 金融機関・専門家との面談では、数字・事実・行動計画の3点セットを常に持参する
このように、銀行融資NGの状況でも、情報を整理・開示しながら再建に取り組むことで、「情報共有=リスク」から「情報共有=信頼構築の手段」へと意味を変えていくことができます。
まとめ
ファクタリングの情報共有といっても、債権譲渡登記による「見える情報」、業界団体や信用情報機関で扱われる情報、銀行との取引の中で問われる情報など、範囲と性質はさまざまです。
重要なのは、「何を隠すか」ではなく、「何がどこまで共有され得るのか」を理解したうえで、二重譲渡防止の社内ルール、複数社利用時の管理方法、金融機関への説明資料(決算書・資金繰り表・再建方針)を整えることです。
情報共有の仕組みを把握し、専門家とも連携しながら透明性の高い情報開示を行うことで、ファクタリングを利用しつつも、中長期的な与信改善と資金調達の選択肢を広げやすくなります。