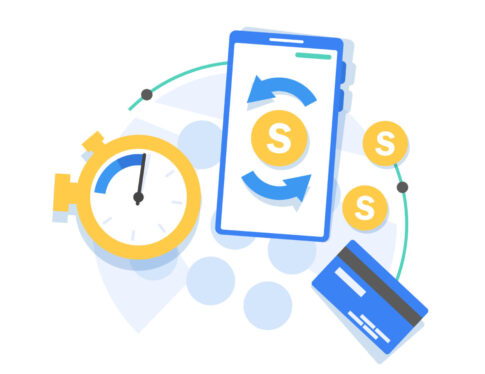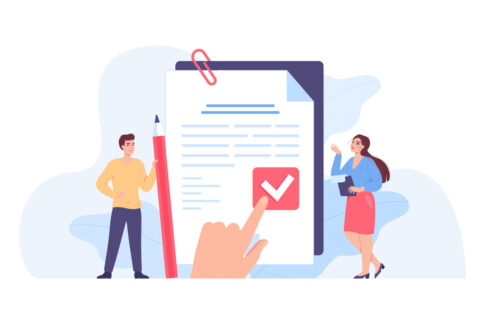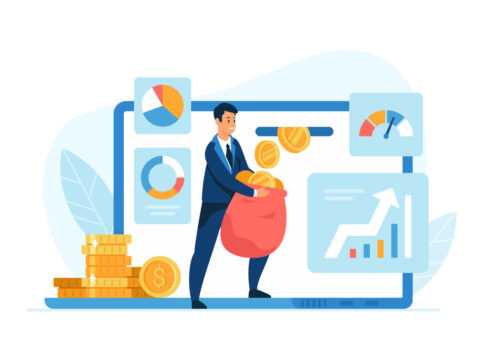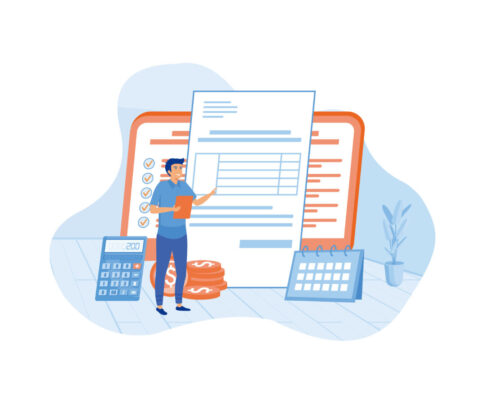赤字決算になったとき、「この赤字は将来の黒字と相殺できる?」「申告を間違えると使えない?」「資金繰りや融資審査にどう影響する?」と不安になる方は多いはずです。
繰越欠損金は、税負担の平準化に役立つ一方で、青色申告や期限内申告など満たすべき条件があります。本記事では、繰越欠損金と繰戻し還付の違い、適用条件・期限の目安、申告書類(別表七(一)等)の準備、資金繰り表への反映や融資説明のポイント、否認リスクと注意点までをまとめて整理します。
目次
繰越欠損金の基礎知識

繰越欠損金とは、法人税の計算で生じた「欠損金(税務上の赤字)」を、翌期以後の所得金額から差し引ける仕組みです。
赤字の年に税金が減るというより、将来黒字に戻った年の税負担を軽くして、利益の波がある事業でも税負担を平準化しやすくします。
注意点として、会計上の赤字と税務上の欠損金は一致しないことがあり、申告書での計算結果が基準になります。
また、控除できる額は当期の所得金額が上限となり、使い切れない分は翌期以後へ繰り越します。制度は見直される可能性があるため、実際の適用は申告前に最新の案内で確認が必要です。
- 欠損金:法人税の計算上の赤字(税務調整後の金額)
- 繰越欠損金:翌期以後に持ち越した欠損金
- 控除の上限:当期の欠損金控除前の所得金額まで
繰越控除のメリットポイント
繰越控除のメリットは、黒字化した期の税負担を抑え、資金繰りに余裕を作りやすくなる点です。
たとえば赤字期に設備投資や人員増を行い、翌期に売上が伸びて黒字化した場合、欠損金が残っていれば利益の一部を相殺でき、法人税等の支払いが軽くなる可能性があります。
実務上は「黒字化したら税金が急に増えて資金が足りない」という場面の緩衝材になり得ます。
一方で、赤字期の資金不足そのものを直接解決する制度ではありません。
赤字期の支払い(家賃・人件費・仕入・借入返済など)は別途手当てが必要で、税負担の軽減は黒字期に表れます。資金繰り表を作り、黒字化見込みの時期と納税時期をセットで把握しておくと判断しやすいです。
- 黒字化後の税負担を抑え、納税資金の確保がしやすくなる
- 利益の波がある業種でも、税負担の平準化に役立つ
- 使い切れない欠損金は翌期以後へ繰り越せる
繰戻し還付との違い比較
繰越控除と似た言葉に「繰戻し還付」があります。繰越控除は将来の黒字と相殺するのに対し、繰戻し還付は原則として直前の1事業年度(または前年)へ“戻して”税額の還付を請求する仕組みです。
資金繰りの観点では、繰戻し還付は要件を満たせば現金が戻る可能性がある一方、対象者や適用可否に条件があります(法人の場合は中小企業者等以外では一定期間、原則不適用とされる扱いがあるなど)。
どちらが有利かは、直前期に課税所得があるか、今すぐ現金が必要か、将来の黒字見込みがどの程度かで変わります。
| 項目 | 繰越控除 | 繰戻し還付 |
|---|---|---|
| 効果の出方 | 翌期以後の黒字と相殺して税負担を軽くする | 原則、直前期へ戻して税額の還付を請求する |
| 資金繰り | 黒字化後の納税資金を減らしやすい | 要件を満たせば早期に現金が戻る可能性 |
| 主な前提 | 欠損金が出た期の申告・書類整備が重要 | 青色申告など一定の要件、適用範囲に注意 |
法人・個人の制度差注意点
「赤字の繰越」は、法人と個人事業主で制度の呼び方や期間が異なります。法人は「欠損金」の繰越控除として、原則、過去10年以内に生じた欠損金を対象に控除する枠組みです。
個人事業主は「純損失(損益通算しても控除しきれない赤字)」の繰越控除として、原則3年間が基本です(特定の災害時など例外的な延長がある扱いもあります)。
また法人は、会社の規模等により欠損金の損金算入に上限が設けられるケースがあり、連続して控除できないことがあります。
さらに、M&Aや支配関係の変動がある場合など、欠損金の引継ぎ・利用に制限がかかる場面もあるため、該当しそうなときは早めに専門家へ確認するのが安全です。
- 法人は「欠損金」、個人は「純損失」と用語・計算が異なる
- 繰越期間は、法人は原則10年、個人は原則3年が基本
- 法人は規模や状況により控除上限・制限が出ることがある
適用条件と期限の目安

繰越欠損金を使う前提は、「欠損金が出た期」と「控除を受ける期」の双方で、要件を満たした申告ができていることです。特に重要なのが青色申告の承認、期限内申告、欠損金を申告書上で正しく引き継ぐことです。
赤字の期に申告が遅れると、その期の欠損金が繰り越せない扱いになることがあるため、資金繰りが厳しいときほど期限管理が重要です。
なお、制度は改正される可能性があるため、申告前に最新の取扱いを確認する前提で進めてください。
| 項目 | 目安と考え方 |
|---|---|
| 青色申告 | 承認申請と帳簿付け等が前提。欠損金の繰越控除を使う土台になります。 |
| 期限内申告 | 原則、法定申告期限(延長特例がある場合は延長後)までに申告が必要です。 |
| 連続性 | 毎期の申告で欠損金の残高を引き継ぎ、控除を受ける期にも申告上の手当てが必要です。 |
| 書類の整合 | 決算書・申告書・別表の数値がつながる状態にし、根拠資料を保存します。 |
青色申告の要件チェック
欠損金の繰越控除は、原則として青色申告を前提に考えるのが安全です。青色申告は「税務署への承認申請」と「適正な帳簿付け・保存」がセットで、赤字が出た期に欠損金として認められるかにも関わります。
たとえば法人を設立した場合、設立後の早い段階で青色申告の承認申請を出し、日々の取引を帳簿に記録して決算書と申告書を作成します。フリーランスでも、青色申告の承認申請と帳簿作成が前提になります。
- 承認申請を期限内に提出している
- 売上・経費の根拠(請求書、領収書、通帳等)を保存している
- 帳簿の記帳が継続できている(後追いでも、根拠が残る形)
- 決算書(または収支内訳)と申告書の数値が説明できる
連続申告の条件注意点
繰越欠損金は「赤字の期に生じた欠損金を、翌期以後へ引き継いで使う」仕組みなので、毎期の申告で欠損金の残高をつないでいくことが大切です。
欠損金があるのに申告をしない、あるいは欠損金の引継ぎを申告書上で行わないと、控除を受けたい期に「残高が確認できない」状態になりやすくなります。
また、期限後申告になると、その期に生じた欠損金の繰越が認められない扱いとなることがあるため、資金繰りが厳しいときほど先に申告スケジュールを確保してください。
- 決算日から申告期限までの作業日数を逆算する
- 赤字期でも申告書を提出し、欠損金の残高を申告書上で引き継ぐ
- 翌期以後も、欠損金の残高表を更新して申告書と一致させる
- 遅れそうな場合は、延長特例の可否や専門家への依頼を早めに検討する
繰越期間10年の計算目安
法人の繰越欠損金は、一般に「過去10年以内に生じた欠損金」を所得から控除できる枠組みです。実務では「いつの欠損金が、いつまで使えるか」を年度別に管理するのが確実です。
たとえば、決算期が3月の会社で、2025年3月期に300万円の欠損金が出た場合、黒字が出た期に順次相殺していき、残った分は10年の範囲内で利用を検討します。期限が近い欠損金から消化するよう残高を並べておくと、控除漏れを防ぎやすいです。
なお、法人の規模や状況により控除の上限が設けられることもあるため、該当しそうな場合は申告前に確認が必要です。
- 「欠損金が出た期」と「使う期」の両方で申告が前提になる
- 年度別に残高と使用額を管理し、申告書の数値と一致させる
- 期限が近い欠損金から優先して使えるよう、順序を見える化する
申告書類と別表の準備
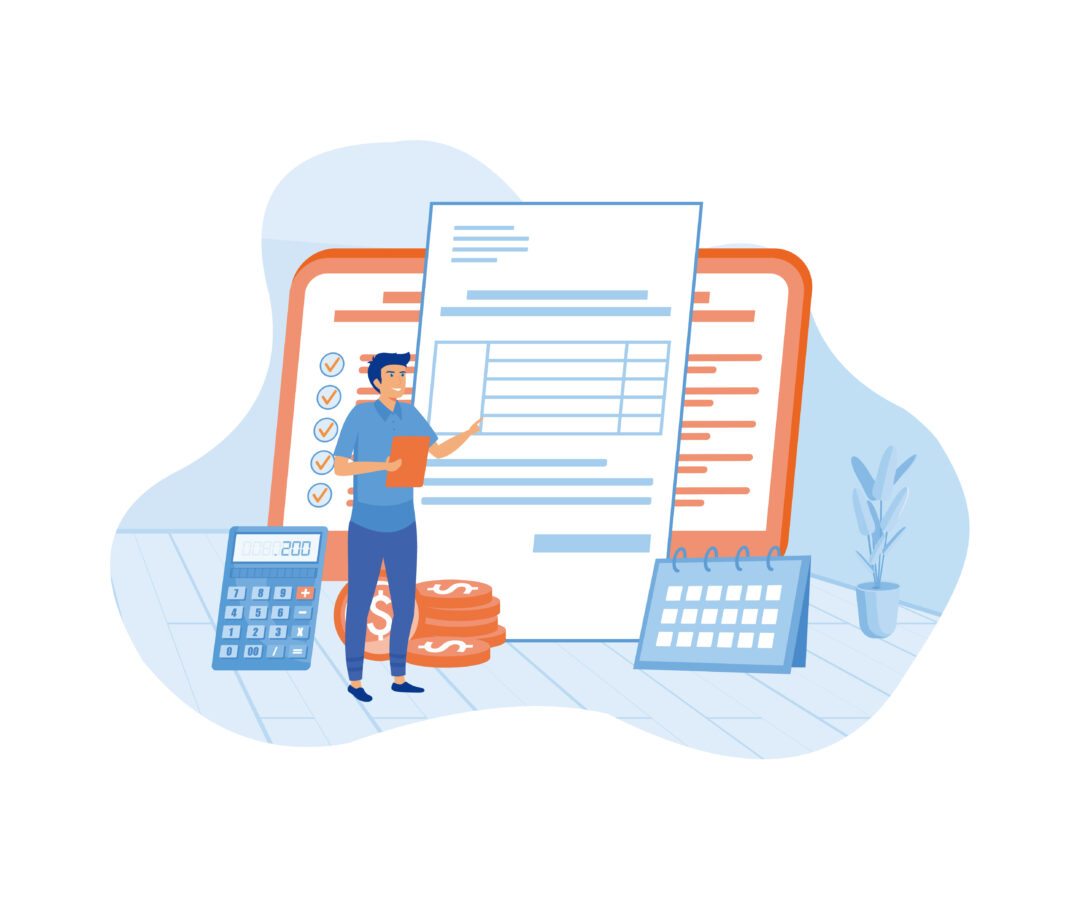
繰越欠損金は「赤字が出た事実」だけでは使えず、申告書類上で欠損金額と繰越残高が一貫して確認できる状態にしておくことが前提です。
ポイントは、当期の欠損金額の計算根拠(税務調整後の金額)と、過去分も含めた繰越残高の引継ぎを、別表などの指定様式でつなぐことです。
また、赤字決算の年は資金繰りが厳しく、申告準備が後回しになりがちですが、期限後申告になると繰越欠損金が使えない扱いになる可能性があります。
決算確定から申告までの作業を「必要書類→別表作成→提出」の順で分解し、早めに着手するのが安全です。
| 書類・別表 | 役割のイメージ |
|---|---|
| 決算書 | 会計上の損益・財産状況の基礎。税務上の欠損金とは一致しないことがあるため、申告書で調整します。 |
| 法人税申告書(所得計算の別表) | 会計利益(損失)を税務上の所得(欠損金)へ調整し、当期の欠損金額を確定させます。 |
| 別表七(一) | 欠損金の「発生年度別の残高」と「当期に控除した額」「翌期へ繰り越す額」を管理します。 |
| 根拠資料(請求書・領収書等) | 費用の実在性や金額の説明に必要。保存が弱いと否認リスクが高まります。 |
別表七(一)の記載ポイント
別表七(一)は、繰越欠損金の「台帳」に近い役割です。ポイントは、当期の欠損金額と、過去からの繰越残高を年度別に並べ、当期に控除した分を差し引いて翌期へつなぐことです。
年度をまたぐ計算なので、転記ミスがあると「残高が合わない」「古い欠損金の期限管理ができない」といったトラブルにつながります。
実務では、当期が赤字の場合でも別表七(一)の作成は重要です。黒字の年だけ作るのではなく、赤字の年に欠損金を確定させ、繰越の“起点”を申告書上に残すイメージで準備します。
- 当期の欠損金額は、所得計算の別表で確定した数値と一致させる
- 前期以前の欠損金は「発生年度ごと」に残高を並べて記載する
- 当期に控除した額は、所得金額を上限として過不足なく反映する
- 控除しきれない残高は「翌期繰越額」として必ずつなぐ
欠損金の年度管理ステップ
欠損金は「10年の範囲内」というルールがあるため、申告書だけに頼らず、社内でも年度管理表を持っておくと安全です。
とくに、複数年にわたって赤字と黒字を行き来する場合、どの年度の欠損金をどれだけ使ったかが見えないと、控除漏れや期限切れが起きやすくなります。
- 管理表を作る(発生年度/欠損金額/当期控除額/残高/期限の欄を用意)
- 赤字期の申告で「当期欠損金額」を確定し、管理表へ転記する
- 黒字期は「当期所得」と「控除可能残高」を照合し、控除額を決める
- 控除後の残高を更新し、期限が近い年度を目立つ形で管理する
たとえば、2024年度に欠損金200万円、2025年度に欠損金100万円があり、2026年度の所得が150万円なら、控除できる上限は150万円です。
古い欠損金から充当する方針で管理すると、2024年度分を150万円控除し、2024年度残高は50万円、2025年度分は100万円のまま翌期へ繰り越す、といった整理がしやすくなります。
提出期限と延長の注意点
法人税の確定申告は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内が提出期限です(期限日が土日祝に当たる場合は翌平日になる扱いです)。繰越欠損金を確実に使うためには、赤字の年ほど「期限内に提出する」ことが重要になります。
決算が確定しないなど特別な事情がある場合、所轄税務署への申請で申告期限の延長が認められることがあります。
ただし、申告期限を延長しても、納付の扱いは別途の注意が必要です。申告が遅れる・納付が遅れると、追加負担(延滞税等)が発生する可能性があるため、延長を検討する局面ほど「見込みでの納付」「必要書類の優先順位付け」を先に決めておくと混乱を減らせます。
- 赤字でも期限内申告が重要(期限後申告だと繰越が使えない扱いになることがある)
- 延長が可能なケースでも、申請手続きが必要になることがある
- 納付が遅れると追加負担が発生する可能性があるため、資金手当てを先に検討する
- 間に合わない兆候が出たら、早めに税理士等へ相談し作業を分解する
中小企業の資金繰り影響

繰越欠損金は、将来の黒字期の課税所得を減らし、法人税等の支払いを抑える方向に働くため、黒字化後の資金繰りを安定させやすくします。
ただし、赤字の期に現金が増える制度ではなく、効果が出るのは黒字が出た期の申告・納付タイミングです。
また、欠損金で直接減るのは主に所得課税であり、消費税(課税売上や仕入税額控除で決まる)や、地方税の均等割などは別途発生し得ます。資金繰りでは「どの税目が、いつ、いくら出ていくか」を分けて見積もることが重要です。
| 観点 | 資金繰りへの影響 |
|---|---|
| 法人税等 | 黒字期に欠損金を控除できると、納付額が小さくなる/ゼロに近づく可能性があります。 |
| 消費税 | 欠損金の有無では決まらず、課税売上・仕入税額控除などで決まるため、別枠で試算が必要です。 |
| 地方税の均等割 | 所得がなくても一定額が発生することがあり、納付ゼロにならない要因になります。 |
| 資金繰り計画 | 税負担の軽減は「黒字化後の納付タイミング」で効くため、月次の資金繰り表に時期を落とし込みます。 |
還付・納付ゼロの見込み目安
「納付ゼロに近いか」を見るときは、黒字見込み(税務上の所得)と繰越欠損金残高の大小関係を先に押さえます。
たとえば、翌期の税務上の所得見込みが300万円で、繰越欠損金が400万円残っている場合、所得は欠損金で相殺され、法人税等の負担が小さくなる可能性があります。
一方、欠損金は所得を下回る分しか使えないため、所得が800万円で欠損金が400万円なら、控除後も所得が残り、納付が発生し得ます。
「還付」については、欠損金の繰越控除そのものが現金を生むわけではありませんが、繰戻し還付が適用できる場合は還付につながる可能性があります。また、税目によっては還付が起きる仕組みが別にあります。
資金繰り判断では、まず所得課税の納付見込みを立て、次に消費税など他の税目を分けて検討するのが実務的です。
- 翌期の税務上の所得見込み(黒字)を出す
- 繰越欠損金の残高と有効期限を確認する
- 所得見込み≦欠損金残高なら、法人税等の負担は小さくなる可能性
- 消費税・均等割など、欠損金と別枠の納付有無も同時に確認する
資金繰り表への反映ステップ
資金繰り表に落とし込む際は、「損益(利益)=現金増減」ではない点に注意し、納税の支払時期を月次で配置します。
欠損金の効果は黒字期の税額見込みに反映されるため、黒字化が見える段階で、税務上の所得見込みと欠損金控除後の納税額を更新していくとズレが減ります。
とくに、資金繰りが厳しい会社ほど、決算月の後に大きな支出が集中しやすいので、申告・納付の月に「税金」行を立てて、先に資金確保の手当てを検討します。
- 月次の入金・支払予定(売掛入金、仕入、人件費、家賃など)を確定する
- 決算月と申告・納付が発生する月を資金繰り表に配置する
- 黒字見込みの期は、欠損金控除後の税額見込みを作り、納税資金の必要額を更新する
- 中間納付等が発生し得る場合は、前年実績をもとに「概算枠」として別行で見込む
- 想定より黒字が増減したら、税額見込みと納付月の残高を更新する
融資審査での説明ポイント
融資審査では、繰越欠損金は「将来の税負担を軽くし得る要素」として説明材料になりますが、欠損金自体は現金ではないため、資金繰りの裏付け(入金予定・支払予定・借入返済計画)とセットで示すことが重要です。
また、赤字が続いている場合は「なぜ赤字になったか」「黒字化の再現性があるか」「固定費や粗利構造の改善が進んでいるか」が見られやすいので、欠損金の話だけに寄せず、事業計画の根拠を簡潔にまとめます。
提出書類としては、直近の決算書・申告書一式、資金繰り表、売上の根拠(受注残・契約・請求予定)などが基本線になります。
- 欠損金の残高と、黒字化後に税負担が軽くなる見込み(ただし現金ではない点)
- 黒字化の根拠(単価・数量・継続率・粗利率の改善など)
- 資金繰り表での納税月の資金手当て(納税資金の積み増し方針)
- 赤字要因への手当て(固定費見直し、回収条件改善、仕入条件の交渉など)
- 提出資料の整合(決算書・申告書・資金繰り表の数値がつながる状態)
否認リスクと注意点
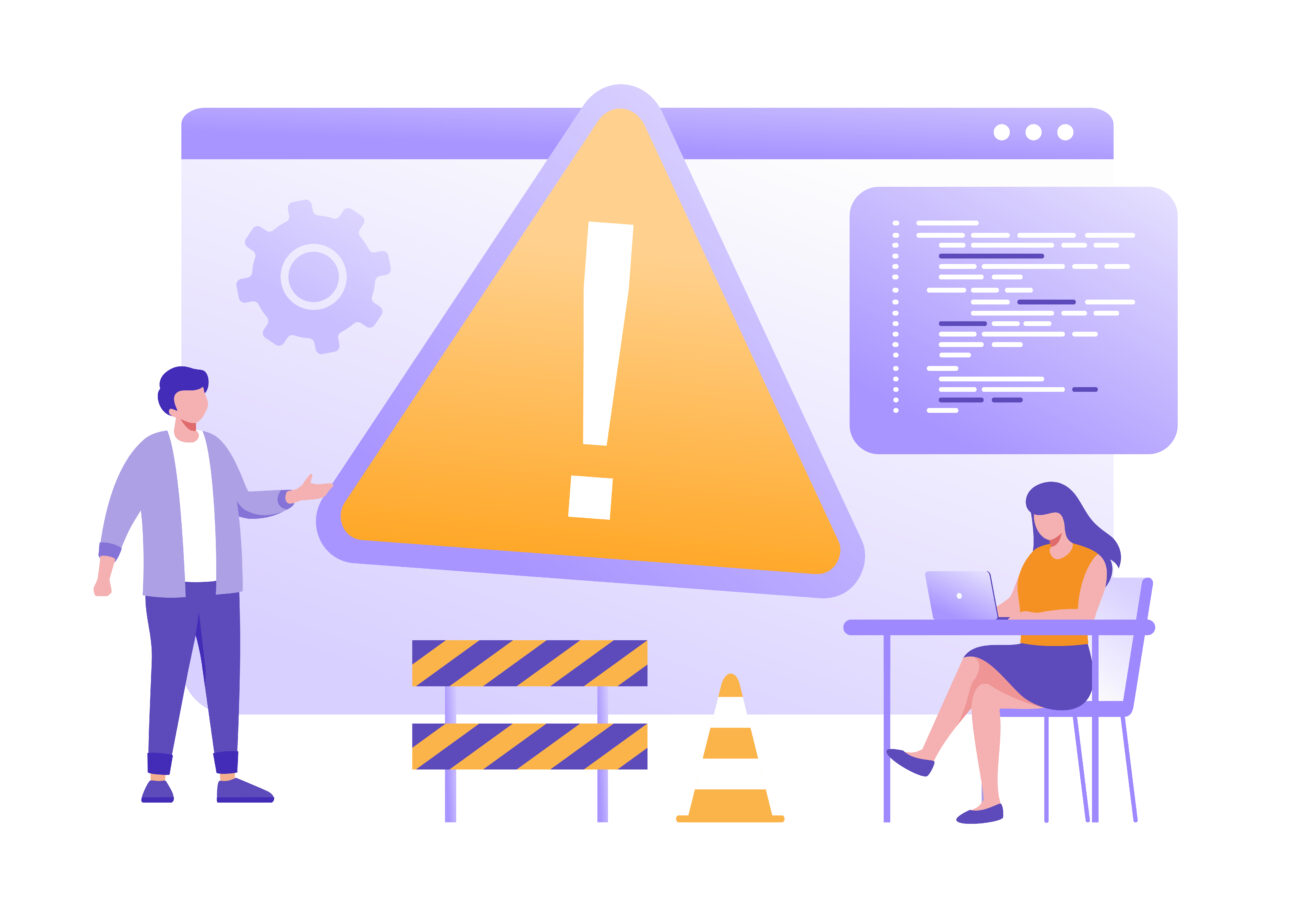
繰越欠損金の「否認」とは、申告した欠損金の全部または一部が税務上認められず、繰り越せる金額が減る(または使えない)状態を指します。
多い原因は、経費の根拠不足・私用混在・計上時期のズレなどにより、所得(または欠損金)が調整されるケースです。
たとえば赤字300万円で申告していても、経費80万円が否認されると欠損金が220万円に縮み、将来の黒字期に相殺できる枠も減ります。
赤字期ほど管理が緩みやすいので、「証拠」「整合」「期限」の3点を押さえ、制度は改正され得る前提で最新の取扱いも確認しながら対応することが重要です。
| 主な論点 | 注意の方向性 |
|---|---|
| 根拠資料 | 請求書・領収書・契約書・通帳明細など、取引実在性を説明できる保存が必要です。 |
| 私用混在 | 役員・事業主の私的支出が経費に入ると否認されやすく、按分根拠も求められます。 |
| 計上時期 | 売上・外注費・棚卸などの期ずれは所得が動きやすく、欠損金額にも影響します。 |
| 申告と帳簿 | 申告書(別表)と帳簿・決算書のつながりが弱いと、説明負荷が増えます。 |
税務調査で見られるチェック
税務調査では、欠損金そのものというより「欠損金を構成する売上・経費・棚卸などが妥当か」が確認されます。特に、赤字幅が大きい年や、売上が急減した年は、計上の正確さが問われやすいです。
初心者がつまずきやすいのは、領収書があるだけで経費が必ず認められると誤解する点です。実際は、業務関連性や取引の流れ(契約→発注→納品→支払)が説明できることが重要になります。
- 売上計上の期ずれ(検収・納品・請求タイミングの整合)
- 外注費・広告費の実在性(契約書、成果物、支払記録)
- 役員・事業主の私用混在(会食、車両、通信費などの按分根拠)
- 棚卸や原価の妥当性(在庫数量、評価、廃棄の証拠)
- 大きな臨時費用の理由(解約違約金、修繕、減損などの背景資料)
期限後申告の影響注意点
繰越欠損金は、原則として期限内申告が土台になります。期限後申告になると、その期に生じた欠損金の繰越控除が認められない扱いとなる場合があるため、赤字期でも申告期限の管理が重要です。
また、黒字期で納税が発生する状況で期限後申告になると、追加負担(加算税や延滞税など)が生じる可能性があり、資金繰りに二重の負担になり得ます。
間に合わない兆候が出た段階で、作業を分解し、提出までの道筋を確保することが現実的です。
- 決算日から申告期限までの作業日数を逆算する
- 不足資料(請求書・通帳・外注契約など)を先に洗い出す
- 欠損金の年度残高が申告書とつながるよう、別表の作成を優先する
- 遅延が濃厚なら、延長の可否や外部支援(税理士等)を早めに検討する
まとめ
赤字決算の繰越(繰越欠損金)は、将来の黒字と相殺して税負担を抑えるための重要な制度です。
要点は①青色申告や期限内申告などの条件を満たすこと、②繰越期間の考え方と年度管理を徹底すること、③別表七(一)など申告書類を正確に整えること、④資金繰り表に税負担の見込みを反映し、融資では根拠を説明できる状態にすること、⑤期限後申告や記載不備による否認リスクに注意することです。
まずは入出金予定と欠損金の年度を整理し、候補となる資金調達手段も比較しながら、必要に応じて税理士や金融機関へ相談できる準備を進めましょう。