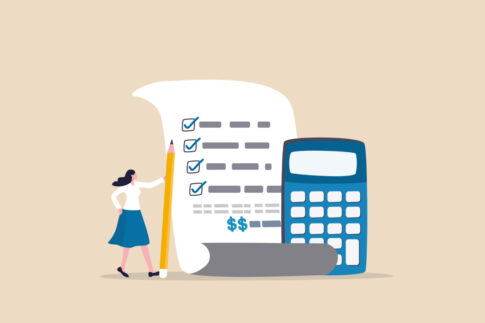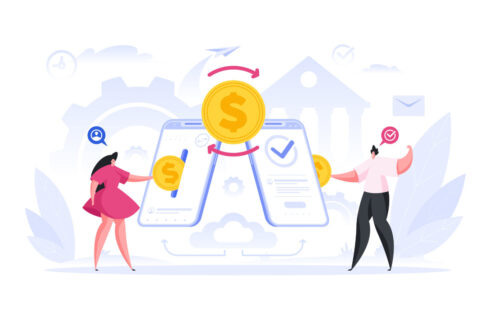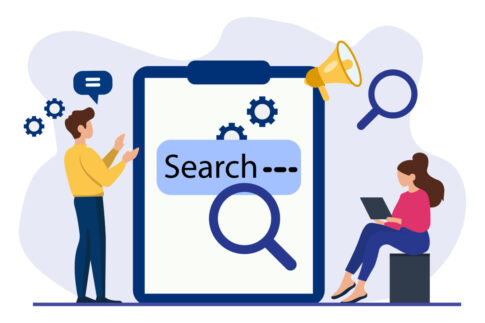「銀行より審査がやさしい」と言われるファクタリングでも、申し込みが通らないケースは少なくありません。原因は、自社の業績だけでなく、売掛先の信用力や売掛金そのものの状態など、複数の軸が絡んでいます。
この記事では、ファクタリング審査が落ちる代表的な理由を「売掛先・債権・利用企業」の三つに整理し、事前チェックのポイントと審査通過に向けた実務対応、他の資金調達手段の検討のヒントまで客観的に解説します。
ファクタリング審査の基本ポイント
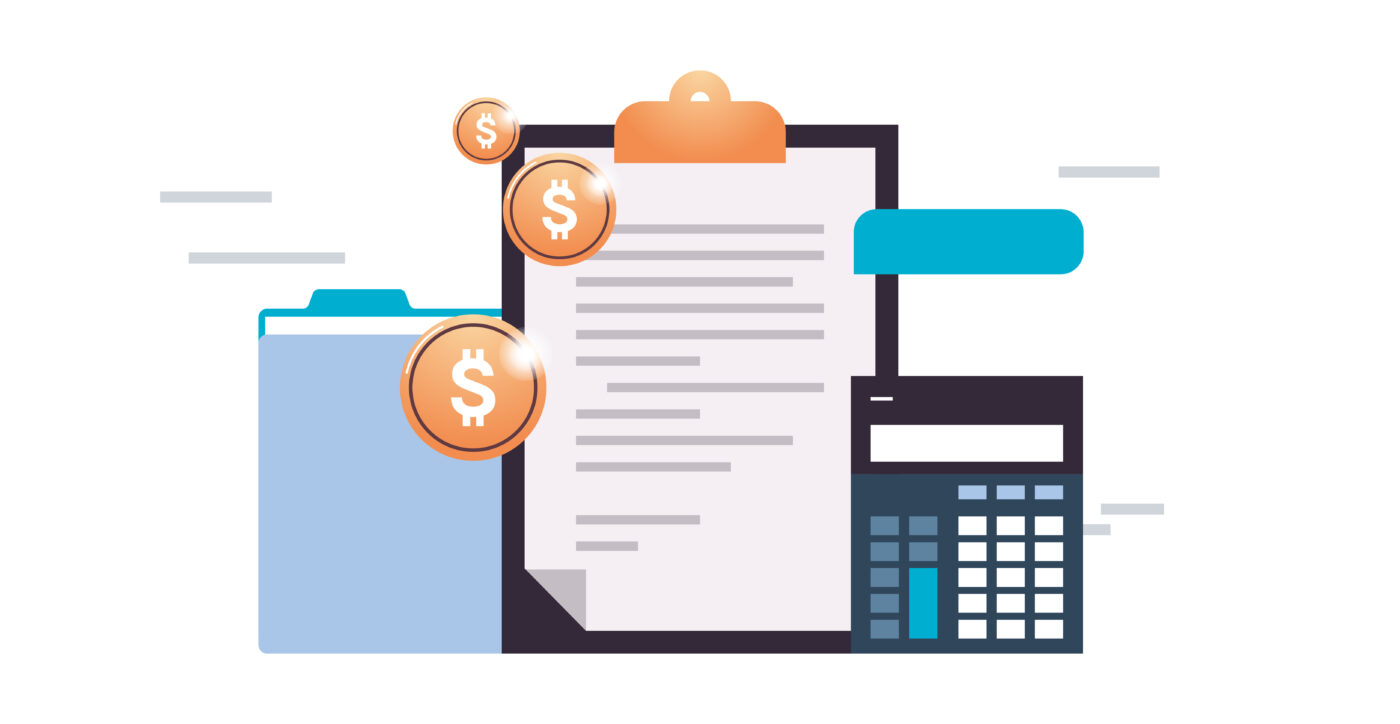
ファクタリングは「売掛金(売掛債権)を売却して資金を早期に受け取る」取引で、融資とは異なり返済義務はありませんが、利用にあたっては必ず審査があります。
銀行融資と違い、ファクタリング会社は「資金を借りる企業」だけでなく「売掛先(取引先)」と「売掛債権そのもの」を重視して判断する点が特徴です。
大手金融機関の解説でも、買取型ファクタリングでは売掛債権の支払企業の信用力を勘案して審査することが明記されています。
審査の基本は、①売掛先の信用力(倒産・延滞のリスク)、②売掛債権の内容(請求書の確実性・支払期日までの日数など)、③利用企業(申込企業)の事業実態・資金使途の三つの軸で構成されます。
オンライン完結型のクラウドファクタリングでも、請求書・口座の入出金明細・決算書/確定申告書・本人確認書類といった複数の情報を組み合わせてAI等で審査する仕組みが採用されており、短時間であっても一定の審査プロセスを経ていることが分かります。
銀行融資と比較すると、ファクタリングは決算内容や担保よりも売掛先と債権の質に重心が置かれるため、「自社が赤字だから絶対に無理」というわけではありません。
その一方で、不良債権を混ぜていたり、売掛先の信用不安が大きかったりすると、審査落ちや買取額の圧縮につながります。まずは、どのポイントが見られているのかを理解しておくことが、審査対策の出発点になります。
| 審査の軸 | 主な確認ポイント |
|---|---|
| 売掛先 | 企業規模・業績・支払実績・税金滞納等の有無など、倒産・延滞リスク。 |
| 売掛債権 | 取引完了の有無、請求金額・支払期日の確定、延滞の有無、譲渡禁止特約の有無など。 |
| 利用企業 | 事業実態、資金使途、口座の入出金状況、決算/確定申告の内容、反社会的勢力との関係の有無など。 |
審査で見られる三つの軸
ファクタリング審査で重視される三つの軸は、「売掛先」「売掛債権」「利用企業」です。
まず売掛先については、売掛金を最終的に支払う相手であるため、ファクタリング会社は取引先の規模・財務内容・支払実績などを与信管理の観点から確認します。
銀行などの解説でも、売掛債権保証やファクタリングの与信判断において、支払企業の信用力が中心的な要素とされています。
具体的には、過去の入金遅れがないか、帝国データバンク等の信用情報に大きなマイナスがないか、税金滞納や法的倒産手続きの情報がないか、といった点がチェックされます。
次に売掛債権自体の内容です。オンライン型ファクタリングでは、「請求金額・入金日が確定している請求書のみ対象」「入金日が5営業日以内の請求書は申込不可」といった条件を明示している例があり、実際に存在し、期日まで一定の期間がある売掛債権であることが前提とされています。
納品前の請求書や、すでに入金済み・延滞中の債権は、審査でマイナス評価となるか、対象外となることが一般的です。
最後に利用企業です。クラウドファクタリングの必要書類を見ると、決算書または確定申告書、事業用口座の入出金明細、本人確認書類などが求められており、事業が実在しているか、口座の入出金が極端に不自然でないか、といった点が確認されます。
銀行融資ほど財務指標を厳しくは見ないサービスもありますが、税金・社会保険料の長期滞納や、反社会的勢力との関係が疑われる場合などは、審査落ちの大きな要因になります。
- 売掛先:支払遅延や経営不安が大きい取引先の債権をまとめて出していないか。
- 売掛債権:取引完了・請求金額・期日・証憑がそろった「正常債権」かどうか。
- 自社:事業実態・口座の入出金・税金等の状況について、説明できる状態か。
二者間・三者間スキームの違い
ファクタリングの契約形態には、主に「二者間ファクタリング」と「三者間ファクタリング」の二種類があります。
二者間ファクタリングは、利用企業とファクタリング会社の二者で契約を締結し、売掛先には原則として債権譲渡を通知しないスキームです。
この場合、売掛先は従来どおり利用企業に代金を支払い、利用企業からファクタリング会社へ資金を渡す形になるため、ファクタリング会社にとっては回収リスクが相対的に高くなります。
そのため、審査も利用企業・売掛先の双方について比較的厳格に行われ、手数料率も高めに設定される傾向があります。
一方、三者間ファクタリングは、利用企業・ファクタリング会社・売掛先の三者が関与し、売掛先に債権譲渡の通知や承諾を行ったうえで、売掛先からファクタリング会社に直接入金してもらうスキームです。
売掛先の承諾が前提となるため、ファクタリング会社は売掛金を直接回収でき、債権未回収リスクを抑えやすくなります。その結果、二者間よりも手数料率は低くなるのが一般的です。
審査の観点では、同じ売掛先・同じ売掛債権であっても、三者間スキームの方が回収リスクが低いため、二者間では審査が通りにくいケースでも三者間なら通過する、といった運用があり得ます。
一方で、売掛先にファクタリング利用を知られたくない利用企業も多く、実務では二者間を選ぶ企業も少なくありません。その場合、売掛先の信用力に加え、自社の決算内容や入金実績、取引関係の安定性などが一層重視されることになります。
- 三者間:売掛先に通知・承諾を行う代わりに、審査ハードル・手数料が下がりやすい。
- 二者間:売掛先に知られない一方、回収リスクが高く、審査・手数料は厳しめになりやすい。
- 「売掛先に知られたくない」事情と、「審査通過・コスト」のバランスを検討する。
申込から入金までの審査フロー
ファクタリングの具体的な審査フローはサービスによって細部が異なりますが、クラウドファクタリングの例では、概ね次のようなステップになっています。
- 申込・書類提出:Webフォームや専用ページから申込を行い、請求書・決算書/確定申告書・事業用口座の入出金明細・本人確認書類などをアップロードする。
- 審査:提出書類とヒアリング内容をもとに、売掛先・売掛債権・利用企業の三つの軸で審査を行う。AIを併用するサービスもある。
- 見積り提示・条件確認:買取可能額・手数料率・入金予定日などの条件が提示され、利用企業が了承すれば契約プロセスへ進む。
- 契約締結:オンライン上の電子契約や書面により、基本契約書・個別契約書などを取り交わす。
- 入金:契約完了後、ファクタリング会社から利用企業の口座に買取金が振り込まれる。
オンライン完結型サービスでは、「必要な情報が不備なくそろってから審査開始」「審査開始後24時間以内に回答」「最短即日入金」といった目安を示している例があり、審査はスピーディーでありつつも、書類の不備や矛盾があるとその分時間がかかるとしています。
審査で落ちるケースの中には、実質的な信用リスクだけでなく、「必要書類がそろっていない」「提出内容に不整合が多い」といった事務的要因も含まれるため、フローを理解したうえで、事前に準備しておくことが重要です。
- 書類がそろってから審査が始まるため、事前準備の有無が入金スピードを左右する。
- ヒアリング内容と書類の内容に矛盾があると、追加確認が入り審査が長引きやすい。
- 「どのステップで滞っているか」を把握し、連絡・追加提出を迅速に行うことが大切。
審査に必要な主な提出書類
ファクタリング審査で求められる書類は、銀行融資より少ないとされますが、最低限の証憑は必須です。
クラウドファクタリングの例では、①本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)、②売却予定の請求書(請求金額・入金日が確定しているもの)、③事業用口座の入出金明細(直近4か月分等)、④法人の決算書一式または個人事業主の確定申告書、が必要書類として案内されています。
他のファクタリング会社では、これに加えて商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、法人の印鑑証明書、売掛先との基本契約書・発注書・納品書・検収書など、取引実在性を裏付ける書類を求めることもあります。
これらの書類から、ファクタリング会社は「事業者として実在しているか」「請求書の裏付けがあるか」「過去の入出金に不自然な点がないか」などを確認します。
| 書類 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 請求書 | 取引先・金額・支払期日・取引内容が明確か、すでに入金済みでないか。 |
| 口座明細 | 継続的な売上入金があるか、返済に追われていないか、不自然な出入りがないか。 |
| 決算書/確定申告書 | 事業規模、継続性、債務超過・税金滞納の有無などの大まかな状況。 |
| 契約書・納品書等 | 請求書が実際の契約・納品に基づくものであるかの裏付け。 |
審査落ちの一部は、「書類を出していない」「スキャンが不鮮明」「取引の流れが追えない」といった形式的な不備が原因になることもあります。特にオンライン申込では、PDFや画像の解像度や、ページ抜けに注意することが大切です。
- 請求書・契約書・納品書・検収書など、取引の流れが分かる一式をそろえておく。
- 事業用口座を分け、売上入金と私的な入出金が混在しないようにしておく。
- オンライン提出時は、必要ページの抜けや不鮮明な画像がないかを必ずチェックする。
売掛先リスクと審査への影響確認

ファクタリングの審査では、「売掛先がきちんと支払ってくれるか」が最も重要なポイントの一つです。
売掛金を回収できなければ、ファクタリング会社は買取代金を回収できないため、売掛先の信用力や取引実績は審査結果に直結します。
業界の解説でも、ファクタリングや売掛債権保証の与信判断は、支払企業の財務状態・支払実績を重視して行われることが示されています。
具体的には、売掛先の決算内容や信用調査機関の評価、税金の滞納や延滞の有無、反社会的勢力との関係、取引年数や支払遅延の頻度などが、総合的にチェックされます。
ファクタリング会社や与信管理の解説では、「取引実績の浅い売掛先」「支払遅延や税金滞納など金銭トラブルを抱える売掛先」は、審査に通過しにくく、手数料率も高くなりやすいとされています。
売掛先リスクの確認は、単に審査に通るかどうかだけでなく、自社の与信管理とも重なります。
売掛先の財務悪化や税金滞納は、将来の貸倒リスクのシグナルでもあるため、ファクタリング審査で指摘された事項は、自社の取引方針の見直しにも活用できます。
| 確認対象 | 主なチェック内容 |
|---|---|
| 売掛先の信用力 | 決算内容、信用調査レポート、支払実績、税金滞納情報など。 |
| 取引実績 | 取引年数、請求・入金の回数、遅延の有無、取引条件の変化など。 |
| 属性・実在性 | 法人か個人事業主か、本店所在地や事業実態、ペーパーカンパニーでないか等。 |
| 反社リスク | 反社会的勢力との関係有無、各種リストとの照合結果など。 |
売掛先の信用力と審査結果
売掛先の信用力は、ファクタリング審査の中核となる要素です。
中小企業向けのファクタリング・与信管理解説では、売掛債権の保証や買取を行う際、「支払企業の経営状態・財務基盤・支払実績」が主な判断材料とされており、経営が安定し倒産リスクの低い企業の売掛金ほど、高い評価を受けやすいと説明されています。
ファクタリング会社は、売掛先の信用調査レポートや公開情報、帝国データバンク等の与信情報を参考にしながら、次のような点を確認します。
- 連続赤字や債務超過になっていないか。
- 支払遅延が頻発していないか。
- 税金や社会保険料を滞納していないか。
- 取引年数や取引量が安定しているか。
業界解説では、「経営状態が安定した売掛先の売掛金は審査に通りやすく、手数料も低くなりやすい」「取引実績が浅い売掛先や過去にトラブルがある先は、審査落ち・手数料増加の要因になる」とされています。
ファクタリング審査が通らない場合、「自社の決算」だけでなく、「どの売掛先の請求書を出しているか」が適切かどうかも確認する必要があります。
- 信用調査レポートや帝国データバンク等のスコアを定期的に確認する。
- 支払遅延が増えている先・決算悪化が続く先の売掛金は、申込対象から外すことも検討する。
- 取引年数が長く、支払実績が安定している売掛先の売掛金を優先的にファクタリングに回す。
経営不安・税金滞納がある売掛先
売掛先に経営不安や税金滞納がある場合、ファクタリング審査において大きなマイナス要因になります。
ファクタリング会社の審査ポイントを解説する記事では、「売掛先が過去に支払遅延や税金滞納などの金銭トラブルを起こしている場合、審査通過は難しくなる」と明記されており、支払能力に疑問がある企業の売掛金は、買取対象から外される可能性が高いとされています。
税金や社会保険料の滞納情報は、信用情報機関のいわゆる「ブラックリスト」には直接登録されませんが、金融機関や保証協会の与信判断では、決算書や納税証明書から滞納の有無がチェックされることがあります。
同様に、ファクタリング会社も、公開情報や調査レポートから、売掛先に税金滞納や公租公課の延滞がないかを確認し、「資金繰りの悪化」「倒産リスクの高まり」といったシグナルとして評価します。
- 税金滞納や社会保険料未納は、資金繰り悪化のサインとして見られる。
- 売掛先の決算書・官報・信用調査レポートなどから、経営不安の兆候がないか確認する。
- 経営不安が強い売掛先の売掛金は、審査落ちや高手数料の原因になりやすい。
- ファクタリング申込対象から外す、または買取額・利用頻度を絞ることを検討する。
- 売掛先の資金繰り悪化が続く場合、取引条件の見直しや与信限度の設定も検討する。
- 複数の売掛先に取引を分散し、特定先への依存を減らすことでリスクを抑える。
個人事業主・ペーパーカンパニー先
売掛先が個人事業主や、実態が不透明なペーパーカンパニーの場合も、ファクタリング審査は慎重になります。
中小企業向けの与信管理解説では、「事業実態が見えにくい先」「資本金が極端に小さいが売上規模が不自然に大きい先」「所在地や代表者情報が頻繁に変わる先」などは、将来の貸倒リスクが高いとされ、与信限度の設定や取引条件の見直しが推奨されています。
ファクタリング会社の観点でも、売掛先が個人事業主で法人登記がなく、決算書や信用情報が十分に得られない場合、信用力の判断材料が限られるため、買取を見送るケースがあります。
また、設立間もない法人や休眠会社の名義を使ったペーパーカンパニーは、架空取引や循環取引の温床になりやすく、架空債権リスクを避ける観点から、厳しくチェックされます。
- 売掛先が個人事業主の場合、事業歴や申告状況、取引実績などを確認する必要がある。
- 実態が不透明なペーパーカンパニーの売掛金は、審査NG・買取対象外となりやすい。
- 自社の与信管理としても、事業実態が確認できない先との取引は慎重に検討する。
- 登記情報・所在地・事業内容・取引実績など、基本情報を事前に確認する。
- 設立直後や実態不明の先との取引は、与信限度や決済条件を厳しめに設定する。
- ファクタリングに出す売掛金は、できるだけ信用情報が把握しやすい先に絞る。
反社会的勢力との関係チェック
反社会的勢力との関係の有無は、ファクタリング審査において絶対に外せないチェック項目です。
金融庁は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインやFAQの中で、金融機関に対し「取引フィルタリング」「ネームスクリーニング」と呼ばれる仕組みを用いて、反社会的勢力や制裁対象者との取引を未然に防止することを求めています。
多くの金融機関や事業会社は、「企業が反社会的勢力との関係を遮断するための指針」(いわゆる反社会的勢力排除に関するガイドライン)を採用しており、反社会的勢力やその関係企業が関与する取引を禁止しています。
ファクタリング会社も同様に、売掛先・利用企業・代表者・実質的支配者などが、警察情報や各種データベースにおける反社会的勢力リストと一致しないかをチェックし、該当が疑われる場合は取引を行いません。
- 売掛先・利用企業・代表者・実質的支配者について、反社チェックが行われる。
- 反社会的勢力との関係が疑われる場合、審査以前に取引そのものが断られる。
- 取引開始後に反社関係が判明した場合は、関係遮断や契約解除が求められる。
- 自社としても、反社会的勢力排除に関する基本方針を定め、取引開始前にチェックを行う。
- 暴排条例や各種ガイドラインに沿って、疑わしい取引があれば関係遮断を検討する。
- ファクタリング審査において、反社チェックは「通るかどうか以前の前提条件」と理解しておく。
売掛債権の状態と審査NG例解説

ファクタリングは「正常に回収が見込める売掛債権」を前提とした資金調達手段です。そのため、売掛債権の状態が悪い場合や、法的・実務的に問題がある売掛金が混ざっていると、審査が通らない、あるいは大きく減額される原因になります。
代表的なNGパターンとしては、すでに支払期日を大幅に過ぎた延滞債権・回収見込みが低い不良債権、支払期日が極端に先の長い売掛金、契約上の譲渡禁止特約が付された債権や、すでに別の金融機関等へ譲渡している二重譲渡、さらに架空取引や証拠が乏しい請求書などが挙げられます。
ファクタリング会社は、利用者だけでなく「売掛債権そのもの」の健全性を確認するために、請求書だけでなく、基本契約書・発注書・納品書・検収書・支払通知書などの裏付け書類の提出を求めます。
これは、債権の存在・金額・支払期日が客観的に確認でき、かつ取引先(売掛先)が支払う意思と能力を持っているかを確かめるためです。
どのNGパターンに該当しているのかを整理しておけば、「審査で落ちた理由」が自社側でも把握しやすくなり、次回申込時にどの債権を出すべきかの判断材料になります。
| NGパターン | 審査で問題になる主な理由 |
|---|---|
| 不良債権・延滞債権 | すでに支払遅延が発生しており、回収可能性が低いと判断される。 |
| 支払期日が遠い債権 | 将来の経営悪化・取引条件変更など不確実性が高く、リスクが読みにくい。 |
| 譲渡禁止特約・二重譲渡 | 契約違反や法的紛争の可能性があり、債権の優先順位が不安定になる。 |
| 架空・裏付け不十分な債権 | 債権の存在自体が疑われ、詐欺リスクとして取引自体が不可能。 |
不良債権・延滞債権を出した場合
不良債権とは、元本や利息の全額回収が困難と見込まれる債権を指し、延滞債権とは支払期日を過ぎても入金がない債権をいいます。
金融機関の監督指針などでは「3か月以上延滞」などを不良債権の目安とする考え方が示されており、長期延滞は回収リスクの高さを意味します。
ファクタリングは、本来「正常債権(期日どおりの入金が見込める売掛金)」を早期に現金化するスキームであるため、すでに支払遅延が発生している債権や、取引先の経営悪化により回収の見込みが立たない債権は、審査NGとなるのが一般的です。
実務的には、延滞・不良債権の処理は、弁護士や債権回収会社(サービサー)が担う領域とされます。
これらは「回収・整理」の対象であり、「資金調達」の対象ではありません。不良債権を含め「何でも買い取ります」といった広告を行う事業者は、回収不能リスクを理由に極端に高い手数料を設定している可能性もあり、法的・実務的なリスクが高いといえます。
また、延滞債権や架空債権を正常債権であるかのように装ってファクタリング会社に提出した場合、単なる審査落ちでは済まず、契約違反や詐欺として重大な法的責任を問われる可能性があります。
審査に通したいあまり、延滞債権を隠したり、取引実態と異なる請求書を作成したりすることは絶対に避ける必要があります。
- 支払期日を過ぎた債権は、ファクタリングではなく「回収・整理」の対象と切り分ける。
- 延滞が発生した時点で、原因と回収方針(分割・法的手続き等)を早期に検討する。
- ファクタリングに出すのは、継続取引で支払遅延がない「正常債権」に限定する。
支払期日が遠すぎる売掛金
ファクタリング会社は、支払期日までの「残り日数」も重要な審査項目としています。
オンライン型ファクタリングの利用条件を見ると、「支払期日まで◯日以上残っている請求書のみ対象」「入金予定日が5営業日以内のものは対象外」といった記載があり、ある程度の期間が残っている売掛金を対象としつつ、期日直前・期日超過の請求書は避ける設計が一般的です。
一方で、支払期日が半年以上先の長期サイトの売掛金は、将来の経営環境や取引条件の変化が読みにくく、リスク評価が難しいため、買取対象外とされることがあります。
例えば、支払期日まで30日残っている請求書100万円を手数料率5%でファクタリングする場合、利用者は95万円を前倒しで受け取りますが、ファクタリング会社が負うリスク期間は30日です。
一方、180日先が支払期日の請求書100万円を同じ5%で買い取るとすると、会社は半年間リスクを負うことになり、同じ手数料では割に合わない計算になります。
このため、支払期日が遠い債権を出すと、①そもそも審査NG、②手数料率が大きく引き上げられる、いずれかの対応になることが多いです。
- 支払期日が極端に長い債権は、リスク期間が長く審査が厳しくなる。
- 支払期日直前・期日経過の債権も、ファクタリングの対象外とされることが多い。
- ファクタリングを検討する際は、「支払期日までの残り日数」も事前に整理しておく必要がある。
- 原則として「30〜90日程度の売掛金」を中心に検討する(サービス条件を必ず確認)。
- 支払期日が長い取引は、取引条件そのものの見直し(サイト短縮交渉等)も検討する。
- 短期の資金ギャップに対して、支払期日とのバランスが良い債権を優先的に出す。
譲渡禁止特約・二重譲渡の問題
売掛先との契約書に「本契約に基づく債権を第三者に譲渡してはならない」(譲渡禁止特約・譲渡制限特約)と書かれている場合、その売掛金をファクタリングに出すことには、法的・実務的な注意が必要です。
民法改正により、譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は原則有効とされましたが、債務者(売掛先)は元の債権者に支払えば足りるなど、債務者保護のルールが維持されています。
つまり、ファクタリング会社から見れば、「譲渡はできるが、自社が確実に支払を受けられるとは限らない」不安定な状態になるため、譲渡禁止特約付き債権の買取には消極的にならざるを得ません。
さらに、同じ売掛金を複数の金融機関やファクタリング会社に譲渡する「二重譲渡」は重大な問題です。
二重譲渡が発覚すると、後順位の譲受人は債権回収ができなくなる可能性があり、故意・重過失があれば詐欺として損害賠償請求や刑事責任を問われる余地もあります。
法的には、債権譲渡の優先順位は「通知や承諾の順番」「債権譲渡登記の先後」などで決まる仕組みがありますが、実務上は二重譲渡の兆候があるだけで、ファクタリング会社は取引を避けるのが通常です。
- 譲渡禁止特約付き債権は、法的には譲渡可能でも、実務上は買取対象外となることが多い。
- 二重譲渡は、契約違反・不法行為として重い責任を負うリスクがある。
- ファクタリング利用前に、既存の担保設定・譲渡契約の有無を必ず確認する必要がある。
- 取引基本契約書に譲渡禁止特約がないか、事前に条文を確認する。
- すでに担保設定や他社との譲渡契約がある債権は、ファクタリング対象から外す。
- 将来ファクタリングを前提とする取引では、取引開始時から譲渡制限条項の有無を交渉する。
架空債権・裏付け不十分な請求書
最も重大なNG例が、架空債権や裏付けの乏しい請求書をファクタリングに出すケースです。架空債権とは、実際には商品・サービスの提供や契約が存在しないにもかかわらず、請求書だけを発行して債権があるように見せかけるものです。
これは、ファクタリング会社から見ると「存在しない債権を売ろうとしている」状態であり、詐欺そのものです。
実務上、ファクタリング会社は、請求書だけでなく、発注書・契約書・納品書・検収書・メール・検査成績書など複数の書類を組み合わせて、取引の実在性を確認します。
裏付けが不十分な請求書とは、必ずしも故意の架空ではないものの、「発注書がない」「契約書がない」「納品が完了している証拠がない」などのため、第三者から見て取引内容が追いにくいものを指します。
例えば、口頭の依頼だけで請求書を発行しているケースや、取引開始直後で契約書が未整備のケースなどが該当します。
このような場合、ファクタリング会社はリスクを判断できないため、審査NGとなるか、買取対象から除外される可能性が高くなります。
- 架空債権の提出は詐欺行為にあたり、刑事・民事の重い責任を負うおそれがある。
- 裏付け書類が薄い請求書は、故意でなくても審査NGとなるリスクが高い。
- 取引開始時から、契約書や発注書などの証憑を整備しておくことが重要。
- 商品・サービス提供前に、契約書・発注書などの基本書類を必ず取り交わす。
- 請求書・納品書・検収書・入金記録をセットで保管し、第三者が見ても追える状態にする。
- ファクタリング審査では、「隠す」より「正直に状況を説明する」ことが結果的に信頼につながる。
利用企業の信用と審査対策実務

ファクタリングは「売掛先の信用力」と「売掛債権の内容」を重視する取引ですが、利用企業(資金を受け取る側)の信用も、審査を左右する重要な要素です。
ファクタリング会社から見ると、利用企業は取引の窓口であり、取引実態や書類を提供する相手でもあります。
二者間ファクタリングでは、売掛先への通知を行わない分、入金管理や報告義務の多くを利用企業に依存するため、事業の継続性やコンプライアンスの状況がより重視されます。
具体的には、税金・社会保険料の滞納状況、決算の内容や赤字の継続度合い、口座の入出金のパターン、反社会的勢力との関係の有無、申込内容と書類の整合性、取引実績の安定性などが確認されます。
銀行融資ほど「利益水準」そのものは重視されないサービスも多いものの、規模や業種に照らしてあまりに不自然な決算・残高・入出金が見られる場合は、審査上の大きなマイナスとなります。
審査を通りやすくするには、「粉飾しない」「隠さない」ことを前提に、自社の状況を整理したうえで説明できる体制を整えておくことが重要です。
| 確認されやすい項目 | 観点 |
|---|---|
| 税金・社保 | 滞納の有無、分納中かどうか、滞納期間の長さなど。 |
| 決算内容 | 売上規模、赤字・債務超過の有無、資金繰りの傾向など。 |
| 口座明細 | 売上入金の安定性、資金の出入り、資金ショートの頻度など。 |
| 取引実績 | 主要取引先の数、継続年数、取引の集中度など。 |
税金・社会保険料の滞納リスク
税金や社会保険料の滞納は、ファクタリング審査において代表的なマイナス要因です。理由はシンプルで、「公的な支払いを滞納している=資金繰りが厳しくなっている」という強いシグナルだからです。
融資や保証の審査でも、納税証明書や完納証明が求められるケースが多く、滞納がある場合は「税務署や年金事務所から差押えが入るリスク」「預金口座が凍結されるリスク」が意識されます。
ファクタリングの場合も同様に、国税・地方税・社会保険料の滞納は、将来的に売掛金の回収や資金の流れに影響を及ぼす可能性があるため、慎重に見られます。
特に注意したいのは、滞納額と滞納期間です。少額かつ一時的な滞納で、すでに分納計画を立てて履行しているようなケースと、長期間多額の滞納が続いているケースでは、評価が大きく異なります。
審査の場面では、「現在の滞納状況」「今後の納付計画」「資金繰り改善の見込み」を具体的に説明できるかどうかがポイントになります。
- 税金・社保の滞納は、資金繰り悪化や差押えリスクのシグナルになる。
- 滞納がある場合は、金額・期間・分納計画を整理して説明する必要がある。
- 長期間の多額滞納は、審査NGの決定打になりやすい。
- まずは税務署・年金事務所と協議し、現実的な分納計画を合意する。
- 合意した分納計画を守っていることを、資料や説明で示せるようにする。
- ファクタリングに頼り切るのではなく、資金繰り表で恒常的な赤字構造を見直す。
決算内容・赤字継続と審査影響
ファクタリングは銀行融資ほど「黒字・自己資本比率」を強く要求しないとされますが、決算内容が全く審査に影響しないわけではありません。
決算書(もしくは確定申告書)からは、売上規模や粗利率の傾向、借入金残高、資金繰りの苦しさ、債務超過の有無など、多くの情報が読み取られます。
「直近数期連続の大幅赤字」「債務超過」「売上の急減少」といった状況は、事業の継続性への懸念として評価され、売掛先や債権の状態が良くても、全体のリスク判断としてマイナス材料になります。
一方で、「一時的な赤字」や「投資負担による赤字」のように、内容と背景を説明できる赤字もあります。
例えば、新規事業への投資で一時的に赤字だが、主要な既存事業は黒字が続いているケースなどです。審査では、数字そのものだけでなく、「なぜそうなっているのか」「今後どう改善するのか」というストーリーも確認されます。
決算内容を隠したり粉飾したりするのではなく、客観的な数字を前提に、将来の見通しや改善策を説明できるかどうかが重要です。
- 継続的な大幅赤字・債務超過は、事業継続リスクとしてマイナス評価される。
- 一時的な赤字であっても、理由と改善計画を説明できないと不信感につながる。
- 数字を取り繕うのではなく、「数字の背景」を正直に伝える方が信頼されやすい。
- 直近2〜3期分の決算の推移(売上・利益・借入残高)を自社でも整理しておく。
- 赤字の理由(投資・不採算案件・一時要因など)を具体的に説明できるよう準備する。
- 改善策(コスト削減・事業整理・増収施策など)を、数値目標と合わせて伝える。
書類不備・説明不整合への注意
ファクタリング審査で意外と多いのが、「信用リスクというより事務的な不備」で足踏みしたり、結果的に審査落ちとなるケースです。
オンライン完結型サービスの案内でも、「必要書類がそろってから審査開始」「不備がある場合は追加の提出をお願いする」と明記されており、書類の欠落や不鮮明なデータは、それだけで審査の遅れやマイナス印象につながります。
典型的な不備としては、次のようなものがあります。
- 請求書・契約書・納品書・検収書のいずれかが不足していて、取引の流れが追えない。
- 決算書(確定申告書)の必要なページが抜けている、または最新年度のものがない。
- 口座明細が個人口座と混在しており、事業と私費の入出金が分かりにくい。
- 申込フォームに入力した内容と、書類の金額・日付・取引先名が一致していない。
審査担当者から見れば、「書類がそろっていない」「説明と数字が合っていない」こと自体が、不信感の原因になります。
逆に言えば、書類が整っていて、申込内容と矛盾しないことが確認できれば、リスクが低く見える分、審査もスムーズになりやすいです。
- 申込前に、請求〜入金までの書類一式がそろっているか社内でチェックする。
- フォーム入力後に、金額・日付・取引先名が書類と一致しているか見直す。
- 事業用口座を分け、日常的に「誰が見ても分かる」状態にしておく。
信頼される取引実績の整え方
審査で有利になるもう一つのポイントが、「信頼される取引実績」を積み上げておくことです。ファクタリング会社が重視するのは、単発の大口案件よりも、「毎月安定して売上と入金が発生している」「支払遅延が少ない」「取引先が分散している」といった継続性・安定性です。
取引実績が安定している企業は、将来もコンスタントに売掛金が発生すると見込めるため、ファクタリング会社にとっても継続的な取引先として魅力的です。
実務上は、次のような点に気を配ることで、信頼される取引実績を整えやすくなります。
- 主要取引先の数を増やし、売上が特定の1社に偏りすぎないようにする。
- 請求〜入金のサイクルをきちんと管理し、請求漏れや入金消し込み漏れを防ぐ。
- 売掛残高の年齢別(何日経過しているか)を管理し、長期滞留を放置しない。
- 契約書・発注書・納品書など、取引証憑を体系的に保管しておく。
これらは本来、自社の与信管理や資金繰り管理のための基本でもありますが、その延長線上に「ファクタリング審査への好影響」があります。
取引実績が整理されている企業は、審査時のヒアリングにもスムーズに答えられ、審査担当者からの信頼も得やすくなります。
- 売掛管理表や資金繰り表を整備し、日常的に数字を更新する習慣をつける。
- 一社集中を避け、取引先の分散を意識した営業計画を立てる。
- 証憑の整備・保管を徹底し、「いつでも第三者に見せられる帳簿」を目指す。
資金難中小企業の審査通過戦略実務
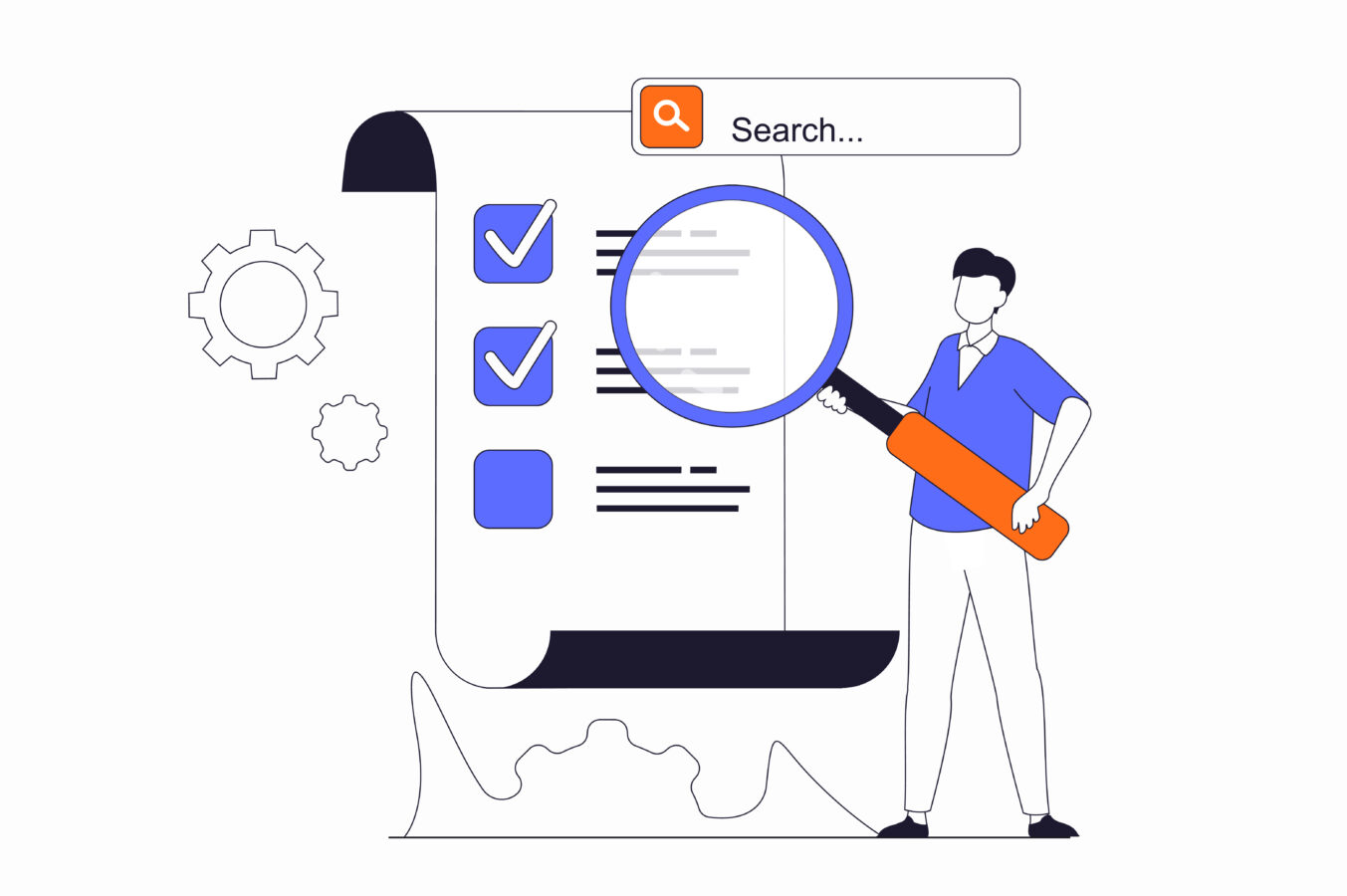
資金難の中小企業がファクタリングを検討する場合、「とにかく申し込む」のではなく、事前準備と案件選別を行うことで、審査通過率と条件を大きく改善できます。
ファクタリングの審査は、銀行融資とは見られているポイントが異なり、売掛先・売掛債権・自社の三つの軸を分けて整理することが実務上の第一歩です。
また、審査に落ちたときに原因を分解し、「どの軸でNGが出たのか」を把握できれば、次回以降の申込戦略や、他の資金調達手段との組み合わせ方も見えやすくなります。
ファクタリングだけに依存すると、手数料負担が累積して資金繰りがかえって悪化するおそれがあります。
そのため、「短期のつなぎ=ファクタリング」「中長期の資金需要=融資・リスケ・固定費見直し」といった役割分担を意識し、悪質業者を避けながら、公的支援や専門家相談も組み合わせていくことが重要です。
自社でできるチェックと外部の力を上手に使い分けることが、資金難局面を乗り切るための現実的な戦略になります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 事前チェック | 売掛先・売掛債権・自社の三つの軸でNG要因を洗い出す。 |
| 案件選別 | 審査に通りやすく、コスト効果の高い請求書を優先する。 |
| 代替手段 | 融資・公的制度・リスケなど、他の資金調達と組み合わせる。 |
| 相談・改善 | 専門窓口と連携し、資金繰りと収支構造の改善策を検討する。 |
申込前に確認したい自社チェック
申込前の自社チェックは、「審査で聞かれることを先に自分で整理しておく」作業です。ポイントは、売掛先・売掛債権・自社の三つの軸ごとに、客観的に見て問題がないかを確認することです。
売掛先については、支払遅延が増えていないか、取引年数や取引規模が極端に偏っていないかを確認します。
売掛債権については、納品・検収・請求が完了した正常債権か、支払期日までの日数が極端に短すぎないか・長すぎないか、譲渡禁止特約や他社への譲渡がないかを整理します。
自社については、税金や社会保険料の滞納状況、直近の決算内容、口座の入出金の状態、反社会的勢力との関係がないことなどを確認し、審査担当者に聞かれたときに説明できる状態にしておきます。
口頭だけで説明するのではなく、資金繰り表や売掛金管理表など、数字と事実を示せる資料を1枚用意しておくと、信用度が高まりやすくなります。
- 売掛先:支払遅延・経営不安・取引集中の有無。
- 売掛債権:取引完了・証憑・支払期日の妥当性・譲渡制限の有無。
- 自社:税金・社保、決算、口座明細、反社チェックなどの基本情報。
- 「この請求書を第三者に見せても問題ないか?」を基準に売掛債権を選ぶ。
- 滞納・赤字などネガティブ情報も含めて、自社の現状を整理し説明できるようにする。
- 売掛先・売掛金・自社の三つの軸で、審査担当者からの質問を想定しておく。
審査に落ちた後の見直しポイント
審査に落ちた場合、「このサービスとは縁がなかった」で終わらせてしまうと、同じ理由で他社でも断られる可能性があります。
重要なのは、「どの軸でNGが出たのか」を推定し、必要であればファクタリング会社に可能な範囲で理由を確認したうえで、自社側で再整理することです。
売掛先が理由の場合(売掛先の経営不安・支払遅延・個人事業主で実態不透明など)は、その売掛先の売掛金を出さない方針に切り替えることが一つの選択肢になります。
売掛債権が理由の場合(債権の一部が延滞・架空に近い・支払期日が遠すぎる・譲渡禁止特約付きなど)は、申込対象の債権を「正常債権だけ」に絞る必要があります。
自社側が理由の場合(税金滞納・決算内容・書類不備など)は、滞納整理・資金繰りの見直し・書類整備といった内部改善が不可欠です。
審査落ちが続く場合、「ファクタリング以前に、収支構造や固定費に根本的な問題があるのではないか」という視点も持つべきです。
- 売掛先・売掛債権・自社のどこに主なNG要因がありそうかを整理する。
- 同じ条件で他社に出しても、同じ理由で断られる可能性が高いと認識する。
- 審査結果を「他人の評価」として受け止め、自社の改善ポイントを抽出する。
- 可能な範囲で、どの点がネックだったのかをファクタリング会社に確認する。
- 売掛先・債権・自社の三つの軸に分けて、NG要因を整理し改善策を考える。
- 同じ条件のまま他社に出す前に、最低限の是正(債権選別・書類整備・滞納対応)を行う。
案件選別と他の資金調達手段
資金難のときほど、「とにかく持っている請求書を全部出したい」という気持ちになりがちですが、審査通過率とコストの観点からは、案件選別が非常に重要です。
ファクタリングに出すべきは、①売掛先の信用力が高い、②支払遅延がなく取引実績が安定している、③支払期日までの残り日数が30〜90日程度である、④粗利率が一定以上ある、といった条件を満たす債権が中心になります。
これにより、審査を通りやすくしつつ、手数料を支払っても利益が残りやすい構成にできます。
一方、恒常的な資金不足や設備投資、赤字補填など、中長期にわたる資金需要をファクタリングだけで賄うと、手数料負担が積み上がり、財務体質を悪化させるおそれがあります。
このようなニーズには、制度融資・信用保証付き融資・リスケジュール(返済条件変更)・出資・固定費削減など、別の手段を組み合わせることが必要です。
ファクタリングはあくまで「短期のギャップ」を埋める手段と位置付け、売上の成長やコスト改善とセットで使うことが重要です。
- ファクタリングに出す債権は、売掛先・期日・粗利率の観点から選別する。
- 中長期資金や赤字補填は、融資・リスケ・コスト削減など別手段で対応する。
- 「ファクタリングで何を解決したいのか」を明確にし、目的外利用を避ける。
- 資金需要を「一時的なギャップ」と「構造的な不足」に分けて整理する。
- 一時的なギャップには、信用力の高い売掛先の正常債権だけをファクタリングに出す。
- 構造的な不足には、事業計画の見直し・融資・固定費削減など、中長期の対策を優先する。
悪質業者回避と安全な相談先
資金難の企業ほど、「審査なし」「どこよりも高額買取」「税金滞納でもOK」といった派手な広告に引き寄せられやすくなりますが、このようなキャッチコピーを前面に出す業者には注意が必要です。
過去には、ファクタリングの名目で実質的に高金利の貸付けを行う「偽装ファクタリング」や、給与ファクタリングのようにヤミ金融と認定された事例もありました。
共通する特徴は、「実態とかけ離れた高い買取率・極端に高額な手数料」「実質的な買戻し義務や違約金」「契約内容の不透明さ」などです。
悪質業者を避けるためには、①運営会社の所在地・代表者・連絡先が明確か、②契約書で手数料・買戻し条件・違約金などが具体的に書かれているか、③相場とかけ離れた「うますぎる条件」になっていないか、といった基本事項を確認することが重要です。
また、資金繰りが厳しいときこそ、商工会議所・金融機関・中小企業支援機関・公的相談窓口(自治体の経営相談窓口など)に相談し、ファクタリング以外の選択肢も含めてアドバイスを受けることが有効です。
- 「審査なし」「即日100%買取」など、極端なキャッチコピーには慎重になる。
- 契約書の内容を読み込み、買戻し義務や高額な違約金の有無を確認する。
- 迷ったときは、公的機関や専門家に相談し、一人で判断しない。
- 会社情報・契約条件・手数料水準が透明な業者以外とは契約しない。
- 資金繰り相談は、商工会議所・金融機関・公的支援機関の窓口も活用する。
- 「今すぐ必要だから」と焦って契約せず、最低一度は第三者に条件を見てもらう。
まとめ
本記事では、ファクタリング審査が落ちる理由を、売掛先リスク・売掛債権の状態・利用企業側の信用という三つの視点から整理しました。
不良債権や譲渡禁止特約、売掛先の経営不安、税金・社会保険料の滞納、書類不備など、具体的なNG要因を把握することで、申込前に自社でセルフチェックしやすくなります。
あわせて、案件の選別や他の資金調達手段の併用、悪質業者を避けるための相談先も押さえることで、資金難の場面でも、より安全で現実的な選択ができるようになります。